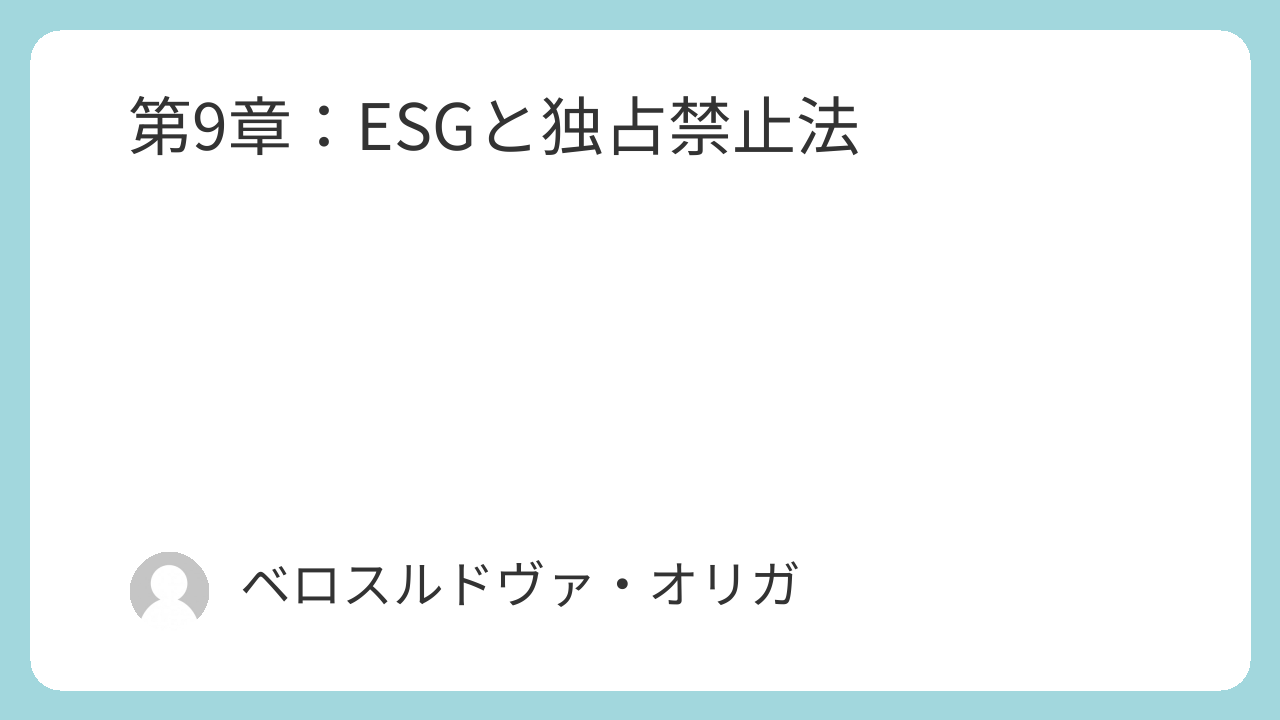気候変動対策や人権尊重といったESGの目標達成には、一企業だけの努力では限界があり、業界全体での協調やサプライチェーンを通じた連携が不可欠となる場面が少なくありません。サステナビリティ基準の設定、業界共通のイニシアチブへの参加、サプライヤーに対する行動規範の要請といった活動は、ESGを推進する上で極めて有効な手段です。しかし、これらの「協調行動」は、意図せずしてアメリカの独占禁止法(Antitrust Law)という、見過ごすことのできない法的リスクの領域に足を踏み入れる危険性をはらんでいます。
司法省(DOJ)や連邦取引委員会(FTC)の反トラスト当局者は、「崇高な目的であっても、競争を阻害する談合的な手段を正当化することはできない」と繰り返し明言しており 、ESGに対する独占禁止法の免除(ESG exemption)は存在しないというのが、現在の法執行機関の一貫した立場です。
さらに近年、保守的な州の司法長官らによる監視の目も厳しさを増しています。彼らは、一部のESG活動が、競合他社を不当に排除したり、消費者に追加的なコストを転嫁したりする、反競争的なカルテルに他ならないのではないかと疑いの目を向けています。
本章では、企業が善意のESG活動を進める中で、いかにして独占禁止法違反という罠を回避するかを解説します。
1. 独占禁止法の基本原則:なぜESG活動が問題になるのか
アメリカの独占禁止法の根幹をなすのが、1890年に制定されたシャーマン法です。その第1条は、「取引を制限する、いかなる契約・結合・共謀」を違法と定めています。この法律が問題とするのは、企業の「協調行動(concerted action)」が、市場における健全な競争を不当に歪めることです。
独占禁止法のリスクを評価する上で、まず理解すべき最も重要な区別は、「一方的な行動(unilateral conduct)」と「協調行動(concerted conduct)」の違いです 。
- 一方的な行動: ある企業が、他社と合意することなく、独立した経営判断としてESG方針を決定し、実行する場合。これは、市場支配的な地位の濫用(シャーマン法2条)に該当しない限り、通常、独占禁止法上のリスクは低いです。
- 協調行動: 複数の企業が、明示的または黙示的に合意し、共同で行動する場合。これはシャーマン法1条の対象となり、その内容によっては深刻な法的リスクを伴います。
ESG活動は、その性質上、業界全体での基準設定やサプライチェーンへの働きかけを伴うことが多く、必然的に「協調行動」の領域に入りやすいです。問題は、その協調が「不当に」競争を制限するかどうかです。
2. 最も危険な領域:競合他社との水平的協定
独占禁止法が最も厳しく禁じているのが、競合他社間の協定(水平的協定)です。特に、価格・生産量・市場分割・顧客分割・入札談合といった、競争の中核をなす要素に関する合意は、その目的や市場への影響を問うまでもなく、それ自体が違法と見なされる「当然違法(per se illegal)」の行為にあたります。
ESGの文脈においても、この原則に例外はありません。たとえその動機が、サステナブルな製品開発の促進や、労働者の賃金水準の向上といった社会的に望ましいものであったとしても、競合他社間で以下のような合意を行うことは、極めて高い確率で違法と判断され、刑事訴追を含む厳しい制裁の対象となります。
- 価格カルテル: 「環境配慮型製品の健全な市場を育成するため、我々の業界では最低価格をXドルに設定しましょう」
- 市場分割: 「A社は東海岸でグリーン製品を販売し、B社は西海岸に集中しましょう。そうすれば無用な競争を避け、研究開発に投資できます」
- 共同ボイコット(取引拒絶): 「環境基準を満たさないサプライヤーY社とは、業界全体で取引を停止しましょう」
- 採用に関する協定(No-Poach): 「DE&I推進のために各社が多額の投資をしているので、お互いの多様な人材を引き抜き合うのはやめましょう」
これらの合意は、たとえ非公式な会話や電子メールでのやり取りであっても、違法な共謀と見なされる可能性があります。
3. サプライチェーンにおける垂直的協定のリスク
メーカーと卸売業者、又は、企業とサプライヤーといった、サプライチェーン上の異なる段階に位置する企業間の合意は「垂直的協定」と呼ばれます 。これらは、競争を促進する側面も持つため、「当然違法」ではなく、競争への悪影響が便益を上回るかどうかを個別に判断する「合理の原則(Rule of Reason)」に基づいて評価されるのが一般的であり、水平的協定に比べて許容される範囲は広いです。
しかし、垂直的協定であっても、それが事実上、競合他社間の水平的なカルテルを促進する手段として機能する場合には、深刻な独占禁止法上のリスクが生じます。特に注意すべきなのが、「ハブ・アンド・スポーク(Hub-and-Spoke)」型の共謀です 。
これは、中心的な企業(ハブ、例えば大手小売業者)が、複数の競合するサプライヤー(スポーク)との間でそれぞれ個別に合意を結ぶことを通じて、結果的にサプライヤー間の価格競争などを抑制する構造を指します。企業がサプライチェーン全体でESGを推進する際には、サプライヤーとのコミュニケーションが、意図せずして競合他社間の情報交換や協調行動の媒介となっていないか、細心の注意を払う必要があります。
4. 情報交換と基準設定のリスク管理
ESG活動において、競合他社との情報交換や基準設定は、しばしば不可欠な要素となります。しかし、これらは独占禁止法上、最も慎重な管理が求められる活動です。
情報交換
競合他社間で、価格、コスト、生産計画、顧客情報、従業員の報酬といった競争上機微な情報(Competitively Sensitive Information – CSI)を交換することは、たとえESGという目的のためであっても、違法なカルテルの証拠と見なされるリスクが極めて高いです。業界のベストプラクティスを学ぶためのベンチマーキング調査などを行う場合は、以下のセーフガードを厳格に遵守することが不可欠です。
- 第三者機関の利用: データの収集・分析は、信頼できる第三者機関に委託し、企業間で直接データを交換しない
- 過去の情報の利用: 交換するデータは、現在または将来の競争に影響を与えないよう、十分に過去のもの(例えば3ヶ月以上前)に限定する
- 匿名化と集計: 公表されるデータは、個々の企業の数値が特定できないよう、十分に集計・匿名化する
基準設定
業界全体でサステナビリティ基準を設定する活動は、イノベーションを促進するなどの競争促進的な側面を持ちます。しかし、そのプロセスと内容によっては、競争を阻害するリスクも伴います。
- 排他的な基準: 基準が、特定の企業や技術を市場から不当に排除する効果を持たないか。
- イノベーションの阻害: 基準が、それ以上の技術革新を目指すインセンティブを削いでしまわないか。
- プロセスの透明性と公平性: 基準設定のプロセスは、業界のすべての関係者に対して開かれており、参加は任意でなければなりません 。
5. 独占禁止法コンプライアンスを「G」に組み込む
ESGと独占禁止法の緊張関係を乗り越えるためには、企業は独占禁止法コンプライアンスを、ESGの「G(ガバナンス)」の不可分の一部として位置づけ、全社的なリスク管理体制に組み込む必要があります。
- 明確な目標設定とリスク評価: ESGイニシアチブを開始する前に、その真の目的を明確に定義します。その目的が、競争を制限することではなく、イノベーションの促進や効率性の向上といった競争促進的なものであることを確認します。
- 従業員への徹底した教育: 特に、業界団体の会合に参加する営業担当者や、サプライヤーとの交渉にあたる調達担当者など、リスクの高い接点を持つ従業員に対し、独占禁止法の基本原則と具体的な禁止事項について、継続的なトレーニングを実施します。
- 会議プロトコルの厳守: 競合他社が参加するすべての会議においては、事前に弁護士のレビューを受けた議題を作成し、会議中は議題から逸脱しないようにします。議事録を正確に作成し、競争上機微な情報に関する議論が行われなかったことを記録として残します。
- 早期の法的助言: 新たな共同イニシアチブや基準設定活動を計画する際には、構想の初期段階から独占禁止法を専門とする弁護士の助言を求めます。