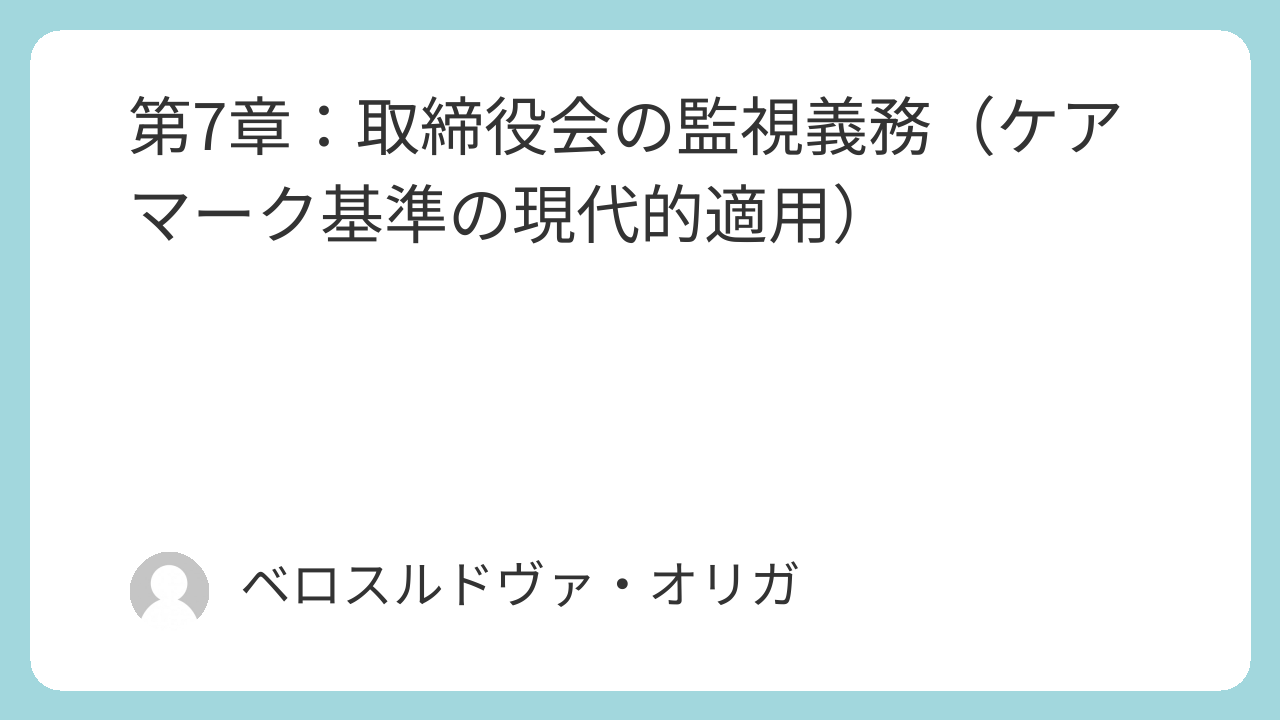株式会社の事業と業務は、取締役会によって行われます。取締役は会社とその株主に対して、忠実義務(Duty of Loyalty)と注意義務(Duty of Care)という2つの基本的な義務(Fiduciary Duty)を負います。
ESGの時代において、これらの義務は、新たな、そして極めて複雑な文脈で解釈されなければなりません。気候変動の科学的知見、サプライチェーンにおける人権侵害、従業員のウェルビーイングといった、これまで財務諸表に直接現れることのなかった非財務的リスクが、今や企業の存続を脅かす「重要(material)」なリスクとして認識されているからです。
1. 取締役の受託者責任と経営判断の原則
取締役会の監視義務を理解する前提として、まずその基礎となる2つの受託者責任と、それらを守る「盾」としての経営判断原則を確認しましょう。
- 注意義務(Duty of Care): 取締役は、意思決定を行う前に、「合理的に入手可能なすべての重要な情報」に基づいて判断しなければなりません。これは、経営陣の提案を鵜呑みにせず、十分な情報を得た上で、思慮深く行動することを求める義務です。
- 忠実義務(Duty of Loyalty): 取締役は、自己の個人的な利益のためではなく、常に会社とその株主の最善の利益のために、誠実に(in good faith)行動しなければなりません。
これらの義務を遵守して行われた取締役の意思決定は、「経営判断の原則(Business Judgment Rule)」によって手厚く保護されます。これは、裁判所が企業の経営判断の当否に事後的に介入することを控え、取締役が誠実かつ合理的な情報に基づいて下した判断を尊重するという、アメリカ会社法の基本原則です。この原則が適用される限り、たとえその決定が結果的に会社に損失をもたらしたとしても、取締役が個人的な法的責任を問われることはありません。
ESGに関する意思決定も、この原則の保護下にあります。例えば、短期的な収益を犠牲にしてでも、長期的なレジリエンス向上のために多額の設備投資を行うという判断は、それが合理的な情報収集と誠実な議論の末に下されたものであれば、経営判断として尊重されます。しかし、問題は、取締役会がそもそも重要なリスクの存在に気づかず「何もしなかった(inaction)」場合にどうなるかです。ここに、監視義務というより厳しい責任論が登場します。
2. 監視義務の金字塔:「ケアマーク基準」
取締役の監視義務に関する現代的な議論の出発点となったのが、1996年のデラウェア州衡平法裁判所判決、In re Caremark International Inc. Derivative Litigation事件です。この事件で裁判所は、取締役が「会社法を遵守するための情報収集・報告システムが社内に存在することを、誠実に保証しようと試みる義務」を負うと判示しました。これが「ケアマーク基準」として知られる、取締役の監視義務の基本形です。
この基準によれば、株主が取締役の監視義務違反を理由に法的責任を追及するためには、以下のいずれかの極めて高いハードルを越えなければなりません。
- 第一の柱(情報システムの欠如): 取締役会がいかなる報告・情報システム又は内部統制をも導入することを完全に怠ったこと
- 第二の柱(監視の懈怠): そのようなシステムを導入したにもかかわらず、その運用を意識的に監視・監督することを怠り、その結果、注意を払うべきリスクや問題について知ることができない状態に自らを陥れたこと
裁判所は、この基準を満たすことは「原告が勝訴を期待しうる会社法の理論の中で、おそらく最も困難なもの」であると述べ、取締役の責任を極めて限定的に捉えました。実際、長年にわたり、株主がケアマーク基準に基づいて取締役の責任を追及することに成功した例はほとんどありませんでした。
3. ケアマーク基準の現代的変容:「ミッションクリティカル」なリスク
しかし、この状況は2019年のデラウェア州最高裁判決、Marchand v. Barnhill事件によって一変します。この事件は、アイスクリーム製造会社ブルーベル社でリステリア菌汚染による死亡事故が発生したにもかかわらず、取締役会が食品安全という「ミッションクリティカル(mission-critical)」なリスクについて、何ら監視を行っていなかったとして責任が問われたものです。
最高裁は、ブルーベル社には経営レベルでの食品安全管理手順は存在したものの、取締役会レベルでの報告・監視システムが全く存在しなかったことを問題視しました。取締役会の議題に食品安全が上ることはなく、関連する委員会も存在せず、経営陣から取締役会への定期的な報告も行われていませんでした。最高裁は、このような状態は、ケアマーク基準の第一の柱である「情報システムの完全な欠如」に該当しうると判断し、株主の訴えを認めました。
このMarchand判決は、ケアマーク基準を実質的に甦らせました。企業が直面するリスクの中でも、その事業の根幹をなし、最大の法的・経済的脅威をもたらす「ミッションクリティカルなリスク」については、取締役会が直接的かつ定常的に監視する仕組みを持たなければならないという明確なメッセージを含むものでした。
この判決以降、デラウェア州の裁判所は、ケアマーク基準をより積極的に適用する傾向を見せています。例えば、2023年1月のIn re McDonald’s Corp. Stockholder Derivative Litigation事件では、同社の取締役会が、社内に「セクシャルハラスメントが蔓延している」という数多くの危険信号(red flags)を認識しながら、それを体系的に監視・是正する仕組みを怠ったとして、元人事担当役員に対する監視義務違反の訴えを認めました。これは、ケアマーク基準が、伝統的な財務や法規制遵守だけでなく、従業員の安全や企業文化といった「S(社会)」の領域にも明確に適用されることを示した点で画期的でした。
これらの判例の積み重ねは、現代のESGリスクを取締役会がどのように捉えるべきかについて、重要な示唆を与えます。すなわち、
- 気候変動リスクは、エネルギー・農業・保険といった多くの産業にとって、もはや「ミッションクリティカル」なリスクです。
- サプライチェーンにおける人権侵害は、グローバルに事業を展開するアパレルや電子機器メーカーにとって、「ミッションクリティカル」なリスクです。
- データプライバシーとサイバーセキュリティは、金融やIT産業にとって「ミッションクリティカル」なリスクです。
取締役会が、これらのESGリスクを「専門的すぎる」「経営陣に任せておけばよい」といった理由で看過し、取締役会レベルでの監視システムを構築・運用することを怠れば、それはもはや経営判断の原則で保護される裁量の範囲を超え、ケアマーク基準の下で法的責任を問われる可能性が十分にあるのです。
4. 実効性のあるESG監視体制の構築
では、取締役会は、この厳格化する監視義務を果たすために、具体的にどのようなガバナンス体制を構築すべきでしょうか。唯一の正解はありませんが、以下の要素を組み合わせ、自社の事業内容やリスクプロファイルに合わせて最適化していくことが求められます。
① 委員会の活用
ESGリスクは広範にわたるため、取締役会全体で全ての詳細を監視することは非効率的です。多くの場合、特定の委員会に監視の主たる責任を委任することが有効です。
- 監査委員会: 伝統的にリスク管理を監督してきた監査委員会は、ESGリスクの財務的影響や、情報開示の正確性を監督する役割を担うことがあります
- 指名・ガバナンス委員会: 取締役会の構成(多様性や専門性)・企業倫理・株主との対話といった「G」の側面を監督します
- 報酬委員会: 役員報酬にESG関連の業績指標を連動させるなど、インセンティブ設計を通じてESG戦略の実行を担保します
- 新設のESG・サステナビリティ委員会: ESGに関する課題を専門的かつ集中的に審議するために、独立した委員会を設置する企業も増えています
重要なのは、どの委員会がどのESGリスクを監督するのかを、委員会の憲章(charter)で明確に定め、各委員会間の情報連携と協働を確保する仕組みを構築することです。
② 取締役会の構成と専門性
取締役会がESGリスクを効果的に監督するためには、その構成員が適切な知識と経験、すなわち「ESGコンピテンシー」を備えている必要があります。これに応えるため、企業は気候科学や人権問題などの専門家を社外取締役として招聘するか、あるいは既存の取締役全員に対して継続的な教育・研修の機会を提供し、外部のコンサルタントを適宜活用するといったアプローチを検討できます。専門家を取締役に加えることは、深い知見をもたらす一方で、他の取締役がその専門家に過度に依存してしまうリスクも指摘されています。
③ 経営陣からの報告体制
Marchand判決が示したように、取締役会が監視義務を果たすためには、経営陣から定期的かつ体系的な報告を受ける仕組みが不可欠です。経営陣は、主要なESGリスクに関する指標(KPI)、目標に対する進捗状況、新たに発生したインシデント等を、取締役会が理解しやすい形で報告しなければなりません。取締役会の議事録に、これらのESGリスクについて議論した記録が明確に残されていることは、万が一訴訟に発展した場合に、取締役会がその監視義務を果たしていたことを示す重要な証拠となります。