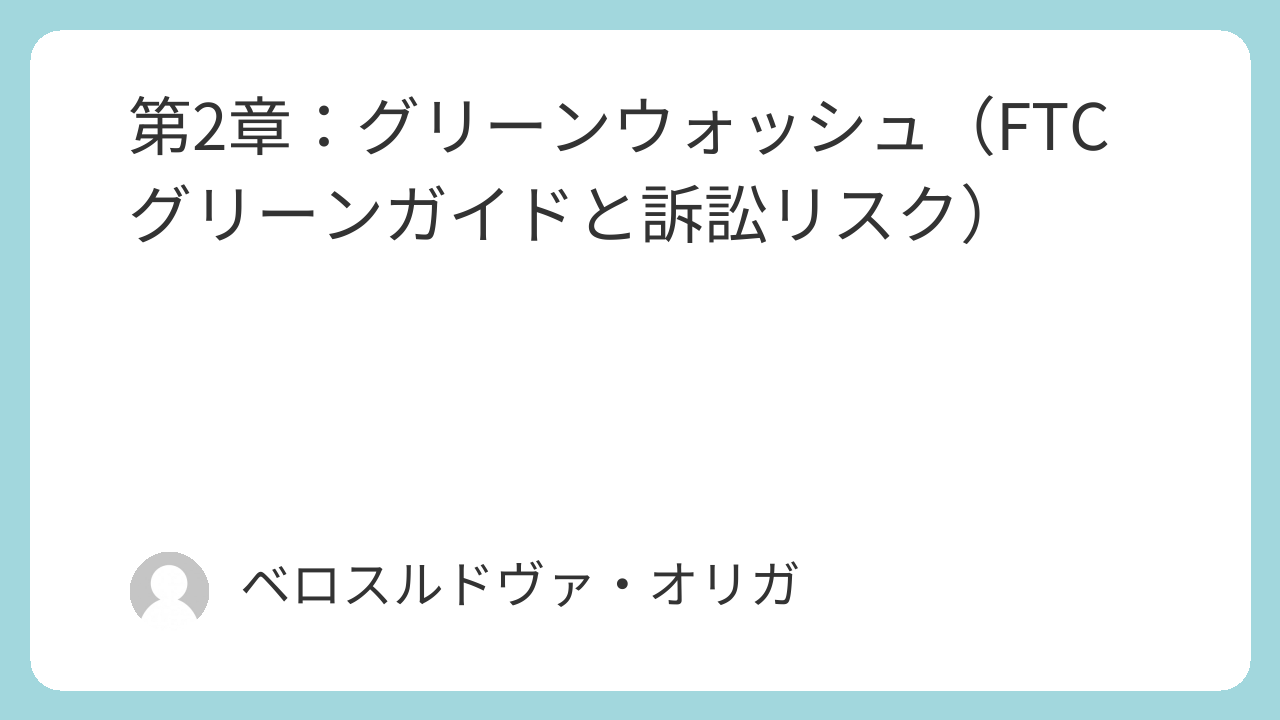ESGへの関心が爆発的に高まる中、企業は自社の製品やサービス、さらには企業活動そのものが環境にいかにポジティブな影響を与えているかを、投資家や消費者に向けて積極的にアピールするようになりました。しかし、その熱意が時に実態を伴わない、あるいは誇張された表現へと繋がり、「グリーンウォッシュ(Greenwashing)」という深刻な法的リスクを生み出しています。グリーンウォッシュとは、環境配慮を装い、実態が伴わないにもかかわらず製品や企業活動が環境に良いと見せかける行為を指します。これは単なる誇大広告の問題に留まりません。投資家を欺き公正な市場競争を歪める資本市場の健全性に対する重大な違背行為です。
アメリカにおいて、このグリーンウォッシュとの闘いの最前線に立つのが、連邦取引委員会(FTC)です。FTCは、長年にわたり不公正または欺瞞的な商慣行を規制してきた経験を活かし、環境関連の表示に対しても厳しい視線を向けています。本章では、FTCがグリーンウォッシングを規制するための法的根拠と、その具体的な指針である「グリーンガイド(Green Guides)」の内容について解説します。
1. 米国の規制フレームワーク:FTCと「グリーンガイド」
アメリカにおけるグリーンウォッシング規制の根幹をなす法律は、FTC法5条(a)項です。この条文は、商業に影響を与える「不公正・欺瞞的な行為または慣行」を広く禁止しており、環境関連の表示もその対象となります。FTCは、ある表示が欺瞞的であるかどうかを判断する際、それが「合理的に行動する消費者を誤解させる可能性が高い重大(material)な表示等」を含んでいるかを検証します。
この一般的で広範な禁止規定を、環境マーケティングという特殊な文脈で具体化するために、FTCは1992年に「環境マーケティング表示の使用に関するガイド(通称:グリーンガイド)」を策定しました。グリーンガイドは、法律そのものではなく、FTCの法解釈を示す行政ガイダンスであり、法的な拘束力を持つものではありません。しかし、ガイドに準拠した表示は、FTC法違反で訴追されるリスクを大幅に低減させる「セーフハーバー」として機能するため、事実上の業界標準となっています。
グリーンガイドは、すべての環境関連表示に適用される4つの基本原則を定めています。
- 明確性と顕著性: 表示は明確で、目立つように、消費者に理解しやすく提示されなければならない
- 製品・サービスの区別: 環境上の便益が、製品そのもの又は関連するサービスのいずれに由来するものかを明確に区別しなければならない
- 便益の誇張の禁止: 環境への便益がごく僅かである場合、それを直接的・間接的に誇張してはならない
- 比較表示の明確化: 競合製品などとの比較を行う場合は、比較の根拠を明確にし、実証可能でなければならない
これらの基本原則に加え、グリーンガイドは特定の表示類型について、より詳細に規定しています。
2. グリーンガイドが示す主要な論点
FTCが特に問題視するのは、曖昧で科学的根拠に乏しい表示です。グリーンガイドは、具体的な用語を挙げながら、企業が陥りやすい罠に警鐘を鳴らしています。
一般的・曖昧な環境便益表示の危険性
グリーンガイドが最も厳しく規制しているのが、「エコフレンドリー(eco-friendly)」「グリーン(green)」「環境にやさしい」といった、漠然とした環境便益をうたう表示です。これらの言葉は、消費者に製品のライフサイクル全体にわたって環境負荷がないかのような広範な印象を与えますが、それを実証することは事実上不可能に近いと言えます。
したがって、FTCはこうした非限定的な表示を用いることは欺瞞的である可能性が高いと指摘します。もし企業がこのような言葉を使いたいのであれば、「明確かつ顕著な限定的文言」を付記し、その便益が具体的に何を指すのか(例:「再生可能エネルギーを利用して製造されています」「リサイクル素材から作られています」)を特定しなければなりません。
この点に関する最も有名な事例が、「クリーンディーゼル」事件です。自動車メーカーが、自社のディーゼル車は低排出ガスで環境にやさしいと大々的に宣伝していましたが、実際には排出ガス試験の結果を不正に操作する「ディフィートデバイス」を搭載していました。FTCはこれをFTC法違反とみなし、同社は巨額の制裁金を支払うこととなりました。この事件は、たとえ技術的な偽装を凝らしたとしても、実態を伴わない一般的な環境性能のうたい文句がいかに高いリスクを伴うかを示しています。
カーボンオフセットと再生可能エネルギーに関する表示
企業の気候変動対策が加速する中で、「カーボンオフセット」と「再生可能エネルギー」に関する表示は、グリーンウォッシングの新たな火種となりつつあります。グリーンガイドは、これらの比較的新しい表示についても具体的なガイダンスを提供しています。
カーボンオフセットに関する表示については、以下の3点が重要となります。
- 科学的根拠と二重計上の禁止: 排出削減量を適切に定量化するための、信頼できる科学的会計手法を用いること。また、同一の削減部分について二重に計上してはならない。
- 削減の時期の明示: 排出削減が、購入後すぐに行われるのか、又は、将来(例えば2年以上先)になるのかを明確に開示すること。将来の削減であるにもかかわらず、あたかも即時に効果があるかのように見せかけるのは欺瞞的です。
- 法律で義務付けられた削減量の取扱い: 法律によってすでに義務付けられている排出削減(例:埋立地からのメタン回収)を、自社のオフセットとして表示することはできません。自主的な追加の取り組み(additionality)でなければ表示してはならない。
再生可能エネルギーに関する表示では、特に再生可能エネルギー証書(REC)の扱いが重要です。企業がRECを購入することで、自社の電力使用を再生可能エネルギー由来と見なすことは広く行われています。しかし、もし企業が自社で太陽光発電などを行い、そこで生まれた電力のRECを市場で売却した場合、その企業はもはや自社が再生可能エネルギーを使用していると表示することはできません。RECという「環境価値」を他者に売却した以上、その価値を自社のものとして主張することは、消費者を欺く二重表示(ダブルカウンティング)にあたります。
3. 表示の裏付け:「実証(Substantiation)」という高いハードル
FTCが環境関連表示を評価する上で最も重視する概念が「実証(substantiation)」です。これは、企業が表示を行う前に、その主張を裏付けるための「合理的な根拠(reasonable basis)」を保有していなければならないという原則です。事後的に証拠を集めることは許されません。
環境関連表示の場合、この「合理的な根拠」として求められるのは、通常、「適格かつ信頼できる科学的証拠(competent and reliable scientific evidence)」です。これは、客観的な方法で実施・評価され、専門分野で一般的に正確かつ信頼できる結果をもたらすと認められている試験・分析・研究・調査を意味します。顧客からの裏付けに乏しい証言や、新聞記事、製造元の販売資料などは、これに含まれません。
FTCは、この実証の基準を厳格に適用します。例えば、プラスチック添加剤メーカーのECM BioFilms社は、自社製品がプラスチックの生分解を促進すると謳い「生分解性」と表示していましたが、FTCは、同社が主張を裏付けるために提出した科学的試験が実際の埋立地の環境を正確に再現しておらず、実証として不十分であると判断しました。
また、LED電球メーカーのLights of America社は、製品の寿命や明るさについて具体的な数値を表示していましたが、FTCは同社が保有する試験データがいずれもその表示を裏付けていないと結論付けました。この事例は、たとえ社内に試験データが存在したとしても、その内容が表示内容と一致していなければ実証とは見なされないことを示しています。
法務・コンプライアンス部門は、マーケティング部門が新たな環境関連表示を打ち出す前に、その主張のあらゆる側面が、客観的かつ科学的な証拠によって裏付けられているかを検証するプロセスを構築する必要があります。
4. FTCを超えた訴訟リスク:州法と消費者クラスアクション
グリーンウォッシングのリスクは、FTCによる執行措置だけではありません。むしろ近年、企業にとってより大きな脅威となっているのが、州法に基づく訴訟、特に消費者によるクラスアクションです。
中でも、カリフォルニア州は、全米で最も厳格な消費者保護法制を持つことで知られています。同州の環境マーケティング表示法(Environmental Marketing Claims Act)は、FTCのグリーンガイドを州法に取り込むだけでなく、特定の表示(例:リサイクルマーク)に対して、州独自の厳格な基準を設けています。
この法律に基づいて、カリフォルニア州の地方検事や消費者団体は、企業に対する訴訟を積極的に提起しています。近年では、大手小売業者が販売する犬の糞処理袋が「生分解性」と表示されていながら基準を満たしていなかったとして、多額の和解金を支払う事例がありました。
さらに深刻なのが、消費者個人が原告となり、企業を相手取って損害賠償を求めるクラスアクションです。コーヒーメーカーのキューリグ社は、同社のコーヒーカプセルが「リサイクル可能」と表示されていながら、実際には多くの自治体でリサイクルが困難であったとして訴えられ、最終的に1000万ドルの和解金を支払うとともに、表示の変更を余儀なくされました。
同様の訴訟は、「持続可能な方法で調達された(sustainably sourced)」チョコレート、「100%リサイクル可能」なペットボトル、「サンゴ礁にやさしい(reef friendly)」日焼け止め等、あらゆる製品と表示に及んでいます。これらの訴訟は、たとえ最終的に企業が勝訴したとしても、その過程で多大な訴訟費用と、ブランドイメージの毀損という大きな代償を払うことになります。
5. EU等の状況
グリーンウォッシングの問題は、アメリカ国内に留まりません。EUやイギリスも、不公正な商業慣行を禁じる指令やガイダンスを通じて、環境関連表示に対する監視を強めています。特にEUでは、企業のサステナビリティに関する主張をより広範に規制する動きが活発化しており、グローバルに事業を展開する企業は、各国の規制の差異にも注意を払う必要があります。
国際資本市場協会(ICMA)のような市場の自主規制機関も、グリーンウォッシングがサステナブルファイナンス市場全体の信頼性を損なうことを懸念しています。ICMAは、グリーンウォッシングを単なる「欺瞞」だけでなく、より広範な「懸念領域(areas of concern)」として捉えることを提唱しています。これには、以下のようなものが含まれます。
- 野心の欠如(Lack of ambition): 例えば、サステナビリティ・リンク・ボンドの目標が、現状維持(business as usual)と大差ないレベルに設定されている。
- 戦略との不整合(Strategic inconsistency): グリーンボンドを発行しているにもかかわらず、企業全体の事業戦略が依然として環境負荷の高い事業に依存している。
- 広範なサステナビリティリスクの管理不全: ある環境目標を追求するあまり、他の環境や社会への悪影響(例:生物多様性の損失)を無視している。
これらの「懸念領域」は、直ちにFTC法違反となるわけではないかもしれません。しかし、これらは投資家やNGOからの厳しい批判の対象となり、結果としてレピュテーションリスクや訴訟リスクへと発展する可能性を秘めています。
これらの複雑で多岐にわたるリスクに対応するため、企業法務・コンプライアンス部門は、以下のような包括的な対策を講じる必要があります。
- 全社的な表示審査プロセスの構築: マーケティング・広報・法務・研究開発といった関連部署が連携し、すべての環境関連表示を公開前に多角的に審査する体制を構築する。
- 実証資料の一元管理: すべての表示について、その根拠となる科学的データや第三者認証を法務・コンプライアンス部門が一元的に管理し、いつでも当局や訴訟の場で提示できるよう準備しておく。
- 従業員トレーニングの徹底: マーケティング担当者だけでなく、製品開発から顧客対応に至るまで、全従業員に対してグリーンウォッシングのリスクと関連法規に関する継続的な教育を行う。
- 開示情報の一貫性の確保: SECへの提出書類、サステナビリティ報告書、ウェブサイト、広告、製品ラベルなど、すべてのコミュニケーションチャネルで発信する情報に矛盾が生じないよう、厳格な管理を行う。
- 目標と実態のバランス: 高邁な環境目標を掲げることは重要ですが、それが現時点での技術や事業の実態と乖離しすぎていないか、常に冷静に評価する。目標達成に向けた具体的なロードマップと進捗状況を、透明性をもって開示することが信頼を繋ぎとめる鍵となります。
グリーンウォッシングは、意図的な欺瞞だけでなく、善意からくる過剰な期待や、科学的知見の不足によっても生じえます。このリスクをコントロールするためには、常に自社の取り組みを客観的に検証し透明性を確保することが重要になります。