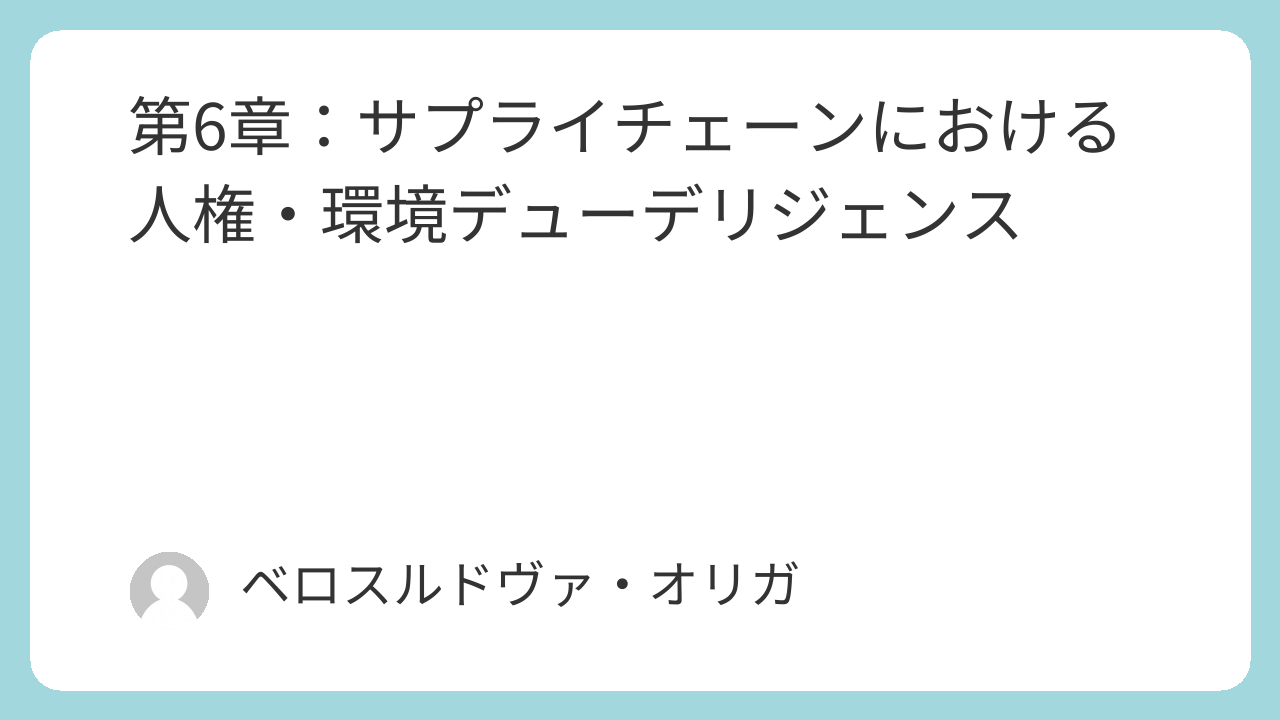現代企業の事業活動は、国境を越えて広がる複雑で多層的なサプライチェーンの上に成り立っています。原材料の調達から部品の製造、製品の組み立て、そして最終的な消費者への配送に至るまで、その連鎖はグローバルに張り巡らされています。しかし、このグローバル化の恩恵の裏側で、サプライチェーンはESGにおける最も深刻なリスクの温床となっています。遠く離れた国の二次、三次のサプライヤーが引き起こす強制労働や児童労働、深刻な環境汚染は、企業のブランド価値を毀損し、法的な制裁を招き、資本市場からの信頼を失墜させる、経営の根幹を揺るがすリスクとなります。
1. 国際的な行動規範:デューデリジェンスという新たな責任
サプライチェーンにおける企業の責任を考える上で、国際社会の共通言語となっているのが「デューデリジェンス」の概念です。これは、企業が自社の事業活動およびサプライチェーンにおいて、人権や環境への負の影響を特定し、防止・軽減するために実施すべき継続的なプロセスを指します。この概念を確立した二つの国際的な枠組みが、UNGPsとOECD多国籍企業行動指針です。
国連ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)
2011年に国連人権理事会で承認されたUNGPsは、「保護・尊重・救済」という三つの柱から構成されます。
- 国家の保護義務: 国家は、企業による人権侵害から個人を保護する義務を負います。
- 企業の人権尊重責任: 企業は、自らの事業活動を通じて人権を侵害することを回避し、負の影響に対処する責任を負います。
- 救済へのアクセス: 人権侵害の被害者が、司法的・非司法的な救済措置へアクセスできることを確保します。
この中で、企業に直接求められるのが第二の柱である「人権尊重責任」であり、その責任を果たすための具体的な手段が人権デューデリジェンスです。
OECD多国籍企業行動指針と責任ある企業行動のためのデューデリジェンス・ガイダンス
OECD多国籍企業行動指針は、人権・労働・環境・腐敗防止など、幅広い分野における企業の責任ある行動を推奨する包括的な国際基準です。この指針も、企業がサプライチェーン全体で負の影響を管理するための手段としてデューデリジェンスを中核に据えています。
さらにOECDは、より実践的な手引きとして「責任ある企業行動のためのデューデリジェンス・ガイダンス」を公表しています。このガイダンスは、デューデリジェンスを6つのステップからなる循環的なプロセスとして提示しており、多くの企業にとって実務上の重要な参照点となっています。
これらの国際規範は、直接的な法的拘束力を持つものではありません。しかし、多くの国の国内法や機関投資家のエンゲージメント方針、企業のサプライヤー行動規範の基礎となっており、事実上のグローバルスタンダードとして機能してきています。
2. 米国の法規制:ターゲットを絞ったアプローチ
EUが包括的な人権・環境デューデリジェンスの義務化へと進む一方、アメリカの法制度は、現時点では特定の課題に焦点を当てたターゲット型のアプローチを特徴としています。
① 強制労働:関税法307条とウイグル強制労働防止法(UFLPA)
アメリカのサプライチェーン人権法制で最も強力なツールが、1930年に制定された関税法307条です。この条文は、強制労働によって採掘・生産・製造された物品の米国への輸入を全面的に禁止しています。
この法律の執行を劇的に強化したのが、2022年6月に施行されたウイグル強制労働防止法(UFLPA)です。この法律は、中国の新疆ウイグル自治区で全部または一部が生産されたすべての製品を、強制労働によって生産されたものと「反証可能な推定(rebuttable presumption)」の下に置くという、極めて強力な措置を導入しました。
これにより、新疆ウイグル自治区に関連するサプライチェーンを持つ企業は、米国税関・国境警備局(CBP)に対して「明確かつ説得力のある証拠(clear and convincing evidence)」をもって、強制労働が一切介在していないことを証明するという、非常に高いハードルを課されることになりました。
② 情報開示を通じた規律:カリフォルニア州サプライチェーン透明法(CTSCA)
カリフォルニア州で2012年に施行されたサプライチェーン透明法(CTSCA)は、直接的な輸入禁止ではなく、情報開示を通じて企業の自主的な取り組みを促すアプローチを採っています。この法律は、カリフォルニア州で事業を行う一定規模以上の小売業者および製造業者に対し、自社のサプライチェーンから奴隷労働と人身売買を根絶するための取り組みについて、ウェブサイトで開示することを義務付けています。
③ 紛争鉱物:ドッド=フランク法1502条
2010年に成立したドッド=フランク法(金融規制改革法)の第1502条は、紛争鉱物(Conflict Minerals)に関する規制を定めています。これは、コンゴ民主共和国(DRC)およびその周辺国で産出され、現地の武装勢力の資金源となっている4つの鉱物(スズ・タンタル・タングステン・金)について、SECに上場する製造業者が自社製品にこれらの鉱物が含まれているかどうかを調査し原産地を特定するためのデューデリジェンスを実施し、その結果を年次でSECに報告することを義務付けるものです。
3. 環境デューデリジェンスとスコープ3排出量
サプライチェーンにおけるデューデリジェンスの対象は、人権問題だけではありません。企業の環境フットプリントの大部分は、自社の直接的な事業活動(スコープ1、2)ではなく、サプライチェーン(スコープ3)に存在することが多いです。
第1章で取り扱ったSECの気候関連開示規則案は、この状況を一変させる可能性を秘めています。この規則案が、スコープ3排出量が「重要」である場合にその開示を義務付ければ、企業はもはやサプライヤーの環境パフォーマンスに無関心ではいられなくなります。
自社のスコープ3を算定するためには、主要なサプライヤーからGHG排出量やエネルギー消費量に関するデータを収集し、信頼性を検証する必要があります。これは、事実上の環境デューデリジェンスをサプライヤーに対して行うことを意味します。GHG排出量だけでなく、森林破壊、生物多様性の損失、水ストレスといった他の重要な環境課題も、多くが企業のサプライチェーンと深く結びついています。
4. ガバナンス:実効性のあるサプライチェーン管理の基盤
サプライチェーンにおける人権・環境リスクを効果的に管理するためには、付け焼き刃の対応では不十分です。それは、取締役会の監督から現場の調達担当者の日常業務に至るまで、企業活動のあらゆるレベルに組み込まれた、堅牢なガバナンス体制を必要とします。
- 取締役会の監督責任: サプライチェーンリスクの管理は、取締役会が監督すべき重要な経営課題です。取締役会は、サプライチェーンにおける人権・環境方針を承認し、その実施状況について経営陣から定期的に報告を受け、監督する責任を負います。
- 方針とサプライヤー行動規範の策定: 企業は、人権の尊重、強制労働・児童労働の禁止、環境保護などに関する自社のコミットメントを明確にした方針を策定し、それを「サプライヤー行動規範(Supplier Code of Conduct)」として、すべてのサプライヤーに遵守を求めるべきです。
- リスク評価とデューデリジェンスの実施: 地理的、産業的なリスク評価に基づき、人権・環境リスクが特に高いと特定されたサプライヤーや地域に、デューデリジェンスの資源を集中させることが重要です。
- 契約への組み込みと監査: サプライヤー行動規範の遵守を、調達契約の必須条件として明記します。また、契約には、企業自身または第三者機関が、サプライヤーの工場などを査察(監査)する権利が含まれるべきです。
- 是正と能力構築: 監査などで問題が発見された場合、直ちに取引を停止するのではなく、まずはサプライヤーと協力して是正計画(Corrective Action Plan)を策定し、その実行を支援することが、サプライチェーン全体の人権・環境パフォーマンスを向上させる上で効果的です。