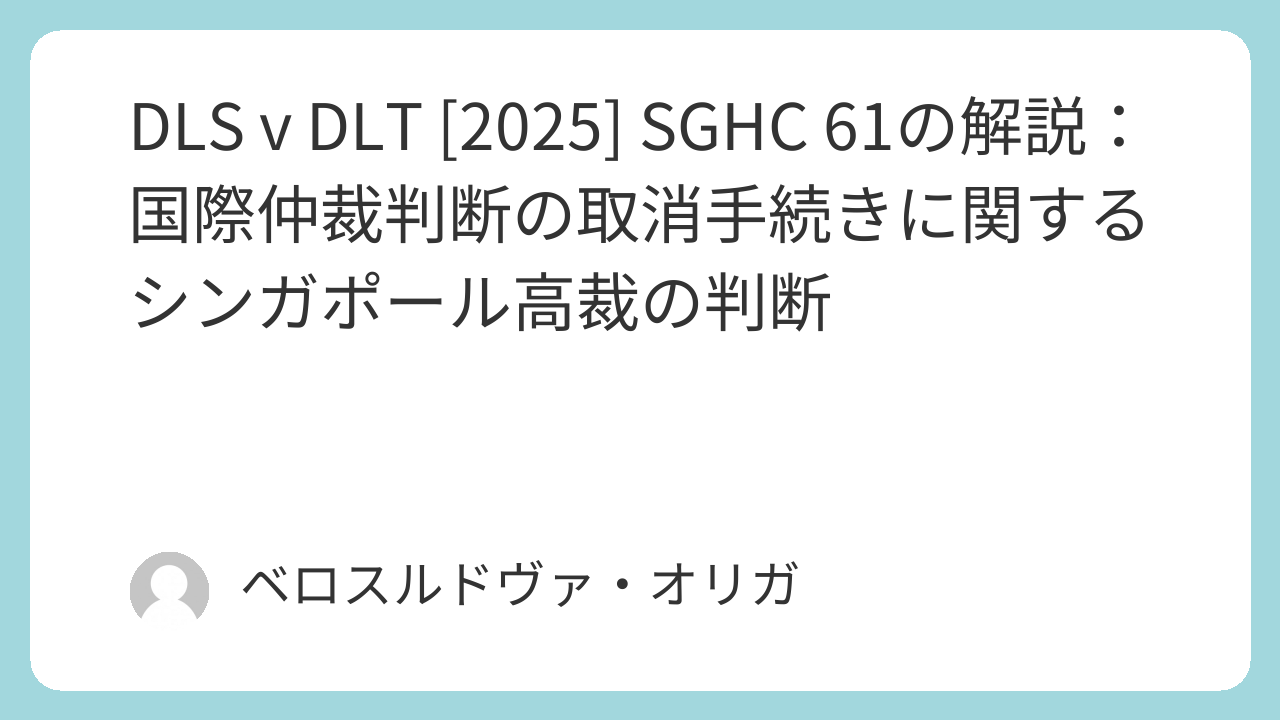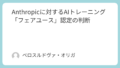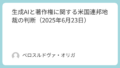1 概要
2025年4月10日、シンガポール高等裁判所(General Division of the High Court)は、DLS v DLT [2025] SGHC 61(以下「本判決」)において、国際仲裁判断の取消手続きに関する重要な判断を示しました。本件は、建設プロジェクトをめぐる紛争に関するICC仲裁において下された第一部分裁定(First Partial Award)の取消しが申し立てられた事案です。
本判決は、特に①仲裁廷による決定が取消申立ての対象となる「仲裁判断(award)」に該当するのか、それとも対象外の「暫定措置(interim measure)」なのかという区別、②仲裁判断の取消申立期間(3ヶ月)が経過した後に新たな取消理由を追加することの許容性、そして③仲裁人の「外観上のバイアス(apparent bias)」の存否という、国際仲裁実務において頻繁に問題となる論点について、具体的な判断基準を提示しています。
シンガポールを仲裁地として選択する日本企業にとって、同国の裁判所が示す仲裁フレンドリーな姿勢と、その手続きの厳格性を理解する上で、本判決は多くの示唆を与えるものと考えられます。本稿では、本判決の事実関係と判断内容を整理し、その実務上の意義について解説します。
2 事実関係
(1) 裁判に至る経緯
本件の原告は建設プロジェクトの元請業者(以下「DLS」)であり、被告はその下請業者(以下「DLT」)です。両者間の下請契約には、シンガポールを仲裁地とし、ICC仲裁規則に準拠する仲裁条項が含まれていました。
プロジェクトの進行に伴い、両者間で工事代金の支払いをめぐる紛争が生じ、DLTはDLSを相手方としてICCに仲裁を申し立てました。
仲裁手続きにおいて、仲裁廷はDLTの申立てを認め、DLSに対して金銭の支払いを命じる「第一部分裁定(First Partial Award)」を下しました。この裁定には、大きく分けて二つの支払命令が含まれていました。
- DLSに対し、DLTが発行した特定の支払い請求(payment claims)に基づき、月々の支払い(Monthly Payment)を行うよう命じる部分。ただし、この支払いは最終的な裁定において見直される可能性があり、またDLTは支払いを受けるにあたり銀行保証(bank guarantee)を提供することが条件とされていました。
- DLSに対し、上記とは別個の請求に基づき、一時金(Lump Sum Payment)を支払うよう命じる部分。こちらには特段の条件は付されていませんでした。
この第一部分裁定を不服とするDLSは、シンガポール国際仲裁法(International Arbitration Act 1994、以下「IAA」)に基づき、シンガポール高等裁判所に対して本裁定の取消しを求める申立て(setting-aside application)を行いました。
さらにDLSは、取消申立ての法定期間である3ヶ月が経過した後に、申立理由を追加する許可を裁判所に求めました。追加の申立理由は、仲裁廷を構成する仲裁人の一人に、DLTに有利な判断をする可能性を示唆する「外観上のバイアス」が存在するというものでした。
(2) 判決内容
Kwek Mean Luck裁判官は、DLSによる申立てをいずれも棄却しました。主要な争点に関する判断は以下の通りです。
① 仲裁判断(Award)と暫定措置(Interim Measure)の区別
裁判所は、仲裁廷による決定が取消しの対象となる「仲裁判断」に該当するか否かは、その性質と効果によって実質的に判断されるべきであるとしました。
- 月々の支払い(Monthly Payment)に関する命令について:
裁判所は、この命令が将来の最終裁定で見直される可能性(subject to review and adjustment)が明示されていること、またDLTによる銀行保証の提供が条件とされていることを重視しました。これらの要素から、当該命令は当事者間の権利義務を最終的に確定させるものではなく、手続き的な性質が強いと判断。したがって、これはIAA上の取消しの対象となる「仲裁判断」ではなく、むしろ「暫定措置」に類するものと評価し、本件取消申立ての対象にはならないと結論付けました。 - 一時金(Lump Sum Payment)に関する命令について:
これに対し、一時金の支払命令は、特段の条件が付されておらず、その文言や文脈から、当事者間の特定の争点について最終的かつ拘束力のある判断を下したものと解釈されました。したがって、こちらは取消しの対象となる「仲裁判断」に該当すると判断しました。
② 法定期間経過後の取消事由の追加
裁判所は、IAAが定める3ヶ月の取消申立期間が経過した後に、新たな取消事由を追加する申立てを許可するか否かについて、裁判所には裁量権があると述べました。
その上で、そのような追加を許可するためには、少なくとも追加しようとする取消事由が「勝ち目がないものではない(not hopeless)」、すなわち、一応の法的根拠(prima facie case)を備えている必要があるとの判断基準を示しました。
本件において、DLSが追加しようとした「外観上のバイアス」という取消事由は、後述の通り、その主張自体に根拠がなく「勝ち目がない」と判断され、結果として取消事由の追加は許可されませんでした。
③ 外観上のバイアスの存否
DLSは、仲裁人の一人が、過去にDLTの関連会社が関与する別の仲裁案件において、当該関連会社に有利な判断を下したことがある点を指摘し、これが外観上のバイアスに当たると主張しました。
裁判所は、仲裁人の公平性に対する客観的な疑念が生じるか否かという観点から、この主張を検討しました。検討の結果、以下の理由から、外観上のバイアスは存在しないと結論付けました。
- 当該仲裁人は、本件の仲裁人就任時に、問題とされた過去の案件について開示していました。
- DLSが主張するような、DLTと過去の案件の当事者との密接な関係を示す証拠は提出されませんでした。
- 仲裁人が過去にある当事者に有利な判断をしたという事実だけで、将来の別の案件においても同様の判断をするという推測は成り立ちません。
裁判所は、仲裁人の開示義務は重要であるとしつつも、本件においては仲裁人の対応に問題はなく、情報に通じた公正な第三者の視点から見て、仲裁人の公平性に疑念を抱かせるような状況は認められないと判断しました。
3 本判決の意義
本判決は、シンガポールの裁判所が国際仲裁に対して基本的に友好的(pro-arbitration)なスタンスを取りつつも、仲裁判断の取消手続きについては厳格な基準を適用する姿勢を改めて明確にした点で、実務上重要な意義を持ちます。
第1に、仲裁廷による決定の性質決定に関する指針を示した点です。
仲裁手続き中に出される金銭支払命令等が、取消しの対象となる「仲裁判断」なのか、対象外の「暫定措置」なのかという区別は、しばしば実務上の判断に迷う点です。本判決は、①その決定が最終的かつ拘束的なものか(final and binding)、②将来の裁定で見直される可能性が留保されているか、③何らかの条件(担保提供など)が付されているか、といった要素を総合的に考慮して実質的に判断するアプローチを明確にしました。
これは、仲裁当事者が仲裁廷から何らかの決定を受領した際に、その法的性質を評価し、不服申立ての可否やその後の戦略を立てる上での重要な指針となります。
第2に、取消事由の追加に関する裁判所の裁量基準を明らかにした点です。
UNCITRALモデル法を基礎とする多くの国の仲裁法と同様、シンガポールのIAAも3ヶ月という厳格な取消申立期間を定めています。本判決は、この期間の重要性を強調しつつも、例外的な状況下での追加申立ての可能性を完全に閉ざしたわけではないことを示しました。ただし、そのハードルとして、追加事由が「勝ち目のないものではない」ことを要求しており、安易な追加申立てを牽制しています。
これは、申立期間の遵守を当事者に強く促す一方で、期間経過後に極めて重大な瑕疵が発覚した場合の救済の余地を残すという、バランスの取れた判断と言えるでしょう。
第3に、仲裁人の利益相反・開示義務に関する判断基準を再確認した点です。
仲裁人の公平性・中立性は仲裁制度の根幹をなす要素であり、その「外観」もまた重要です。本判決は、IBAガイドライン等で議論される仲裁人の利益相反や開示義務について、シンガポールの裁判所が客観的かつ合理的な基準で判断する姿勢を示したものです。単に過去の案件に関与していたという事実だけでは足りず、公正な第三者の視点から見て、バイアスを疑うに足る具体的な状況が示されない限り、取消事由としては認められないことが改めて確認されました。これは、仲裁人の選任プロセスや、手続き中の異議申立てのタイミングの重要性を当事者に再認識させるものです。
4 おわりに
本判決は、シンガポールにおける国際仲裁判断の取消手続きに関し、近時の裁判所の判断傾向を追認し、その解釈をより具体化したものとして位置づけられます。特に、仲裁判断と暫定措置の区別や、取消事由の追加申立てに関する判断基準は、今後の実務において参照されるべき重要なリーディングケースの一つとなる可能性があります。
シンガポールを仲裁地として利用する企業法務担当者としては、同国が仲裁制度の自律性を尊重する一方で、その手続き的正義を確保するため、裁判所が限定的ながらも厳格な監督権限を行使することを十分に理解しておく必要があります。本判決は、その具体的な現れとして、今後の仲裁実務を考える上で示唆に富むものと言えるでしょう。