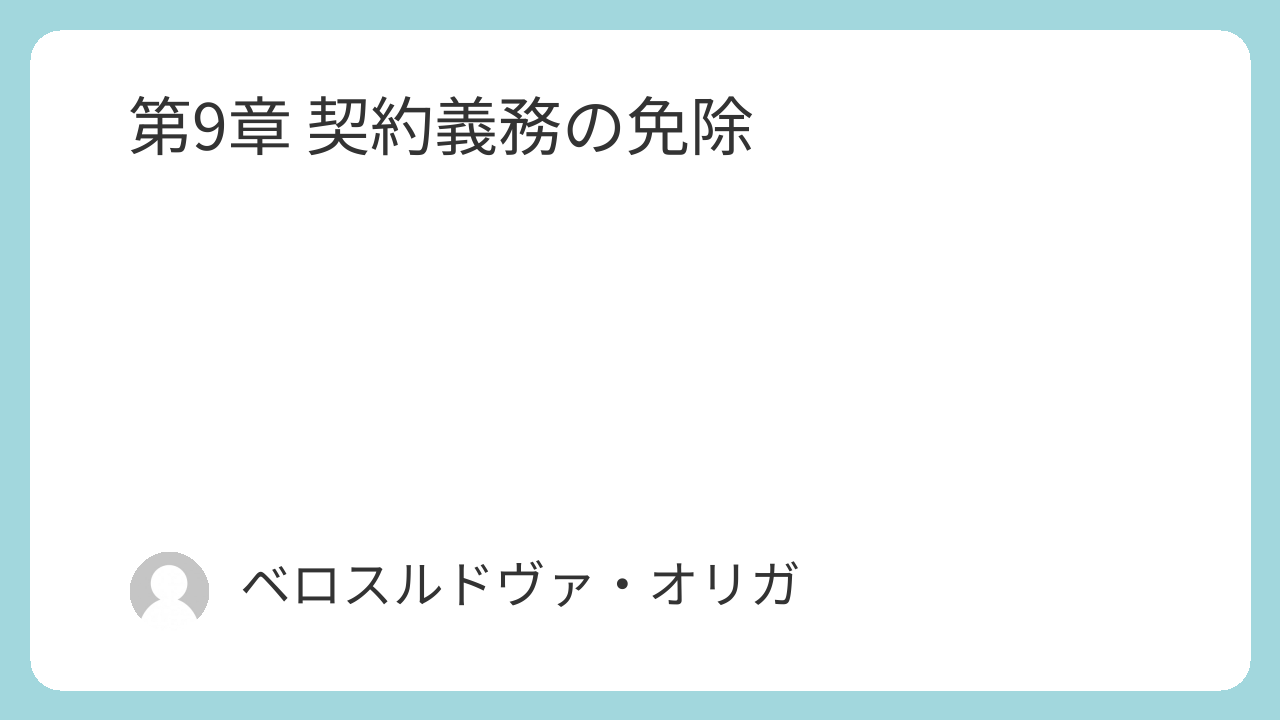契約は当事者を法的に拘束する約束です。一度有効に成立した契約は履行されなければなりません。しかし、世の中は常に変化し、契約締結時には当事者の誰もが予期しなかったような出来事が発生することがあります。戦争の勃発、パンデミックによる政府の操業停止命令、契約の対象物が火事で焼失してしまうなど、後発的な事情によって契約の履行が物理的に不可能になったり、当初想定していたものとは全く異なる、極めて過酷なものに変貌したりすることがあります。
このような場合にまで、契約の文言通りに履行を強制することは、当事者にとってあまりに酷であり、不公平です。そこでアメリカ契約法は、特定の状況下において、当事者を契約上の義務から解放する、すなわち「免責(Excuse)」を認める法理を発展させてきました。
9.1 履行不能(Impossibility)
契約義務が免責される典型例が、履行が物理的に不可能になった場合です。
A. 法理の起源:厳格な履行義務
かつてのイギリス・コモンローは極めて厳格でした。17世紀の Paradine v. Jane 事件では、戦争によって敵軍に土地を占領され、使用できなくなった借地人が、それでも地代の支払義務を免れないと判断されました。裁判所は、「当事者は契約によって自ら義務を課したのだから、それを免れるための条項を契約書に入れておくべきだった」と考えたのです。つまり、予期せぬ事態のリスクは、契約で手当てしない限り、義務を負った側が全て引き受けるべきだ、という厳しい立場でした。
B. 免責が認められる古典的な類型
しかし、このような厳格なルールは、やがて緩和されていきます。裁判所は、特定の状況下では、当事者が暗黙のうちに「その状態が継続すること」を契約の前提としていたと解釈するようになりました。これにより、以下の3つの典型的な類型で履行不能による免責が認められるようになりました。
- 契約の対象物(Subject Matter)の滅失
有名な Taylor v. Caldwell 事件がこの原則を確立しました。コンサートのために音楽ホールを借りる契約が結ばれましたが、コンサートの直前にホールが火事で焼失してしまいました。裁判所は、当事者双方が契約の前提として「ホールが存在し続けること」を暗黙のうちに条件としていたと判断し、ホールの所有者の履行義務は不能になったとして免除を認めました。売買契約の対象である特定の物品が、売主にも買主にも責任のない理由で滅失した場合も同様です。 - 特定の個人の死亡・能力喪失
契約の履行が、特定の個人の技能や存在に不可欠な場合(役務契約)、その個人が死亡したり、病気で履行不能になったりすれば、義務は免除されます。例えば、有名な歌手がコンサートの前に病気で声が出なくなった場合、その出演義務は免責されます。ただし、誰にでも代替可能な一般的な労働(例えば、単純な建設作業)については、この類型にはあたりません。 - 法律の変更による違法化
契約締結時には合法であった行為が、その後の法律の制定や政府の命令によって違法となった場合、その履行義務は不能となり免除されます。
9.2 履行困難(Commercial Impracticability)
履行不能の法理は、時代とともにさらに進化し、物理的に「絶対不可能」でなくとも、予期せぬ事態によって履行が「商業的に実行不可能(Commercially Impracticable)」になった場合にも免責を認める、より柔軟な履行困難の法理へと発展しました。この考え方は、UCC(§2-615)および契約法リステイトメント(§261)に取り入れられ、現代アメリカ契約法の標準的なルールとなっています。
履行困難を理由に免責が認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 契約の「基本的想定」の覆り
契約の前提となっていた、ある出来事が起こらないという「基本的想定(basic assumption)」が、後発的な事情によって覆されたこと。例えば、中東での戦争勃発によるスエズ運河の閉鎖や政府による予期せぬ価格統制の導入などがこれにあたり得ます。ただし、単なる市場価格の変動や原材料費の上昇は、通常、当事者が引き受けるべきビジネス上のリスクとみなされ、「基本的想定」の覆りとは認められません。 - 履行が「実行不可能」になること
その出来事によって、履行が著しく困難または過大な費用を要するものになること。単に「採算が合わなくなった」「利益が出なくなった」というだけでは不十分です。当初の想定とは比較にならないほどの、極端な困難性が要求されます。 - 当事者がリスクを負担していないこと
免責を主張する当事者が、契約上、その予期せぬ出来事のリスクを自ら引き受けていなかったこと。ある出来事が「予見可能(foreseeable)」であった場合、当事者はそのリスクを契約時に考慮し、引き受けたと解釈されやすくなります。例えば、戦争の危機が迫る中で締結された運送契約では、戦争勃発のリスクはある程度予見可能であり、免責は認められにくいでしょう。
9.3 契約目的の達成不能(Frustration of Purpose)
履行困難と似ていますが、異なる法理として契約目的の達成不能があります。これは、予期せぬ事情の発生により、契約の履行自体は可能であるものの、その契約を締結した当事者の主たる目的が、もはや完全に失われてしまった場合に免責を認めるものです。
この法理を確立したのも、有名なイギリスの判例です。Krell v. Henry 事件(戴冠式事件)では、国王エドワード7世の戴冠式パレードを見るためだけに、パレードのルートが見える部屋を借りる契約が結ばれました。しかし、国王の急病によりパレードは延期。部屋を借りること自体は可能でしたが 、裁判所は、パレードを見るという契約の「主たる目的」が失われたとして、借主の賃料支払義務を免除しました。
目的達成不能が認められるための要件は、履行困難とほぼ同じです。
- 当事者の主たる目的が、後発的な事情によって実質的に達成不能になったこと
- その事情の不発生が、契約の「基本的想定」であったこと
- 当事者がそのリスクを負担していないこと
履行困難が「履行の手段」に着目するのに対し、目的達成不能は「履行の価値」に着目する点で異なります。履行はできるものの、それが当事者にとって全く無価値になってしまった場合に適用される法理です。
9.4 不可抗力条項(Force Majeure Clauses)
これまで見てきた免責の法理は、契約に特別な定めがない場合に適用される、いわば「デフォルト・ルール」です。実際のビジネスにおいては、このようなデフォルト・ルールに頼るのではなく、契約書の中に「不可抗力条項(Force Majeure Clause)」を設けることで、どのような場合に履行義務が免除されるのかをあらかじめ具体的に定めておくのが一般的です。
この条項では、天災・戦争・ストライキ・政府の行為等、免責の対象となる出来事を具体的に列挙します。不可抗力条項を設けることで、当事者は、コモンローの曖昧な「基本的想定」や「実行不可能」といった基準に頼ることなく、予見可能なリスクを明確に分配し、契約の安定性を高めることができるのです。ただし、条項に列挙されていない事象が発生した場合、それが免責事由に含まれるかどうかの解釈(例えば「ejusdem generis」の原則の適用)が問題となることはあります。