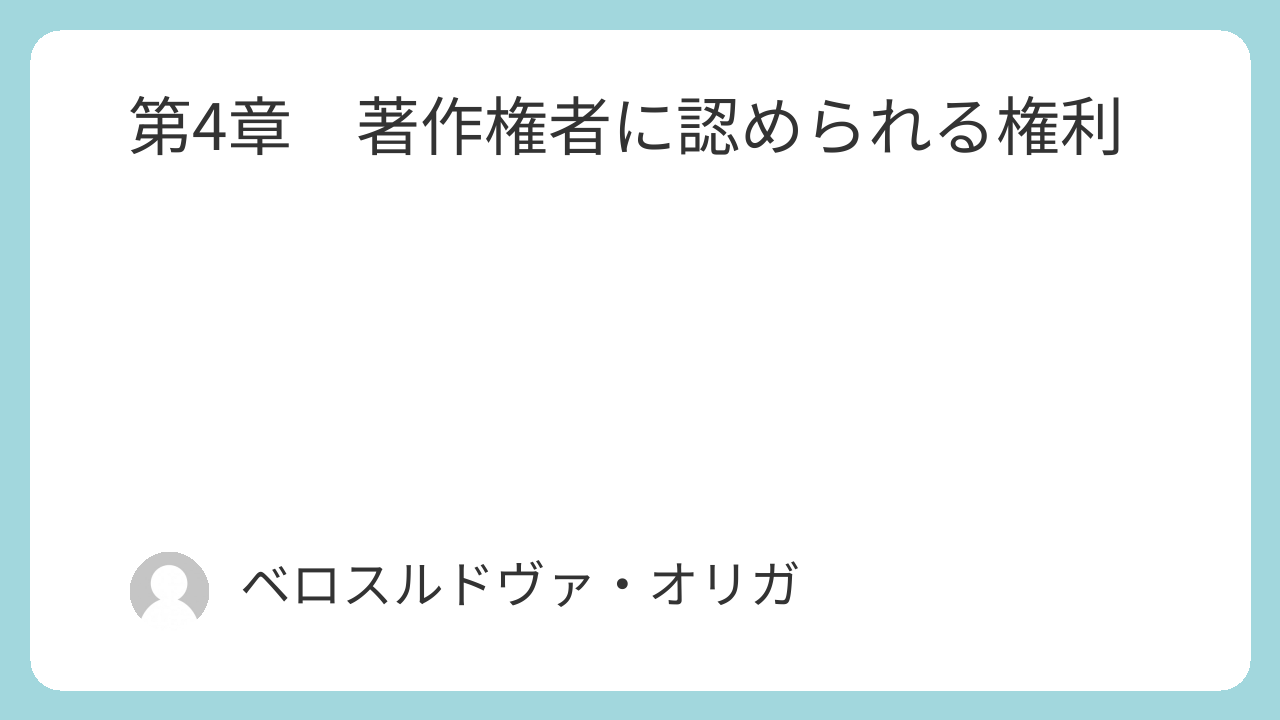著作権とは、具体的にどのような権利なのでしょうか。著作権保護の核心は、1976年著作権法106条に定められた、著作権者が専有する一連の排他的権利(Exclusive Rights)にあります。これは、他者が許諾なしに特定の行為を行うことを禁止する権利の「束(bundle of rights)」と考えることができます。この権利の束は、第3章で見たように、個別に分割して譲渡したりライセンスしたりすることが可能です。
106条は、以下の6つの基本的な権利を定めています。
- 複製権(Right of Reproduction)
- 翻案権(Right to Prepare Derivative Works)
- 頒布権(Right of Distribution)
- 実演権(Right of Public Performance)
- 展示権(Right of Public Display)
- 録音物に関するデジタルトランスミッション実演権(Right of Public Performance by Digital Audio Transmission)
これらの権利は、著作権者が自らの作品から経済的利益を得るための法的基盤となります。しかし、これらの権利は絶対的なものではありません。後述のように、フェアユースをはじめとする様々な権利制限に服します。本章では、まずこれら6つの権利がそれぞれどのような内容を持つのか、判例を踏まえて解説します。
1. 複製権(Right of Reproduction)
複製権は、著作権の中で最も基本的な権利です。これは、著作物を「複製物又はレコードに有形的に固定する(to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords)」権利を専有するものです。
「固定」と「複製」
第2章でも触れましたが、「固定」とは、作品を一時的な期間を超えて知覚・再現できる程度に、安定的・永続的に媒体に具体化することです。そして、「複製」とは、録音物以外のすべての有形媒体を指し、「レコード」は音を固定した媒体を指します。つまり、小説を印刷して書籍にする、絵画を撮影して写真にする、音楽をCDに録音する、ソフトウェアをハードディスクにインストールする、といった行為はすべて複製権の対象となります。
デジタル時代の「複製」
デジタル技術は、「複製」の概念を大きく拡張しました。コンピュータのRAM(ランダム・アクセスメモリ)にプログラムやデータを一時的に読み込む行為も、それが知覚・再現可能な状態である以上、「コピー」を作成する行為、すなわち「複製」に該当しうるというのが画期的なMAI Systems判決以来の裁判所の基本的な立場です。この「RAMコピー」理論は、インターネットの閲覧やストリーミングといった行為が技術的には複製権を侵害しうるという、デジタル時代の著作権法の解釈の基礎を形成しています。
侵害の成立
複製権の侵害は、たとえ一部の複製であっても、それが著作物の独創的な表現部分に及んでいれば成立します。また、個人的な利用目的であっても、許諾なく複製すれば原則として権利侵害となります(ただし、フェアユースなどの権利制限が適用される場合があります)。さらに、複製された物が販売されたり、公衆に頒布されたりしなくても、複製行為そのものが独立した権利侵害行為となる点も重要です。
2. 翻案権(Right to Prepare Derivative Works)
翻案権は、既存の著作物を基に二次的著作物(Derivative Works)を作成する権利を専有するものです。二次的著作物とは、既存の著作物を「改作、変形、または翻案(recast, transformed, or adapted)」した創作物を指します。
翻案権の重要性
この権利は、著作権者が自らの作品を多様なメディアや市場に展開し、その価値を最大化するために不可欠です。小説が映画化され、その映画のキャラクターが商品化されるように、二次的著作物から生まれる市場は、しばしば元の著作物の市場をはるかに凌駕する経済的価値を持つことがあります。翻案権は、その利益を元の著作者に還元するための重要な法的根拠となります。
翻案の範囲
翻案権が及ぶ範囲は非常に広く、媒体の変更を伴う利用(クロス・メディア侵害)も含まれます。
- 典型的な例: 小説の翻訳、楽曲の編曲、戯曲の映画化
- より広範な例: バレエの振り付けを基にした写真集の作成 、物理学の教科書の問題に対する解答マニュアルの出版
ただし、翻案権の侵害が成立するためには、元の著作物の独創的な表現が二次的著作物の中に具体的に取り込まれている必要があります。単に元の作品からアイデアやコンセプトを得ただけで、具体的な表現が依拠していない場合は、翻案権の侵害にはなりません。
コンピュータによる機能拡張と翻案権
コンピュータソフトウェアの世界では、既存のプログラムの機能を拡張したり、変更したりする製品が登場し、これが翻案権の侵害に当たるかが争われてきました。Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc.事件では、任天堂のゲームの内容を一時的に変更する「ゲームジニー」という装置が問題となりました。裁判所は、ゲームジニーは元のゲームカートリッジのデータを恒久的に変更するものではなく、固定された二次的著作物を作成しないため、翻案権の侵害には当たらないと判断しました。この判決は、利用者が個人的な範囲で著作物の享受の仕方を変える行為に対して、翻案権の適用が限定的であることを示唆しています。
3. 頒布権(Right of Distribution)
頒布権は、著作物の複製物等を、販売等の所有権移転又はレンタル・リース・貸与によって公衆に提供する権利を専有するものです。
「最初の公の頒布」のコントロール
この権利の核心は、著作物の有体物(書籍、CD、DVDなど)が、最初に市場に流通する時点をコントロールする点にあります。一度、著作権者の許諾を得て適法にコピーが販売されると、その特定のコピーに対する頒布権は「消尽」し、購入者はそれを自由に再販売したり、譲渡したりすることができます。これが、次章で詳述する第一販売権(First Sale Doctrine)の原則です。
複製権との違い
頒布権は複製権とは独立した権利です。例えば、海賊版CDを製造した者は複製権を侵害し、その海賊版CDを販売した小売店は、たとえ自ら複製行為を行っていなくても頒布権を侵害します。侵害の事実について知らなかったとしても、原則として責任を免れることはできません。
デジタル時代の「頒布」
インターネットを通じてファイルをダウンロードさせる行為が、「頒布権」の侵害となるか否かについては議論が分かれています。受信者のコンピュータに新たなコピーが作成されることから複製権の侵害となることは明らかですが、物理的な「コピー」の移転がないため、伝統的な頒布の概念とは異なります。しかし、多くの裁判所は、ウェブサイトに著作物をアップロードし、公衆がダウンロード可能な状態に置く行為(Making Available)自体が、頒布権の侵害に当たると判断する傾向にあります。
4. 実演権(Right of Public Performance)
実演権は、著作物を「公に(publicly)」実演する権利を専有するものです。「実演(perform)」とは、著作物を朗読・上演・演奏等する行為を指します。ラジオをつけたり、CDを再生したりすることも「実演」に含まれます。
対象となる著作物
この権利は、文学・音楽・演劇・舞踊・映画・視聴覚著作物等に適用されます。重要なのは、美術、グラフィック、彫刻著作物、そして(デジタルトランスミッションを除き)録音物には、原則として実演権が認められていない点です。
「公に」とは?
実演権の侵害となるのは、「公の」実演に限られます。家族や親しい友人の輪の中で映画を観たり、音楽を聴いたりする私的な実演は、権利の対象外です。法律は、「公に」を2つの場合に分けて定義しています。
- 公衆に開かれた場所での実演: レストラン・店舗・映画館等、不特定の公衆が出入りする場所での実演や、家族等の通常の範囲を超えた相当数の人々が集まる場所での実演です。Columbia Pictures Industries, Inc. v. Redd Horne, Inc.事件では、ビデオ店の個室で顧客に映画を鑑賞させるサービスが、店自体が公衆に開かれているため「公の実演」に当たると判断されました。
- 公衆への送信: テレビ放送やインターネットストリーミングのように、著作物を公衆に向けて送信する行為です。受信者が別々の場所にいたり、別々の時間に受信したりしても「公の実演」となります。この規定は、ケーブルテレビやオンデマンドサービスが実演権の対象となる根拠となっています。近年の
American Broadcasting Companies, Inc. v. Aereo, Inc.事件で連邦最高裁は、個々のユーザーに専用の小型アンテナを割り当ててテレビ放送をインターネット経由で送信するサービスも、全体としてみればケーブルテレビと同様に公衆へ送信する行為であり、「公の実演」に該当すると判断しました。
5. 公の展示権(Right of Public Display)
1976年法で初めて明記されたこの権利は、著作物のコピーを「公に(publicly)」展示する権利を専有するものです。「展示(display)」とは、著作物のコピーを直接に、又は、フィルム・スライド・テレビ画像等を通じて見せる行為を指します。映画等の視聴覚著作物の場合は、個々の画像を非連続的に見せる行為が「展示」に当たります。
対象となる著作物と制限
実演権と同様、この権利は録音物や建築著作物には適用されません。また、権利が及ぶのは「公の」展示に限られます。美術館が所蔵する絵画を展示する行為は、典型的な公の展示です。
インターネットと展示権
ウェブサイトに画像を掲載する行為は、公の展示権の侵害となりえます。Perfect 10, Inc. v. Google, Inc.事件では、検索エンジンが他者のウェブサイトにある画像をインラインフレーム等で自らの検索結果ページに表示させる行為が問題となりました。裁判所は、Googleのサーバー自体に画像データが保存されていない限り、Googleはコピーを「展示」していることにはならないという「サーバーテスト」と呼ばれる基準を示しました。この判断は、インターネットの仕組みを考慮したものですが、誰が「展示」の主体なのかという点で、現在も議論が続いています。
6. 録音物に関するデジタルトランスミッション実演権
前述の通り、アメリカ著作権法は伝統的に録音物(Sound Recordings)自体には実演権を認めてきませんでした。ラジオで楽曲が放送された場合、ロイヤリティを受け取るのはその曲の作詞家・作曲家(音楽的著作物の権利者)であり、その曲を歌った歌手や演奏した楽団・レコード会社(録音物の権利者)ではありませんでした。
しかし、1995年のデジタル実演権録音物法(DPRSRA)によって、この原則に大きな例外が設けられました。これは、CDクオリティの音質で音楽を送信できるデジタル技術、特にユーザーが好きな曲を好きな時に聴けるサービスが、CDの売上を代替してしまうという音楽業界の強い懸念に応えたものです。
この改正により、106条に第6の権利として、「デジタル音声送信によって録音物を公に実演する」限定的な権利が追加されました。この権利の構造は非常に複雑ですが、大まかには以下の三層構造になっています。
- 権利が及ばない(免除される)送信: 従来の地上波ラジオやテレビ放送のデジタル版(サイマル放送など)
- 法定許諾(Compulsory License)の対象となる送信: ケーブルテレビの音楽チャンネルや、インターネット上の非インタラクティブなストリーミングサービス(Pandoraの旧サービスなど)。これらのサービスは、法定料率のロイヤリティを支払うことで、録音物を利用できます。
- 完全な許諾交渉が必要な送信: ユーザーが曲を選択できるインタラクティブなオンデマンドサービス(Spotify等)。これらのサービスは、録音物の権利者(主にレコード会社)と直接交渉し、許諾を得なければなりません。
さらに、2018年の音楽近代化法(MMA)の一部であるCLASSICS Actにより、これまで連邦著作権法の保護対象外であった1972年2月15日以前に固定された録音物にも、このデジタル実演権が及ぶことになりました。
これら6つの排他的権利は、著作権者が自らの創作物から対価を得るための強力な武器です。しかし、社会の利益とのバランスを取るため、法律はこれらの権利に様々な制約を課しています。次章以降では、その重要な権利制限である第一販売権とフェアユース等について解説します。