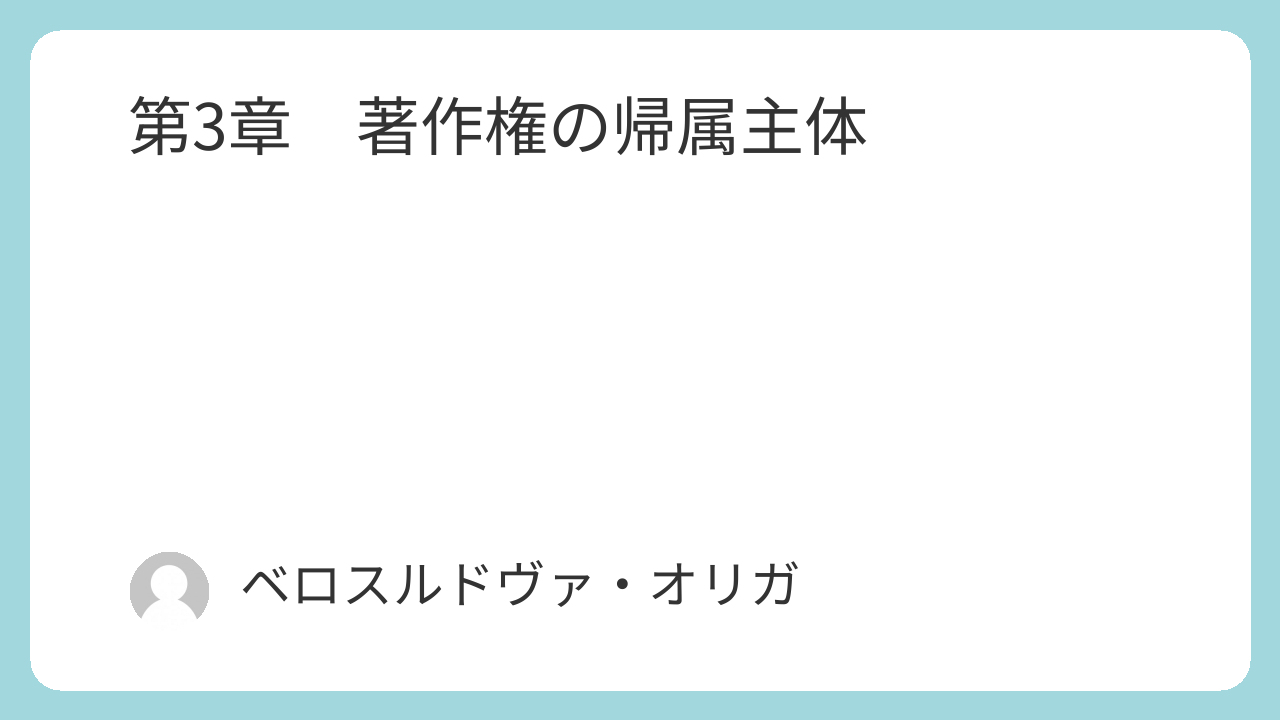著作物が創作されたとき、その著作権は一体誰のものになるのでしょうか。この問いは、クリエイターの権利保護と、創作物の円滑な利用の両方にとって極めて重要です。アメリカ著作権法は、その出発点として、「著作権は、原始的に、著作物の著作者に帰属する」という単純明快な原則を定めています。通常、「著作者」とは、その著作物を創作した個人を指します。
しかし、現代の創作活動は、個人のインスピレーションだけに依存するわけではありません。企業活動の一環として、又は、チームでの共同作業として生み出される著作物が数多く存在します。このような複雑な状況に対応するため、著作権法は「誰が著作者か」を決定するための特別なルールを設けています。本章では、著作権の原始的な帰属を決定する上で最も重要な2つの概念、「職務著作(Work Made for Hire)」と「共同著作(Joint Works)」について解説します。
1. 職務著作(Work Made for Hire)
アメリカ著作権法における重要な概念の1つが、「職務著作」です。この法理が適用されると、著作物を物理的に創作した個人ではなく、その雇用主または委託者が法的に「著作者」と見なされます。その結果、著作権のすべての権利が、原始的に雇用主等に帰属することになります。
職務著作に該当するか否かは、極めて重大な結果をもたらします。
- 権利の帰属: 雇用主が完全な権利者となり、創作した従業員には何の所有権も残りません。
- 保護期間: 通常の「著作者の死後70年」ではなく、「刊行から95年または創作から120年のいずれか短い方」という異なる保護期間が適用されます。
- 譲渡の終了権: 著作者が一度譲渡した権利を後から取り戻すことができる「譲渡の終了権」という制度がありますが、職務著作にはこの権利が適用されません。
1976年著作権法は、職務著作が成立する場合を、以下の2つの明確なカテゴリーに限定しています。
カテゴリー1:従業員が職務の範囲内で作成した著作物
これは、企業などに雇用されている従業員が、その仕事の一環として作成した著作物を指します。例えば、広告代理店のデザイナーが作成した広告デザインや、新聞社の記者が執筆した記事、ソフトウェア会社のプログラマーが開発したコードなどがこれに該当します。この場合、法律はその著作物が職務著作であると推定し、書面による別段の合意がない限り、雇用主が著作者となり全ての権利を有することになります。
ここで鍵となるのが「従業員(employee)」とは誰か、そして「職務の範囲内(scope of his or her employment)」とはどこまでかという点です。この定義を巡る混乱に終止符を打ったのが、連邦最高裁判所の画期的な判決、Community for Creative Non-Violence (CCNV) v. Reid事件です。この判決で最高裁は、「従業員」か否かは給与支払いの有無といった形式的な点だけでなく、コモンロー上の代理法(agency law)の原則に基づき、多数の要素を総合的に考慮して判断すべきであるとしました。考慮される要素には、以下のようなものがあります。
- 創作活動の手段や方法に対する雇用主の指揮監督権
- 創作に必要な技能のレベル
- 創作のための道具や仕事場所の提供者
- 当事者間の関係の継続期間
- 給与・福利厚生・税金の源泉徴収といった待遇
この判決により、単に業務を委託しただけで指揮監督関係が希薄なフリーランスや独立した請負人は、原則としてこのカテゴリーの「従業員」には当たらないことが明確になりました。
カテゴリー2:特別に委嘱された著作物(Specially Ordered or Commissioned Works)
フリーランスや独立請負人に業務を委託した場合でも、例外的に職務著作が成立する道が残されています。しかし、そのためには以下の2つの厳格な要件を両方とも満たす必要があります。
要件①:著作物が9つの法定カテゴリーのいずれかに該当すること
委託された著作物が、以下の9種類のいずれかでなければなりません。
- 集合著作物への寄与物
- 映画または他の視聴覚著作物の一部
- 翻訳
- 補足的著作物
- 編集著作物
- 教科用テキスト
- テスト
- テストの解答資料
- 地図
重要なのは、例えば委託されて制作された彫刻やコンピュータプログラム等は、この9つのカテゴリーに含まれないという点です。
要件②:当事者が書面で職務著作である旨を明示的に合意すること
たとえ著作物が上記9つのカテゴリーに該当したとしても、それだけでは職務著作にはなりません。委託者と制作者(独立請負人)とが、「署名された書面において、これを職務著作と見なすことに明示的に合意」することが不可欠です。
CCNV v. Reid判決以降、企業はフリーランスに業務を委託する際、職務著作の要件を満たすかどうかの不確実性を避けるため、契約書に「仮に職務著作に該当しない場合でも本契約により著作権のすべてを譲渡する」といった趣旨の譲渡条項を併記することが一般的になっています。
2. 共同著作(Joint Works)
複数の著作者が協力して1つの著作物を創作した場合、それは「共同著作物」となる可能性があります。著作権法は共同著作物を、「2名以上の著作者が、その寄与部分を、分離不能または相互依存的な部分として一つの統合された全体に合体させる意図をもって作成した著作物」と定義しています。
共同著作の成立要件
共同著作が成立するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
要件①:各寄与者が「著作者」であること
共同著作者とされるためには、各人が単なるアイデアの提供や補助的な作業に留まらず、それ自体が著作権保護の対象となりうる独創的な表現を寄与している必要があります。貢献が著作物性を有するものでなければなりません。
要件②:共同創作の「意図」があること
これが最も重要な要件です。各寄与者が、創作の時点で、自らの貢献が他者の貢献と合体して1つの作品を形成することを意図していなければなりません。この「意図」は、単に協力して作業したという事実だけでは足りません。判例(Childress v. Taylor)によれば、当事者双方がお互いを「共同著作者」として認識し、そのように扱っていたかどうかが重視されます。例えば、クレジット(氏名表示)の扱いや、利益配分に関する合意の有無等が、意図を判断する上での重要な指標となります。
共同著作の効果
共同著作が成立すると、各共同著作者は、その著作物全体の著作権について、共有持分を持つ共有者(tenants-in-common)となります。これは、各人が著作物全体に対して、自らの貢献度合いにかかわらず、均等かつ不可分な権利を持つことを意味します。その結果、各共同著作者は、以下の行為を単独で行うことができます。
- 著作物全体を自ら利用すること。
- 第三者に対して、著作物全体の非排他的なライセンスを許諾すること。
ただし、これらの行為によって得た利益は、他の共同著作者に対して利益を分配する義務(duty to account)を負います。一方で、著作権全体の譲渡や第三者への排他的ライセンスの許諾といった、他の共有者の権利を大きく左右する行為は、共有者全員の同意がなければ行うことはできません。
3. 著作権の譲渡とライセンス
著作権は財産権の一種であり、その全部または一部を他者に譲渡したり、利用を許諾(ライセンス)したりすることができます。
権利の分割可能性(Divisibility of Copyright)
1976年著作権法は、著作権が「分割可能」であることを明確にしました。これは、著作権という権利の束(複製権、翻案権、頒布権など)を細分化し、その一部だけを個別に譲渡したりライセンスしたりできることを意味します。例えば、小説家は、自作の小説について、A社には映画化権(翻案権)を、B社には書籍の出版権(複製権・頒布権)を、C社には舞台化権(実演権)を、それぞれ排他的に許諾することができます。独占的ライセンスを受けた各社は、その権利の範囲内で自らが著作権者として、侵害訴訟を提起するなど権利行使を行うことができます。
譲渡の方式(書面要件)
著作権の「譲渡」や「排他的ライセンス」といった、権利の所有権の移転(transfer of copyright ownership)を伴う契約は、「権利の所有者が署名した書面」がなければ有効となりません。この厳格な書面要件は、権利者が安易に重要な権利を手放すことを防ぎ、誰が権利者であるかを明確にするためのものです。口頭での合意は、所有権の移転に関しては無効です。
一方で、他者に著作物の利用を許諾するだけで所有権は移転しない「非排他的ライセンス」については、書面は必ずしも必要ではなく、口頭での合意や、当事者の行動から黙示的に成立することもあります。