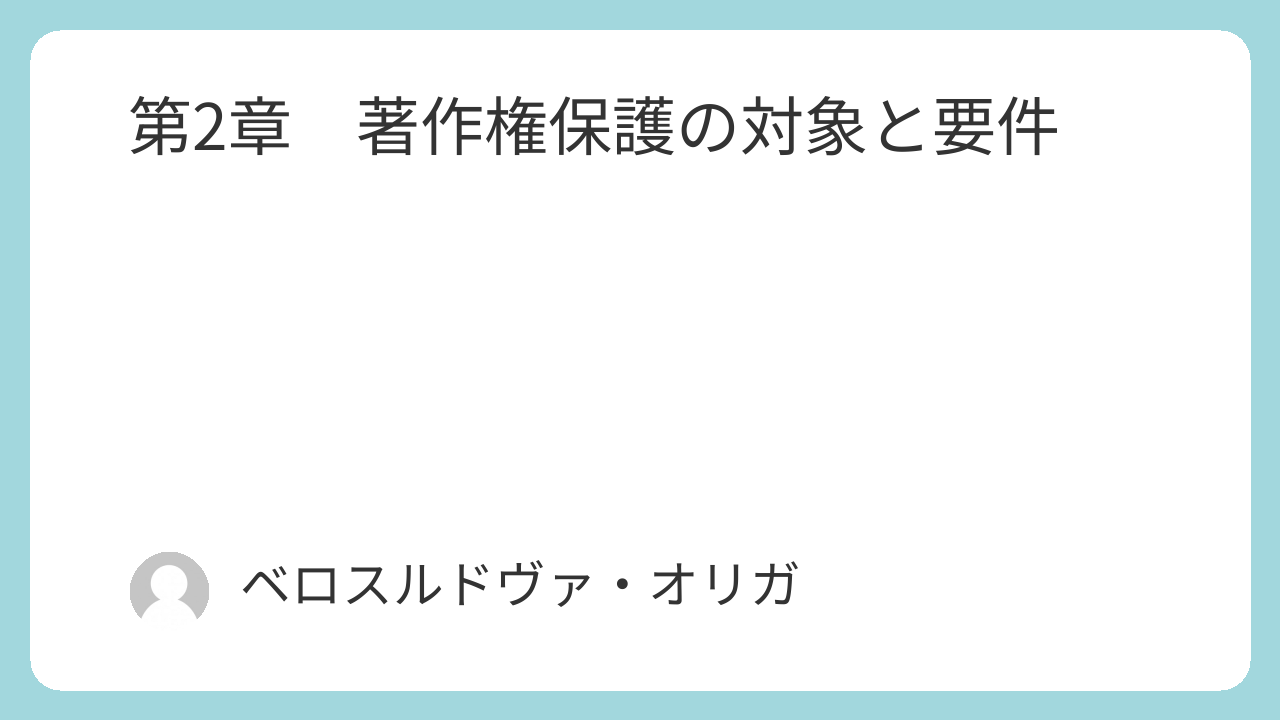アメリカ著作権法が、どのような創作物にいかなる条件で保護を与えるかは、1976年著作権法102条(a)項の条文に集約されています 。
Copyright protection subsists … in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression…
(著作権保護は、有形の表現媒体に固定された、独創的な著作者の著作物に存続する…)
この短い一文の中に、アメリカ著作権法の根幹をなす2つの絶対的な要件、「独創性(Originality)」と「有形的媒体への固定(Fixation)」が示されています。特許のような政府機関による登録や認可は不要で、著作者がこの2つの要件を満たす創作活動を行った瞬間に、著作権は自動的に発生します。
1. 保護を受けるための2大要件
要件1:有形的媒体への固定(Fixation)― アイデアから作品へ
頭の中に浮かんだメロディや口頭で語られた物語、即興のダンスは、原則としてそれ自体では著作権法の保護を受けません。アメリカ著作権法が保護するのは、形のないアイデアそのものではなく、それが具体的な「形」になったものです。この「形」にする行為が「固定(Fixation)」です。
著作権と「物」の分離
「固定」を理解する上でまず重要なのは、無形の「著作物(Work)」と有形の「物(Material Object)」を明確に区別することです。例えば、『ハリー・ポッターと賢者の石』という「著作物」は一つですが、それは書籍・電子書籍・オーディオブックといった様々な「物」に固定されます。著作権が宿るのは、個々の書籍や電子ファイルといった「物」ではなく、その背後にある無形の物語、すなわち「著作物」そのものです。したがって、あなたが書店で買った一冊の『ハリー・ポッター』の所有権はあなたにありますが、その本に収録されている物語をコピーしたり、翻訳したりする権利(著作権)は依然として権利者に留まります。
「固定」とはどういう意味か
著作権法は、「固定」を「その表現が、一時的(transitory)な期間を超えて知覚・複製・伝達することを可能にする程度に永続的・安定的であること」と定義しています。これは、ある程度の持続性が求められることを意味します。例えば、テレビスクリーンに一瞬映し出される画像や、コンピュータのRAM(ランダム・アクセス・メモリ)に一時的に読み込まれるデータは、原則としてこの「固定」の要件を満たさないと解釈されてきました。しかし、デジタル技術の発展により、この定義も揺らいできています。
- RAMコピーの論点: コンピュータでプログラムを実行したり、ウェブサイトを閲覧したりする際、データはRAMに一時的に読み込まれます。これは電源を切れば消えてしまう一時的なものですが、判例(MAI Systems Corp. v. Peak Computer Inc.)は、このRAMへの読み込みも、プログラムを知覚・複製可能な状態にするための「固定」であり、したがって「複製」に該当しうると判断しました。この判断は、デジタル時代の著作権侵害の範囲を大きく広げるものとして、多くの議論を呼びました。
- ビデオゲームの事例: ビデオゲームの画面表示はプレイヤーの操作によって刻々と変化しますが 、裁判所は、ゲームのプログラムがROM(読み出し専用メモリ)という物理的な媒体に永続的に固定されており、そこから再現されるものである以上、「固定」の要件を満たすと判断しています(Stern Electronics, Inc. v. Kaufman)。
「機械の助けを借りて」
かつて1909年法時代の判例(White-Smith Music Publishing Co. v. Apollo Co.)では、人間の目では直接読めない自動ピアノ用のピアノロールは著作物の「コピー」ではないと判断されました。しかし、1976年法はこれを明確に覆し、「機械または装置の助けを借りて」知覚できるものであればよいと定めました。この規定のおかげで、コンピュータプログラム、CDに記録された音楽、フィルムに焼き付けられた映画など、現代の多様なメディアに固定された著作物が、問題なく保護されるようになりました。
要件2:独創性(Originality)― 何が「オリジナル」か
「独創性」は、著作権保護の根源(sine qua non)であり、憲法上の要請であると連邦最高裁判所は断言しています(Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.)。しかし、この「独創性」という言葉は、特許法における「新規性(Novelty)」とは全く意味が異なります。著作権法における独創性は、2つの要素から成り立っています。
① 独立した創作(Independent Creation)
これは、他人の作品を模倣したものではなく、著作者が自ら創作したものであることを意味します。たとえ結果的に既存の作品と酷似していたとしても、それを知らずに独自に創作したのであれば、その作品は「独創性」の要件を満たします。ラーンド・ハンド判事いわく「もし仮に、キーツの『ギリシャの壺のオード』を全く知らなかった者が、魔法によって同じ詩を新たに創作したとすれば、彼は『著作者』であり、著作権を取得できる」のです。これが、偶然の一致や、同じ公知の事実から出発した結果として類似の作品が生まれた場合に、著作権侵害とならない理由です。著作権侵害を証明するためには、単に作品が似ていることだけでなく、被告が原告の作品に「依拠(copying)」したことを証明しなければなりません。
② 僅かな創造性(A Modicum of Creativity)
独立して創作されたことに加え、その作品には最低限の創造性がなければなりません。しかし、そのハードルは極めて低いものです。裁判所は、芸術的な価値や審美的なメリットを一切問うべきではないという原則を確立しています(Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.)。オリバー・ウェンデル・ホームズ判事は、「法律の訓練しか受けていない者が、絵画の価値について最終的な判断者となるのは危険な試みだ」と述べ、裁判官の芸術的評価が著作物性を左右することを戒めました。
このため、ケーキの箱のラベルデザインやプラスチック製の造花といった単純なものでも、僅かながら著作者の選択や判断が介在していれば、この要件を満たすとされてきました。一方で、ごくありふれた言葉や短いフレーズ(例:「I Love You」)、スローガン、タイトル、ありふれた幾何学模様などは、この僅かな創造性の基準に達しないとして、保護の対象外とされています。
2. 保護される著作物のカテゴリー
1976年著作権法102条(a)項は、保護の対象となる「著作者の著作物(works of authorship)」の例として、以下の8つのカテゴリーを挙げています。これらはあくまで例示列挙であり、限定列挙ではありません。テクノロジーの進化によって将来生まれるであろう新たな表現形式にも対応できるよう、柔軟な解釈が許されています。
- 文学の著作物(Literary Works)
- 音楽の著作物(Musical Works, including any accompanying words)
- 演劇の著作物(Dramatic Works, including any accompanying music)
- 舞踊・無言劇の著作物(Pantomimes and Choreographic Works)
- 美術・グラフィック・彫刻の著作物(Pictorial, Graphic, and Sculptural Works)
- 映画その他の視聴覚著作物(Motion Pictures and Other Audiovisual Works)
- 録音物(Sound Recordings)
- 建築の著作物(Architectural Works)
これらのカテゴリーは互いに重なり合うことがあります。例えば、歌の歌詞は「文学的著作物」でもあり、「音楽的著作物」の一部でもあります。ここで重要なのは、録音物(Sound Recordings)と、それに収録されている音楽的著作物(Musical Works)とを明確に区別することです。例えば、あるCDには、作曲家が創作した楽曲という「音楽的著作物」と、それを歌手や演奏家がパフォーマンスし、プロデューサーが録音・編集した「録音物」という、2つの異なる著作権が存在します。両者の権利内容は異なるため、この区別は極めて重要です。
3. 保護されないもの ― パブリックドメイン
著作権法は、特定の表現を保護する一方で、社会の共有財産として誰もが自由に利用できるべき領域を確保しています。その境界線を画するのが、102条(b)項に定められた「アイデアと表現の二分論(Idea-Expression Dichotomy)」です 。
In no case does copyright protection … extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery…
(いかなる場合も、著作権保護は、いかなるアイデア、手続き、プロセス、システム、操作方法、コンセプト、原理、または発見にも及ばない…)
この原則は、著作権が保護するのはアイデアの具体的な「表現(Expression)」であって、その根底にある「アイデア(Idea)」そのものではないという考え方です。例えば、「敵対する家系の若い男女が恋に落ち、悲劇的な結末を迎える」というアイデアは誰でも自由に利用できますが、シェイクスピアがそれを『ロミオとジュリエット』という戯曲で具体的に表現したセリフや場面構成は保護されます。もしアイデア自体を独占させてしまえば、後の創作活動が著しく阻害され、文化の発展という著作権法の究極的な目的が損なわれてしまうからです。
この原則から、以下のものは著作権で保護されないことが導かれます。
- 事実(Facts)と歴史的調査: 事実は誰かによって「創造」されるものではなく、「発見」されるものです。したがって、歴史上の出来事・科学的なデータ・ニュース記事で報じられる事実そのものには独創性がなく著作権は及びません。たとえ膨大な時間と労力をかけて歴史的事実を発掘したとしても、その努力(いわゆる「額の汗(sweat of the brow)」)自体は保護の対象とはなりません。この点を明確にしたのが、連邦最高裁で電話帳の著作物性が争われた
Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.事件です。この判決は、電話帳の氏名・住所・電話番号のリストは単なる事実の集合体であり、それをアルファベット順に並べるというありふれた方法には創造性がないとして、著作権保護を否定しました。 - システムと操作方法: ある目的を達成するための手順や方法は、アイデアの領域に属します。この原則を確立したのが、19世紀の
Baker v. Selden事件です。この事件では、独自の簿記システムを解説した書籍に付いていた帳簿フォームが争われました。最高裁は、その帳簿フォームはシステムを使用するために不可欠なものであり、フォームの表現を保護することは、その根底にある簿記システムというアイデア自体を独占させることに等しいとして、著作権保護を認めませんでした。 - マージャー・ドクトリン(Merger Doctrine): アイデアと表現の二分論の延長線上にあるのが、この法理です。あるアイデアを表現する方法が一つしかなかったり極めて限られている場合、そのアイデアと表現は「融合(merge)」していると見なされ、表現部分も保護の対象外となります。例えば、コンテストの応募ルールやゲームの基本的なルールなどがこれに該当します。
- 合衆国政府の著作物(U.S. Government Works): 連邦政府の職員が職務上作成した著作物は、法律(105条)により著作権保護の対象外とされ、作成された時点からパブリックドメインとなります。これは、国民が税金で賄われた政府の活動成果に自由にアクセスできるようにするための重要な政策です。
4. 二次的著作物と編集著作物
著作権法は、完全にゼロから創作されたものだけでなく、既存の著作物やデータに基づいて創作された新しい著作物も保護の対象とします。これらは二次的著作物(Derivative Works)と編集著作物(Compilations)と呼ばれます。
二次的著作物(Derivative Works)
これは、既存の著作物を「改変、変形、または翻案(recast, transformed, or adapted)」して創作された新しい著作物を指します。具体例としては、小説の映画化・翻訳・楽曲の編曲などが挙げられます。二次的著作物の著作権は、新たに追加された独創的な部分にのみ及びます。元の著作物(基礎著作物)の権利には何ら影響を与えません。したがって、二次的著作物を創作するには、基礎著作物がパブリックドメインにない限り、その著作権者の許諾を得る必要があります。
編集著作物(Compilations)
これは、既存の素材やデータを「収集し、組み立て(collection and assembling)」て創作された著作物です。二次的著作物と異なり、個々の素材を改変することは必ずしも伴いません。保護の核心は、素材の「選択(selection)、調整(coordination)、または配列(arrangement)」に現れる独創性です。
- 例: 詩のアンソロジー、百科事典、記事を集めた雑誌、データベース
ここでもFeist判決が重要な基準となります。単に全てのデータを網羅し、アルファベット順や年代順といったありふれた方法で並べただけでは、独創性があるとは言えません。例えば、「20世紀アメリカの代表的な短編小説50選」といったアンソロジーであれば、どの作品を「代表的」として選択し、どのようなテーマや順序で配列するかに編集者の独創的な判断が介在するため、編集著作物として保護され得ます。その場合でも、保護されるのはあくまでその選択と配列の仕方であり、収録されている個々の短編小説そのものではありません。