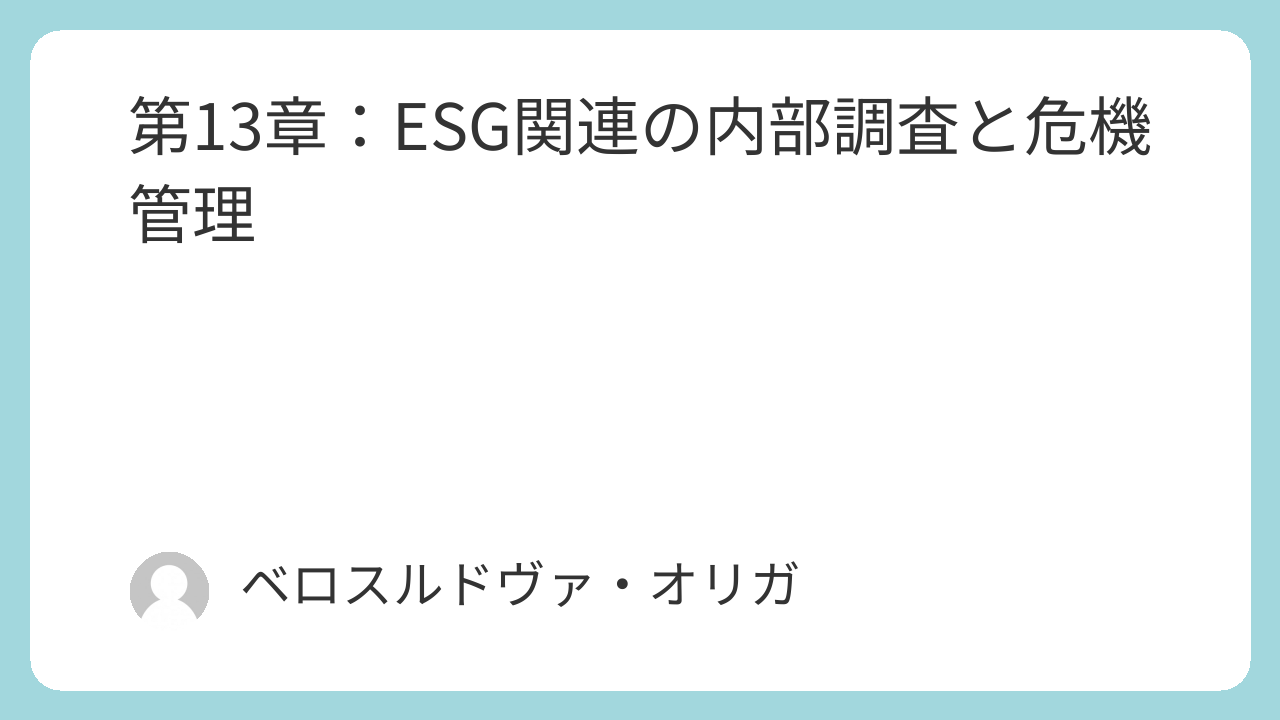ESGが企業経営の表舞台に立つにつれ、それに伴う不正行為やコンプライアンス違反の疑惑もまた、白日の下に晒されるようになりました。グリーンウォッシング、職場におけるハラスメント、サプライチェーンでの人権侵害、データプライバシーの侵害といったESG関連の疑惑は、もはや単なる評判の問題ではありません。それらは、米国証券取引委員会(SEC)のような強力な規制当局による執行措置、株主による代表訴訟、そして高額な報奨金を伴う内部告発へと発展し、企業の存続そのものを脅かす経営上の重大な危機となりえます。
2021年3月、SECは執行部門内に「気候・ESGタスクフォース」を設置しました。このタスクフォースは、企業のESGに関する開示の不備や虚偽記載、投資ファンドのグリーンウォッシングなどを積極的に摘発することを目的としており、すでにBNYメロンや鉱業大手ヴァーレ社などに対する執行措置を開始しています。
このような厳しい監視の目が光る中、ESG関連の疑惑が浮上した際に、企業がその真偽を究明し、適切に対処するために不可欠なプロセスが「内部調査(Internal Investigation)」です。内部調査は、問題を早期に発見し、被害の拡大を防ぎ、当局への協力姿勢を示すことで制裁を軽減するための、重要な危機管理ツールです。しかし、ESG関連の調査は、その対象が広範で専門的、かつ社会的に非常にセンシティブであるため、伝統的な会計不正調査とは異なる特有の難しさを伴います。
1. 調査の開始と弁護士・依頼者間秘匿特権の確保
ESG関連の内部調査は、内部通報・規制当局からの問い合わせ・訴訟の提起・メディアによる報道等、様々なきっかけで開始されます。疑惑が浮上したら、企業は直ちに初動対応に着手しなければなりません。その最初の、そして最も重要なステップが、弁護士を関与させ、調査全体を弁護士・依頼者間秘匿特権(attorney-client privilege)およびワーク・プロダクト主義(attorney work-product doctrine)の下に置くことです 。
秘匿特権が確保されていれば、弁護士と会社(依頼者)との間の法的助言を目的としたコミュニケーションや、弁護士が訴訟を予期して作成した資料(インタビューメモ、分析レポートなど)は、原則として外部(規制当局や訴訟の相手方)への開示を強制されません。これにより、企業は外部からの圧力を遮断した安全な空間で、事実関係を徹底的に調査し、率直な議論を通じて最善の対応策を検討することが可能になります。
社内弁護士か、外部弁護士か
調査を主導するのが社内弁護士か、外部の法律事務所かという判断は、事案の性質によって決まります。日常的なコンプライアンス違反であれば、社内事情に精通した社内弁護士が迅速に対応できる場合もあります 。しかし、ESG関連の調査は、以下のような理由から、外部弁護士を起用することが推奨されます。
- 客観性と独立性: 経営幹部が関与している可能性のある重大な事案では、社内弁護士は独立性を疑われる可能性があります。外部弁護士による調査は、その客観性から、規制当局や裁判所に対してより高い信頼性を与えます 。
- 秘匿特権の確保: 社内弁護士は法務とビジネスの両方の役割を担うことが多いため、その活動が「法的助言」ではなく「ビジネス上の助言」と見なされ、秘匿特権が否定されるリスクがあります。外部弁護士を起用することで、調査の主たる目的が法的助言の提供にあることが明確になります。
- 専門知識: ESG関連法規は複雑で、急速に変化しています。気候科学、人権デューデリジェンス、データプライバシーといった分野は、高度な専門知識を必要とします 。多くの大手法律事務所は、これらの分野を専門とする弁護士や専門家を擁しており、的確な調査と分析が可能です。
調査の監督は、通常、会社の法務部長(General Counsel)が行いますが、取締役や上級役員の不正行為が疑われる場合には、取締役会内に独立した取締役のみで構成される特別委員会を設置し、その委員会が外部弁護士を直接雇用して調査を監督するのが適切です。
2. 調査の実施:証拠保全から聞き取り調査まで
調査を開始する決定が下されたら、法務部門は直ちに証拠保全に着手しなければなりません 。
① 文書保存通知(Document Hold Notice)の発行
まず、関連する可能性のある全ての従業員に対し、本件に関する文書・データその他の情報を破棄しないよう命じる「文書保存通知」を発行します。この通知は、電子メールやチャット、テキストメッセージ、個人のデバイスに保存された業務関連データ等、あらゆる形式の情報を対象とすることを明確にしなければなりません。また、通常の文書破棄サイクルを停止する「サイレント・ホールド」も同時に実施します。証拠の意図的な破棄は、司法妨害として極めて深刻な刑事罰の対象となりえます。
② 証拠の収集とレビュー
次に、IT部門や外部のeディスカバリー専門業者と協力し、関連する電子データを収集・保全します。収集されたデータは、レビュー用のプラットフォームに搭載され、弁護士チームによって内容が精査されます。この過程で、秘匿特権の対象となる文書を特定し、ラベリングする作業も同時に行われます。
③ 聞き取り調査(Witness Interview)の実施
聞き取り調査は、内部調査の核心です。調査担当の弁護士は、対象者へのインタビューを通じて、文書だけでは分からない事実関係や背景、動機などを明らかにしてきます。
- Upjohn警告(Upjohn Warning): 聞き取り調査を開始する前に、弁護士は必ず対象者に対して、いわゆる「Upjohn警告」を行わなければなりません 。これは、以下の点を明確に伝えるものです。
- 弁護士は会社を代理しており、従業員個人を代理しているわけではないこと
- したがって、インタビューにおける秘匿特権は会社に帰属し、従業員個人に帰属するものではないこと
- 会社は、その裁量により、秘匿特権を放棄し、インタビューの内容を政府機関などの第三者に開示する可能性があること
この警告は、従業員が自らの法的立場を誤解することなく、誠実に調査に協力するために不可欠です。
- 守秘義務と内部告発者の権利: 会社は、調査の完全性を保つために、従業員に対して調査内容に関する守秘義務を課すことができます。しかし、その際に、政府機関への通報を妨げるような表現を用いてはなりません。SECは、従業員が当局と話す前に会社の許可を得るよう求める守秘義務契約が、内部告発を妨害する違法な行為であるとして、企業に制裁を科した事例があります。
3. 最大の難関:内部告発者への対応
ESG関連の調査の多くは、内部告発者(Whistleblower)からの通報によって始まります。ドッド=フランク法に基づき設立されたSECの内部告発者報奨金プログラムは、100万ドル以上の制裁金に繋がる重要情報を提供した告発者に対し、回収額の10%から30%という高額な報奨金を支払います。この強力なインセンティブにより、SECには毎年記録的な数の通報が寄せられており、その多くがESG関連の疑惑に関するものです。
内部告発者の存在は、内部調査を極めてデリケートなものにします。対応を誤れば、社内で解決できたはずの問題が、大規模な政府調査へと発展し、企業は深刻なダメージを受けることになります。
内部告発者対応のベストプラクティス
- 迅速な受理と初期対応: 告発を受け取ったら、可能な限り即日、受理したことを本人に通知します。告発を真摯に受け止めているという姿勢を示すことが、信頼関係構築の第一歩です。
- 最優先での聞き取り調査: 内部告発者は、調査対象者の中で真っ先に聞き取りを行うべきです。これにより、告発者が当局に駆け込む前に、会社として事実関係を把握し、調査の主導権を握ることができます。
- 報復行為の絶対的禁止: 内部告発者に対するいかなる報復行為(解雇、降格、嫌がらせなど)も、法律で固く禁じられています 。調査の過程で、告発者の匿名性を可能な限り保護し、報復を禁止する社内方針を全従業員に周知徹底する必要があります。
- 継続的なコミュニケーション: 調査の進捗状況や最終的な結果について、守秘義務の範囲内で、告発者本人にフィードバックを行うことが望ましいです。
多くの告発者は、最初から会社を陥れようとしているわけではありません。彼らは、社内の不正を正したいという倫理観から行動していることが多いのです。彼らが当局に向かうのは、社内の報告チャネルが機能せず、「自分の訴えが無視された」と感じたときです。したがって、信頼性のある内部通報制度を構築し、すべての通報を公平かつ迅速に調査する体制を整えることこそが、最大の防御策なのです。
4. 調査結果の報告と是正措置
調査が完了したら、その結果と勧告を、調査を監督する取締役会や特別委員会に報告します。
書面報告か、口頭報告か
調査結果を書面報告書としてまとめるか、口頭で報告するかは、慎重な戦略的判断を要します。詳細な書面報告書は、事実関係と分析を明確に記録し、取締役会が情報に基づいた意思決定を行う上で有用です。しかし、この報告書は、万が一秘匿特権が放棄された場合、政府調査官や原告側弁護士にとって、企業の弱点を詳細に記した「ロードマップ」となりえます。そのため、多くの弁護士は、詳細な書面報告書の作成を避け、主要な発見事項と勧告をスライドにまとめた上で、口頭での報告を好む傾向があります。
是正措置と開示統制の強化
内部調査の最終目的は、過去の過ちを正し、将来の再発を防ぐことです。調査で不正行為や内部統制の不備が発見された場合、取締役会は、関係者の懲戒処分・業務プロセスの改善・コンプライアンス研修の強化といった、具体的な是正措置を速やかに実行しなければなりません。
さらに重要なのが、開示統制および手続(Disclosure Controls and Procedures)の見直しです。SECがActivision Blizzard社に対して下した措置は、この点に関する重要な教訓となります。同社は、広範な従業員からのハラスメントに関する苦情を収集・評価し、それが開示すべき重要なリスクであるかどうかを判断するための仕組みが欠如していたとして、開示統制違反を問われました。
この事例は、ESG関連のリスク情報が、法務・財務部門と適切に共有され、経営陣と取締役会に報告され、最終的に投資家への開示の要否が検討されるという、一連の情報フローを確立することの重要性を示しています。