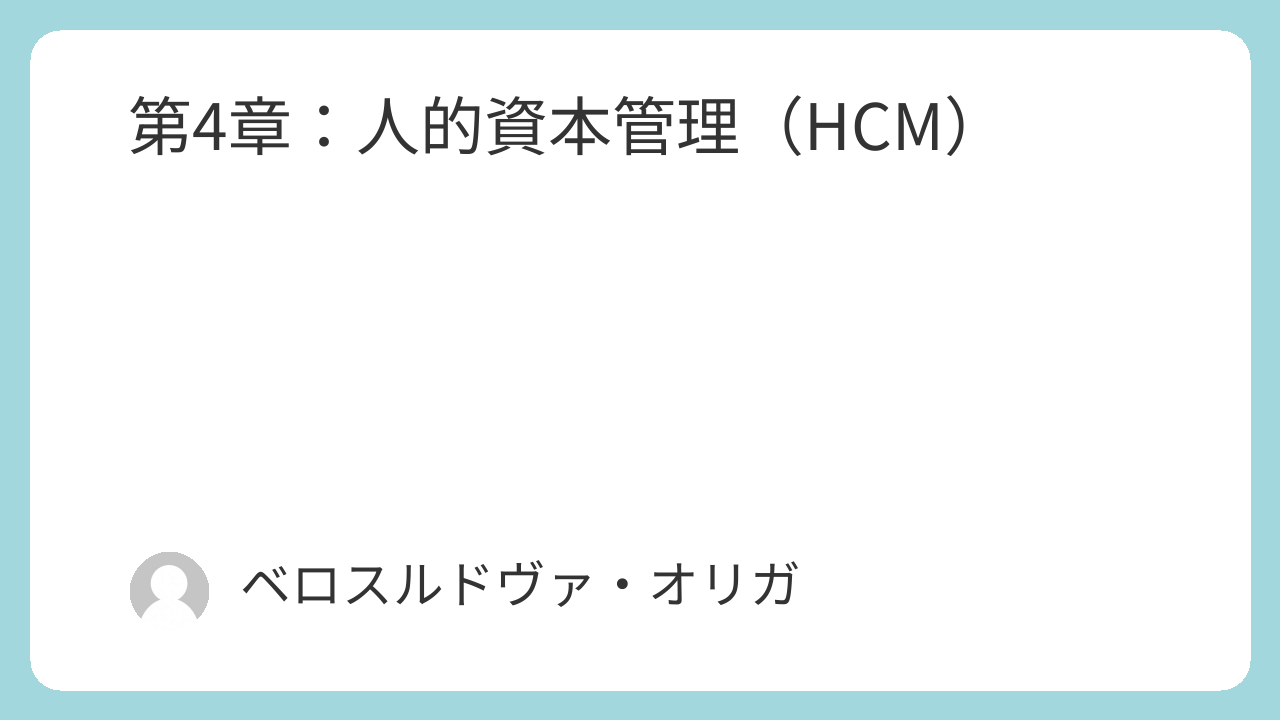ESGの議論において、「環境(E)」と「ガバナンス(G)」が規制や制度の側面から注目を集める一方で、「社会(S)」の柱の中核をなす「人的資本管理(Human Capital Management – HCM)」の重要性が急速に高まっています。HCMとは、従業員を単なるコストではなく、事業のパフォーマンスを左右する重要な「資産」と捉え、その価値を最大化するための戦略的な投資と管理を行う経営手法です。報酬や福利厚生、心身の健康、そして労働組合を通じた従業員の声の尊重等、その範囲は多岐にわたります。
かつては人事部門の専門領域と見なされていたHCMは、今や投資家が企業価値を評価する上での重要な指標となりました。ブラックロックのラリー・フィンクCEOが年次書簡で企業に従業員への投資と訓練の重要性を説いて以来、HCMはESG投資のメインストリームへと躍り出ました。そして、米国証券取引委員会(SEC)が人的資本に関する情報開示を義務化したことで、その流れは決定的となりました。
1. SECによる人的資本開示の義務化
アメリカにおけるHCMの議論を加速させた最大の要因は、SECによる情報開示規則の改正です。2020年11月、SECはレギュレーションS-Kの改正を施行し、上場企業に対して、年次報告書(Form 10-K)の中で「自社の人的資本に関する資源(human capital resources)」についての開示を義務付けました。
この規則は、企業に対し、「事業全体を理解する上で重要(material)である限りにおいて」、従業員数に加え、経営陣が事業を管理する上で重視している人的資本に関する指標や目標を開示することを求めています。SECが例として挙げる指標には、従業員の育成、惹きつけ(attraction)、定着(retention)に関するものが含まれますが、具体的な開示項目は定められておらず、各企業が自社の事業内容や労働力の性質に応じて重要と判断する情報を開示するという、原則ベース(principles-based)のアプローチが採られています。
この柔軟なアプローチは、企業に裁量を与える一方で、何をどこまで開示するべきかという新たな課題を生みました。多くの企業は、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)に関する指標、従業員の離職率、安全衛生に関するデータ、研修プログラムなどを開示していますが、その内容や粒度は企業によって大きく異なります。投資家からは、より比較可能性の高い定量的な情報の開示を求める声が依然として強く、SECが将来的にさらに具体的な開示要件を導入する可能性は高いです。この開示義務化は、企業に対し、自社のHCM戦略を体系的に整理し、その有効性を客観的なデータで示すことを迫るものであり、法務・コンプライアンス部門は、開示内容の正確性と網羅性を担保する上で重要な役割を担います。
2. 報酬制度の公平性という課題
HCMの中核をなすのが、従業員への報酬です。報酬は、人材の獲得・定着、業績目標達成へのインセンティブ、そして企業文化の維持といった多岐にわたる機能を持っています。ESGの文脈では、特に以下の2つの側面から、報酬制度のあり方が厳しく問われています。
役員報酬と従業員報酬の格差
近年、企業のCEOと一般従業員の報酬格差が、社会的な公正性の観点から大きな問題となっています。この問題に対応するため、ドッド=フランク法に基づき、SECは上場企業に対して、CEOの年間総報酬と従業員の年間総報酬の中央値との比率(Pay Ratio)の開示を義務付けています 。
この開示により、投資家・従業員・社会全体に対し、企業の報酬分配に関する姿勢を明確に示します。極端に高い報酬比率は、従業員の士気を低下させるだけでなく、企業の優先順位が短期的な株主利益に偏っているとの批判を招き、レピュテーションリスクに繋がります。
さらに、2022年8月には、SECは「業績と連動した報酬(Pay Versus Performance)」に関する新たな開示規則を採択しました。これは、役員に「実際に支払われた報酬」と、自社の株主総利回り(TSR)や同業他社のTSR、純利益といった業績指標との関係性を、明確な表形式で開示することを求めるものです。これらの規則は、役員報酬の決定プロセスにおける透明性と客観性を高め、取締役会の報酬委員会に対して、より厳しい説明責任を課すものです。
ESG指標と役員報酬の連動
企業のESGへのコミットメントを確実なものにするため、役員報酬のインセンティブプランにESG関連の目標達成度を組み込む動きが広がっています。S&P500企業では、すでに半数以上が何らかの形でESG指標を報酬決定に連動させています。
最も一般的に用いられるのは、DE&Iに関する目標(例:女性やマイノリティの管理職比率向上)、人材育成や離職率の改善、従業員の安全衛生に関する目標等、HCM関連の指標です。気候変動関連では、GHG排出削減目標の達成度が用いられることもあります。
ESG指標を報酬に連動させることは、経営陣に対してESG目標達成への強力なインセンティブを与える一方で、いくつかの課題も存在します。指標の選定が適切でなかったり、目標設定が低かったりすると、かえってグリーンウォッシング(あるいはソーシャルウォッシング)との批判を招きかねません。法務部門は、報酬委員会と連携し、報酬プランの設計が企業の長期的なESG戦略と整合しており、かつ、開示内容が投資家を誤解させることのないよう、慎重に検証する必要があります。
3. 従業員のウェルビーイングと福利厚生
従業員のウェルビーイングは、生産性やエンゲージメントに直結する重要な経営課題です。特に、新型コロナウイルスのパンデミックを経て、企業は従業員のメンタルヘルスに対して、これまで以上に大きな責任を負うようになりました。多くの企業が、従業員支援プログラム(EAP)の拡充やカウンセリングサービスの提供等メンタルヘルス対策を強化しています。
社会問題と福利厚生制度
近年、企業は福利厚生制度を通じて、政治的・社会的に分断の激しい問題へのスタンスを示すことを、従業員や社会から期待されるようになっています。その最も顕著な例が、2022年の連邦最高裁判決(Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization)による人工妊娠中絶の権利の否定です 。
この判決を受け、多くの先進的な大企業は、中絶が制限される州に住む従業員が、合法的な州で医療サービスを受けるための交通費や宿泊費を福利厚生として補償する方針を相次いで発表しました。これは、企業が従業員の健康と選択の自由を支援するという明確なメッセージであると同時に、優秀な人材を惹きつけ、維持するための戦略的な判断でもありました。しかし、こうした対応は、保守的な州政府や政治家からの反発を招くリスクも伴います。企業は、自社の価値観・従業員の構成・事業を展開する地域の政治的状況などを総合的に勘案し、慎重な意思決定を迫られます。
退職給付制度におけるESG投資
従業員のウェルビーイングは、退職後の生活設計にも及びます。アメリカの企業年金制度の中心である401(k)プランにおいて、ESG投資をどのように扱うかは、長年の法的・政治的な論争の的となってきました。
労働省(DOL)は、エリサ法(ERISA)に基づき、年金プランの受託者が加入者の利益のためにのみ行動するよう、厳格な忠実義務と注意義務を課しています。この義務とESG投資との関係について、DOLの解釈は政権交代のたびに揺れ動いてきました。トランプ政権下の2020年の規則では、受託者は「金銭的要因(pecuniary factors)」のみに基づいて投資判断を行うべきだとされ、ESG要因の考慮は厳しく制限されました。
しかし、バイデン政権下の2022年12月に公表された最終規則では、この方針が転換されました。新規則は、ESG要因が「リスク・リターンの分析に重要である」と判断される場合には、受託者がそれを考慮することを明確に許可しました。ただし、受託者が加入者の退職所得の確保という主目的を犠牲にして、ESGという副次的な便益を追求することは依然として禁じられています。
4. 労働組合との関係と従業員の健康・安全
労働組合の再活性化
アメリカにおける労働組合の組織率は歴史的に低い水準にありましたが、近年、スターバックスやアマゾンといった巨大企業で、新たな組合結成の動きが活発化しています。バイデン政権が明確に組合支持の姿勢を打ち出していることも、この流れを後押ししています。
全国労働関係法(NLRA)は、従業員が組合を結成し団体交渉を行う権利を保障しており、使用者がこれらの権利を妨害することを禁じています。企業は、組合結成の動きに対して、脅迫や差別といった不当労働行為(ULP)と見なされることのないよう慎重な対応が求められます。
従業員の健康と安全
従業員の物理的な健康と安全の確保は、企業の最も基本的な責任の一つです。労働安全衛生庁(OSHA)は、職場における安全基準を定め、企業にその遵守を義務付けています 。これには、危険な化学物質からの保護、安全な機械の使用、必要な保護具の提供などが含まれます 。
また、ワクチン接種の義務化は、障害を持つアメリカ人法(ADA)や公民権法第7編(宗教上の理由)との関係で、複雑な法的問題を生みました。企業は、ワクチン接種を拒否する従業員に対し、それが医療上または真摯な宗教上の信念に基づくものである場合、「過度の負担(undue hardship)」とならない範囲で、合理的配慮(reasonable accommodation)を提供する義務を負います。