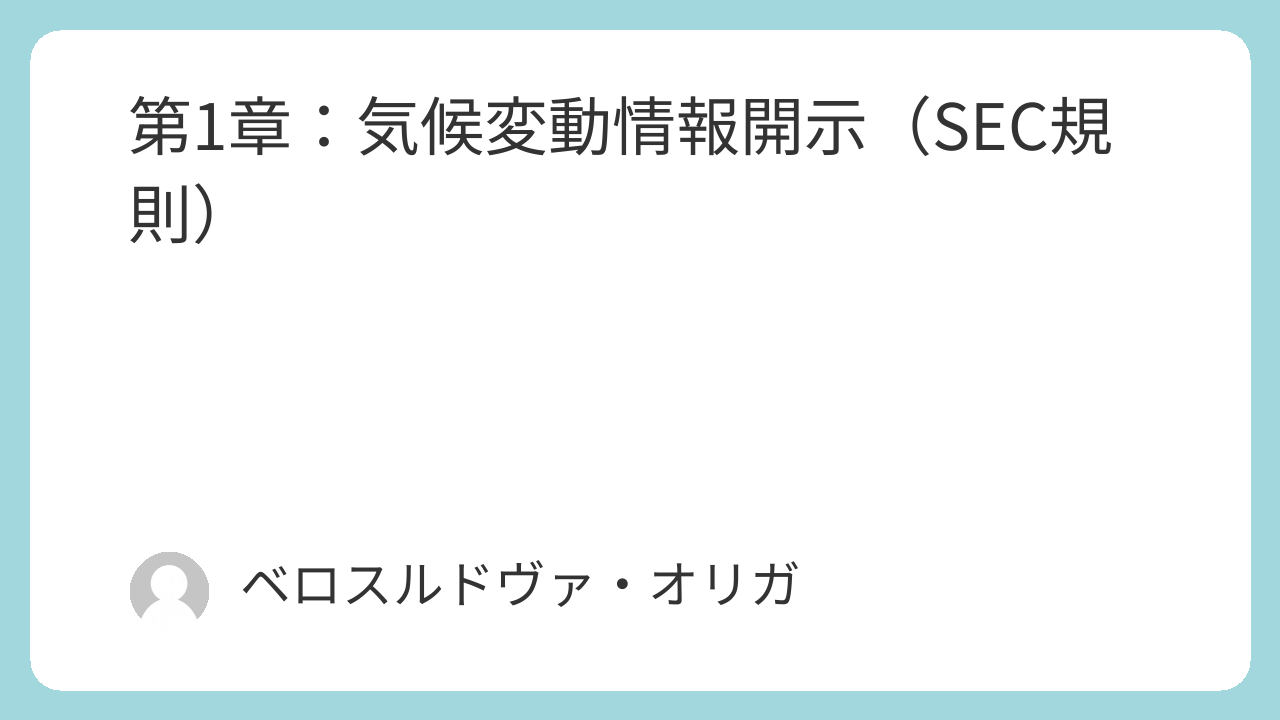ESGの3本柱の中で、アメリカの企業法務に最も大きな影響をもたらしているのが「環境(Environment)」、とりわけ気候変動に関する情報開示です。かつては一部の先進的な企業が任意で行うサステナビリティ報告の一部であった気候関連情報は、今や投資家の投資判断・企業の資金調達・取締役の法的責任を左右する、経営とガバナンスの根幹に関わる重要情報になりました。この変革の立役者が米国証券取引委員会(SEC)です。
1. SECによる気候関連開示規則の概要と目的
既存の開示制度の限界から、SECは気候変動に関する開示の包括的なルール作りへと乗り出しました。SECは2010年に気候変動関連の開示に関するガイダンスを公表していましたが、これはあくまで既存の規則(レギュレーションS-K)の解釈指針に過ぎず、開示の具体的内容や形式は各企業の判断に委ねられていました。その結果、投資家が最も重視する情報の「比較可能性」と「信頼性」が著しく欠如する事態を招きました。企業のサステナビリティ報告書(CSRレポート)で語られる華々しい目標と、SECへの提出書類(Form 10-Kなど)におけるリスク開示との間に乖離が見られるケースも少なくありませんでした。
このような状況下で、機関投資家からの「意思決定に有用な信頼性と比較可能性のある情報」を求める声は日に日に高まっていきました。彼らは、気候変動がもたらすリスクが、もはや倫理的な問題ではなく、投資ポートフォリオの長期的なリターンを毀損しかねない重大な財務リスクであると明確に認識していたのです。この市場からの強い要請に応える形で、SECはついに包括的かつ具体的な開示を義務付ける規則の策定へと踏み切りました。
約510ページに及ぶ本規則案は、国際的に広く参照されている気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言を色濃く反映しており、その内容は極めて野心的かつ広範にわたります。その核となるのが、気候関連のリスクと機会に関する情報を、企業の年次報告書(Form 10-K)や登録届出書において、一貫性のある独立したセクションで開示させ、さらにその財務的影響を監査済みの財務諸表の注記として記載させることです。これは、気候関連情報を、「別冊」のサステナビリティ報告ではなく投資家が最も信頼を置く財務報告の枠組みへと統合するものでした。
本規則案が企業に求める開示内容は、大きく分けて以下の5つの柱から構成されます。
- ガバナンス: 取締役会および経営陣による気候関連リスクの監視・管理体制
- 戦略: 気候関連リスク・機会が事業、戦略、見通しに与える影響
- リスク管理: 気候関連リスクを特定、評価、管理するためのプロセス
- GHG排出量: スコープ1・2・3のGHG排出量データ
- 財務諸表指標: 気候関連の財務的影響、支出、仮定に関する指標
以下、各項目について解説します。
2. GHG(温室効果ガス)排出量開示:スコープ1・2・3の算定と法的課題
本規則案の中で企業にとって負担が大きいのが、GHG排出量の開示義務です。GHGプロトコルで定義されている通り、排出量は以下の3つの「スコープ」に分類されます。
- スコープ1: 事業者自らによるGHGの直接排出(例:工場での燃料燃焼、社用車の利用)
- スコープ2: 他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出
- スコープ3: 上記以外の間接排出で、企業のバリューチェーン(サプライチェーンや製品の使用・廃棄など)全体で発生する排出
本規則案は、すべての上場企業に対し、スコープ1とスコープ2の排出量を開示することを義務付けています。これは、企業の直接的な事業活動から生じる環境負荷を明確にするためです。
さらに本規則案は、一歩踏み込んでスコープ3の開示にも言及しています。具体的には、スコープ3排出量が「重大(material)」である場合又は企業がスコープ3を含むGHG削減目標を設定している場合に開示を義務付けるというものです。金融機関にとっては、投融資先の排出量(ファイナンスド・エミッション)がスコープ3に含まれるため、大きな影響を受けます。
スコープ3の算定は、自社の管理外にある無数のサプライヤーや顧客からデータを収集する必要があるため、極めて困難でコストがかかります。このことに配慮し、SECはスコープ3の開示義務について、小規模報告企業(Smaller Reporting Companies)を適用除外とし、また、開示された情報が誠実かつ合理的な根拠に基づいていれば虚偽記載とは見なされないセーフハーバー規定を設けています。
信頼性を担保するため、本規則案はスコープ1と2の排出量データに対して、第三者機関による保証(attestation)を段階的に義務付けています 。これは、排出量データが財務情報と同等の信頼性を持つべきであるという考えによります。
3. 気候関連リスクの開示:物理的リスクとトランジション(移行)リスク
本規則案は、企業が直面する気候関連リスクを「物理的リスク」と「トランジション(移行)リスク」の2つに大別し、それらが企業の事業・財務状況に与える「重要な影響」の開示を求めています。
物理的リスクとは、気候変動がもたらす物理的な事象によるリスクです。これには、ハリケーン・洪水・山火事・海面上昇といった急性リスクと、干ばつ・平均気温の上昇・水資源の枯渇といった慢性リスクが含まれます。企業は、これらのリスクに晒されている事業拠点や資産の物理的な所在地を特定し、その財務的影響を定量的に開示する必要があります。
移行リスクとは、低炭素社会への移行に伴って生じるリスクです。具体的には、以下のようなものが含まれます。
- 政策・法規制リスク: 炭素税の導入、排出量規制の強化等
- 技術リスク: 低炭素技術への移行の遅れや、既存技術の陳腐化
- 市場リスク: 省エネ製品への消費者嗜好の変化、ESGを重視する投資家からの資金引き揚げ
- レピュテーションリスク: 環境への取り組みが不十分と見なされることによるブランド価値の毀損
企業は、これらのリスクが自社の戦略やビジネスモデルにどのような影響を与えるかを、短期・中期・長期の時間軸で分析し開示することが求められます。また、リスク対応策として「移行計画(Transition Plan)」を策定している場合には、その詳細な内容も開示対象となります。
4. 財務諸表への影響と監査法人の役割
本規則案の画期的な点は、気候関連のリスクと機会が財務に与える影響を、監査済み財務諸表に注記として記載することを義務付けたことです。これにより、気候関連情報が企業の公式な財務報告の不可分の一部となります。
具体的には、以下の3種類の指標の開示が求められます。
- 財務的影響指標: 気候関連の事象(物理的リスク)や移行活動が、貸借対照表や損益計算書の各勘定科目に与える影響額。個々の影響額が当該勘定科目の1%以上になる場合に開示が必要です。
- 支出指標: 物理的リスクや移行リスクを低減するための支出額(費用計上分と資産計上分の両方)
- 財務上の見積り: 気候関連リスクが資産の減損・引当金の算定・資産の耐用年数といった財務諸表上の見積りに与える影響
これらの情報が監査の対象となることで、その信頼性は飛躍的に向上します。監査法人は、企業の気候関連リスク評価の妥当性や、財務への影響額の算定プロセスの適切性を検証する新たな役割を担うことになります。
5. SEC規則に対する批判
本規則案は、公表以来、産業界や一部の政治家から「SECの権限逸脱である」「過度に規範的でコストがかかりすぎる」といった強い批判に晒されてきました。特に、共和党系の州司法長官らは、本規則案が「重要問題の原則(Major Questions Doctrine)」に抵触する可能性を指摘しています。これは、議会が明確な権限を与えていないにもかかわらず、行政機関が経済的・政治的に重要な問題を独自に規制することは許されないという連邦最高裁が示した原則です。
しかし、たとえ規則の内容が修正されたとしても、「気候変動情報の開示を標準化し義務化する」という大原則が揺らぐことはないでしょう。EUでは既に企業サステナビリティ報告指令(CSRD)が施行され、「ダブルマテリアリティ」というさらに踏み込んだ概念に基づく開示が始まっています。