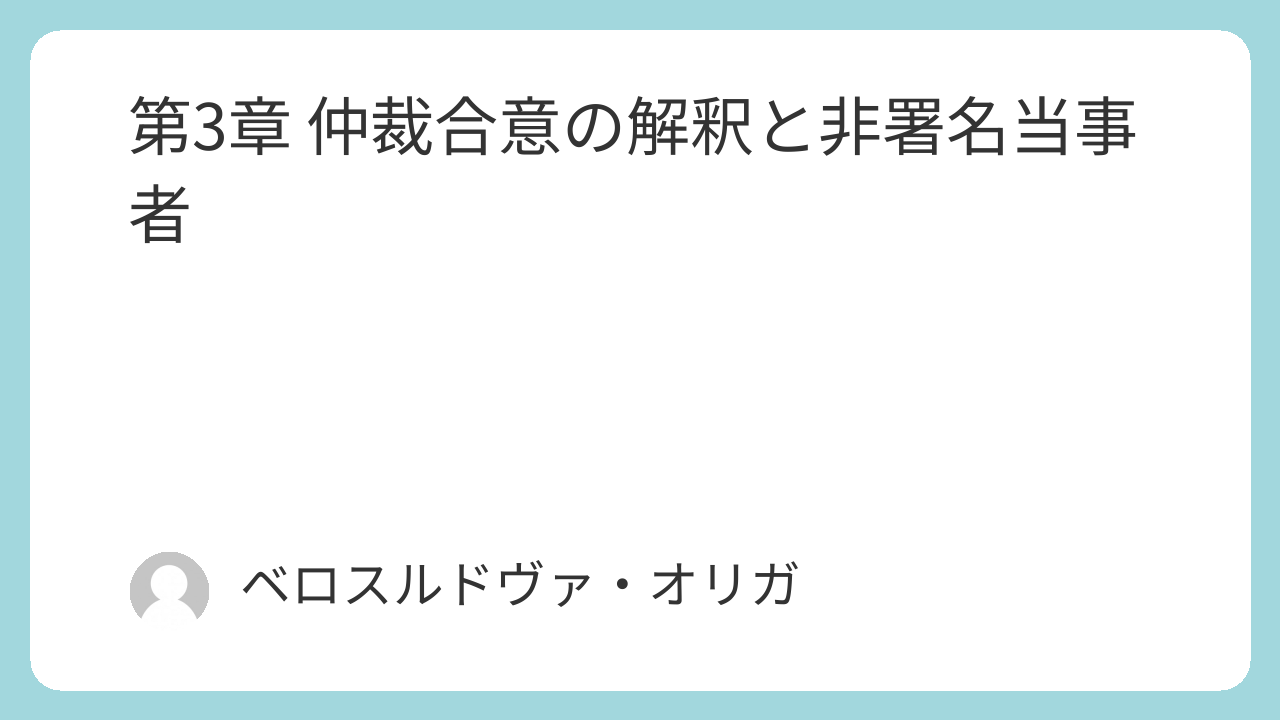前章までで、仲裁合意が国際仲裁の礎であり、その有効性が国際条約や各国の法制度、そして分離可能性といった法理によって強力に支えられていることを見てきました。有効な仲裁合意が存在し、その準拠法が特定され、かつ紛争の主題が仲裁による解決になじむものである(仲裁可能性がある)と判断された後、次に避けては通れない問題が生じます。それは、「今、目の前で起きているこの紛争は、果たして当事者が締結したあの仲裁合意の対象に含まれるのか?」そして「そもそも、この仲裁合意は一体誰を拘束するのか?」という二つの問いです。
一つ目の問いは仲裁合意の「解釈」と「範囲(Scope)」の問題であり、二つ目の問いは「非署名当事者(Non-signatory)」の問題です。これらは理論的に区別されるべきですが、実務上は密接に関連しあっています。紛争が発生すると、一方の当事者は、自らの請求が契約違反だけでなく不法行為にも基づくと主張したり、契約書に署名していない親会社の責任を追及しようとしたりします。このような状況で、仲裁廷がどこまでの紛争を、誰との間で審理する権限を持つのかは、仲裁合意の解釈にかかっています。
本章では、これら二つの重要なテーマ、すなわち仲裁合意の適用範囲と人的範囲をめぐる国際的な原則と実務上の主要な論点について解説します。
第1部 仲裁合意の解釈と範囲
1. 仲裁合意の解釈原則
仲裁合意も契約の一種である以上、その解釈は、まず準拠法とされている国の契約解釈の一般原則に従います。しかし、国際仲裁の文脈においては、これに加えて極めて重要な特殊な解釈原則が存在します。それが「仲裁に好意的な解釈(Pro-arbitration Principle of Interpretation)」の原則です。
(1) 「仲裁に好意的な解釈」の原則
これは、仲裁条項の文言に曖昧さがある場合、その条項の適用範囲を狭く限定するのではなく、紛争を仲裁の対象に含める方向で広めに解釈すべきである、という国際的に広く承認された原則です。この原則の背後には、当事者が紛争を単一の場で効率的に解決しようとした意思を尊重し、非効率な並行手続を回避するという強力な政策的配慮があります。
(2) 典型的な文言の解釈
- “arising out of or relating to this contract” (本契約に起因または関連して生じる): 最も広範な文言と解され、契約違反請求のみならず、契約に関連する不法行為請求や法定請求も包含するのが一般的です。
- “arising under this contract” (本契約に基づき生じる): より限定的と解釈される余地がありますが、現代的な傾向としては、この文言も比較的広く解釈されます。
実務的には、将来の紛争を避けるため、可能な限り「relating to」といった広範な文言を含む、仲裁機関のモデル条項を利用することが賢明です。
(3) 不法行為請求(Tort Claims)および法定請求(Statutory Claims)への適用
当事者の一方は、請求を「不法行為」や「法律違反」と構成することで仲裁合意の適用を免れようとすることがあります。しかし、仲裁廷や裁判所は、請求の法的な「ラベル」に惑わされることなく、その実質的な内容に着目します。主張されている不法行為や法令違反が、契約の存在、履行、または違反と事実的に密接に関連している場合には、広範な仲裁条項の範囲に含まれると判断するのが一般的です。
(4) 複数の契約(Multiple Contracts)
1つのプロジェクトが複数の契約から構成される場合、一部の契約にしか仲裁条項がなかったり、契約ごとに矛盾する紛争解決条項が存在したりすると問題が複雑になります。関連する紛争を1つの手続で解決するという当事者の合理的な意思を推測しつつも、契約の文言が優先されるため、契約起草段階で紛争解決条項を統一しておくことが極めて重要です。
2. 病的な仲裁条項(Pathological Arbitration Clauses)
不適切であるために、有効性や運用をめぐって深刻な問題を引き起こす仲裁条項は「病的(pathological)」な仲裁条項と呼ばれます。
- 類型: 不明確・曖昧な条項(空っぽの条項)、矛盾する条項(仲裁と裁判管轄の併記など)、実現不可能な条項(存在しない仲裁機関の指定など)があります。
- 救済的解釈: このような病的条項に直面した場合でも、裁判所や仲裁廷は、安易に仲裁合意を無効とするのではなく、当事者が紛争を仲裁によって解決しようとした根本的な意思を最大限尊重し、その意思を実現する方向で条項を解釈しようと努めます。欠落部分を補充したり、矛盾を合理的に解消したり、明らかな誤記を訂正したりすることで、仲裁合意を救済しようと試みます。
第2部 仲裁合意と非署名当事者
1. 非署名当事者をめぐる問題の所在
契約の相対効の原則によれば、仲裁合意は署名した当事者のみを拘束します。しかし、現代の国際取引では、契約に署名した子会社の背後で親会社が実質的に取引を主導しているなど、形式的な当事者と実質的な当事者が乖離していることが少なくありません。このような状況で、形式的な署名の有無のみを理由に、実質的な関係者を仲裁手続から排除することは、紛争の包括的解決を妨げ、不公正な結果をもたらす可能性があります。
2. 非署名当事者を拘束するための法理論
国際仲裁の実務は、この問題に対処するため、当事者の「同意」を拡張して解釈する様々な法理論を発展させてきました。
(1) 代理(Agency)
代理人が本人に代わって契約を締結した場合、本人は契約書に署名していなくても、代理人の署名を通じて仲裁合意に拘束されます。形式的な代理権がなくとも、黙示の代理権や表見代理が認定されれば、非署名当事者である本人が拘束される可能性があります。
(2) 法人格否認の法理(Alter Ego / Piercing the Corporate Veil)
例外的な状況において、会社の独立した法人格を無視し、その背後にある株主(通常は親会社)の責任を追及する法理です。会社が株主の「分身(Alter Ego)」として利用され、法人格の独立性が不正な目的のために濫用されている場合に適用されます。適用が認められるためのハードルは極めて高いです。
(3) 会社群理論(Group of Companies Doctrine)
国際仲裁、特にICC仲裁の実務から発展した法理です。契約に署名していない企業であっても、それが署名会社と同一の企業グループに属し、かつ、契約の交渉、履行、終了に実質的に関与していた場合には、仲裁合意に拘束されるという黙示の合意があったと推断されます。この理論は、多国籍企業グループが一体として経済活動を行っているという商業的な現実を重視しますが、その適用については国によって見解が大きく分かれています。
(4) 禁反言(Estoppel)
主に英米法系の法理で、特に「直接的な利益の禁反言(Direct Benefit Estoppel)」が重要です。非署名当事者が、仲裁条項を含む契約から直接的な利益を享受した場合、その契約の負担部分である仲裁条項の適用のみを拒否することは許されない、という考え方です。
(5) その他の理論
- 承継および譲渡(Succession and Assignment): 会社の合併や債権譲渡などにより、仲裁合意を含む契約上の地位が、非署名当事者である承継会社や譲受人に移転します。
- 第三者のための契約(Third-Party Beneficiary): 契約によって直接利益を受ける第三受益者は、その権利の根拠となる契約に含まれる仲裁条項にも拘束されると解されることが多いです。
3. 結論
仲裁合意の解釈は、国境を越えた紛争を、予測可能で効率的な1つの手続に集約するという、国際仲裁の根幹をなす政策を実現するためのプロセスです。そのため、国際的な実務は一貫して、当事者の「仲裁をする」という根本的な意思を尊重し、その範囲を広く捉え、たとえ不完全な合意であってもそれを救済する方向で動いています。
同様に、非署名当事者をめぐる法理の発展は、国際仲裁が、形式的な法の壁を乗り越え、いかにして複雑な商業的現実に即した公正な解決を目指すかという、ダイナミックな法創造の最前線を示しています。契約を起草する際には、これらの解釈原則を念頭に置き、誰が、どのような紛争について仲裁に服するのかを、可能な限り明確に規定しておくことが、将来の無用な争いを避けるための最善策と言えるでしょう。