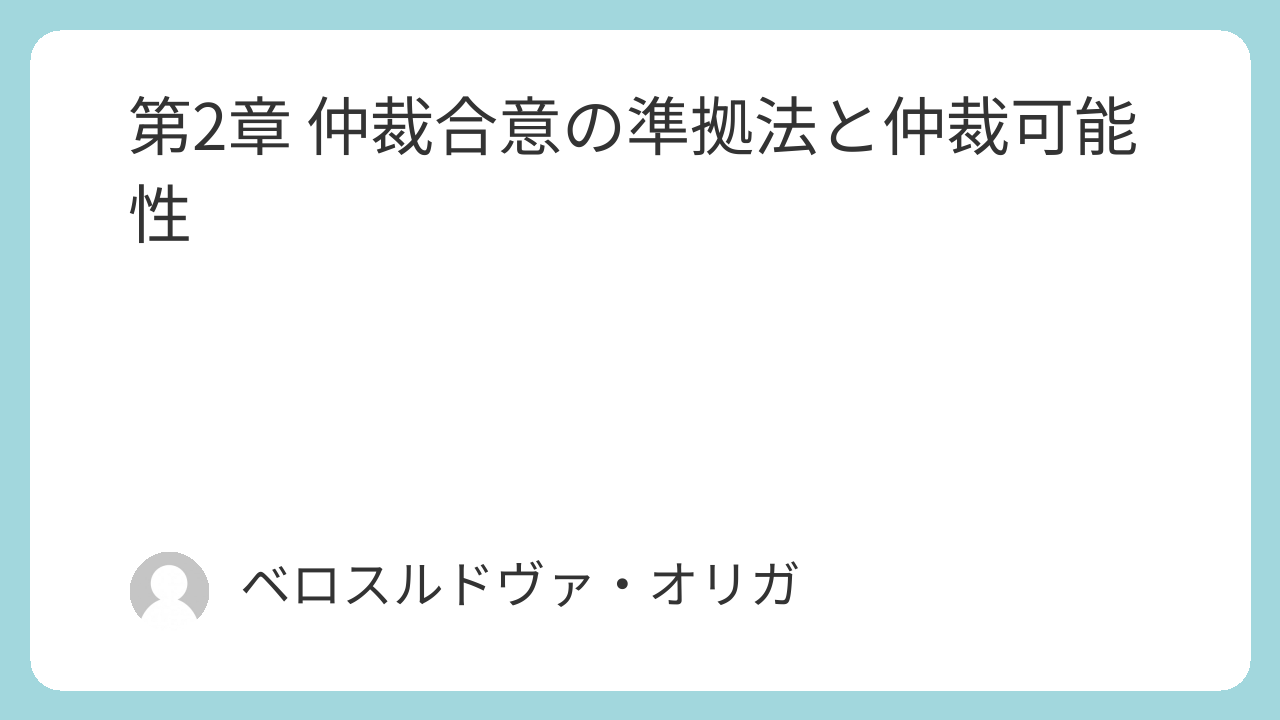前章では、国際仲裁の礎である仲裁合意が、国際条約や各国の国内法によってその有効性を強力に支持されていること、そして「分離可能性」や「コンペテンス・コンペテンス」といった法理によって支えられていることを見てきました。仲裁合意は、それを含む主契約から独立した存在として扱われ、自らの有効性に関する紛争さえも、まずは自らが指定する仲裁廷で判断されるという、自己完結的な性質を持っています。
しかし、この「独立した合意」である仲裁合意は、一体どの国の法律に基づいてその有効性や解釈が判断されるのでしょうか。また、当事者が有効な仲裁合意を結んだとしても、あらゆる種類の紛争を仲裁に委ねることが許されるのでしょうか。本章では、「仲裁合意の準拠法」と「仲裁可能性」について深く掘り下げていきます。これらの論点は、国際仲裁の有効性と限界を画するものであり、その理解は国際取引における紛争解決戦略を立てる上で不可欠です。
1. 仲裁合意の準拠法
国際的な契約には、通常、「本契約は日本法に準拠する」といった形で、契約全体に適用される法律を指定する「準拠法条項」が設けられています。では、その契約に含まれる仲裁条項も、当然にこの準拠法(この例では日本法)に規律されるのでしょうか。
前章で学んだ「分離可能性の原則」を思い起こしてください。この原則によれば、仲裁条項は主契約から独立した合意です。そうであるならば、主契約の準拠法と仲裁条項の準拠法が、論理的には異なっていても不思議ではありません。仲裁合意の有効性、範囲、解釈、そして非署名当事者への効力といった問題は、この仲裁合意の準拠法によって判断されるため、どの国の法律が適用されるのかは極めて重要な問題となります。
(1) 準拠法決定の重要性
どの国の法律が仲裁合意の準拠法となるかによって、結論が大きく変わることがあります。例えば、ある国の法律では、契約の当事者ではない関連会社(親会社など)も「会社群(Group of Companies)」理論に基づき仲裁合意に拘束されると解釈されるかもしれませんが、別の国の法律ではそのような解釈は認められないかもしれません。また、ある法律の下では有効な仲裁合意が、別の法律の下では形式不備や公序違反で無効と判断される可能性もあります。したがって、準拠法の特定は、仲裁廷が管轄権を有するか否かを左右する死活問題となり得るのです。
(2) 準拠法の決定方法
仲裁合意の準拠法は、どのようにして決まるのでしょうか。国際的なコンセンサスは、以下の階層的なアプローチを支持しています。これは、ニューヨーク条約第5条1項(a)の規定にも反映されています。
a. 当事者による明示または黙示の選択(Express or Implied Choice)
まず最優先されるのは、当事者の意思です。当事者は、仲裁合意に適用される法律を自由に選択することができます。
- 明示の選択: 最も明確なのは、当事者が「本仲裁条項はスイス法に準拠する」というように、仲裁条項自体に適用される法律を明示的に指定する場合です。しかし、実務上、このように仲裁条項の準拠法を主契約の準拠法と別に定める例は稀です。
- 黙示の選択: 問題となるのは、多くの場合、「黙示の選択」があったと解釈できるか否かです。ここで国際的に見解が分かれているのが、「主契約の準拠法条項が、仲裁条項の準拠法の黙示の選択をも意味するか」という点です。
- 英国の立場(主契約準拠法を優先): 英国最高裁は、近年のリーディングケースである Enka v Chubb 事件判決(2020年)において、当事者が契約全体の準拠法を選択した場合、特段の反対事由がない限り、その選択は契約の一部である仲裁条項にも及ぶと解釈するのが合理的である、との立場を明確にしました。これは、当事者は通常、契約全体を単一の法体系で規律することを意図しているはずだ、という商業的な常識に基づく判断です。
- フランス等の立場(仲裁地法を重視): 一方、フランスの裁判所などは、仲裁合意の分離可能性をより徹底し、主契約の準拠法の選択が当然に仲裁条項に及ぶとは考えません。むしろ、当事者が特定の国を「仲裁地」として選択したこと自体が、その国の法律を仲裁合意の準拠法として「黙示的に選択」したことの強い証拠となると考えます。
このように、黙示の選択の解釈については国際的にアプローチが統一されておらず、どの国の裁判所や仲裁廷で争われるかによって結論が変わり得ることに注意が必要です。
b. 当事者による選択がない場合の決定ルール(Default Rule)
当事者による明示も黙示の選択も認められない場合、客観的な基準によって準拠法を決定する必要があります。この点について、国際的に最も広く支持されているのが、「仲裁地の法(Law of the Arbitral Seat)」を適用するというルールです。
ニューヨーク条約第5条1項(a)は、当事者による選択がない場合、仲裁判断がなされた国(すなわち仲裁地)の法によって仲裁合意の有効性を判断すべきと規定しています。この規定は、仲裁判断の承認・執行段階のルールですが、仲裁手続開始前の段階においても類推適用されるのが一般的です。
仲裁地の法が選択される論理的根拠は、「最も密接な関連性(Closest Connection)」にあります。仲裁手続の進行を監督し、仲裁判断の取消訴訟を管轄するのは仲裁地の裁判所です。仲裁合意は、まさにこの仲裁手続を設定するための合意であるため、他のどの地よりも仲裁地こそが、仲裁合意と最も密接な関連性を有すると考えられるのです。前述の Enka v Chubb 事件判決においても、英国最高裁は、主契約の準拠法が選択されていない場合には、仲裁地の法が仲裁合意の準拠法となると判断しており、この点では国際的なコンセンサスと軌を一にしています。
(3) 有効化原理(Validation Principle)
仲裁合意の有効性をできる限り維持しようとする「仲裁に好意的な政策」をさらに推し進めるのが、「有効化原理」です。これは、スイス法などが採用する考え方で、仲裁合意が、当事者が選択した法、主契約の準拠法、仲裁地の法のいずれか一つでも満たせば有効とみなす、というものです。このアプローチは、当事者が仲裁による紛争解決を意図したことを最大限尊重し、偶発的な法の選択によってその意図が覆されることを防ぐ機能を持っています。
2. 仲裁可能性(Arbitrability)
当事者が有効な仲裁合意を締結したとしても、その紛争の「主題(Subject Matter)」が、そもそも私的な手続である仲裁による解決になじむものであるか、という問題が残ります。これが「仲裁可能性」の問題です。
各国の法制度は、公益性の高い特定の種類の紛争については、国家の司法権の専属的な管轄に服させるべきであり、当事者の合意によってその管轄を排除することは許されない、と考えています。このような紛争は「仲裁可能性がない(non-arbitrable)」とされ、たとえ仲裁合意の対象となっていても、その部分については仲裁合意が無効となります。仲裁可能性は、当事者自治に対する公序(Public Policy)による重要な制限です。
(1) 仲裁可能性の法的根拠
仲裁可能性の概念は、ニューヨーク条約にも明確に規定されています。条約第2条1項は、仲裁合意の対象を「仲裁による解決が可能である事項に関するもの」に限定しています。さらに、第5条2項(a)は、紛争の主題が承認・執行地の国の法律上「仲裁による解決が不可能なものである」場合には、仲裁判断の承認・執行を拒絶できると定めています。UNCITRALモデル法も同様の規定を置いています。
(2) どのような紛争の仲裁可能性が問題となるか
どのような紛争が仲裁可能でないかは、国によって大きく異なります。しかし、国際的に議論となることが多い分野は、ある程度共通しています。
- 独占禁止法・競争法(Antitrust and Competition Law): かつて、独占禁止法違反のような公益性の高い紛争は、裁判所が専属的に管轄すべきであり、仲裁可能性はないと考えるのが一般的でした。しかし、米国最高裁が Mitsubishi v. Soler 事件判決(1985年)で、国際取引に関する連邦独占禁止法違反の請求は仲裁可能であると判断して以来、国際的な潮流は大きく変化しました。現在では、多くの国で、私人間での損害賠償請求のような私法上の効果に関する限り、独占禁止法違反の紛争も仲裁可能であると解されています。ただし、仲裁判断が執行される段階で、裁判所がその判断が競争法上の公序に違反しないかを改めて審査する(「セカンド・ルック(Second Look)」)という留保が付されることがあります。
- 知的財産権(Intellectual Property): ライセンス契約に基づくロイヤリティの支払請求など、当事者間の権利義務に関する紛争は、一般的に仲裁可能です。しかし、特許や商標の有効性(無効かどうか)に関する紛争は、対世的な効力を持つ公的な権利の設定に関わるため、国の特許庁や裁判所の専属管轄とされ、仲裁可能性が否定される国が多くあります。
- 倒産(Bankruptcy): 破産手続の開始決定や管財人の選任といった、倒産手続の中核をなす事項(Core Bankruptcy Matters)は、多数の債権者の利益を公平に調整する必要があるため、一般に仲裁可能性はないとされています。一方で、破産管財人が倒産した会社の契約上の権利を行使するために、その契約に含まれる仲裁条項に基づいて仲裁を申し立てるといった、倒産手続に付随する紛争の仲裁可能性については、各国の法制度によって扱いが異なります。
- 消費者・労働紛争(Consumer and Labor Disputes): 消費者や労働者は、事業者との関係で交渉力が弱い立場にあるため、多くの国では、紛争発生前に画一的な契約条項によって裁判を受ける権利を奪うことを問題視し、消費者契約や労働契約における仲裁合意の有効性を制限または無効としています。特にEU指令は、消費者契約における仲裁条項に厳しい規制を課しています。
- 贈収賄・汚職(Bribery and Corruption): 汚職が絡む契約に基づく請求は、国際公序に反するとして、仲裁廷が請求を棄却したり、裁判所が仲裁判断の承認・執行を拒否したりすることがあります。これは、紛争の主題そのものが仲裁になじまないというよりは、違法な請求権の行使を法は助けないという一般原則の現れです。
(3) 仲裁可能性の準拠法
ある紛争に仲裁可能性があるか否かを判断する際に、どの国の法律を基準にすべきでしょうか。この点については、国際的に複雑な議論がありますが、実務上、少なくとも二つの国の法律が重要になります。
- 仲裁地の法(Lex Arbitri): 仲裁手続を監督し、仲裁判断の取消しを管轄する仲裁地の法律上、その紛争が仲裁可能でなければ、そもそも有効な仲裁判断を得ることができません。
- 承認・執行地の法(Lex Executionis): ニューヨーク条約が明示するように、たとえ仲裁地で有効な仲裁判断が下されても、最終的に資産が所在し、執行を求める国の法律上、その紛争の主題が仲裁になじまないものであれば、執行は拒絶されます。
したがって、国際仲裁においては、仲裁地の法と、将来執行が見込まれる国の法の両方において、紛争の主題が仲裁可能であることが求められるのです。
仲裁合意は、国際仲裁の出発点であり、その有効性と範囲は、準拠法と仲裁可能性という二つの観点から検証されます。当事者としては、契約交渉の段階で、主契約の準拠法だけでなく、仲裁条項自体の準拠法を意識すること、そして、想定される紛争が仲裁可能なものであるかを見極めておくことが、将来の紛争解決を円滑に進めるための鍵となります。