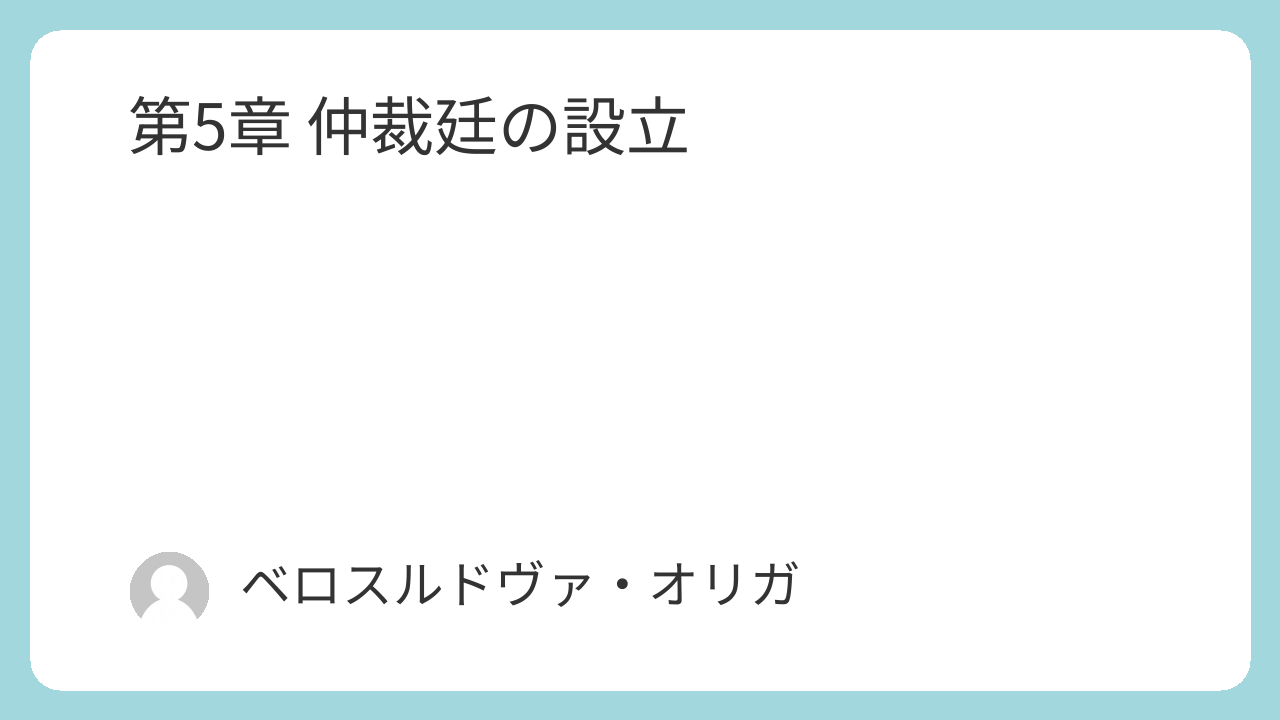有効な仲裁合意が成立し、その解釈と範囲が定まったならば、国際仲裁はいよいよ具体的な手続の段階へと移行します。裁判所が常に開廷している常設の国家機関であるのとは対照的に、仲裁廷は紛争ごとにオーダーメイドで設立される私的な裁判体です。したがって、仲裁手続を開始するための最初の、そして最も重要なステップは、紛争を審理・判断する権限を持つ「仲裁廷(Arbitral Tribunal)」を設立することです。
仲裁廷の設立プロセスは、単なる事務手続ではありません。それは、紛争解決の舞台となる「国」を法的に確定させ(仲裁地の選定)、紛争を裁く「裁判官」を選ぶ(仲裁人の選任)という、仲裁手続全体の性格と質を決定づける極めて戦略的なプロセスです。当事者がどのような仲裁廷を構築するかによって、その後の手続の効率性、判断の質、そして最終的な紛争解決の満足度が大きく左右されます。
本章では、この仲裁手続の出発点である仲裁廷の設立について、その前提となる「仲裁地」の決定から、仲裁人の人数、選任方法、仲裁人に求められる資質、そして仲裁人の独立性・公平性をめぐる問題までを包括的に解説します。
1. 仲裁地(Seat of Arbitration)の決定とその重要性
国際仲裁手続の法的枠組みを決定づける最も重要な概念が「仲裁地」です。仲裁地は、単に審問(ヒアリング)が行われる地理的な場所を意味するのではありません。それは、仲裁手続全体が法的に根ざす場所、いわば仲裁の「法的なホーム」あるいは「国籍」を決定する、極めて重要な法的概念です。
(1) 仲裁地の法的意義
仲裁地を選択することは、その国の法律を仲裁手続の手続準拠法(Lex Arbitri)として選択することを意味します。この仲裁地法は、仲裁手続全体を法的に支え、監督する役割を果たします。具体的には、仲裁地の選択は以下のような重大な法的帰結をもたらします。
- 手続法の決定: 仲裁手続の進行に関する基本的なルールは、仲裁地の仲裁法によって規律されます。例えば、仲裁人の選任手続で当事者の合意が機能しない場合にどの裁判所が介入するか、仲裁廷がどのような暫定措置を命じることができるか、証拠調べの方法に関する基本的なルールなどは、仲裁地法によって定められます。
- 監督裁判所の特定: 仲裁手続を監督し、必要な場合に支援を提供する裁判所は、仲裁地の裁判所です。仲裁人の忌避申立ての最終的な判断や、証人召喚への協力など、仲裁廷自身の権限だけでは不十分な場合に、この監督裁判所の支援が必要となります。
- 仲裁判断の「国籍」の決定: 仲裁判断は、仲裁地で「なされた」ものと法的に扱われます。これにより、仲裁判断は例えば「スイスの仲裁判断」や「シンガポールの仲裁判断」といった「国籍」を持つことになります。この国籍は、後述するニューヨーク条約に基づく執行の場面で重要となります。
- 取消訴訟の管轄: 仲裁判断に重大な瑕疵があるとしてその効力を覆そうとする場合、その仲裁判断の「取消し(Setting Aside / Annulment)」を申し立てることができるのは、原則としてその仲裁地の裁判所のみです。
このように、仲裁地の選択は、仲裁手続の法的安定性と予測可能性を確保するための根幹的な決定なのです。
(2) 審問地(Venue/Place of Hearing)との違い
仲裁地(Seat)と、実際に審問や会議が行われる物理的な場所である「審問地(Venue)」は、明確に区別されなければなりません。仲裁地は法的な概念であり、一度決定されると、たとえ審問が世界の他の都市で行われたとしても、法的な仲裁地は変わりません。
例えば、仲裁地をパリと定めた場合でも、当事者や仲裁人の便宜のために、一部の会議を東京で、証人尋問をニューヨークで、そして仲裁廷の評議をオンラインで行うことが可能です。主要な仲裁機関の規則や近代的な仲裁法は、このような地理的な柔軟性を認めています。この場合でも、仲裁手続はあくまでフランスの仲裁法に準拠し、仲裁判断はフランス(パリ)でなされたものとみなされ、その取消しはパリの裁判所でのみ争うことができます。
(3) 仲裁地の選定方法
仲裁地は、以下のいずれかの方法で決定されます。
- 当事者による合意: 最も望ましいのは、当事者が契約交渉の段階で、仲裁条項の中で仲裁地を明確に合意しておくことです。
- 仲裁機関による決定: 当事者間に合意がない場合、ICCやLCIAといった仲裁機関の規則では、仲裁機関自身が適切な仲裁地を決定する権限を持ちます。
- 仲裁廷による決定: UNCITRAL仲裁規則のように、当事者の合意がない場合には、設立された仲裁廷が、事案の状況を考慮して仲裁地を決定すると定める規則もあります。
(4) 仲裁地選定における考慮要素
では、どこを仲裁地に選ぶべきでしょうか。これは極めて戦略的な判断であり、以下の要素を総合的に考慮する必要があります。
- 中立性: 当事者のいずれとも関係のない中立国を選ぶのが大原則です。
- ニューヨーク条約への加盟: 仲裁判断の国際的な執行可能性を確保するため、仲裁地国がニューヨーク条約に加盟していることは必須条件です。
- 仲裁に好意的な法制度: 仲裁地の国内仲裁法が、UNCITRALモデル法に準拠するなど、近代的で「仲裁に好意的(Arbitration-friendly)」であることが重要です。具体的には、当事者自治を尊重し、裁判所の介入を必要最小限に限定し、かつ仲裁手続を円滑に進めるための支援制度が整っている法律が望ましいです。
- 質の高い司法: 仲裁を監督・支援する裁判所の質も重要です。仲裁に精通し、国際的な事案を迅速かつ適切に処理できる経験豊富な裁判官がいることが望ましいです。
- インフラと利便性: 質の高い法律専門家、専門家証人、通訳、審問施設などが利用可能であること、また、交通の便が良く、当事者や関係者が渡航しやすいことも実務上重要な要素となります。
これらの要素から、伝統的にロンドン、パリ、ジュネーブ、ストックホルムなどが主要な仲裁地として選ばれてきましたが、近年では、極めて仲裁に好意的な法制度と優れたインフラを整備したシンガポールや香港が、アジアにおけるハブとして急速にその地位を高めています。
2. 仲裁人の人数
仲裁廷を構成する仲裁人の人数は、通常1名または3名です。どちらを選択するかは、紛争の規模や複雑性、コスト、そして当事者の戦略によって決定されます。
(1) 独任仲裁人(Sole Arbitrator)
1名の仲裁人が紛争を審理・判断する形式です。
- メリット:
- コストと時間: 仲裁人の報酬が1名分で済むため、3名の場合に比べて費用を大幅に削減できます。また、仲裁人間のスケジュール調整や評議が不要なため、手続が迅速に進む傾向があります。
- デメリット:
- 判断の偏りのリスク: 仲裁人が1名しかいないため、その個人の知識、経験、価値観が判断に強く反映され、誤った判断が下されるリスクが相対的に高まります。
- 選任の困難: 当事者双方が納得する1名の仲裁人候補に合意するのは、3名の場合に各当事者が1名ずつ指名するよりも困難な場合があります。合意に至らない場合、仲裁機関や裁判所による選任に委ねることになり、当事者の選択権が失われます。
紛争の金額が比較的小さく、争点が限定的な事案では、独任仲裁が適しています。
(2) 三人制仲裁廷(Three-Member Tribunal)
3名の仲裁人で構成される仲裁廷であり、国際仲裁では最も標準的な形式です。通常、申立人と被申立人がそれぞれ1名ずつ仲裁人(共同仲裁人、Co-arbitrator)を指名し、その2名の共同仲裁人が協議して3人目の仲裁人である議長仲裁人(Presiding Arbitrator / Chairman)を選任します。
- メリット:
- 判断の質の担保: 3名の専門家が異なる視点から事案を検討し、評議を通じて結論を導き出すため、より慎重でバランスの取れた判断が期待できます。独任仲裁人に比べて判断の誤りが生じるリスクが低くなります。
- 当事者の納得感: 各当事者が自ら選んだ「信頼できる裁判官」が仲裁廷に参加するため、手続の正当性に対する当事者の納得感が高まります。特に、当事者の国籍や文化的背景が異なる場合、自らが指名した仲裁人がその背景を他の仲裁人に説明する役割を果たすことも期待されます。
- 多様な専門性の確保: 例えば、法律問題と技術的問題が複雑に絡み合う紛争で、法律家2名と技術専門家1名といった構成にすることで、多角的な審理が可能となります。
- デメリット:
- コストと時間: 3名分の仲裁人報酬が必要となり、費用が高額になります。また、3名の多忙な専門家のスケジュールを調整するのは困難な場合が多く、手続が長期化する傾向があります。
紛争の金額が大きい、または争点が複雑な事案では、三人制仲裁廷が適しています。主要な仲裁機関の規則では、当事者の合意がない場合、紛争の規模や複雑性を考慮して、機関が1名とするか3名とするかを決定する旨が定められていることが多いです。
3. 仲裁人の選任
仲裁廷を構成する具体的な仲裁人を決定するプロセスは、仲裁手続の成否を分ける重要なステップです。
(1) 選任方法
仲裁人の選任は、主に以下の方法で行われます。
- 当事者による合意: 独任仲裁人の場合、当事者双方が協議して1名の仲裁人を選任します。三人制の場合も、当事者双方が3名全員について合意することも理論的には可能ですが、実務上は稀です。
- 共同仲裁人による議長仲裁人の選任: 三人制仲裁廷における最も一般的な議長選任方法です。各当事者が指名した2名の共同仲裁人が、中立的な第三者として議長を選任します。
- 仲裁機関による選任: 当事者間で仲裁人の選任について合意できない場合や、一方当事者が選任手続に協力しない(欠席する)場合に、仲裁機関がその規則に従って仲裁人を選任します。選任方法には、機関が直接1名を指名する方法と、候補者リストを当事者に提示し、当事者が希望順位を付けたり、忌避したりした結果を基に機関が最終決定するリスト方式があります。
- 任命権者(Appointing Authority)による選任: Ad Hoc仲裁において、当事者が仲裁人の選任で合意できない場合に備え、仲裁機関や特定の個人を、仲裁人を選任する権限を持つ「任命権者」として予め指定しておく方法です。
- 裁判所による選任: 上記のいずれの方法でも仲裁人が選任できない場合の最終的なセーフティネットとして、仲裁地の裁判所が国内仲裁法に基づき仲裁人を選任します。
(2) 仲裁人に求められる資質
どのような人物を仲裁人として選ぶべきでしょうか。求められる資質は多岐にわたりますが、特に以下の点が重要です。
- 独立性と公平性: これは仲裁人に求められる最も根本的な資質であり、後ほど詳述します。
- 専門性: 紛争の主題に関する法的な知識や、特定の業界(建設、エネルギー、金融など)に関する深い知見。
- 経験: 国際仲裁手続の運用に関する豊富な経験。特に議長仲裁人には、手続を効率的に指揮する能力が強く求められます。
- 言語能力: 仲裁の使用言語に堪能であること。証拠となる文書や証言が多言語にわたる場合は、複数の言語能力が有利に働きます。
- 国籍: 当事者のいずれとも異なる第三国の国籍を持つことが、中立性の観点から強く推奨されます。多くの仲裁機関規則では、独任仲裁人や議長仲裁人は当事者と異なる国籍を持つことを原則としています。
- 可用性(Availability): 仲裁手続に十分な時間を割くことができるか。著名な仲裁人は多忙なことが多く、選任前にその旨を確認することが不可欠です。
- 多様性(Diversity): 近年、仲裁人の人選において、性別、人種、地理的出身、年齢などの多様性を確保することの重要性が増しています。多様な視点を取り入れることで、より公正で質の高い判断につながると期待されています。
(3) 候補者のインタビュー
当事者が仲裁人候補者と事前に面談(インタビュー)することは、その人物の適性を見極めるために行われることがあります。ただし、その際には、紛争の実体について議論することは厳しく禁じられており、あくまで候補者の経歴、専門性、経験、可用性、そして利益相反の有無などを確認する範囲に留めなければなりません。不適切な接触は、その候補者の公平性を損ない、選任後の忌避の原因となりえます。
4. 独立性と公平性
仲裁人に求められる最も重要な義務は、独立(Independent)かつ公平(Impartial)であることです。この二つの要件は、仲裁判断の正当性と信頼性の根幹をなします。
- 独立性: 主に客観的な側面を指し、仲裁人と当事者、その代理人、または紛争内容との間に、判断に影響を与えうるような密接な個人的、職業的、または金銭的な関係が存在しないことを意味します。
- 公平性: 主に主観的な側面を指し、仲裁人がいずれかの当事者に対して偏見や先入観を持たず、開かれた心で事案を審理・判断する精神状態にあることを意味します。
(1) 情報開示義務(Duty of Disclosure)
仲裁人は、独立性・公平性に関する「正当な疑い(justifiable doubts)」を生じさせる可能性のあるいかなる事実または状況も、自発的に開示する継続的な義務を負います。これは、UNCITRALモデル法や主要な仲裁機関規則に定められた基本原則です。
重要なのは、開示すべきか否かの判断基準が、仲裁人自身の主観ではなく、「合理的な第三者の視点」または「当事者の視点」から見て疑いを生じさせる可能性があるか、という客観的・外形的な基準である点です。たとえ仲裁人自身は全く偏見がなく、判断に影響はないと確信していても、外形的に疑わしい状況があれば開示しなければなりません。「疑わしきは開示する(when in doubt, disclose)」が鉄則です。
(2) IBA利益相反ガイドライン
何が「正当な疑い」を生じさせる状況にあたるのか、その具体的な基準を明確にするため、IBAが策定した「国際仲裁における利益相反に関するガイドライン(IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration)」が、ソフトローとして国際実務で広く参照されています。
このガイドラインは、「Traffic Light System」を用いて、様々な状況をその深刻度に応じて分類しています。
- レッドリスト(Red List): 深刻な利益相反が存在する状況。
- 放棄不能なレッドリスト: 仲裁人が当事者の一方と同一であったり、紛争の結果に直接的な金銭的利害関係を有する場合など、当事者の同意があっても許されない絶対的な欠格事由。
- 放棄可能なレッドリスト: 仲裁人が過去3年以内に当事者の一方に重要な法律意見を提供したことがある場合など、当事者全員が事実を知った上で明確に同意すれば許容される可能性がある状況。
- オレンジリスト(Orange List): 状況によっては、独立性・公平性について正当な疑いを生じさせる可能性があるため、開示が義務付けられる状況。例えば、仲裁人が過去3年以内に当事者の代理人法律事務所に所属していた、当事者の一方から過去に複数回仲裁人として選任された(リピート・アポイントメント)、など。
- グリーンリスト(Green List): 通常は利益相反を生じさせず、開示義務もないと考えられる状況。例えば、仲裁人が当事者企業の株式を僅かに保有している、仲裁人と当事者の代理人が同じ法律協会の会員である、など。
このガイドラインは法的な拘束力を持つものではありませんが、仲裁人、当事者、仲裁機関、裁判所が利益相反の問題を判断する際の、事実上の国際標準となっています。
5. 仲裁人の忌避(Challenge)と交代
仲裁人の独立性・公平性に疑義が生じた場合、当事者はその仲裁人の「忌避」を申し立てることができます。
忌避の申立ては、まず仲裁機関(機関仲裁の場合)や任命権者、他の仲裁人に対して行われます。その決定に不服がある場合、最終的には仲裁地の裁判所に判断を求めることができます。忌避の申立ては、その根拠となる事実を知ってから速やかに行わなければならず、不当に遅延した申立ては権利の放棄(Waiver)とみなされます。紛争に負けそうになってから、以前から知っていた事実を基に忌避を申し立てるといった戦術的な利用は許されません。
仲裁人が死亡、辞任、または忌避によって欠員となった場合、原則として、その仲裁人が選任されたのと同じ手続に従って、後任の仲裁人が選任されます。そして、新たに構成された仲裁廷は、それまでの手続をどの程度やり直すかを決定します。
仲裁廷の設立は、国際仲裁が当事者自治の原則に深く根ざしていることを最もよく示すプロセスです。当事者は、自らの紛争を裁く「場所」と「人」を自ら選ぶという、訴訟にはない広範な権限を与えられています。しかし、その自由には、公正で実効的な紛争解決を実現するという重い責任が伴います。適切な仲裁地と、専門性と公平性を兼ね備えた仲裁人を選ぶ当事者の賢明な判断こそが、成功裏の仲裁への第一歩なのです。