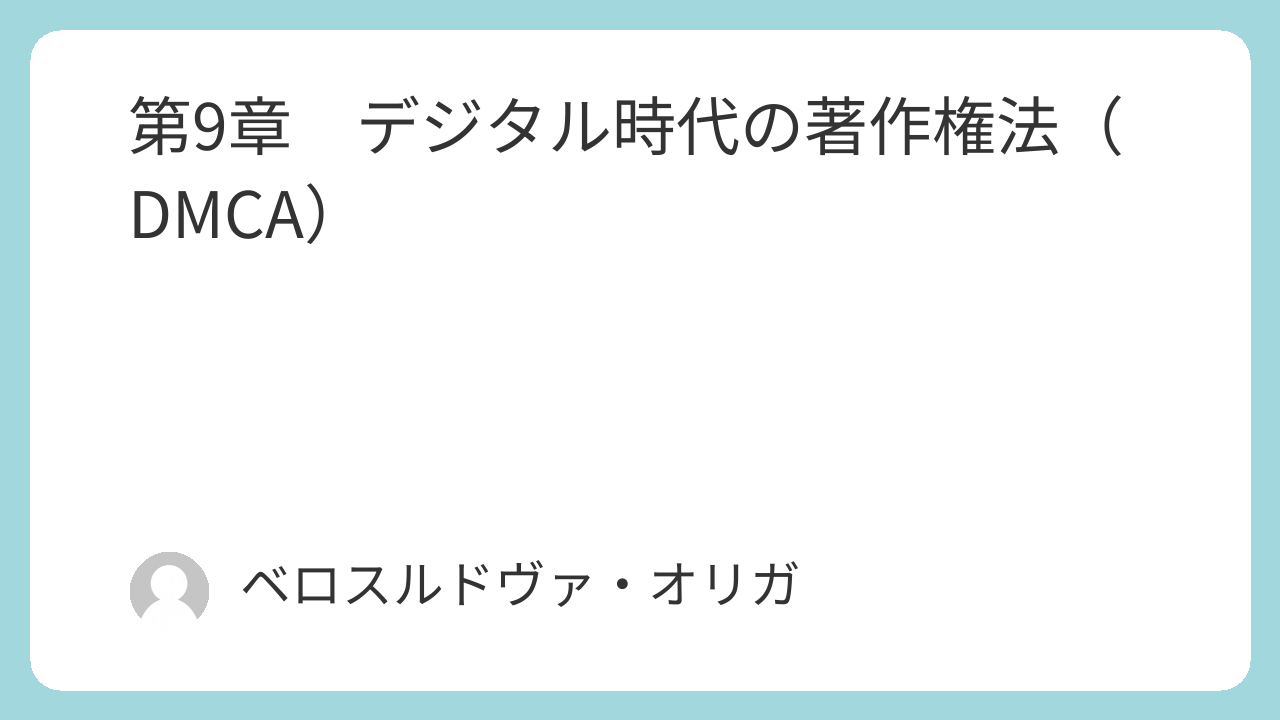1990年代後半、インターネットの爆発的な普及は、著作権の世界を根底から揺るがしました。デジタルデータは、劣化することなく瞬時に低コストで完璧なコピーを作成し、世界中に拡散させることが可能です。この新たな現実は、コンテンツ産業に計り知れないビジネスチャンスをもたらすと同時に、かつてない規模の海賊版のリスクをもたらしました。従来の著作権法が、物理的な「コピー」の製造と頒布を規制することを主眼としていたのに対し、デジタルネットワーク上を情報が奔流のように駆け巡る時代には、新たな法的枠組みが必要になりました。
このような背景の下、世界知的所有権機関(WIPO)は1996年に「WIPO著作権条約」および「WIPO実演・レコード条約」という2つの新条約を採択しました。これらの条約は、デジタル時代の著作権保護の新たな国際基準を定めるものであり、加盟国に対して、技術の進化に対応した国内法を整備することを求めました。
この国際的な要請に応え、アメリカ議会が1998年に制定した法律が、デジタルミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act、以下DMCA)です。DMCAは、従来の著作権侵害の枠組み(「複製したか否か」)に加えて、著作物への「アクセス」そのものをコントロールする、全く新しい概念を導入しました。
本章では、今日のインターネット社会のルールを形作る上で決定的な役割を果たしているDMCAの二つの柱、「オンラインサービスプロバイダの責任制限(セーフハーバー規定)」と「技術的保護手段の回避禁止(アンチサーカムベンション規定)」について、解説します。
1. オンラインサービスプロバイダの責任制限(セーフハーバー規定)
インターネットの黎明期、ウェブサイトの運営者やインターネット接続プロバイダ(ISP)は、常に法的な不安に晒されていました。自社のサービス上でユーザーが著作権侵害を行った場合、プロバイダ自身が寄与侵害や代位責任といった間接侵害の責任を問われるリスクがあったからです。もしプロバイダがユーザーのあらゆる行為を監視する責任を負わなければならないとすれば、インターネットという自由な情報交換のプラットフォームそのものが成り立ちません。
この問題を解決するため、DMCA512条は、特定の条件を満たすオンラインサービスプロバイダ(Online Service Provider、以下OSP)に対して、ユーザーの著作権侵害行為に関する金銭的賠償責任を免除する「セーフハーバー(安全な港)」を提供しました。この規定は、今日のYouTube・Facebook・X(旧Twitter)といったUGC(User Generated Content)プラットフォームが存続するための法的基盤となっています。
対象となるOSPと適用要件
セーフハーバーの保護を受けるためには、OSPはまず、以下の基本的な適用要件を満たす必要があります。
- 侵害を繰り返すユーザーのアカウントを停止するポリシーを策定し、合理的に実施していること。
- 著作権者が用いる標準的な技術的措置(例えば、デジタル指紋技術)を妨害しないこと。
4つのセーフハーバー
DMCAは、OSPの機能に応じて、4種類の具体的なセーフハーバーを設けています。
① 一時的なデジタルネットワーク通信(§ 512(a))
これは、インターネット接続プロバイダのように、ユーザーの指示に従ってデータをA地点からB地点へ中継(Conduit)するだけの、純粋な通信路としての機能に関するものです。OSPがコンテンツの内容や受信者を選択せず、自動的なプロセスでデータを通過させている限り、その過程で生じる一時的なコピーについて責任を負いません。
② システムキャッシング(§ 512(b))
ウェブページの表示を高速化するため、OSPがコンテンツを自社のサーバーに一時的に保存(キャッシュ)する行為に関するものです。OSPが定めたルールに従ってキャッシュの更新や削除を行い、コンテンツへのアクセス条件を変更しない限り、キャッシュ内のデータによる侵害の責任は免除されます。
③ ユーザーの指示によるシステム上の情報保存(§ 512(c))
これが、UGCプラットフォームにとって最も重要なセーフハーバーです。YouTubeの動画投稿や、SNSへの写真のアップロードのように、ユーザーが自らの意思でコンテンツをOSPのサーバーに保存する場合に適用されます。この保護を受けるためには、OSPは以下の条件を満たす必要があります。
- 侵害の事実を現実に知らないこと
- 侵害の事実や状況が明白でないこと(Red Flag Knowledgeがないこと)
- 侵害の事実を知るか明らかになった場合に、迅速にそのコンテンツを削除またはアクセス不能にすること
- その侵害行為から直接的な金銭的利益を得ていないこと
④ 情報検索ツール(§ 512(d))
Googleのような検索エンジンや、ハイパーリンクを提供するサイトに関するものです。侵害コンテンツへのリンクを提供したとしても、それが侵害であると知るか明らかになった場合に迅速にリンクを削除すれば、責任を免れます。
ノーティス・アンド・テイクダウン
上記③と④のセーフハーバーを機能させるための具体的な手続きが、「ノーティス・アンド・テイクダウン(Notice and Takedown)」です。これは、今日のインターネットにおけるコンテンツ管理の基本ルールとなっています。
- 権利者からの通知(Notice): 著作権を侵害されたと考える権利者は、法律の定める要件(侵害された著作物の特定、侵害箇所の情報、誠実な信念に基づく陳述等)を満たした通知書を、OSPが指定した代理人に送付します。
- OSPによる削除(Takedown): 適法な通知を受け取ったOSPは、迅速に(expeditiously)、侵害が指摘されたコンテンツを削除またはアクセス不能にする義務があります。この時点では、OSPは侵害の有無を実質的に判断する必要はありません。通知の形式的要件が満たされていれば、削除義務が生じます。
- 投稿者への通知と異議申し立て(Counter-Notice): OSPは、コンテンツを削除したことを投稿者に通知します。投稿者は、削除されたコンテンツが侵害に当たらない(例えば、フェアユースである)と考える場合、OSPに対して異議申し立て通知(カウンターノーティス)を送ることができます。
- コンテンツの復元: OSPが投稿者から適法なカウンターノーティスを受け取った場合、OSPはその旨を権利者に通知します。もし権利者が、通知から10~14営業日以内に、投稿者を相手取って訴訟を提起したことを証明しない限り、OSPは削除したコンテンツを復元しなければなりません。
権利を偽って不当なテイクダウン通知を送る行為(虚偽通知)は、通知者に損害賠償責任を生じさせる可能性があると定められています。
2. 技術的保護手段の回避禁止(Anticirvumvention規定)
DMCAがもたらしたもう一つの、そしてより大きな衝撃が、著作権法第12章に新設されたAnticirvumvention規定です。これは、DVDのコピーガードやソフトウェアのアクティベーションキーといった、著作権者が自らの作品を保護するために用いる技術的保護手段(Technological Protection Measures、以下TPM)を、不正に「回避(circumvent)」する行為そのものを禁止するものです。
この規定の画期的な点は、それが著作権侵害とは独立した、新たな法的請求権を創設したことにあります。つまり、たとえTPMを回避した後の利用がフェアユースに該当するような場合であっても、TPMを回避する行為自体が違法となるのです。これにより、著作権法は、従来の「表現の不正な利用」の規制から、「著作物への不正なアクセス」の規制へと、その保護の範囲を大きく踏み出したことになります。
1201条は、TPMを2つの種類に分け、それぞれ異なる規制を課しています。
① アクセスコントロールの回避禁止(§ 1201(a))
これは、著作物を閲覧・視聴するために破らなければならないTPM(例えば、暗号化されたDVDのCSSプロテクションや、有料サイトのパスワード認証)に関する規制です。この規制はさらに2つに分かれます。
- 回避「行為」の禁止(§ 1201(a)(1)):
アクセスコントロールを回避する行為そのものが禁止されます。これは、エンドユーザーの行為を直接規制するものです。ただし、この規定はあまりに影響が大きいため、議会は3年ごとに著作権局長官と協議し、非侵害的な利用が不当に妨げられている特定のクラスの著作物について、一時的な適用除外を設ける権限を与えています。 - 回避「装置」の頒布禁止(§ 1201(a)(2)):
アクセスコントロールを回避するための装置・ソフトウェア・サービスを製造・輸入・頒布することが禁止されます。いわゆる「ハッキングツール」の提供者を規制するものです。この禁止は、以下のいずれかに該当する装置等に適用されます。- 主として回避を目的として設計・製造されている。
- 回避以外の商業的に重要な目的や用途が限定的である。
- 回避のために使用されるものとして販売促進されている。
② コピーコントロールの回避禁止(§ 1201(b))
これは、著作物へのアクセスは許可されているものの、その後の複製(コピー)を制御するTPM(例えば、一度しかコピーできないようにするシリアルコピー管理システム)に関する規制です。
ここで重要なのは、アクセスコントロールとは異なり、コピーコントロールについては回避「行為」自体は禁止されていないという点です。これは、フェアユースのような、複製を伴う非侵害的な利用の余地を残すためです。しかし、コピーコントロールを回避するための回避「装置」の頒布は、アクセスコントロールの場合と同様に厳しく禁止されています。
その結果、理論的にはフェアユース目的でコピーコントロールを回避する行為は適法であっても、そのためのツールを入手することが違法であるため、多くのユーザーにとっては事実上回避が不可能になるという状況が生まれています。
Anticirvumvention規定を巡る裁判と議論
この規定の合憲性と解釈について、多くの訴訟が行われました。Universal City Studios, Inc. v. Corley事件では、DVDのアクセスコントロール技術であるCSSを回避するプログラム「DeCSS」をウェブサイトに掲載した行為が争われました。被告側は、DeCSSはコンピュータコードという「言論」であり、その公開を禁じることは憲法修正1条の表現の自由に反すると主張しました。しかし、第2巡回区控訴裁判所は、DMCAの規定はコードの表現内容ではなく、それが持つ機能的な側面(暗号を解読する機能)を規制するものであり、表現の自由に対する付随的な制約にすぎないとして合憲と判断しました。
また、Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies, Inc.事件では、ガレージのドア開閉システムの製造者が、自社のリモコンでしか作動しないように組み込んだソフトウェアのTPMを、互換リモコンの製造者が回避したとして訴えました。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、DMCAのAnticirvumvention規定は、著作権法が保護する権利の侵害に結びつくようなアクセスを禁止するものであり、単に消費者が購入した製品(ガレージドア)を通常通り使用するためのアクセスを可能にする装置の提供は、DMCA違反には当たらないと判断しました。この判決は、DMCAが著作権の保護という本来の目的を逸脱し、製品のアフターマーケットにおける競争を不当に阻害する手段として濫用されることに歯止めをかける、重要な意義を持つものと評価されています。
Anticirvumvention規定の例外
DMCAは、正当な目的を持つ特定の回避行為を保護するため、いくつかの例外を設けています。
- 非営利の図書館・文書保管機関・教育機関による、購入を検討するためのアクセス
- 法執行機関や諜報機関による合法的な活動
- リバースエンジニアリングによる、互換性のあるソフトウェアを開発するためのアクセス
- 善意の暗号研究
- 未成年者のインターネットアクセスを制限するためのフィルタリング
- 個人のオンライン活動に関する個人情報を収集する機能を無効化するためのアクセス
- コンピュータシステムのセキュリティテスト
3. 著作権管理情報(CMI)の保護
DMCAは、1202条において、著作権管理情報(Copyright Management Information、以下CMI)を保護するための規定を設けています。CMIとは、著作物に電子的に付された、その著作物に関する権利情報のことです。
- CMIに含まれる情報:
- 著作物の題号、著作者名
- 著作権者名
- 利用許諾の条件
- これら情報にリンクするための識別子や番号(デジタルウォーターマークなど)
DMCAは、以下の2つの行為を禁止しています。
- CMIを意図的に除去または改変すること
- CMIが不正に除去・改変されたことを知りながら、その著作物を頒布したり、頒布することを知りながら輸入したり、公に実演したりすること
これらの行為が違法となるのは、それが「著作権侵害を誘発、可能にし、助長し、または隠蔽することを知りながら、またはそう信じるに足る合理的な理由がありながら」行われた場合に限られます。このCMI保護規定は、デジタルコンテンツの権利処理を円滑にし、著作権者が自らの作品の利用状況を追跡し、適正な対価を得ることを支援するための重要な制度です。