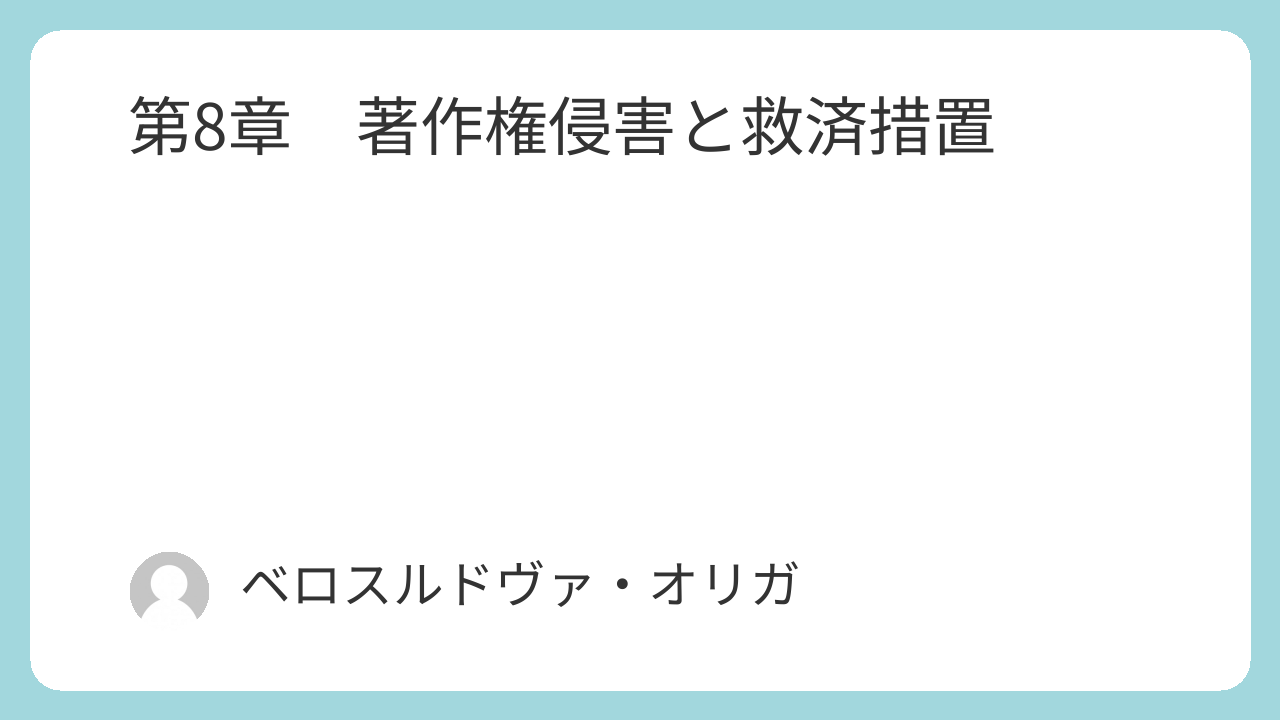著作権は、権利者がその排他的な支配を維持し、侵害行為に対して実効的な対抗手段を取ることを可能にする、法的な強制力を伴う権利です。
第1部 侵害の立証
著作権侵害訴訟において、原告(著作権者)の請求が認められるためには、以下の3つの要素を証明しなければなりません。
- 原告が、有効な著作権の所有者であること(Ownership)
- 被告が、原告の著作物に依拠して創作したこと(Copying)
- 被告の行為が、不適切な流用にあたること(Improper Appropriation)
1. 侵害の前提:有効な著作権の所有
まず原告は、訴訟の対象となっている著作物について自らが有効な著作権を有していることを証明する必要があります。これには、著作物が独創性を持ち著作物性の要件を満たしていること、原告自身が著作者であるか又は著作者から正当に権利を譲り受けた承継人であることが含まれます。
この証明において、後述する著作権登録が重要になります。著作物の刊行から5年以内に登録された場合、その登録証は、著作権の有効性および登録証に記載された事実について、一応の証拠(prima facie evidence)となります。これにより、証明の負担は被告側に転換され、被告が著作権の有効性を覆す証拠を提出しない限り、この要素は満たされたものとして扱われます。
2. 「依拠(Copying)」の証明(偶然の一致か、模倣か)
著作権が保護するのは模倣からの保護であり、偶然の一致や独立創作からの保護ではありません。したがって、原告は、被告が自らの作品を参照して(依拠して)創作したという事実、すなわち「事実としてのコピー行為」を証明する必要があります。
侵害者がコピー行為を認めることは稀であり、その行為が密室で行われることも多いため、直接的な証拠(自白や目撃証言など)が得られることはほとんどありません。そのため、裁判実務では、状況証拠を積み重ねて依拠の事実を推認する方法が確立されています。その2つの柱が「アクセス(Access)」と「類似性(Similarity)」です。
① アクセス(Access)
「アクセス」とは、被告が原告の著作物を見たり、聞いたりする合理的な機会があったことを意味します。単なる憶測や可能性(「同じ街に住んでいた」など)では不十分で、事実認定者がアクセスの合理的な確率を推認できる程度の証拠が必要です。
- 典型的な証明方法:
- 原告の作品が、被告も取引のあった第三者(出版社、レコード会社など)に提出されていた。
- 原告の作品が、被告企業のファイル内に保管されており、従業員が閲覧可能な状態にあった。
- 原告の作品が、テレビやラジオで広く放送されたりベストセラーになったりするなど、広範に頒布されていた。Bright Tunes Music Corp. v. Harrisongs Music, Ltd.事件では、ジョージ・ハリスンの「My Sweet Lord」が、先行するヒット曲「He’s So Fine」に依拠したと認定された際、後者の楽曲が当時ラジオで広く流れていたことが、ハリスンの(たとえ無意識であっても)アクセスの強力な証拠とされました。
② 依拠を推認させる類似性(Probative Similarity)
アクセスが証明された上で、両作品間に類似性が認められれば、裁判所は被告が依拠したとの推認を働かせることができます。ここでいう類似性は、後の「不適切な流用」で問われる「実質的類似性」とは少し意味合いが異なります。ここでは、偶然では説明しがたい類似点が存在し、それが被告の依拠行為を強く示唆しているかどうかが問われます。
- 共通の誤り: 依拠の最も強力な証拠の一つが、両作品における「共通の誤り」の存在です。例えば、地図や名簿において、原告が意図的に仕込んだ架空の地名や人名(コピーライト・トラップ)が被告の作品にも存在した場合、それは偶然の一致ではありえず、依拠の動かぬ証拠となります。
- 顕著な類似性(striking similarity): アクセスの直接的な証拠が乏しい場合でも、両作品が極めて複雑かつ詳細にわたり酷似しており、それが独立創作の結果であるとは到底考えられない場合、裁判所は類似性の事実そのものからアクセスを推認することがあります。ただし、ありふれた題材や単純な構成の作品については、この「顕著な類似性」が認められるハードルは非常に高くなります。
これらの状況証拠によって依拠が推認されると、今度は被告側が、独立創作であったことや、両者が共通のパブリックドメインのソースを参照した結果として類似したことなどを証明して、その推認を覆す責任を負います。
3. 「不適切な流用(Improper Appropriation)」の証明(許される借用と許されない盗用の境界線)
被告が原告の作品に依拠したという事実だけでは、まだ著作権侵害は成立しません。著作権法が保護するのはアイデアではなく、その具体的な表現です。したがって、原告はさらに、被告が保護されるべき表現を実質的な量だけ盗用したこと、すなわち、その依拠が「不適切な流用」にあたることを証明しなければなりません。この判断基準が「実質的類似性(Substantial Similarity)」です。
① 実質的類似性の2つの態様
「実質的類似性」は、2つの異なる形で現れます。
- 逐語的類似性(Verbatim Similarity):
これは、歌詞の一節、小説の数段落、プログラムのコードの一部といった、著作物の特定の部分を文字通り、あるいはほぼそのままコピーすることです。作品全体をコピーする必要はなく、たとえ量的に僅かであっても、それが作品の質的な「核心部分(heart of the work)」であれば、実質的類似性が認められます。 - 非逐語的類似性(Non-Literal Similarity / Pattern Similarity):
これは、個々の言葉や音符をそのままコピーするのではなく、プロット・登場人物・場面展開・構成・全体の雰囲気といった、著作物の全体的なパターンや構造(structure, sequence, and organization)」を盗用することです。巧妙なパラフレーズや、小説を映画化するような媒体の変換を伴う侵害は、主にこの非逐語的類似性が問題となります。
② 非逐語的類似性の判断手法(「抽象化テスト」)
非逐語的類似性を判断する上で、どこまでが保護されない「アイデア」で、どこからが保護される「表現」なのか、その境界線を引くことは極めて困難です。この難問に対する最も有名な分析手法が、ラーンド・ハンド判事がNichols v. Universal Pictures Corp.事件で示した「抽象化テスト(Abstractions Test)」です。
ハンド判事は、いかなる作品もその具体的な要素を削ぎ落としていくことで、より一般的・抽象的なパターンの連続として捉えることができると述べました。この抽象化の階段を上っていくと、ある地点でそれは保護される「表現」ではなく、誰もが自由に利用できる「アイデア」の領域に入ります。実質的類似性の判断とは、被告が盗用したのが、この階段のどのレベルにある要素なのかを見極める作業なのです。
この「抽象化テスト」は、特にコンピュータソフトウェアの非逐語的類似性が争われた一連の訴訟で、その現代的な意義が再確認されました。初期のWhelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.判決は、プログラムの「目的」をアイデアとし、それ以外の構造・順序・構成(SSO)はすべて表現であるという、過度に保護的なアプローチを取りました。しかし、その後の主流となったComputer Associates Int’l, Inc. v. Altai, Inc.判決は、このWhelanのアプローチを退け、ハンド判事の思考法に立ち返る、より精緻な三段階の分析手法を確立しました。
- Altaiの三段階テスト(Abstraction-Filtration-Comparison Test):
- 抽象化(Abstraction): まず、原告のプログラムを、コードレベル(最も具体的)・構造・モジュール・アルゴリズム・機能レベル(最も抽象的)まで、様々な抽象度の階層に分解する。
- 濾過(Filtration): 次に、各階層の要素を分析し、著作権法で保護されない要素を「濾過」して取り除く。取り除かれる要素には、①アイデアそのもの、②表現がアイデアと融合(merge)してしまっている要素、③外的要因によって事実上表現が決定されてしまう要素(scènes à faire)、④パブリックドメインから取られた要素等が含まれます。
- 比較(Comparison): 最後に、濾過を経て残った「保護されるべき表現の核心(golden nugget)」と、被告のプログラムの対応する要素とを比較し、両者の間に実質的類似性が認められるかを判断する。
このAltaiテストは、ソフトウェアに限らず、機能的・事実的要素を多く含む著作物の侵害分析における標準的な手法となっています。
③ 侵害判断の主体(「一般の聴衆」の視点)
実質的類似性を最終的に判断するのは誰か。裁判実務では、「一般の聴衆(Ordinary Observer / Audience)」の視点が基準とされます。専門家による分析的な分解ではなく、その著作物の本来の受け手である一般人が、両作品に接したときに、被告の作品が原告の作品から流用されたものであると感じるかどうかが問われるのです。ただし、コンピュータプログラムのように専門的な知識を持つ受け手を想定した作品の場合、裁判所は、その分野の専門知識を持つ「一般の聴衆」の視点を採用することもあります。
第2部 間接侵害(第三者の責任)
著作権侵害の責任は、直接コピー行為を行った者だけに限定されません。特定の状況下では、侵害行為を助長したり、侵害行為から利益を得たりした第三者も間接侵害(Indirect Infringement)として責任を問われます。間接侵害には、主に2つの類型があります。
1. 寄与侵害(Contributory Infringement)
寄与侵害は、他人の直接侵害行為を知りながら、その侵害を誘発したり、実質的にそれに貢献したりする場合に成立します。
この理論が現代において大きな試練に直面したのが、家庭用ビデオデッキ(VCR)の登場でした。Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.(ベータマックス事件)で最高裁は、ある製品が、実質的な非侵害用途(substantial non-infringing uses)に堪えるものである限り、たとえそれが侵害目的で使われることがあっても、その製造者は寄与侵害の責任を負わない、という「ソニー・ルール」を確立しました。
この「ソニー・ルール」は、その後のファイル共有ソフトを巡る訴訟で再び中心的な争点となりました。MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.事件で最高裁は、新たな判断基準を示しました。たとえ技術的に非侵害用途に用いることが可能であったとしても、侵害を助長する目的で製品を頒布した者は、その結果生じた侵害について責任を負うという「誘発理論(Inducement Theory)」です。Grokster社が、かつてのNapsterユーザーをターゲットに自社製品を宣伝するなど、積極的に違法コピーを奨励していた証拠が、この判断の決め手となりました。
2. 代位責任侵害(Vicarious Infringement)
代位責任侵害は、直接の侵害行為に対する指揮監督権を有し、かつ、その侵害行為から直接的な金銭的利益を得ている場合に、たとえ侵害の事実を具体的に知らなくても成立します。この理論の古典的な例は、店内でバンドに生演奏をさせている飲食店の経営者です。経営者はバンドの演奏内容に対して指揮監督権を持ち、その演奏が集客につながり金銭的利益を得ているため、バンドが無許諾で楽曲を演奏した場合に代位責任を負います。
第3部 救済措置:権利回復のための法的手段
著作権侵害が認定された場合、権利者は裁判所に対して様々な救済措置を求めることができます。
1. 差止命令(Injunctive Relief)
差止命令は、侵害行為を将来にわたって停止させるための、最も基本的かつ強力な救済措置です。緊急性がある場合は仮差止命令が、判決後には恒久的な差止命令が発せられます。近年の最高裁判決(eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.)により、差止命令の発令にあたっては、より慎重な判断が求められるようになっています。
2. 損害賠償及び利益の掃き出し(Damages and Profits)
権利者は、侵害行為によって被った金銭的損害の回復を求めることができます。このとき、原告は以下の2つの選択肢から、いずれか有利な方を選ぶことができます。
① 実損害 + 侵害者の利益
- 実損害(Actual Damages): 侵害行為がなければ得られたであろう原告の逸失利益(ライセンス料収入の喪失等)や著作物の市場価値の低下分等
- 侵害者の利益(Infringer’s Profits): 被告が侵害行為によって得た利益。原告は被告の総売上を証明すればよく、そこから差し引かれるべき経費や、侵害と無関係な利益の割合(寄与度)を証明する責任は被告側にあります。
② 法定損害賠償(Statutory Damages)
実損害や利益の立証が困難な場合に備えて、著作権法は、裁判所が一定の範囲内で裁量的に賠償額を決定できる法定損害賠償の制度を設けています。
- 賠償額の範囲:
- 通常の場合:1侵害著作物あたり $750 ~ $30,000
- 侵害が故意(willful)と認定された場合:最大 $150,000
- 侵害者が善意無過失(innocent)と認定された場合:最小 $200
- 利用の条件: 法定損害賠償を請求するためには、原則として、侵害が発生する前に著作権登録が完了している必要があります。
- 陪審による決定権: 連邦最高裁はFeltner v. Columbia Pictures Television, Inc.事件で、法定損害賠償額を決定する権利は、陪審にあるとの判断を示しました。
3. 訴訟費用および弁護士費用
裁判所は、その裁量により、勝訴当事者(prevailing party)が負担した合理的な弁護士費用を含む訴訟費用を、敗訴当事者に支払うよう命じることができます。Fogerty v. Fantasy, Inc.事件で最高裁は、この裁量的判断にあたり、勝訴したのが原告か被告かで区別することなく公平に考慮すべきであるとの指針を示しました。
4. 刑事罰
著作権侵害は、故意かつ商業的利益・私的金銭的利得のために行われた場合、犯罪とされ、罰金や禁固刑が科されます。特に、1997年のNo Electronic Theft (NET) Actは、金銭的利益を目的としない大規模な侵害行為(例えば、インターネット上での大規模なソフトウェアの無償配布)も処罰の対象とし、デジタル時代の海賊行為に対する刑事的執行を強化しました。
第4部 訴訟手続上の重要事項
1. 著作権登録(訴訟提起の前提条件)
アメリカ国籍の著作物については、著作権侵害訴訟を連邦裁判所に提起するための前提条件として、その著作物が著作権局に登録されていることが必要です。Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC事件で最高裁は、単に登録申請をしただけでは足りず、著作権局がその申請を認めるか拒絶するかの判断を下した後でなければ訴訟を提起できないことを明確にしました。
2. 時効(Statute of Limitations)
著作権侵害に対する民事訴訟は、請求権が発生してから3年以内に、刑事訴追は5年以内に提起しなければなりません。近年の最高裁判決(Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.)は、原則として各侵害行為の発生時から個別に時効が進行する「侵害時ルール(injury rule)」が適用されるべきであるとの方向性を示しました。これにより、3年以上前の侵害行為に対する損害賠償請求は原則として認められませんが、差止命令のような衡平法上の救済の可能性は残されています。
3. 懈怠(Laches)
衡平法上の抗弁であるラケス(懈怠)は、原告が不当に長期間権利行使を怠ったために被告に不利益が生じた場合に、権利行使を制限するものです。しかし、Petrella判決は、時効期間内に提起された損害賠償請求を、ラケスを理由に棄却することはできないと判断しました。