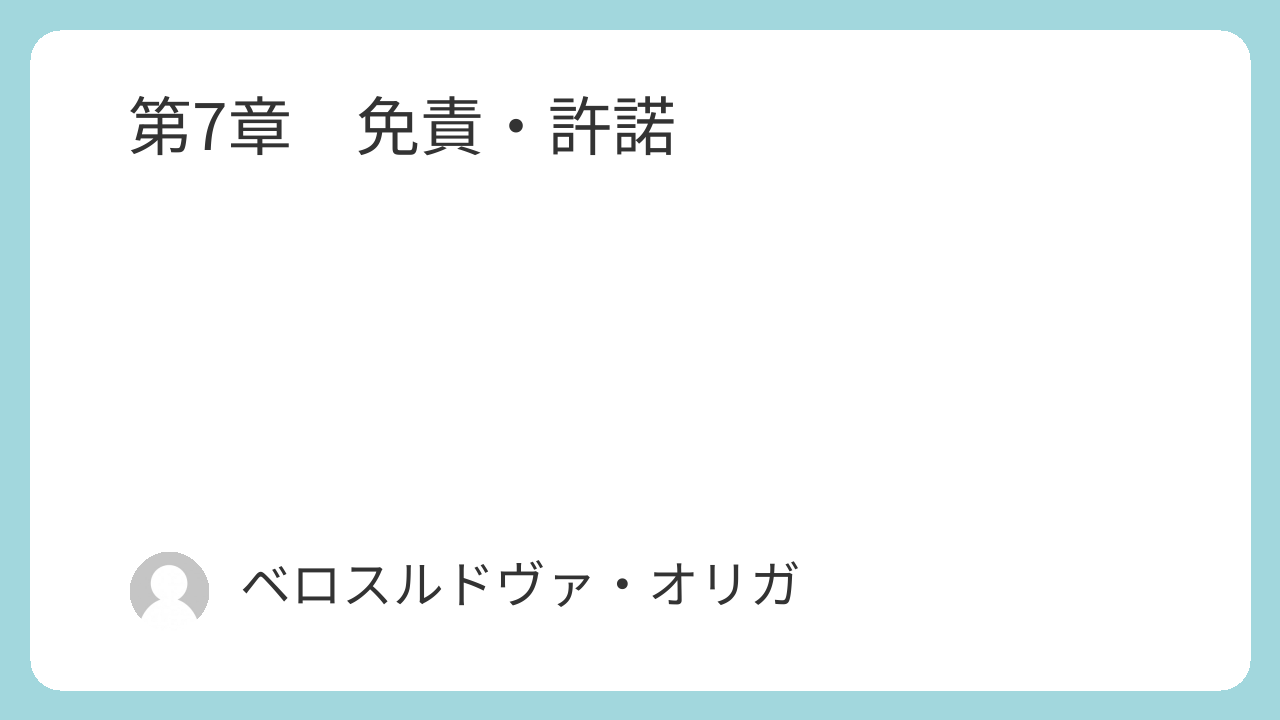前章で見たフェアユースは、著作権者の権利に対する包括的かつ柔軟な制限であり、裁判所が事案ごとに衡平の理念に照らして判断を下すための重要な指針です。しかし、著作権法は、特定の状況下における著作物の利用について、より明確で具体的なルールも規定しています。それが、著作権法108条から122条に定められた、一連の免責規定(Exemptions)と強制許諾制度(Compulsory Licenses)です。
これらの権利制限規定は、フェアユースのような曖昧さを排し、特定の利用者(例えば、図書館、教育機関、放送事業者等)が、どのような条件下で著作物を利用できるかを具体的に定めています。これらは、社会の様々な場面における情報へのアクセスを確保し、円滑な文化的・経済的活動を促進するために、議会が政治的な判断と産業界の利害調整を経て設けたものです。
本章では、これらのフェアユース以外の重要な権利制限について、その目的と具体的な内容を解説していきます。
1. 教育・宗教・非営利目的での実演・展示(110条)
著作権法110条は、特に教育や宗教活動といった公共性の高い分野における著作物の利用を円滑にするため、公の実演権及び展示権に対する一連の免責規定を設けています。
① 対面教育活動における免責(§ 110(1))
非営利教育機関において、教員・学生が対面式の教育活動の一環として著作物を実演または展示する行為は著作権侵害とはなりません。これは、伝統的な教室での授業を想定した、最も基本的な教育免責です。
- 場所: 授業が行われる教室やそれに類する場所に限定されます。学校の講堂で行われる、父兄も参加するような娯楽目的の演奏会は、この免責の対象外です。
- 主体: 教員または学生による実演・展示に限られます。
- 対象著作物: 映画を含む、あらゆる種類の著作物が対象となりますが、使用されるコピーが不法に作成されたものであることを知っていた場合は適用されません。
② 遠隔教育における免責 ― TEACH Act(§ 110(2))
デジタルネットワークの発展に伴い、オンラインでの遠隔教育が普及しました。これに対応するため、2002年に制定されたTEACH Actは、110条2項を大幅に改正し、遠隔教育における著作物利用の免責範囲を拡大しました。
- 対象: 認定された非営利教育機関や政府機関による、組織的な教育活動の一環としての送信が対象です
- 利用できる著作物:
- 非演劇的な文学・音楽作品:全体の実演が可能
- その他の著作物(映画、演劇的な音楽作品など):合理的かつ限定された部分の実演・展示が可能
- 厳格な条件: 免責を受けるためには、教育機関は以下のようないくつかの厳格な技術的・制度的条件を満たす必要があります。
- アクセスをその授業の履修者に限定すること
- 受講者が授業期間を超えて著作物を保持したり、さらに他者に頒布したりすることを合理的に防ぐための技術的措置を講じること
- 著作権に関するポリシーを定め、学生に周知すること
③ 宗教的儀式における免責(§ 110(3))
礼拝所やその他の宗教的な集会において、儀式の一環として非演劇的な文学・音楽作品又は宗教的な性質を持つ演劇的音楽作品(オラトリオ、ミサ曲など)を実演する行為は、著作権侵害とはなりません。
この免責は、あくまで宗教「儀式」の過程に限定されます。したがって、同じ教会で行われるものでも、社交・教育・資金集めを目的としたコンサート等は対象外です。また、礼拝の様子をテレビやインターネットで広く一般に放送・配信する行為も、この免責には含まれません。
④ その他の非営利目的の実演(§ 110(4))
これは、特定の条件下で行われる非営利の公開演奏会などを想定した、より一般的な免責規定です。適用されるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 直接的または間接的な商業的利益を目的としないこと
- 実演者・プロモーター・主催者に対していかなる報酬も支払われないこと
- 入場料を徴収しないこと
ただし、入場料を徴収する場合でも、その収益から経費を差し引いた全額が、教育的・宗教的・慈善的目的のために使われるのであれば、免責が認められる可能性があります。しかし、この場合には、著作権者が公演の7日前までに書面で反対の通知をすれば、その公演を拒否する権利(Veto Power)を持っています。これは、著作者が自らの意に反する目的の資金集めに、その作品が利用されることを防ぐための規定です。
⑤ 家庭用受信機の公衆への伝達 ― Aiken免責(§ 110(5))
店舗やレストランが、BGMとしてラジオやテレビを流す行為は、形式的には「公の実演」に該当します。この問題について、1975年の連邦最高裁判決(Twentieth Century Music Corp. v. Aiken)は、小規模なファストフード店が家庭用のラジオといくつかのスピーカーで放送を流す行為は、著作権侵害に当たらないと判断しました。
この判決の趣旨を成文化したのが110条5項で、通称「Aiken免責」と呼ばれます。1998年の音楽ライセンス公正法(Fairness in Music Licensing Act)による改正で、この免責は2つのカテゴリーに分けられ、その適用範囲がより明確化・拡大されました。
- A. Homestyle Exemption(家庭用免責):
- 店舗の規模にかかわらず、家庭で通常使用されるような単一の受信装置(例:ポータブルラジオ、テレビ)で放送を受信して流す行為は、入場料を徴収せず、さらにそれを再送信しない限り免責されます
- B. Business Exemption(事業用免責):
- より大規模な装置を使用する場合でも、以下の面積基準または設備基準を満たせば免責されます。
- 面積基準: 飲食店以外の事業所は2,000平方フィート(約186㎡)未満、飲食店は3,750平方フィート(約348㎡)未満であること
- 設備基準: 上記面積を超える場合でも、使用するスピーカーが6台以下(天井埋め込み型は4台以下)、テレビが4台以下(画面サイズ55インチ以下)であること
- より大規模な装置を使用する場合でも、以下の面積基準または設備基準を満たせば免責されます。
この規定により、多くの中小規模の店舗やレストランは、ASCAPやBMIといった演奏権管理団体からライセンスを取得することなく、店内でラジオやテレビを流すことが可能になっています。
2. 図書館・文書保管機関における複製(108条)
図書館や文書保管機関は、知識の保存とアクセスを担う重要な社会的機関です。108条は、これらの機関がその公共的使命を果たすために、一定の条件下で著作物を複製し、頒布することを認める特別な免責規定です。これは、フェアユースとは別に設けられた、図書館のための具体的な権利制限規定です。
免責の基本条件
免責を受けるために、図書館・文書保管機関は以下の基本条件を満たす必要があります。
- 複製・頒布が、直接的・間接的な商業的利益を目的としないこと
- その蔵書が公衆に開かれているか、その分野の研究者に利用可能であること
- 複製物には著作権表示を含めること
認められる複製の種類
- 保存・保全のための複製: 蔵書が損傷・劣化・紛失した場合又はその形式が旧式化した場合に、保存目的で最大3部まで複製を作成することが認められています。デジタル形式で複製することも可能ですが、そのデジタルコピーを図書館の敷地外で公衆に利用可能な形にしてはなりません。
- 利用者の求めに応じた複製(ILL:図書館間相互貸借など):
- 著作物の一部: 利用者が学術・研究目的で利用する場合、その利用者のために一部を複製して提供することができます。
- 著作物全体: 図書館による合理的な調査の結果、その著作物が公正な価格で新品を入手できないと判断された場合に限り、全体を複製して提供することができます。
「組織的複製」の禁止
108条の免責には重要な制限があります。それは、「組織的な(systematic)」複製・頒布の禁止です。これは、図書館が事実上の出版社のようになり、著作物の購入や購読の代替となるような規模でコピーを提供することを防ぐためのものです。例えば、ある企業が特定の雑誌を購読する代わりに、その都度、図書館に論文のコピーを大量に依頼するような行為は、この「組織的複製」に該当し免責の対象外となります。
3. コンピュータプログラムの所有者による複製・翻案(117条)
コンピュータプログラムは、その性質上、利用するためにハードディスクにコピー(インストール)したり、万一の際に備えてバックアップを取ったりする必要があります。117条は、このようなコンピュータプログラム特有の利用実態に鑑み、プログラムの適法なコピーの所有者に限定的な複製権と翻案権を認めるものです。
- ① 実行のための複製(Essential Step Copy): プログラムをコンピュータで利用するために不可欠な工程として作成されるコピー(例:RAMへの読み込み、ハードディスクへのインストール)は、適法とされます。
- ② バックアップのための複製(Archival Copy): 機械的な故障などによる破壊や損傷に備えて、保存目的でのみバックアップコピーを作成することが認められています。ただし、元のプログラムの所有権を失った場合(売却した場合など)は、バックアップコピーも破棄しなければなりません。
この条文で重要なのは、免責の主体がプログラムの「所有者(owner)」に限定されている点です。多くのソフトウェアは、「販売」ではなく「ライセンス」という形式で提供されており、利用者は単なる「ライセンシー(licensee)」であって「所有者」ではない、とメーカーは主張してきました。この解釈に従うと、117条の免責はほとんど適用されないことになります。しかし裁判所は、ライセンス契約の内容にかかわらず、利用者が対価を支払って永続的な占有権を得ているような場合には、実質的な「所有者」と見なすという、より現実的な解釈を示す傾向にあります。
また、1998年のDMCAによる改正で、コンピュータの修理・メンテナンスのために機械を起動した結果として、プログラムがRAMに自動的にコピーされる行為も侵害とはならないことが明確化されました。これは、MAI Systems判決が修理業者に与えた影響を是正するためのものです。
4. 強制許諾制度:交渉によらない利用の枠組み
強制許諾(Compulsory License)は、著作権者が許諾を拒否したとしても、利用者が法律の定める手続に従い、定められた使用料(ロイヤリティ)を支払うことで、著作物を強制的に利用できる制度です。これは、特定の産業分野において著作権者の独占権が過度に強くなることを防ぎ、円滑な作品利用を促進するために設けられた市場メカニズムへの例外的介入です。使用料の料率は、著作権使用料委員会(Copyright Royalty Board, CRB)という専門機関によって定期的に決定・調整されます。
① 音楽の機械的ライセンス(メカニカル・ライセンス)(§ 115)
これは、最も古くから存在する強制許諾制度です。一度、音楽作品がレコードとして適法に頒布されると、その後は誰でも、その楽曲の「カバー」バージョンを自ら演奏・歌唱して録音し、レコードとして販売することができます。
- 歴史的背景: 20世紀初頭、特定のピアノロール製造会社が人気楽曲の権利を買い占め、市場を独占することを防ぐために導入されました。
- 対象: 非演劇的な音楽作品に限られます。オペラやミュージカルの楽曲は対象外です。
- 制限: 許諾されるのは、あくまで自分で新たに演奏を録音することです。他人のレコード(原盤)をそのままコピーすることは、録音物の著作権(原盤権)の侵害となり、この制度では許諾されません。また、楽曲の基本的なメロディや性格を変えるような大幅な編曲も許されません。
- 音楽近代化法(MMA)による改革: 2018年の音楽近代化法は、デジタルストリーミング時代に対応するため、この制度を抜本的に改革しました。特にデジタル配信については、機械的ライセンス団体(Mechanical Licensing Collective, MLC)という単一の組織が、Spotifyのようなストリーミングサービスに対して包括的なライセンス(Blanket License)を発行し、使用料を一括して徴収・分配する仕組みが導入され、2021年から施行されています。これにより、デジタルサービス事業者は、楽曲ごとに許諾を得るという煩雑な手続きから解放されました。
② ケーブルテレビ・衛星放送による再送信(§ 111, § 119, § 122)
ケーブルテレビ局や衛星放送事業者は、遠隔地の放送局の電波を受信し、それを自らのサービスエリア内の加入者に再送信しています。この再送信行為は「公の実演」に該当しますが、放送される膨大な番組それぞれについて許諾を得ることは事実上不可能です。そのため、これらの事業者には、CRBが定める使用料を支払うことで、放送信号を再送信できる強制許諾が与えられています。この制度は、放送局、番組の著作権者、ケーブル・衛星事業者といった巨大産業間の利害を調整する複雑な規制となっています。