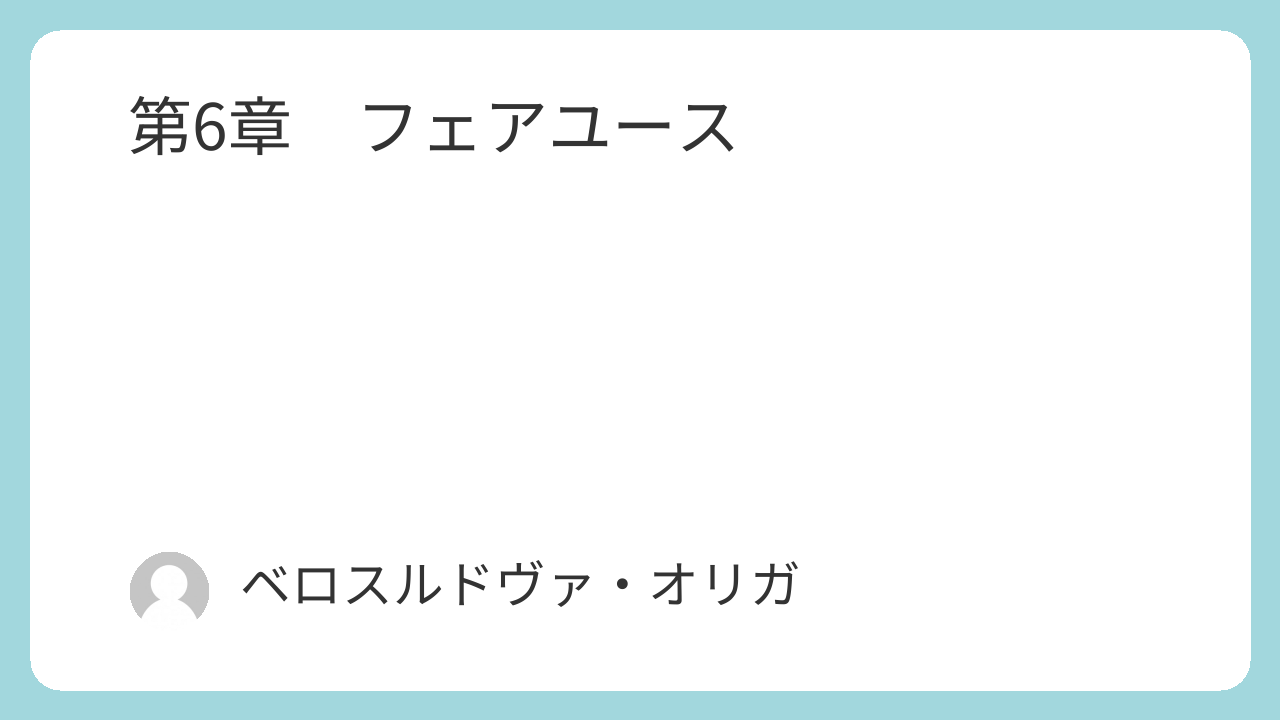著作権法は、著作者に強力な排他的権利を与える一方で、その権利が社会における自由な言論や創造活動を不当に抑制することのないようバランスをとっています。その中核をなし、アメリカ著作権法において最も重要かつ難解な法理が「フェアユース(Fair Use)」です。
フェアユースとは、著作権者の許諾を得ることなく、著作物を一定の条件下で「公正に」利用することを認める、裁判所によって形成されてきた法理上の抗弁です。著作権法の厳格な適用が、かえってその究極目的である「科学および有用な技術の進歩の促進」を阻害してしまうような場合に、裁判所が衡平の精神に基づき、侵害の成立を否定することを可能にします。
この法理は、1976年著作権法107条に明文化されましたが、その条文はフェアユースを厳密に定義するものではありません。むしろ、判例法の中で培われてきた柔軟なアプローチを維持し、新たなテクノロジーや社会の変化に対応できるよう、あえて曖昧さを残した設計となっています。そのため、フェアユースの判断は、依然として「ケースバイケースの理性のルール(equitable rule of reason)」に委ねられており、「著作権法において最も厄介な問題」とも評されます。
1. フェアユースとは何か(歴史的背景と「変容的利用」)
歴史的起源:Folsom v. Marsh事件
フェアユースの源流は、1841年の巡回裁判所判決、Folsom v. Marsh事件に遡ります。この事件では、ジョージ・ワシントンの書簡を含む伝記の著作権者が、被告がその書簡を353ページ分も引用して別の伝記を出版した行為を訴えました。ジョセフ・ストーリー判事は、侵害を認定するにあたり、将来のフェアユース分析の礎となる判断基準を示しました。
「我々は、選択の性質と目的、使用された素材の量と価値、そしてその利用が原作の販売を妨げ、利益を減少させ、またはその目的を代替する度合いを検討しなければならない。」
これらの3つの要素(①利用の性質と目的、②利用の量と価値、③市場への影響)は、驚くほど現代のフェアユース分析の枠組みと一致しており、180年以上経った今もなお、この法理の根幹をなしています。
107条の構造と「変容的利用(Transformative Use)」
1976年著作権法107条は、この判例法の伝統を成文化したものです。条文は、まず前文でフェアユースに該当しうる利用目的の例として「批評、コメント、ニュース報道、教育(教室での複数コピーを含む)、学術、研究」を挙げています。これらはあくまで例示であり、これらに限定されるものではありません。
そして、フェアユースか否かを判断する際に考慮すべき4つの要素を定めています。
- 使用の目的と性格(the purpose and character of the use)
- 著作物の性質(the nature of the copyrighted work)
- 使用された部分の量と実質性(the amount and substantiality of the portion used)
- 著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響(the effect of the use upon the potential market for, or value of, the copyrighted work)
裁判所は、これら4つの要素を機械的に適用するのではなく、総合的に比較衡量して結論を導き出します。
近年のフェアユース分析において、これら4要素を横断する極めて重要な概念として台頭してきたのが「変容的利用(Transformative Use)」という考え方です。これは、ピエール・ルヴァル判事が提唱し、1994年の連邦最高裁判決であるCampbell v. Acuff-Rose Music, Inc.事件(後述するパロディの事例)で全面的に採用されました。
変容的利用とは、元の著作物を単に複製するのではなく、それに「新たな表現・意味・メッセージ」を付け加え、元の作品とは異なる目的や性格を持つ新しい何かに「変容」させる利用を指します。批評家が作品を引用して論評を書くといった行為やパロディ作家が元の歌を風刺的に作り変えるといった行為がその典型例です。
変容的利用がフェアユース分析において重視されるのは、それが著作権法の究極的な目的である「進歩の促進」に直接貢献するからです。単なる複製(代替的利用)は、元の作品の市場を奪うだけで新たな価値を生みませんが、変容的利用は、元の作品を土台として新たな創造物を社会にもたらします。したがって、ある利用が変容的であればあるほど、他の要素(例えば商業的利用であること)が不利に働いたとしても、フェアユースと認められる可能性が高まります。
しかし、この「変容」という言葉は、著作権者が専有する翻案権(二次的著作物を作成する権利)における「変形(transform)」という言葉と重なるため、両者の境界線が問題となります。この点について、近年の連邦最高裁判決(Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith)は、フェアユースにおける変容的利用は、二次的著作物となるための変形を超えるものでなければならず、特に二次的利用の目的が、元の著作物の目的と同じか、酷似している場合には、変容的とは言えないとの考え方を示しました。これにより、単に媒体を変えたり、スタイルを変えたりしただけでは変容的利用とは認められにくくなり、その利用が社会にどのような新たな価値や目的をもたらすのかという点がより一層問われることになったのです。
2. フェアユースを判断するための4つの要素
第1要素:使用の目的と性格
この要素は、利用者が著作物を「何のために、どのように」使ったのかを問います。分析の軸は主に2つあります。
① 変容的利用か、代替的利用か
前述の通り、これが最も重要な分析軸です。利用が変容的であれば、この要素は利用者に有利に働きます。例えば、Google Books事件(Authors Guild, Inc. v. Google, Inc.)では、Googleが膨大な書籍をスキャンして全文検索可能なデータベースを構築した行為が争われました。裁判所は、この行為は書籍を読むという本来の目的とは全く異なる、「検索」という新たな機能を提供する高度に変容的な利用であると認定し、フェアユースを認める上での最も重要な要素としました。
② 商業的利用か、非営利教育目的か
条文が明記するように、利用が商業的か非営利かも重要な考慮要素となります。商業的利用は、それ自体がフェアユースを否定するものではありませんが、一般にフェアユースの主張を弱める方向に働きます。特に、利用が変容的でなく、単なる代替的利用である場合、その商業性はフェアユースの成立を極めて困難にします。Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.(ベータマックス事件)では、家庭内でのテレビ番組のタイムシフティング(録画して後で見る)行為が、非商業的な私的利用であることがフェアユース認定の重要な根拠となりました。
また、非営利の教育目的での利用は、フェアユースに有利に働きます。ただし、教育目的であっても無制限に許されるわけではありません。例えば、大学教授向けのコピーサービス業者が、教員の依頼で教科書の各章をコピーして「コースパック」として製本・販売したPrinceton University Press v. Michigan Document Services, Inc.事件では、コピーサービス業者の行為は商業的であり、大学のライセンス市場を害するとして、フェアユースが否定されました。
第2要素:著作物の性質
この要素は、利用された元の著作物がどのような性格を持つかが問題となります。ここでの分析軸は主に2つあります。
① 事実に基づく著作物か、創作性の高い著作物か
著作権法の保護は、事実そのものではなく表現に及びます。したがって、歴史書・科学論文・ニュース記事といった事実や情報に重きを置く著作物の方が、小説・詩・音楽といった著作者の想像力や感性が色濃く反映された創作性の高い著作物よりも、フェアユースが認められる範囲は広いです。後者は著作権保護の「核心(core)」に位置するため、他者による利用はより厳しく制限されます。
② 刊行済みか、未刊行か
著作者は、自らの作品をいつどのような形で世に出すかを決定する権利(最初の公表権)を持ちます。そのため、未刊行の著作物の利用は、当該権利を侵害する可能性が高く、フェアユースの主張は認められにくくなっています。
この点を厳格に適用したのが、フォード元大統領の未刊行の回顧録から約300語を無断で引用した雑誌社を訴えたHarper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises事件です。最高裁は、引用された部分は量的に僅かでも、回顧録の「核心部分(heart of the work)」であり、何よりも作品が未刊行であったことが決定的な要因であるとして、フェアユースを否定しました。この判決を受けて、議会は後に107条を改正し、「作品が未刊行であるという事実それ自体は、フェアユースの認定を妨げるものではない」という一文を加えましたが、未刊行であるという事実は、依然としてフェアユースに不利に働く要素となっています。
第3要素:使用された部分の量と実質性
この要素は、元の著作物全体との関係で、利用された部分がどれくらいの量で、どれほど重要かを問題とします。分析は量的(quantitative)・質的(qualitative)両方の側面から行われます。
量的側面
利用された部分の絶対量や、全体に占める割合が考慮されます。当然ながら、作品全体をコピーする行為は、フェアユースの成立を著しく困難にします。ベータマックス事件やGoogle Books事件のように、技術的な過程で一時的に作品全体がコピーされる場合でもフェアユースが認められることはありますが、それは極めて例外的なケースです。
質的側面
量的に僅かであっても、それが作品の「核心部分」である場合、この要素は利用者に不利に働きます。前述のHarper & Row事件で引用されたのがわずか300語であったにもかかわらずフェアユースが否定されたのは、その部分が質的に極めて重要だったからです。
パロディの文脈では、この要素は「元の作品を想起(conjure up)させるのに必要な範囲を超えていないか」という基準で判断されます。パロディは、鑑賞者が元の作品を思い浮かべなければ成立しないため、ある程度の引用は不可欠です。しかし、必要以上に元の作品の要素を取り込み、単なる「安上がりな笑い」のために元の作品にフリーライドしていると見なされれば、フェアユースの範囲を逸脱していると判断されます。
第4要素:著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響
この要素は、「フェアユース分析において、疑いなく最も重要な単一の要素」と最高裁が位置づけるほど、決定的な意味を持ちます(Harper & Row事件)。これは、利用者の行為が、元の著作物の現在の市場及び将来展開されうる潜在的な市場(derivative markets)にどのような悪影響を及ぼすかを問うものです。
市場の代替(Market Substitution)
考慮されるべき最も直接的な害は、二次的利用が元の著作物の需要を代替してしまうことです。もし消費者が、二次的利用物があれば元の著作物を購入する必要がなくなると感じるのであれば、それは市場への直接的な害となります。例えば、楽曲のファイル共有は、CDや有料ダウンロードの市場を直接的に代替するため、この要素は極めて不利に働きます(A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.事件)。
ライセンス市場への影響
直接的な代替関係になくても、その利用が、著作権者が通常ライセンスを与えているような市場や将来ライセンスを与える可能性のある市場からの収益を奪う場合も、市場への悪影響と見なされます。American Geophysical Union v. Texaco Inc.事件では、企業の研究所の研究者が科学雑誌の記事を系統的にコピーしていた行為が、出版社が運営するコピー許諾センター(Copyright Clearance Center)を通じて得られるはずだったライセンス料収入を失わせるとして、フェアユースが否定されました。
変容的利用と市場への影響
利用が変容的であればあるほど、元の著作物の市場を代替する可能性は低くなります。批評やパロディは、元の作品の市場とは異なる市場を形成し、むしろ元の作品への関心を喚起することさえあります。しかし、Warhol事件が示したように、たとえ変容的であっても、二次的利用が元の著作物と同じ商業的市場(この場合は雑誌の表紙イラスト)で直接競合する場合、市場への悪影響は否定できません。
3. フェアユースの具体的な適用例
パロディ
パロディは、フェアユースが保護すべき重要な表現形式と考えられています。Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.事件で最高裁は、ラップグループ「2 Live Crew」によるロイ・オービソンの名曲「Oh, Pretty Woman」のパロディを分析しました。最高裁は、たとえ商業目的であっても、パロディの変容的な性格を重視し、フェアユースが成立しうると判断しました。ここでの重要な点は、パロディが単なるユーモラスな模倣に留まらず、元の作品のスタイルやメッセージに対して批評的なコメントを加えている必要があるという点です。元の作品を単なる「踏み台」として、全く別の社会事象を風刺するような場合は、フェアユースの保護を受けるのは難しいです。
リバースエンジニアリング
コンピュータソフトウェアの分野では、競合製品のプログラムを分析して、互換性のある製品を開発するためにリバースエンジニアリングが行われることがあります。この過程では、機械語で書かれたオブジェクトコードを、人間が読めるソースコードに逆変換(逆コンパイル)する必要があり、技術的に著作物の「複製」が伴います。Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc.事件では、セガ社のゲーム機で動作する互換ゲームソフトを開発するために、Accolade社がセガ社のプログラムをリバースエンジニアリングした行為が争われました。裁判所は、プログラムに含まれる保護されないアイデアや機能的要素にアクセスする唯一の方法がリバースエンジニアリングである場合、その過程で生じる中間的な複製は、変容的な目的を持つフェアユースであると判断しました。これは、著作権がソフトウェアのアイデアや機能を不当に独占する手段となることを防ぐための重要な判断でした。
生成AIとフェアユース
現在、フェアユースの最前線となっているのが、生成AI(Generative AI)です。ChatGPTのような生成AIモデルは、インターネット上から収集した膨大なテキストや画像データ(その多くは著作物)を「学習」することで、新たなコンテンツを生成します。この学習過程における著作物の利用は、フェアユースに当たるのでしょうか。
AI開発企業側は、学習はGoogle Booksの検索データベース構築と同様に、元の作品とは全く異なる目的(AIモデルのトレーニング)のための変容的利用であり、フェアユースであると主張します。彼らは、個々の著作物の表現をAIが記憶・出力するわけではなく、あくまで統計的なパターンを学習しているに過ぎないと説明します。
一方、クリエイターや著作権者側は、AIの生成物が元のクリエイターの市場(イラスト制作、記事執筆など)を直接代替し、ライセンス市場を破壊するものであり、フェアユースには当たらないと強く反発しています。また、学習データとして自らの作品が無断で利用されること自体が不公正であると主張します。
この問題は、フェアユースの4要素すべてにわたる複雑な論点を含んでおり、現在、米国各地で多数の訴訟が進行中です。裁判所が、AIの学習という新たな利用形態を、変容的利用と捉えるのか、それとも市場を破壊する代替的利用と捉えるのか。その判断は、今後のクリエイティブ産業とテクノロジーの未来を大きく左右することになるでしょう。