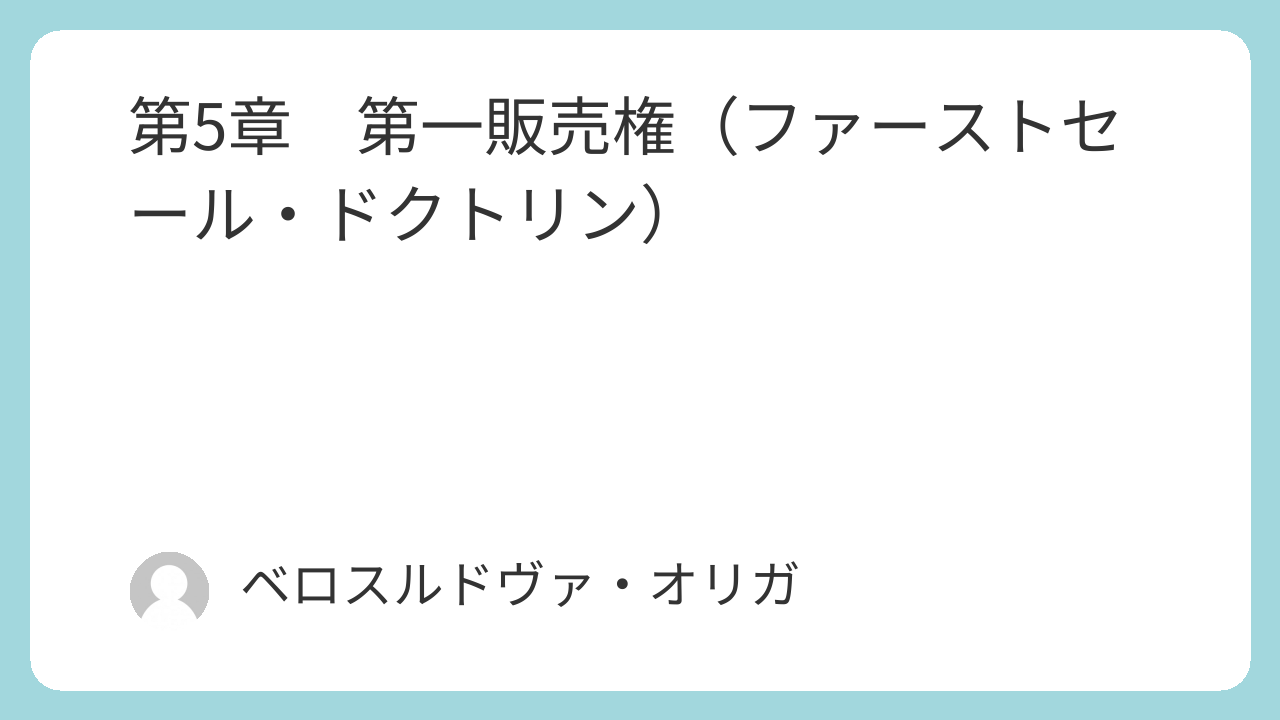前章で解説したように、著作権者は著作物のコピー(書籍、CD、DVDなど)を公衆に頒布する排他的な権利を有しています。しかし、一度適法に販売された書籍を、購入者が古本として友人に売る場合にも、著作権者の許諾が必要になるとすれば、中古市場は成り立たず、図書館が本を貸し出すことも、友人間でCDを貸し借りすることも、すべて著作権侵害になってしまいます。
このような不都合を回避し、有体物の自由な流通を確保するために、アメリカ著作権法が設けている極めて重要な権利制限が「第一販売権(First Sale Doctrine)」です。これは、著作権法109条(a)項に定められており、「権利消尽の原則」とも呼ばれます。
1. 第一販売権の原則
第一販売権の原則は、「著作権者の許諾を得て適法に作成された特定のコピー又はレコードの所有者は、著作権者の許諾なしに、そのコピー又はレコードの占有を販売その他の方法で処分することができる」と定めています。
平たく言えば、「一度適法に売られた物(複製物)の所有者は、その物を自由に転売したり、貸したり、譲渡したりできる」ということです。著作権者の頒布権は、その特定の「物」が最初に販売(First Sale)された時点で「消尽(exhausted)」し、それ以降の流通には及ばないのです。
この法理は、著作権という無体財産権と、その著作物が固定された書籍やCDといった有体物の所有権とを明確に分離するものです。著作権者は、作品の最初の販売を通じて利益を得る機会を保障されますが、一度市場に投入された個々の「物」の運命までを永久に支配することはできません。これにより、著作権者の利益と、社会における物品の自由な流通という2つの要請のバランスが図られています。
この原則がアメリカの判例法で確立されたのは、1908年の連邦最高裁判決、Bobbs-Merrill Co. v. Straus事件です。この事件で出版社は、自社が出版する書籍に「1ドル未満での再販売を禁ず」という注意書きを掲載しました。しかし最高裁は、著作権者に認められた「販売(vend)」する権利は、最初の販売までであり、その後の再販売価格を拘束するような権利までを含むものではないと判断しました。この判決の考え方が、後の著作権法に明文化されたのです。
第一販売権が適用されるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- そのコピーが、著作権者の許諾を得て適法に作成されたものであること
- そのコピーが、著作権者の下で最初に譲渡されたものであること
- 被告(再販売などを行う者)が、問題となっている特定のコピーの適法な所有者であること
- 被告の行為が、頒布権のみに関わるものであり、複製権や翻案権を侵害するものではないこと
2. 権利の限界(頒布権と他の権利の区別)
第一販売権が制限するのは、あくまで106条3項の頒布権だけです。著作物が固定された有体物(コピー)の所有者は、その「物」を自由に処分できますが、その中に含まれる「著作物」を自由に利用できるわけではありません。
例えば、あなたが適法に購入した小説の書籍を持っているとします。第一販売権に基づき、あなたはその書籍を古本屋に売ったり、友人に貸したりすることは自由です。しかし、その小説をコピーして配布したり(複製権の侵害)、その小説を基に映画の脚本を書いたり(翻案権の侵害)、喫茶店で朗読会を開いたり(公の実演権の侵害)することはできません。これらの権利は、最初の販売後も依然として著作権者に留保されています。
この頒布権と翻案権の境界線が問題となったのが、C.M. Paula Co. v. Logan事件です。被告は、原告が製造したグリーティングカードを適法に購入し、そのカードに描かれた絵を切り抜いてセラミックタイルに貼り付け、製品として販売しました。裁判所は、これは翻案権の侵害には当たらないと判断しました。被告は、カードの絵を改変したり、描き直したりしたわけではなく、購入したカードそのものを物理的にタイルに移転させたにすぎません。これは、購入した絵画を別の額縁に入れ替えるようなものであり、新たな二次的著作物を創作したとは言えないと裁判所は考えたのです。この判決は、第一販売権が、購入したコピーを物理的に加工して再利用する一定の行為までを許容することを示唆しています。
3. デジタル時代の第一販売権
書籍やCDといった物理的な媒体の流通を前提としてきた第一販売権は、デジタルネットワーク時代を迎え、深刻な問題に直面しています。あなたがiTunes Storeで購入した音楽ファイルを、聴き終わった後に「中古デジタルファイル」として友人に売ることはできるのでしょうか。
現在の米国の法解釈では、答えはNOです。その理由は、デジタルファイルの「譲渡」が、物理的な媒体の譲渡とは根本的に異なる性質を持つからです。
あなたが友人にCDを譲渡する場合、あなたの手元からCDという「物」がなくなり、友人の手元に移動します。市場に存在するCDの総数は変わりません。しかし、あなたが音楽ファイルを友人にEメールで送信したり、サーバー経由でダウンロードさせたりする場合、あなたのコンピュータから元のファイルが消えるわけではありません。実際には、友人のコンピュータに新たなコピーが作成されています。この行為は、頒布権だけでなく、著作権の最も根源的な権利である複製権を直接侵害することになります。第一販売権は複製権の侵害に対する抗弁にはなりません。
この問題を正面から扱ったのが、Capitol Records, LLC v. ReDigi, Inc.事件です。ReDigi社は、ユーザーがiTunesなどで適法に購入した音楽ファイルを「中古品」として売買できるオンラインサービスを提供していました。ReDigiは、売却されるファイルが元の所有者のコンピュータから完全に削除され、常に1つのファイルしか存在しないようにする独自の技術を用いて、物理的な中古品売買をデジタルで再現しようと試みました。しかし、第2巡回区控訴裁判所は、技術的な工夫があったとしても、ReDigiのシステムがファイルをある場所から別の場所に移動させる過程で、必然的に新しいコピーを作成している事実に着目し、これは複製権の侵害であり、第一販売権では保護されないと結論付けました。
この判決の背景には、デジタルコピーが物理的なコピーと異なる経済的な性質を持つことへの配慮があります。物理的な書籍やCDは、使用するうちに劣化します。しかし、デジタルファイルは何度コピーされても劣化せず、常に新品同様の品質を保ちます。もしデジタルファイルの中古市場が自由に認められれば、新品の市場と直接競合し、著作権者の利益を著しく害する可能性があるのです。著作権局も、「有体物であるという性質は、第一販売権の法理を定義づける要素であり、その理論的根拠にとって極めて重要である」との見解を示しており、現行法の下で「デジタル第一販売権」を認めることには消極的です。
4. 第一販売権の例外と修正
第一販売権は強力な原則ですが、議会は特定の市場を保護するため、法律によっていくつかの重要な例外を設けています。
レコード・レンタルとソフトウェア・レンタル
1980年代、レコード店がCDをレンタルし、消費者がそれを家庭でカセットテープにダビングするというビジネスが広まりました。これは、CDの販売市場を直接的に破壊する行為であるとして、音楽業界は強く反発しました。これを受けて議会は1984年にレコード・レンタル改正法を制定し、商業目的でレコード(CDなど)をレンタルすることを、第一販売権の例外として禁止しました。
同様の懸念は、コンピュータソフトウェアの分野でも生じました。高価なソフトウェアを安価にレンタルし、家庭でコピーを作成する行為が横行したため、1990年にはソフトウェア・レンタル改正法が制定され、商業目的でのソフトウェアのレンタルが原則として禁止されました。
これらの法律は、第一販売権の原則が、著作権者の市場を不当に侵害するような新たなビジネスモデルに対しては、議会の判断によって修正されうることを示しています。ただし、いずれの法律も、非営利の図書館や教育機関による貸与は例外として認めています。
5. 並行輸入品と第一販売権
第一販売権を巡る最も複雑で国際的な問題が並行輸入品で、グレーマーケットとも呼ばれます。これは、海外で安く販売されている正規品を第三者が購入し、著作権者の許諾なく米国に輸入して、正規代理店よりも安く販売するビジネスを指します。
著作権法602条(a)項は、著作権者の許諾を得ないコピーの米国への輸入を、頒布権の侵害として禁止しています。ここで、第一販売権との間に深刻な対立が生じます。海外で適法に製造・販売された製品(例えば、ある教科書のアジア市場向け廉価版)は、第一販売権の対象となる「適法に作成されたコピー」ではないのでしょうか。もしそうなら、そのコピーの所有者は、第一販売権に基づき、それを米国に輸入して販売する権利があるのではないでしょうか。
この問題を巡り、連邦最高裁判所は2つの重要な判断を下しました。
Quality King Distributors, Inc. v. L'Anza Research International, Inc.事件(1998年)
この事件で最高裁は、米国内で製造され、一度海外に輸出された後、再び米国に輸入された製品については、第一販売権が適用されると判断しました。602条の輸入禁止権は、106条の頒布権の一部であるため、第109条の第一販売権による制限を受けるというのがその理由です。この判決は、米国内で製造された製品の並行輸入に道を開きました。しかし、判決は「海外で製造された製品」については判断を留保しました。
Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.事件(2013年)
この事件で、最高裁はさらに踏み込んだ判断を示しました 。タイ出身の大学院生であったKirtsaeng氏は、出版社Wileyがタイで安価に販売していた英語版の教科書を家族に購入してもらい、それを米国に送らせてeBayで販売し、利益を上げていました。Wileyは、これは602条に違反する違法な輸入であると主張しました。
最高裁は、Kirtsaeng氏の行為を適法と判断しました。判決の鍵となったのは、第一販売権の条文にある「lawfully made under this title(この法律に基づき適法に作成された)」という文言の解釈です。最高裁は、この文言に地理的な限定はなく、米国外で製造されたコピーであっても、それが著作権者の許諾を得て製造されたものであれば、第一販売権の対象となると結論付けました。
このKirtsaeng判決は、グローバル市場に大きな影響を与えました。これにより、出版社やメーカーが国ごとに価格を変えて製品を販売する「市場分断戦略」が、法的に困難になったからです。この判決は、第一販売権が、著作物の物理的なコピーの自由な国際的流通を強く保障するものであることを明確にした、画期的なものと言えます。