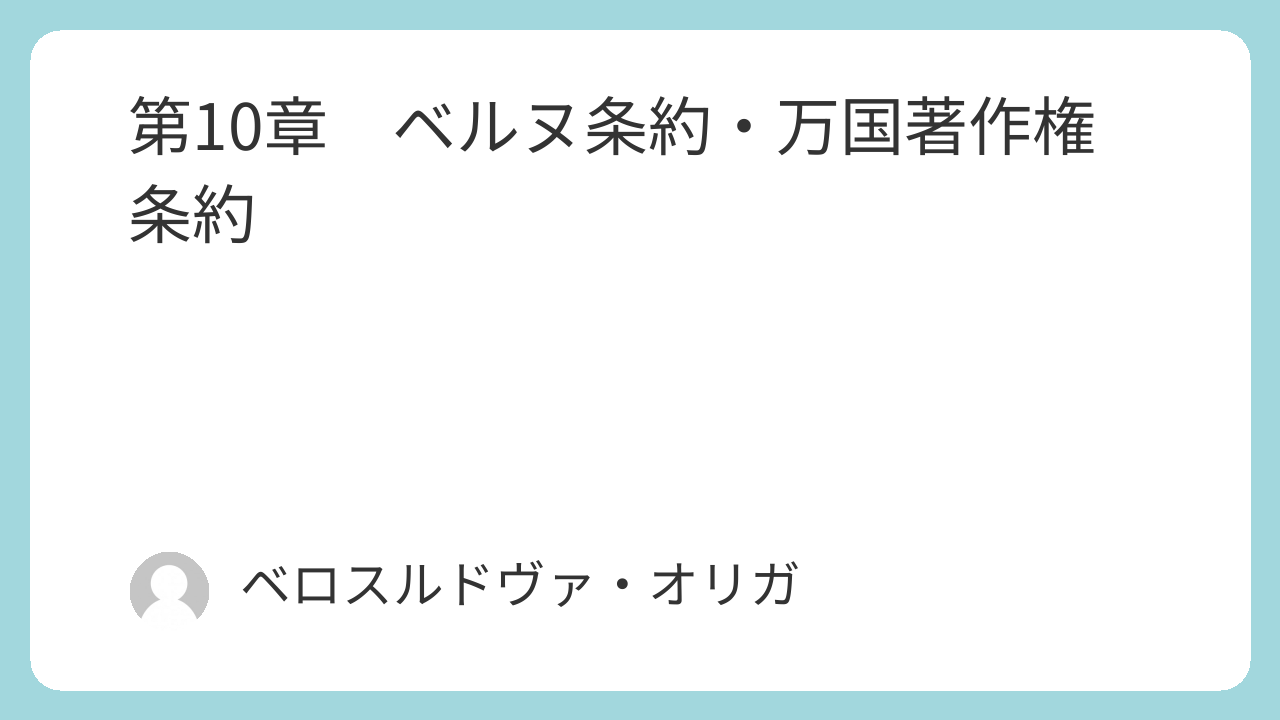インターネット、衛星放送、ブロードバンド技術の進化は、国境という物理的な障壁をいとも簡単に乗り越え、著作物を瞬時に世界中へ届けることを可能にしました。しかしその一方で、国境を越えた大規模な海賊版の蔓延という深刻な問題にも直面しています。
「世界共通の著作権法」というものは存在しません。ある国で著作権を保護するためには、その国の国内法に基づいて権利を主張し、行使する必要があります。しかし、それでは国ごとに手続きが必要となり、国際的な権利保護は著しく困難になります。この問題を解決するのが、多数の国が加盟する国際条約です。これらの条約は、各国が互いの国民の著作物をどのように保護すべきかについての共通のルールを定めています。
第1部 著作権に関する主要な国際条約
国際的な著作権保護の枠組みは、いくつかの重要な多国間条約によって形成されています。これらの条約は、加盟国に対して、他国の国民の著作物を自国民の著作物と同様に保護することを義務付けるとともに、保護に関する最低限の基準(ミニマム・スタンダード)を定めています。
1. ベルヌ条約
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(通称ベルヌ条約)は、1886年にスイスのベルンで成立した、最も古い国際著作権条約です。世界知的所有権機関(WIPO)が管理し、数度の改正を経て、現在ではアメリカを含む世界の主要国のほとんどが加盟しています。アメリカは、国内法の様々な規定(特に、著作権表示を義務付ける方式主義)が条約の要件と相容れなかったため、成立から100年以上が経過した1989年にようやく加盟しました。
ベルヌ条約は、以下の3つの基本原則に基づいています。
① 内国民待遇の原則(National Treatment)
これは、各加盟国が、他の加盟国の国民の著作物(条約上保護される著作物)に対し自国民に与える保護と同等の保護を与えなければならないという原則です。例えば、日本で創作された小説は、アメリカにおいて、アメリカの作家が創作した小説と全く同じようにアメリカの著作権法に基づいて保護されます。
② 無方式主義の原則(No Formalities)
著作権の享受および行使にあたり、登録・納入・著作権表示といったいかなる方式(formality)の履行も要求してはならないという原則です 。著作権は、創作の事実そのものによって自動的に発生し、保護されるべきであるという考え方に基づいています。かつてのアメリカが著作権表示を厳格に要求していたことは、ベルヌ条約加盟への最大の障害でした。1988年のベルヌ条約加盟実施法(BCIA)によって、アメリカはこの表示義務を撤廃し無方式主義へと移行しました。
③ 遡及効の原則(Retroactivity)
条約が新たに発効する国において、その時点で本国(著作物が創作された国)でまだ保護期間が満了していない著作物は、たとえその国で過去にパブリックドメインとなっていたとしても、保護を回復させなければならないという原則です。米国は加盟当初、この遡及効の適用に否定的でしたが、後のTRIPS協定の履行に伴い、特定の外国著作物の権利を回復させる措置を講じました。
ベルヌ条約が定める最低限の保護基準(ミニマム・スタンダード)
ベルヌ条約は、内国民待遇を定めるだけでなく、加盟国が遵守すべき保護の最低基準を具体的に定めています。
- 保護期間: 原則として、著作者の死後50年まで
- 排他的権利: 翻訳権・翻案権・実演権・放送権・複製権等、米国著作権法106条に定められた権利と類似の権利を認めることを求めています。
- 著作者人格権(Moral Rights): 経済的権利とは別に、著作者が自らの氏名を表示する権利(氏名表示権)と作品の完全性を守る権利(同一性保持権)を保護することを求めています。米国は、国内の様々な法律がこの要請を事実上満たしているとの立場を取ってきましたが、1990年には限定的ながら美術家の権利法(VARA)を制定し人格権保護を明文化しました。
2. 万国著作権条約(UCC)
万国著作権条約(Universal Copyright Convention、UCC)は、第二次世界大戦後、アメリカの主導で1952年に成立した条約です。当時、ベルヌ条約の無方式主義を受け入れられなかったアメリカが、ソ連などの非ベルヌ加盟国との著作権関係を構築するための、いわば「橋渡し」的な条約として機能しました。
UCCも内国民待遇を基本原則としていますが、ベルヌ条約に比べて保護の最低基準は緩やかです。特に、方式主義については完全な撤廃を求めず、著作権表示(©マーク、著作権者名、最初の発行年)を付すことで、加盟国が要求する登録などの国内手続きを満たしたものと見なすという妥協的な規定を設けています。
アメリカのベルヌ条約加盟により、UCCの重要性は相対的に低下しましたが、ベルヌ条約には加盟していないがUCCには加盟している国との関係においては、依然として意味を持っています。
3. WIPOインターネット条約
1996年、デジタルネットワーク時代の到来に対応するため、WIPOは2つの新たな条約を採択しました。これらは「WIPOインターネット条約」と呼ばれます。
- WIPO著作権条約(WCT): コンピュータプログラムを文学的著作物として保護すること、データベースの独創的な選択・配列を保護することを明確化しました。
- WIPO実演・レコード条約(WPPT): 実演家(歌手、俳優など)やレコード製作者の権利を強化しました。
これらの条約の重要な役割は、デジタル環境における新たな権利として、インタラクティブな送信(オンデマンド配信など)をコントロールする「公衆送信権(Right of Communication to the Public)」を認めた点です。また、加盟国に対し、コピーガードなどの技術的保護手段を回避する行為を禁止する法整備と著作物の権利情報を保護する著作権管理情報(CMI)の保護を義務付けました。アメリカが1998年に制定したデジタルミレニアム著作権法(DMCA)は、これらの条約上の義務を履行するための国内法でもあります。
第2部 外国著作物の保護と国際私法
1. アメリカ国内法における外国著作物の保護(104条)
アメリカ著作権法104条は、どのような外国著作物がアメリカ国内で保護されるかを定めています。
- 未刊行の著作物: 国籍を問わず、すべての未刊行著作物は、有形的媒体に固定された時点でアメリカ著作権法による保護を受けます。
- 刊行された著作物: 以下のいずれかの条件を満たす場合に保護されます。
- 著作者の1人が、アメリカ国民・アメリカの永住者・アメリカが著作権関係を有する国(ベルヌ条約、UCC、二国間協定の締約国など)の国民・居住者であること
- 著作物が、最初にアメリカまたはUCC加盟国で刊行されたこと
- 著作物が、最初にベルヌ条約加盟国で刊行されたこと
- 著作物が、国連や米州機構によって刊行されたこと
- 大統領布告によって保護が与えられている国の著作物であること
アメリカがベルヌ条約に加盟したことで、現在では世界のほとんどの国の著作物が、これらの条件のいずれかを満たし、アメリカ国内で保護されることになります。
2. 国際的な侵害における法の適用
著作権は、基本的に権利が主張される国の法律が適用される属地主義の原則に基づいています。しかし、インターネット上での侵害のように、行為地と被害地が複数の国にまたがる場合、どの国の法律を適用し、どの国の裁判所で裁判を行うべきかという複雑な問題が生じます。
① アメリカ法の域外適用
原則として、アメリカ著作権法はアメリカ国内で発生した侵害行為にのみ適用され、完全に海外で行われた侵害行為には適用されません(域外不適用)。Subafilms, Ltd. v. MGM-Pathe Communications Co.事件では、アメリカ国内で海外での海賊版ビデオの頒布を「許諾」した行為が問題となりましたが、控訴裁判所は、海外で発生する直接侵害行為自体がアメリカ法の管轄外である以上、その許諾行為だけをアメリカ法で裁くことはできないと判断しました。
ただし、侵害行為の一部(例えば、海賊版のマスターコピーの作成)がアメリカ国内で行われ、それが海外での損害につながった場合には、その海外での利益についてもアメリカの裁判所が賠償を命じることができるとした下級審判決も存在します。
② 準拠法と裁判管轄
国境を越えた著作権紛争では、「どの国の法律に基づいて権利の有無を判断するか(準拠法選択)」と「どの国の裁判所で訴訟を提起できるか(国際裁判管轄)」という2つの問題が生じます。
- 準拠法:
- 侵害の成否: ベルヌ条約の原則に従い、一般に保護が求められる国(侵害が発生したとされる国)の法律(lex loci delicti)が適用されます。例えば、アメリカのウェブサイトに掲載された日本の写真がフランスで無断ダウンロードされた場合、フランスの著作権法に基づいて侵害の有無が判断されます。
- 著作権の帰属: 誰が正当な権利者かという問題については、著作物の「本国」(著作者の国籍や最初の発行地など)の法律が適用される傾向にあります。Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc.事件では、ロシアの通信社が配信した記事の著作権の帰属はロシアの法律で、その記事がニューヨークで無断転載されたことによる侵害の成否はアメリカの法律で判断されました。
- 裁判管轄:
被告の住所地や侵害行為が行われた地に管轄が認められるのが一般的です。アメリカの裁判所は、たとえ侵害が海外で発生したとしても、被告がアメリカ国内に拠点を持ち、人的な管轄権が及ぶ限り、外国の著作権法を適用して事件を審理することができます。ただし、「フォーラム・ノン・コンビニエンス(不便な法廷地)」の原則に基づき、証拠や証人がすべて外国に存在する場合等、他の国の裁判所で審理する方が著しく効率的であると判断されれば、訴えを却下することもあります。
第3部・第4部 著作権と国際通商
1980年代以降、著作権保護は単なる文化政策の枠を超え、国際的な通商政策の重要な柱となりました。アメリカは、自国のコンテンツ産業が海外で被る海賊版による莫大な損害に対抗するため、著作権保護を二国間および多国間の貿易交渉における主要な議題としてきました。
1. TRIPS協定とWTO
この流れの頂点にあるのが、1995年に世界貿易機関(WTO)の発足とともに発効した「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」です。TRIPS協定は、それまでの国際著作権条約を大きく超える、画期的な内容を含んでいます。
- ベルヌプラス・アプローチ: TRIPS協定は、ベルヌ条約の実質的な規定(人格権に関する6条の2を除く)を加盟国に遵守する義務を課した上で、コンピュータプログラムやデータベースの保護など、さらに高いレベルの保護基準(ベルヌ・プラス)を定めました。
- 強力な執行措置: TRIPS協定の最も重要な貢献は、加盟国に対して、著作権を実効的に行使するための国内手続き(差止命令、損害賠償、税関での水際措置、刑事罰など)を整備することを義務付けた点です。
- 紛争解決手続: 加盟国がTRIPS協定上の義務を履行しない場合、他の加盟国はWTOの紛争解決手続に訴えることができます。これは、勧告に従わない国に対して、他の貿易分野での譲許の停止(いわゆる「報復措置」)を認める、極めて強力な執行メカニズムです。
TRIPS協定の登場により、著作権保護は、努力目標ではなく国際貿易上の拘束力のある義務へと昇華しました。
2. 地域貿易協定(NAFTA/USMCA)と二国間交渉
多国間交渉であるWTO/TRIPSを補完するものとして、アメリカは地域貿易協定や二国間交渉も積極的に活用してきました 。北米自由貿易協定(NAFTA)およびその後継である米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)は、TRIPS協定よりもさらに高いレベルの著作権保護(例えば、より長い保護期間)を定めるなど、新たな国際基準を形成する上で主導的な役割を果たしています。
また、アメリカ通商代表部(USTR)は、知的財産権の保護が不十分な国をリストアップした「スペシャル301条報告書」を毎年公表し、これを基に二国間の交渉を行い、改善が見られない場合には貿易制裁を発動することを示唆することで各国に著作権法の強化を促してきました。