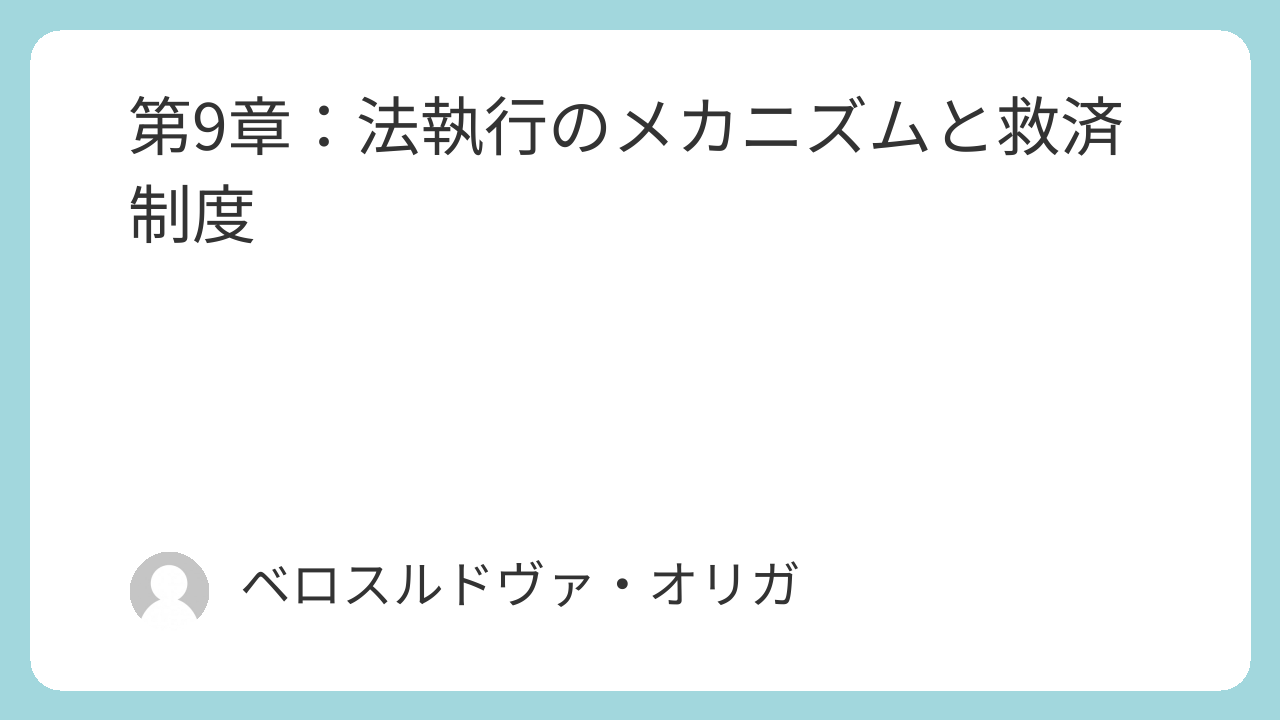反トラスト法が市場における強力なルールとして機能しているのは、その背後に多層的かつ強力な法執行のメカニズムと、違反行為を抑止し損害を回復するための実効的な救済制度が存在するからです。反トラスト法の執行は、政府機関による公的執行と、被害を受けた私人による私的執行という2つの柱によって支えられています。この両輪が相互に補完し、時には競い合うように機能することで、法の網の目は広く、深く張り巡らされているのです。
公的執行は、司法省(DOJ)や連邦取引委員会(FTC)が、公益の代表者として市場全体の競争秩序を維持するために行使する権限です。一方、私的執行は、反トラスト法違反によって直接的な損害を被った企業や消費者が、自らの権利を回復するために訴訟を起こす制度であり、特に損害額の3倍の賠償を認める規定は、違反を摘発する強力なインセンティブとなっています。
§9.1 公的執行
連邦レベルでの公的執行を担うのは、司法省(Department of Justice: DOJ)反トラスト局と連邦取引委員会(Federal Trade Commission: FTC)という2つの機関です。両機関は多くの領域で執行権限を共有していますが、その権限の根拠や行使の方法には重要な違いがあります。
9.1a 司法省反トラスト局(DOJ)
司法省反トラスト局は、アメリカの反トラスト法執行において中心的な役割を果たす機関です。DOJは、シャーマン法・クレイトン法を含む全ての連邦反トラスト法を執行する権限を有しており、その執行手段は民事と刑事の両面にわたります。
- 刑事執行: DOJが持つ最も強力な権限は、反トラスト法違反に対する刑事訴追です。これはFTCには認められていない、DOJ固有の権限となります。刑事執行の対象となるのは、主として、その行為自体から反競争的な意図が明白であり、かつ、競争促進効果が全く期待できない「当然違法」とされる行為です。具体的には、価格カルテル・入札談合・水平的な市場分割といった、いわゆる「ハードコア・カルテル」が刑事訴追の主たる標的となります。これらの行為は、反トラスト法上の「重罪(felony)」とされており、有罪となれば、企業には巨額の罰金が、関与した個人(役員や従業員)には罰金に加えて禁固刑が科される可能性があります。
- 民事執行: DOJは、反トラスト法違反に対して民事訴訟を提起する権限も持ちます。民事執行の目的は、罰則を科すことではなく、反競争的な行為を差し止め、競争状態を回復させることにあります。DOJが民事訴訟を提起する対象は、企業結合(M&A)・独占化・垂直的制限など多岐にわたります。訴訟の結果、裁判所は、問題となる行為を禁じる差止命令(Injunction)や違法な企業結合を元に戻すための資産売却命令(Divestiture)等、様々な救済措置を命じることができます。
多くの民事事件は、裁判の判決に至る前に、DOJと当事者企業との間の和解によって終結します。この和解は同意判決(Consent Decree)という形で裁判所の承認を得て確定し、判決と同様の法的拘束力を持ちます。
9.1b 連邦取引委員会(FTC)
連邦取引委員会(FTC)は、1914年のFTC法制定によって設立された、5人の委員からなる独立した行政機関です。FTCもクレイトン法を執行する権限を持ちますが、シャーマン法を直接執行する権限はありません。しかし、FTCの権限の核心は、FTC法5条にあります。
FTC法第5条は、「不公正な競争方法(unfair methods of competition)」を禁じています。この文言は、シャーマン法やクレイトン法が禁じる行為よりも広い範囲をカバーすると解釈されています。すなわち、FTCは、既存の反トラスト法の条文には明確に違反しない行為であっても、それが競争政策の精神に反し、競争を阻害する可能性のある「不公正な」行為であれば、5条に基づきこれを差し止めることができるのです。
FTCの執行は、主に行政審判手続きを通じて行われます。FTCが違反行為があると判断した場合、行政法判事(Administrative Law Judge)による審理が行われ、違反が認定されれば排除措置命令(Cease and Desist Order)が発出されます。近年、FTCは、特に巨大デジタル・プラットフォームによる優越的地位の濫用や、スタートアップ競争者の買収(キラー・アクイジション)など、既存の反トラスト法の枠組みでは捉えきれない可能性のある新しいタイプの競争問題に対し、このFTC法5条の権限を積極的に活用しようとする姿勢を見せています。
9.1c 企業結合の事前届出制度(HSR法)
DOJとFTCが企業結合を効果的に審査するための重要な制度が、1976年に制定されたハート・スコット・ロディノ法(HSR法)に基づく事前届出制度です。この法律により、一定規模を超える企業結合を行おうとする当事者は、結合を実行する前に、DOJとFTCの両方にその計画を届け出ることが義務付けられています。届出後、当事者は原則として30日間の待機期間を経なければ、結合を完了させることはできません。この期間中に執行機関は審査を行い、必要であれば差止訴訟を提起します。
§9.2 私的執行
アメリカ反トラスト法の執行件数の9割以上を占めるのが、被害を受けた私人による訴訟、すなわち私的執行です。その原動力となっているのが、クレイトン法が定める強力なインセンティブ制度です。しかし、誰でも訴訟を起こせるわけではなく、裁判所は濫訴を防ぐための重要な法理を確立しています。
9.2a 私的執行を支える制度
- 3倍額賠償(Treble Damages): クレイトン法4条に基づき、原告が証明した実損害額の3倍の金額が賠償として命じられます。これは、被害者の損害を回復する(補償的機能)と同時に、違反者に対して強力なペナルティを科し、将来の違反を抑止する(抑止的機能)という2つの目的を持ちます。
- 弁護士費用: 勝訴した原告は、訴訟に要した合理的な弁護士費用と訴訟費用を被告に請求することができます。これにより、損害額が比較的小さい個人や中小企業であっても、訴訟提起の経済的なハードルが大幅に下がります。
- クラスアクション(Class Action): 消費者のように、個々の損害額は小さくとも、被害者が多数にのぼる場合に、一部の代表者が全被害者のために訴訟を追行することを認める制度です。これにより、個別に提起したら採算が合わない少額の損害賠償請求も、集団で行うことが可能となります。
9.2b 反トラスト法上の損害(Antitrust Injury)
私的執行における最も根源的な要件が「反トラスト法上の損害」の法理です。これは、原告が被った損害が、単に被告の行為によって生じたというだけでは不十分であり、「その行為を違法たらしめている反競争的な側面から生じた種類の損害」でなければならないという原則です(ブランズウィック社事件、1977年)。反トラスト法は、競争者を保護するための法律ではなく、競争そのものを保護するための法律であるという理念を反映したものです。
9.2c 原告適格と間接購入者の原則
反トラスト法違反の影響は、取引の連鎖を通じて社会の広範な範囲に及ぶ可能性があります。この問題に対処するため、裁判所は「間接購入者の原則」を確立しました(イリノイ・ブリック社事件、1977年)。
これは、価格カルテルなどによる過払い損害の賠償請求は、原則として直接の取引相手に限定され、そのコストの転嫁を受けた間接購入者は、連邦反トラスト法の下では損害賠償を請求できないというルールです。その理由は、①コストがサプライチェーンを通じてどの程度転嫁されたのかを正確に算定することが極めて困難であること、②法の執行者として最も効率的な直接購入者に損害全額の請求権を集中させて違反を摘発する強力な動機付けを与えるべきであること、にあります。
§9.3 救済制度
違反が認定された場合、裁判所は競争を回復し、将来の違反を抑止するために、様々な救済措置を命じます。
9.3a 損害賠償額の算定
損害賠償額の算定は、「もし違反がなかったならば、原告はどのような状態にあったか」という仮定の状況を想定する必要があり、多くの不確実性を伴います。この点を考慮し、最高裁判所は「損害が発生したという事実」の立証には厳格さを求める一方で、「損害額の算定」については推測や概算を許容するという、立証基準を緩和する姿勢を一貫して示しています。
- 過払い損害の算定: 価格カルテルなどの場合、「ヤードスティック法」(競争的な他の市場の価格を基準とする)や「ビフォア・アンド・アフター法」(違反期間の前後の価格を比較する)といった経済学的手法を用いて、「違反がなかった場合の競争的な価格」を推計し、実際の価格との差額を損害として算定します。
- 逸失利益の算定: 排他的行為によって競争者が市場から排除された場合、その損害は逸失利益(Lost Profits)として計算されます。これも同様の手法で、違反がなければ得られたであろう利益を推計します。
9.3b 衡平法上の救済
金銭賠償に加えて、裁判所は将来の損害を防ぐための衡平法上の救済を命じることができます。
- 差止命令(Injunctive Relief): 進行中の違反行為や、将来行われるおそれのある違反行為を差し止める命令です。違法な企業結合の実行を差し止めたり、排他的な契約条項を無効にしたりするために用いられます。
- 構造的救済(Structural Relief): 最も強力かつ抜本的な救済措置が、企業の組織や資産そのものに介入する構造的救済です。違法な企業結合に対する資産売却(Divestiture)がその典型です。独占化事件における企業分割(Breakup)は、企業の内部成長によって形成された組織を解体するものであり、極めて例外的な場合にのみ用いられます。歴史的にはスタンダード・オイル事件(1911年)やAT&T事件(1982年)が有名ですが、その後のマイクロソフト事件(2001年)では、裁判所は企業分割ではなく差止命令を選択しました。裁判所は、構造的救済がもたらす事業への混乱や効率性の損失を懸念し、近年は、問題となる行為を具体的に禁じる行為救済(Conduct Remedy)を優先する傾向が強くなっています。