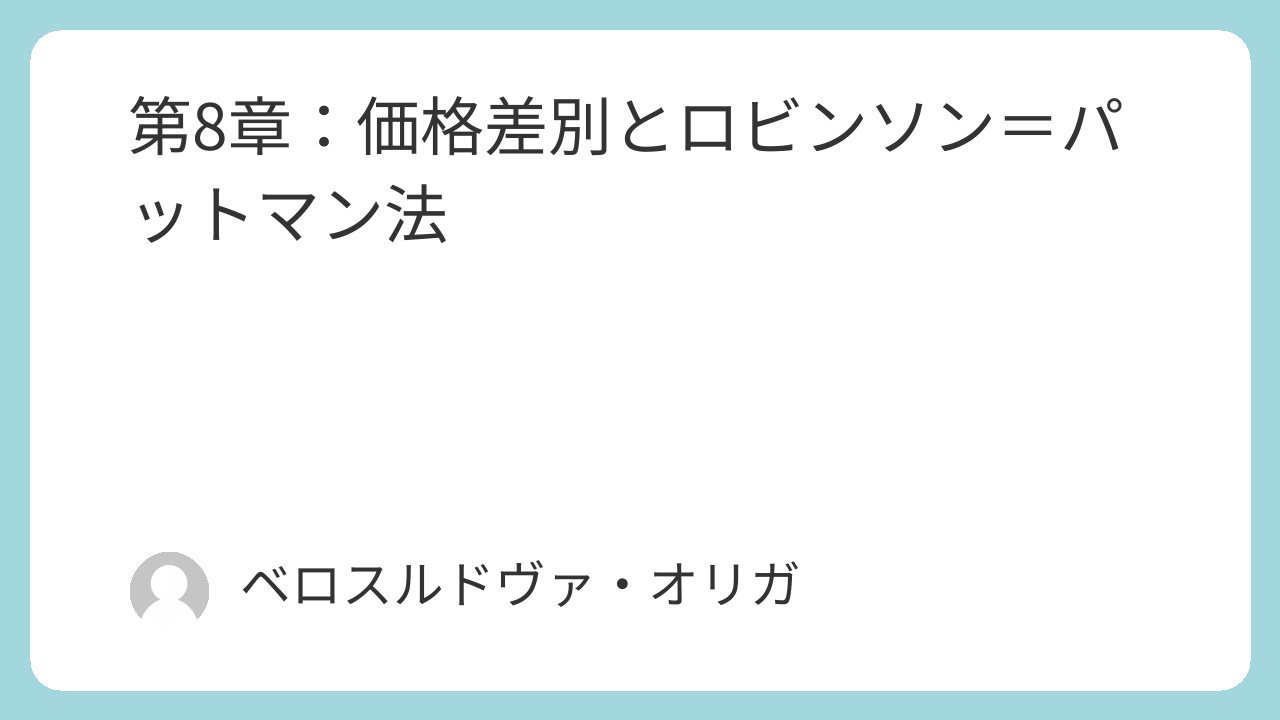反トラスト法には、カルテル・独占による価格の吊上げ・生産量削減等とは異なる論理で価格設定を規制する特殊な領域が存在します。それが価格差別(Price Discrimination)であり、それを直接の規制対象とするのがロビンソン=パットマン法です。
§8.1 価格差別の経済学
8.1a 価格差別と価格差
経済学における「価格差別」とは、「同一の製品を異なるマージン(利潤率)で異なる顧客に販売すること」を指します。これは、単なる「価格差」とは異なる概念です。
例えば、あるメーカーがA社には1個100円で、B社には1個95円で製品を販売したとします。これは価格差です。しかし、もしB社への販売が、大量注文による輸送コストの削減分(5円)を正確に反映したものであれば、メーカーの利益率は同じであり、これは経済学的な価格差別にはあたりません。逆に、もしA社とB社に全く同じ100円で販売していても、B社への輸送コストの方が5円安いのであれば、メーカーはB社からより高い利益率を得ており、これは価格差別となります。
8.1b 価格差別と市場支配力
持続的な価格差別は、市場支配力が存在しなければ不可能です。完全競争市場では、もしある企業が特定の顧客にだけ高い価格を提示すれば、その顧客はすぐに他の競争相手から競争価格で購入するでしょう。価格差別が成立するためには、売手が、少なくとも一部の顧客(高価格を支払う「不利な扱いを受ける購入者」)に対して、コスト以上の価格を課すことができるだけの力を持っている必要があります。
8.1c 価格差別の三類型
経済学では、価格差別を以下の3つに分類します。
- 第1次価格差別(完全価格差別): 各顧客が支払ってもよいと考える上限価格(留保価格)を売手が完全に把握し、顧客一人ひとりに対して異なる価格を設定します。これにより、売手は全ての消費者余剰を獲得することができます。理論的には、生産量は競争市場と同じ水準になり効率的ですが、現実には不可能です。
- 第2次価格差別: 顧客を事前に選別できない場合に、数量割引や抱き合わせ販売など、顧客自らの選択によって異なる価格体系に振り分けられるようにする手法です。
- 第3次価格差別: 学生割引やシニア割引のように、「学生」「シニア」といった観察可能な属性によって顧客をグループ分けし、グループごとに異なる価格を設定する手法です。
§8.2 ロビンソン=パットマン法
1936年に制定されたロビンソン=パットマン法は、クレイトン法2条を改正する形で成立しました。その立法目的は、経済的効率性の追求ではなく、当時台頭してきた大規模なチェーンストアから、伝統的な中小の卸売業者・小売業者を保護することにありました。この法律は、価格差別の経済学的定義ではなく、価格差そのものを出発点としていることに特徴があります。
8.2a 競争阻害の2つの類型
ロビンソン=パットマン法違反は、その競争阻害がどの段階で生じるかによって、2つの類型に大別されます。
- 一次的損害(Primary-line Injury): 価格差別を行った売手の競争相手が被る損害です。これは実質的に、地域的な略奪的価格設定の法理です。すなわち、ある企業が、特定の地域市場で競争相手を駆逐するためにコスト割れの低価格を設定し、その損失を他の地域市場での高価格販売で補填するようなケースがこれにあたります。最高裁はブルック・グループ社事件判決で、この一次的損害が認められるためには、シャーマン法2条の略奪的価格設定と同様に、①コスト以下の価格設定と②損失回収の蓋然性という厳格な要件が必要であるとの判断を示しました。
- 二次的損害(Secondary-line Injury): 価格差別を受けた買手の間で生じる競争上の損害です。こちらがロビンソン=パットマン法の中核です。これは、あるサプライヤーが、競争関係にある2つの小売業者AとBのうち、A社にだけ不当に安い卸売価格で製品を販売し、その結果、B社が競争上不利な立場に置かれるという状況を問題にします。
8.2b 二次的損害の要件と問題点
二次的損害が認められるためには、原告(不利な扱いを受けた購入者)は以下の点を証明する必要があります。
- 2つの実在する販売: 異なる2人の購入者に対する、合理的に近接した時点での2つの販売が存在すること。
- 州際通商: 少なくとも一方の販売が州境を越えて行われていること。
- 商品の販売: サービスではなく、「商品」の販売であること。
- 同質・同等の品質: 2つの販売にかかる商品が、実質的に同じ等級・品質であること。ブランドの違いや些細な物理的差異は、通常、この要件を否定しません。
- 価格差の存在: 2つの販売の価格に差があること。
- 競争上の損害の可能性: 価格差によって、不利な扱いを受けた購入者の競争能力が実質的に損なわれる可能性があること。
ここでの最大の特徴は、裁判所が「競争上の損害」を、市場全体の競争への影響ではなく、個々の競争者(原告)が被った不利益と捉えてきた点にあります。大口の購入者に対する数量割引は、規模の経済を反映した効率的な価格設定であり、最終的には消費者価格の低下に繋がる可能性があります。しかし、ロビンソン=パットマン法は、その結果として競争に敗れる小規模な購入者を保護するために、このような効率的な価格設定に介入します。これは、競争「プロセス」ではなく競争「者」を保護するものとして、他の反トラスト法の考え方とは真逆です。
8.2c 抗弁
被告(売手)には、価格差を正当化するための2つの主要な抗弁が認められていますが、いずれもその適用は厳しく制限されてきました。
- コストによる正当化(Cost Justification): 価格差が、製造、販売、配送におけるコストの違いを反映したものであることを証明する抗弁です。しかし、裁判所が要求するコスト計算の厳密さは極めて高く、この抗弁が成功することは稀です。
- 競争対抗(Meeting Competition): 低価格が、競争相手が提示した同等の低価格に誠実に対抗するために設定されたものであることを証明する抗弁です。これは、硬直的な価格体系を崩し、競争を促進する上で重要な抗弁ですが、かつては非常に厳格に解釈されていました。
§8.3 結論:批判と現状
ロビンソン=パットマン法の目的は中小企業保護という政治的なものであり、経済的効率性や消費者利益の最大化という現代反トラスト法の主流的な価値観とは相容れません。むしろ、効率的な価格設定を妨げ、価格の硬直化を招くことで、競争を阻害し、消費者に不利益をもたらすと批判されています。
このような批判を受け、司法省やFTCによる公的執行は近年ほとんど行われていません。しかし、法律自体は依然として有効であり、主に不利な扱いを受けたと主張する購入者による私的訴訟の形で存続しています。最高裁判所は、ボルボ社事件(2006年)などで、本法を他の反トラスト法の趣旨と整合的に、より限定的に解釈しようとする姿勢を示していますが、法律の根本的な矛盾が解消されたわけではありません。