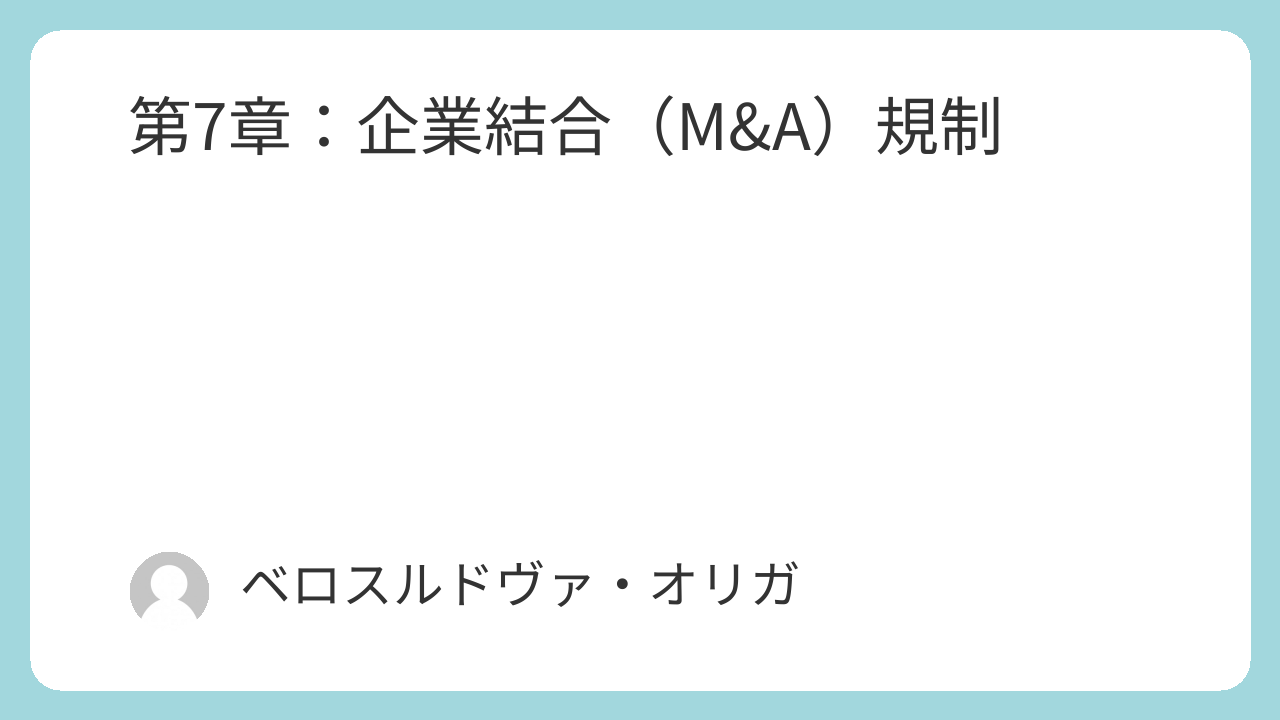反トラスト法は、全てのM&A(Merger & Acquisition、企業結合)を禁じるものではありません。しかし、それが競争を阻害するおそれがある場合には予防的に介入します。クレイトン法7条は、株式・資産の取得が「いずれかの取引分野において、競争を実質的に減殺するおそれがある」場合に、これを禁じています。
企業結合には、サプライチェーンの異なる段階にある企業間の垂直的企業結合や、関連のない市場の企業間の混合型企業結合など様々な形態がありますが、反トラスト法が最も厳しい監視の目を向けるのが、直接の競争相手同士の結合である「水平的企業結合(Horizontal Merger)」です。市場から競争者を直接的に消滅させることで、価格の上昇や生産量の減少、イノベーションの停滞に直結する危険性が高いからです。
本章では、この企業結合、特に水平的企業結合を評価するための分析的枠組みを、司法省(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)が共同で発行する「企業結合ガイドライン」に沿って解説します。
§7.1 企業結合審査の基本思想:効率性と反競争性
水平的企業結合は、2つの相反する効果を同時にもたらします。
- 効率性の向上(Procompetitive Effects): 結合により、生産設備の統廃合、研究開発(R&D)資源の共有、販売網の効率化が行われ、規模の経済や範囲の経済が実現されます。これにより、生産コストが低下し、より良い製品がより安く消費者に提供される可能性があります。
- 反競争的効果(Anticompetitive Effects): 市場から競争者が1人減ることで、残存企業間の協調的行動(カルテルや暗黙の共謀)が容易になったり、結合後の企業が単独で価格を引き上げる力(単独効果)を持ったりする危険性が高まります。
現代の企業結合審査の中心的な課題は、この2つの効果を比較衡量し、当該結合が全体として競争を促進するのか、それとも阻害するのかを見極めることにあります。かつてのブラウン・シュー社事件(1962年)判決に代表されるように、裁判所が効率性の向上そのものを「中小の競争者を圧迫する」として否定的に評価した時代もありましたが、今日の反トラスト法は、消費者利益に資する効率性を明確に肯定的な要素として捉えています。
§7.2 反競争的効果の分析Ⅰ:協調的効果
企業結合が競争を阻害する原因は、それが「協調的効果(Coordinated Effects)」をもたらすからです。これは、市場における競争者の数が減少し、市場集中度が高まることで、残存企業間の価格カルテルや、明示的な合意なき暗黙の共謀(プライス・リーダーシップなど)が、結合前よりも容易に成功しやすくなるという懸念です。
7.2a 市場集中度の計測:HHI指数
市場が協調的行動にどの程度陥りやすいかを測るための第一歩が、市場集中度の計測です。現在、執行機関や裁判所が標準的に用いる指標が「ハーフィンダール・ハーシュマン指数(Herfindahl-Hirschman Index: HHI)」です。
HHIは、関連市場における各企業の市場シェア(%)をそれぞれ2乗し、それらを合計することで算出されます。
HHI = Σ (各企業の市場シェア)²
例えば、市場シェアが40%、30%、30%の3社からなる市場のHHIは、40² + 30² + 30² = 1600 + 900 + 900 = 3400となります。HHIは、企業の数だけでなく、シェアの格差も反映するのが特徴で、市場シェアが大きい企業が存在するほど、指数は高くなります。
2023年企業結合ガイドラインでは、HHIを用いて市場集中度を以下のように分類しています。
- 非集中市場: HHIが1000未満
- 中程度集中市場: HHIが1000以上1800未満
- 高集中市場: HHIが1800以上
7.2b フィラデルフィア銀行判決
企業結合ガイドラインは、これらのHHIの水準に基づき、企業結合の違法性を推定するための基準を設けています。これは、1963年のフィラデルフィア銀行事件判決で確立された考え方に基づくもので、一定の市場集中度を超える市場での企業結合は、それ自体が反競争的であると推定され、被告側(結合当事者)がそれを覆す証拠を提出する責任を負うという、立証責任の転換を伴う枠組みです。
2023年のガイドラインによれば、以下の条件を満たす企業結合は、競争を実質的に減殺する蓋然性が高いと推定され、政府による提訴の対象となりやすくなります。
- 結合後の市場が高集中市場(HHI > 1800)となり、かつ、結合によるHHIの増加分が100を超える場合。
- 結合後の企業の市場シェアが30%を超え、かつ結合によるHHIの増加分が100を超える場合。
この推定は決定的ではなく、当事者は後述する参入障壁の低さや効率性などを主張して反論することができます。しかし、この構造的な基準は、企業結合審査における強力なスクリーニング機能を有しています。
§7.3 反競争的効果の分析Ⅱ:単独効果
市場で製品が差別化されている場合、企業結合は協調的行動を容易にしなくても、競争を阻害することがあります。これが「単独効果(Unilateral Effects)」です。
製品差別化された市場では、各製品は完全な代替品ではありません。例えば、コカ・コーラとペプシコーラは互いに最も近い競争相手ですが、どちらか一方を強く好む消費者もいます。このような状況で、もしコカ・コーラ社がペプシコ社を買収したらどうなるでしょうか。
結合前、コカ・コーラが値上げをすれば、一部の価格に敏感な消費者はペプシコーラに乗り換えたでしょう。この顧客流出の可能性が、コカ・コーラの価格引き上げを抑制していました。しかし、結合後は、ペプシコーラも自社の製品となるため、コカ・コーラが値上げをしても、顧客がペプシコーラに乗り換えることはもはや「損失」ではなくなります。値上げによって失う顧客が少なくなるため、結合後の企業は、単独で一方的に価格を引き上げることが可能になります。
単独効果の分析では、市場全体の集中度よりも、結合当事者の製品が互いにどれだけ近い競争関係にあるかが重要となります。執行機関は、転換率(Diversion Ratio)(一方の製品が値上げした際に、どれだけの顧客がもう一方の製品に乗り換えるか)などを分析し、結合によって価格がどの程度上向きの圧力を受けるか(Upward Pricing Pressure: UPP)を評価します。
§7.4 垂直的企業結合・混合型企業結合
水平的企業結合ほどではありませんが、垂直的企業結合や混合型企業結合も競争上の懸念を生じさせることがあります。
7.4a 垂直的企業結合
サプライチェーンの異なる段階にある企業間の結合は、多くの場合、二重マージン問題の解消などを通じて効率性を高めます。しかし、特に一方の市場で支配的な企業が関与する場合、市場閉鎖のリスクが生じます。企業結合によって競争相手が重要な供給源や販売経路へのアクセスを断たれ、コストが引き上げられることで競争力が削がれる可能性があるためです。
7.4b 混合型企業結合:潜在的競争
直接の競争関係にも垂直関係にもない企業間の結合は、通常、競争上の懸念は小さいです。しかし、例外的に「潜在的競争」を減殺するとして問題となることがあります。これは、買収企業が、もし結合しなければ、将来的に自力で市場に参入し、新たな競争をもたらしたであろう可能性を消滅させてしまうという理論です。この理論の適用には、参入の蓋然性等の不確実な要素の証明が必要となるため適用は限定的です。特に、支配的プラットフォームによる新興企業の買収(キラー・アクイジション)は、この潜在的競争の理論の現代的な応用例として注目されています。
§7.5 審査におけるその他の考慮要素
市場集中度や単独効果の分析に加えて、企業結合の競争効果を評価する上では、以下のような市場の動的な要因が総合的に考慮されます。
7.5a 参入障壁
市場集中度が高くても、参入障壁が低ければ、企業結合による反競争的効果は小さくなります。もし結合後の企業が価格を吊り上げようとしても、その「超過利潤」に惹かれて新規参入が速やかに行われ、価格は再び競争的な水準に押し戻されるからです。したがって、参入が「適時性(timely)」「蓋然性(likely)」「十分性(sufficient)」をもって行われるかどうかは、審査の行方を左右する極めて重要な要素となります。
7.5b 効率性の抗弁
結合当事者は、当該結合が競争を阻害する効果を上回るだけの効率性をもたらすことを主張・立証することで、反競争性の推定を覆すことができます。ただし、そのためには、効率性が「結合に固有(merger-specific)」のものであり(結合以外では達成困難であること)、かつ、「検証可能(verifiable)」であることが求められます。さらに、その効率性の恩恵が、最終的に価格の低下等の形で消費者に還元されることが強く期待されます。
7.5c 経営不振企業の抗弁
極めて例外的な状況では、「経営不振企業の抗弁(Failing Firm Defense)」が認められることがあります。これは、買収される企業が倒産の危機に瀕しており、他に競争上の懸念がより少ない買い手が存在せず、かつ、市場から退出した場合の競争への悪影響が当該結合による悪影響よりも大きい場合に、反競争的な結合であっても例外的に認められるというものです。その適用要件は極めて厳格です。
§7.6 手続き:HSR法
大規模な企業結合を効果的に審査するため、1976年にハート・スコット・ロディノ法(HSR法)が制定されました。この法律は、一定規模を超える企業結合の当事者に対し、結合を実行する前にDOJとFTCに計画を事前届出することを義務付けています。届出後、当事者は一定の待機期間を経なければ結合を完了できません。この期間中に執行機関は審査を行い、必要であれば差止訴訟を提起します。この制度は、反競争的な結合が不可逆的に実行されてしまうのを防ぐ、予防的規制の役割を果たしています。