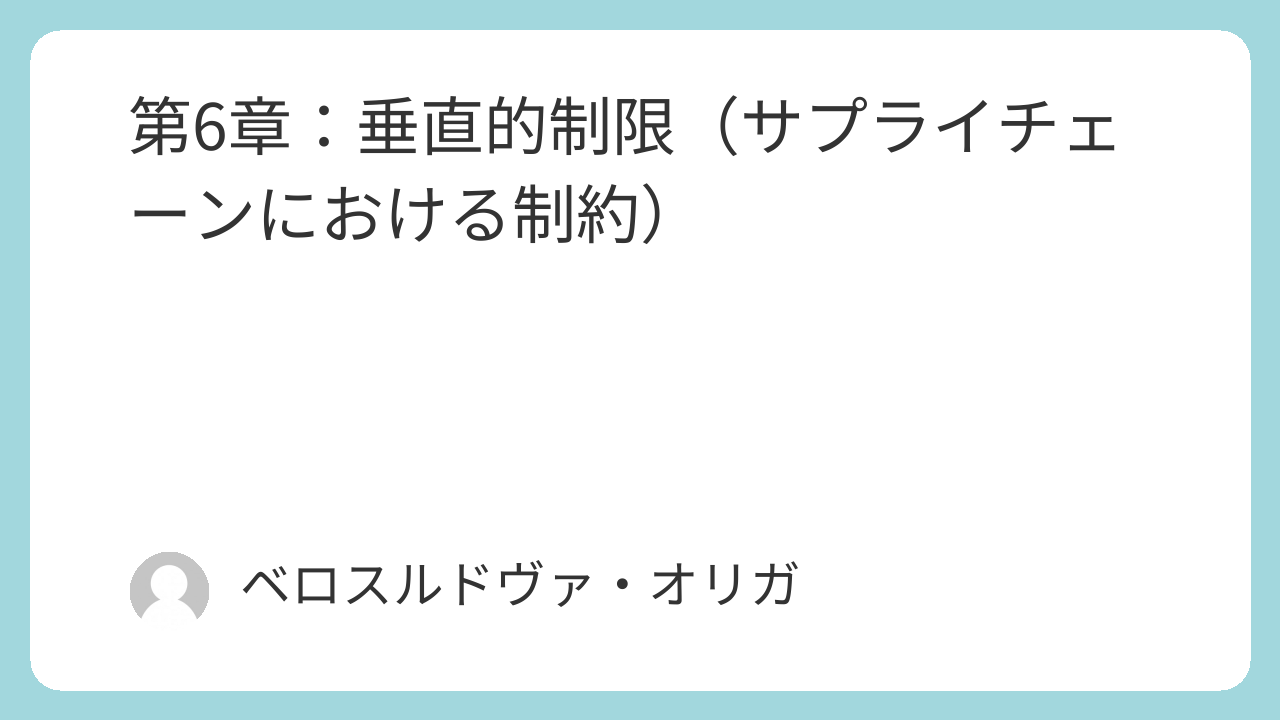これまで取り扱った水平的制限や独占化行為が、主に市場の同一レベルで活動する競争者間の関係や、単独企業の市場全体に対する力を問題としてきたのに対し、本章では垂直的制限(Vertical Restraints)、即ち、サプライチェーンの異なるレベルにある企業間の合意や慣行を分析します。これは、メーカーと卸売業者、卸売業者と小売業者といった、生産から消費者に至るまでの流通プロセスにおける様々な制約を指します。
垂直的制限は、その効果が及ぶ範囲によって、ブランド内制限(Intrabrand Restraints)とブランド間制限(Interbrand Restraints)に大別されます。前者は特定のブランド内での販売業者間の競争を制限するものであり(例:ソニー製品を販売するA店とB店の競争)、後者はあるブランドが他のブランドとの競争に影響を与えるものです(例:ソニー製品を扱う店がパナソニック製品を扱えるか)。
歴史的に、裁判所はこれらの制限、特に価格に関する制限に対して強い警戒感を示してきました。しかし、現代の経済分析は、これらの制限がむしろ流通の効率性を高めブランド間競争の促進を通じて消費者利益に貢献しうることを明らかにし、判例法理に転換をもたらしました。
§6.1 ブランド内制限Ⅰ:再販売価格維持(RPM)
再販売価格維持(Resale Price Maintenance: RPM)とは、メーカーなどのサプライヤーが、自社製品を販売する卸売業者や小売業者の再販売価格を指定または拘束する行為です。これには、指定された価格「以上」で販売することを義務付ける最低再販売価格維持と、指定された価格「以下」で販売することを義務付ける最高再販売価格維持があります。
6.1a 競争上の懸念
再販売価格維持に対する伝統的な懸念は、それが水平的なカルテルの隠れ蓑として機能しうることです。
- 販売業者カルテルの促進: 地域の複数の小売業者が価格競争を避けたいと考えた場合、彼らが直接価格協定を結ぶ代わりに、共通のサプライヤーであるメーカーに働きかけ、全小売業者に対して最低再販売価格を維持させることで、実質的にカルテルと同じ効果を達成できてしまいます。
- メーカーカルテルの促進: 寡占的な市場において、メーカー各社が小売価格を固定すれば、小売段階での価格競争がなくなるため、互いの価格設定を監視しやすくなり、メーカー間の価格協定が安定する可能性があります。
これらの懸念から、最低再販売価格維持は、1911年のドクター・マイルズ事件判決以来、約100年間、当然違法(Per Se Illegal)とされてきました。
6.1b 効率性の抗弁:フリーライド問題の防止
一方で、RPMにはブランド間の競争を促進する強力な経済的合理性が存在する場合があり、その最も重要な正当化理由が「フリーライド問題」の防止です。
これは、製品の販売にあたって、手厚いショールームや専門的な商品説明、アフターサービスといった付加価値を提供するフルサービス店が、そうしたサービスを提供せずに安売りだけを行うディスカウント店に顧客を奪われてしまう現象を指します。消費者は、まずフルサービス店で情報を得てから、実際に購入するのは安価なディスカウント店で行います。この場合、ディスカウント店はフルサービス店が投資したサービスコストに「ただ乗り(フリーライド)」していることになります。
このような状況が続けば、フルサービス店はコストのかかるサービスを提供する意欲を失い、市場全体で製品に関する情報やサービスが不足し、最終的にはブランド間の競争が阻害されてしまいます。
最低再販売価格維持は、このフリーライド問題を解決する手段となりえます。価格競争を制限することで、フルサービス店はサービス提供コストを価格に転嫁できるだけの十分なマージンを確保でき、質の高いサービスを提供するインセンティブが維持されるのです。販売業者は価格ではなく、サービスの質で競争することになり、これがブランド全体の魅力を高め、他のブランドとの競争を促進します。
6.1c 法解釈の転換:Leegin判決
このフリーライド問題の防止という経済的合理性を重視し、最高裁判所は2007年のリージン社事件(Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.)判決において、ドクター・マイルズ判決を覆しました。これにより、最低再販売価格維持は当然違法の原則から離れ、合理の原則(Rule of Reason)の下で、その反競争的効果と競争促進効果を事案ごとに比較衡量して評価されることになりました。
§6.2 ブランド内制限Ⅱ:垂直的非価格制限
メーカーが販売業者の競争を制限する手段は価格だけではありません。販売できる地域や顧客を限定する垂直的非価格制限も広く用いられています。
- テリトリー制限(Territorial Restraints): 各販売業者に排他的な販売地域を割り当て、その地域外での積極的な販売活動を禁じます。
- 顧客制限(Customer Restraints): 特定の顧客層(例:業務用と一般消費者)を割り当て、割り当てられた以外の顧客層への販売を禁じます。
これらの非価格制限も再販売価格維持と同様に、フリーライド問題を防止しブランド間競争を促進する機能を持っています。例えば、テリトリー制限は、販売業者が自らの地域で行った広告宣伝やサービス投資の恩恵を独占できるようにすることで、地域に根差した販売促進活動へのインセンティブを高めます。
この点に着目し、最高裁判所は1977年のGTEシルバニア社事件判決で、垂直的非価格制限を当然違法としていたかつての判例を覆し、合理の原則を適用することを確立しました。この判決は、垂直的制限の分析に経済学的合理性をもたらした画期的なものとして、その後のリージン判決にも大きな影響を与えました。
§6.3 ブランド間制限Ⅰ:抱き合わせ販売(タイイング)
抱き合わせとは、ある製品(主たる製品、タイイング製品)を販売する際に、別の製品(従たる製品、タイド製品)も併せて購入することを取引の条件とする行為です。
伝統的に、抱き合わせは当然違法とされてきましたが、その適用は、①2つの別個の製品の存在、②強制、③タイイング製品市場における十分な経済的勢力、④タイド製品市場における相当量の取引への影響、という複数の要件を満たす必要がありました。
そこで懸念されていたのは、ある市場での独占力を別の市場に不当に及ぼす「レバレッジ理論」でしたが、この理論は現代の経済学では多くの批判を受けています。むしろ、抱き合わせは、価格差別の手段や製品の品質管理、ブランドイメージの維持のために用いられることが多いです。近年の判例では、特にイリノイ・ツール・ワークス社事件(2006年)判決で特許権から市場支配力を推定する原則が否定されたことにより、抱き合わせに対する当然違法の原則は形骸化し、合理の原則に近い分析へと移行しています。
§6.4 ブランド間制限Ⅱ:排他的取引
排他的取引とは、販売業者が、特定のサプライヤーの製品のみを取り扱い、競争相手の製品を取り扱わないことを合意する契約です。
この行為は、常に合理の原則の下で評価されます。主な競争上の懸念は、競争相手が有力な販売経路を失う市場閉鎖ですが、一方で、販売業者のブランドへの忠誠心を高め、販売促進への投資を促すという強力な効率性も認められています。裁判所は、閉鎖される市場の割合、契約期間の長さ、参入障壁の高さなどを総合的に考慮し、その行為が全体として競争を促進するのか、阻害するのかを判断します。
結論として、垂直的制限に関する現代の反トラスト法は、かつての形式的で硬直的なアプローチから脱却し、個々の行為が市場において実際にどのような経済的効果をもたらすのかを問う、より実質的な分析へと移行しています。その中心にあるのは、「ブランド内競争への制約が、それを上回るだけのブランド間競争の促進効果をもたらすか」という、経済学的合理性に基づいた比較衡量の視点です。