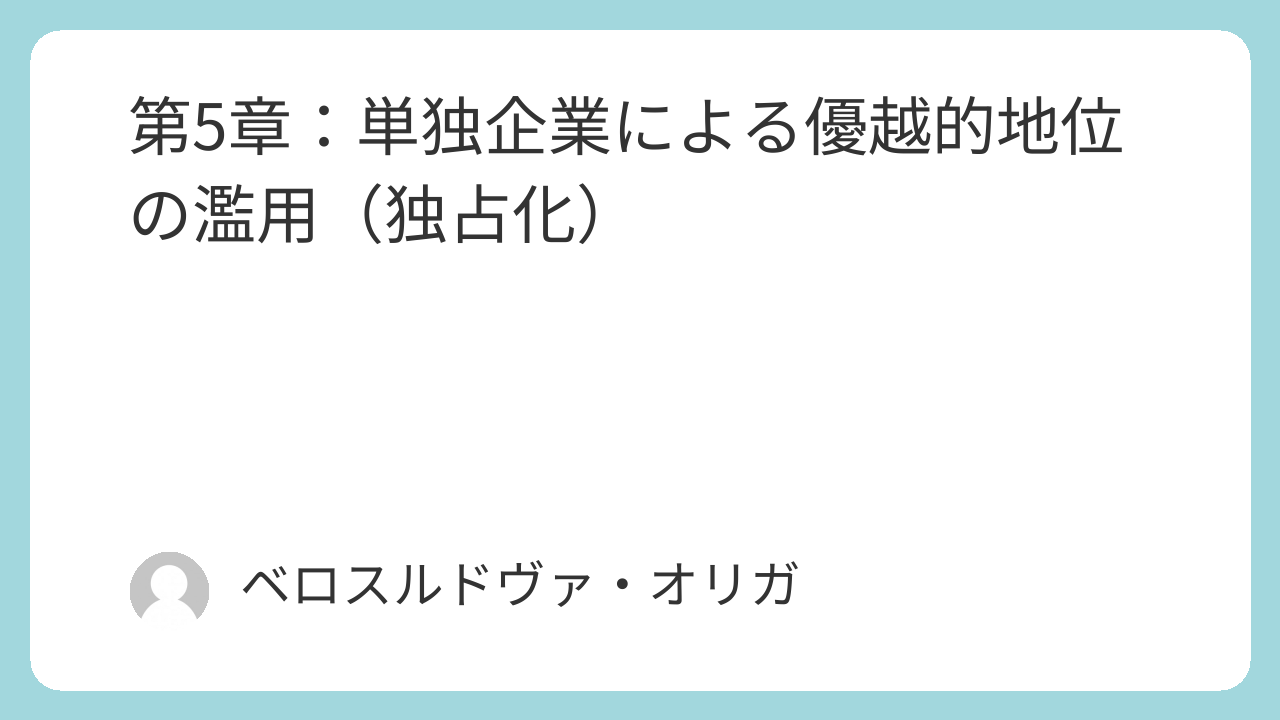シャーマン法1条が複数の企業による「共謀」という共同行為を規制するのに対し、同法2条は、原則として単独の企業による市場支配力の獲得・維持・行使を規律します。この条文は、「何人も、州際または外国との取引・通商のいずれかの部分を独占し、独占しようと試み、あるいは何人とも共謀してはならない」と定めています。
本章では、このシャーマン法2条の中核をなす「独占化(Monopolization)」と「独占化企図(Attempt to Monopolize)」の法理を詳述します。ここでの最大のテーマは、反トラスト法が、単に市場を支配しているという「独占(monopoly)」という状態そのものを罰するのではなく、競争を不当に阻害する「独占化(monopolize)」という行為をこそ禁じている、という点にあります。優れた製品や経営手腕によって市場の勝者となることは奨励されるべき競争の結果ですが、その優越的(支配的)な地位を利用して競争のルールそのものを捻じ曲げようとするとき、シャーマン法2条が発動されるのです。
§5.1 独占化(Monopolization)の法理
5.1a 独占化の二要件:グリネル・テスト
違法な独占化が成立するための基本的な分析枠組みは、1966年のグリネル社事件(United States v. Grinnell Corp.)判決で最高裁判所によって確立されました。この「グリネル・テスト」によれば、独占化の罪は以下の2つの要件から構成されます。
- 関連市場における独占力(Monopoly Power)の保有
- 優れた製品、経営手腕、歴史的偶然の結果としての成長・発展とは区別される、その力の意図的な獲得・維持行為
この2要件は、反トラスト法が「罪なき独占者(innocent monopolist)」を罰することを意図していないことを明確に示しています。つまり、単に市場で支配的な地位を占めているだけでは違法ではなく、その地位を反競争的な手段によって獲得したか、あるいは維持した場合にのみ、違法性が問われるのです。単に独占的な地位にあって、高い価格を設定しているだけでは、独占化の罪には問われません。
5.1b 要件1:独占力の認定
独占力とは、第3章で扱った市場支配力が極めて高度な状態を指し、「価格をコントロールし、又は、競争を排除する力」と定義されます。この力の有無を判断する上で、裁判所は主に市場シェアと参入障壁を分析します。
- 市場シェア: 独占力の存在を推認させる最も重要な指標です。過去の判例から、90%以上のシェアは独占力を強く推認させ(アルコア事件)、70%程度でも十分とされることが多いです。一方で、50%未満のシェアで独占力が認定されることは極めて稀です。
- 参入障壁: 高い市場シェアも、新規参入が容易であれば、独占力には結びつきません。独占力の認定には、政府の規制・巨額の初期投資・重要な知的財産権・支配的企業自身の排他的行為等、新規参入を著しく困難にする高い参入障壁の存在が不可欠です。
5.1c 要件2:排他的行為(Exclusionary Conduct)
独占力が認定された上で、分析の核心となるのが第2の行為要件です。これは、その独占力が「排他的行為」によって獲得・維持されたかどうかを問うものです。
排他的行為とは、競争者を市場から不当に排除したり、その競争能力を削いだりすることを目的または効果とする行為を指します。重要なのは、すべての「排除」が違法なわけではないという点です。より優れた製品をより安く提供するという「正当な競争」は、必然的に非効率な競争相手を市場から排除します。反トラスト法が問題とするのは、このような正当な競争ではなく、「正当なビジネス上の理由(legitimate business justification)」を欠き、競争そのものを阻害することによって自社の独占的地位を維持・強化するような行為です。
裁判所は、ある行為が違法な排他的行為にあたるかを判断する際に、「消費者危害テスト(consumer harm test)」を用います。すなわち、その行為が、長期的視点に立って、価格・品質・イノベーションといった側面で消費者に利益をもたらすものか、それとも不利益をもたらすものかを評価するのです。
§5.2 排他的行為の具体例
以下に、判例上、違法な排他的行為として問題となってきた主要な行為類型を挙げます。
5.2a 取引拒絶(Refusal to Deal)
企業は原則として取引の自由を有しますが、支配的企業による取引拒絶は例外的に違法となりえます。アスペン・スキーイング社事件(1985年)では、支配的企業が、過去に実施していた競争相手との有利な協力関係(全山共通リフト券)を、正当な理由なく、かつ自らの短期的な利益を犠牲にしてまで一方的に打ち切った行為が、違法な排他的行為と認定されました。
しかし、その後のベライゾン社対トリンコ事件(2004年)判決は、反トラスト法が安易に支配的企業に競争相手との取引を強制するものではないことを強調し、アスペン判決の適用範囲を限定しました。今日、単独の取引拒絶が違法と認定されるハードルは非常に高くなっています。
また、競争に不可欠な施設へのアクセスを拒否する「エッセンシャル・ファシリティ理論」も存在しますが、これもトリンコ判決以降、裁判所はその適用に極めて慎重な姿勢を示しています。
5.2b 抱き合わせ・排他的取引・垂直統合
- 技術的抱き合わせ(Tech Ties): 優越的企業が、契約ではなく製品設計によって、自社の独占製品と別の製品を不可分に統合し、競争相手を排除する行為です。マイクロソフト事件で、Windows OSにブラウザを統合した行為が違法な独占力維持行為とされたのが典型例です。
- 排他的取引: 優越的企業が、流通業者などに対し、自社製品のみを取り扱うよう強制し、競争相手の販売経路を封鎖する行為です。
- プライス・スクイーズ: 垂直統合した優越的企業が、川上市場では競争者に高い卸売価格を課し、川下市場では自ら低い小売価格を設定して、川下の競争者の利幅を圧迫する行為です。リンクライン事件(2009年)判決以降、その適用は大幅に制限されています。
5.2c 知的財産権の濫用
特許権などの知的財産権は正当な独占権ですが、その権利行使が競争を不当に阻害する手段として用いられる場合は、独占化行為となりえます。
- 不正取得特許に基づく訴訟(ウォーカー・プロセス・ドクトリン): 欺罔によって取得した特許に基づいて侵害訴訟を提起する行為です。
- シャム訴訟(見せかけの訴訟): 勝訴を真の目的とせず、訴訟プロセス自体を利用して競争相手を消耗させる目的で、客観的に無価値な訴訟を提起する行為です。
- ペイ・フォー・ディレイ(逆支払合意): 特許を持つ先発医薬品メーカーが、後発医薬品メーカーの市場参入を遅らせる見返りに金銭を支払う和解契約です。
§5.3 略奪的価格設定(Predatory Pricing)
5.3a 略奪的価格設定の2要件:ブルック・グループ・テスト
排他的行為の中で最も議論を呼んできたのが、略奪的価格設定です。これは、競争相手を市場から駆逐する目的で、採算を度外視したコスト割れの価格を設定し、競争相手が退出した後に価格を独占的水準まで引き上げて損失を回収(リクープ)しようとする戦略を指します。
この行為は、短期的には消費者に低価格の恩恵をもたらすため、正当な価格競争との見分けが非常に難しいです。この問題に対し、最高裁判所はブルック・グループ社事件(1993年)判決で、以下の2つの厳格な要件を原告に課しました。
- コスト以下の価格設定: 被告の価格が、適切な尺度で測定されたコスト(通常は平均可変費用(AVC))を下回っていること。これは、1975年に提唱された「アリーダ=ターナー基準」を実質的に採用したものです。
- 損失回収(Recoupment)の危険な蓋然性: 被告が、競争相手を排除した後に価格を引き上げ、略奪期間中の損失を回収できる現実的な見込みがあること。
5.3b 損失回収要件の重要性
特に第2の損失回収要件は、原告にとって極めて高いハードルとなっています。損失回収が可能であるためには、市場に高い参入障壁が存在し、競争相手の退出後に新規参入が容易に行われないという市場構造が必要です。裁判所は、この要件が満たされない限りコスト割れの価格設定は単なる「無謀な価格競争」に過ぎず、長期的には市場メカニズムによって是正されるため、反トラスト法が介入する必要はないという立場をとっています。この結果、現代のアメリカにおいて、略奪的価格設定の主張が認められることは極めて稀となっています。
§5.4 独占化企図(Attempt to Monopolize)
シャーマン法2条は、独占化が完成した場合だけでなく、それを「試みる」行為も禁じています。独占化企図罪の成立には、以下の3つの要件が必要です。
- 反競争的・略奪的な行為
- 独占を達成するという特定の意図(Specific Intent)
- 独占力を獲得する危険な蓋然性(Dangerous Probability of Success)
「独占力を獲得する危険な蓋然性」の要件を満たすためには、被告が関連市場において、独占には至らないまでも、それに近い相当程度の市場シェア(判例では30〜50%が目安とされることがあります)と影響力を持っていることが通常求められます。この規定は、独占という重大な結果が生じる前に反競争的行為を差し止める予防的な役割を担っています。