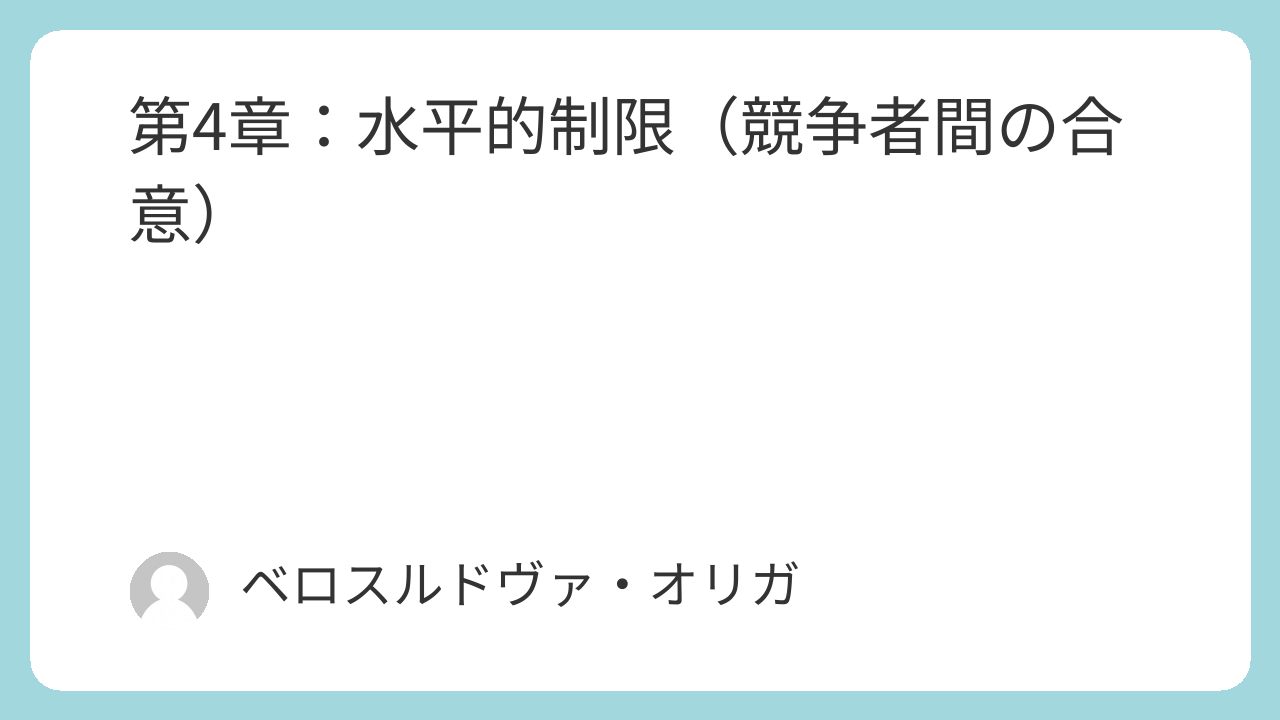反トラスト法の核となるシャーマン法1条は、「取引を制限するあらゆる契約・結合・共謀」を禁じています。この条文が主たる標的とするのは、市場の同一レベルで活動する競争者間の合意、すなわち水平的制限(Horizontal Restraints)です。
競争者間の協力は、反トラスト法において2つの全く異なる側面を持ちます。1つは、価格を吊り上げ、生産量を絞り、市場を分割するためのカルテルという競争の否定そのものです。もう1つは、個々の企業では成し遂げられない技術革新や効率化を実現するための共同事業(ジョイント・ベンチャー)という競争を促進する側面です。
反トラスト法の分析における最も根源的な課題は、この両者をいかにして見分けるかにあります。本章では、まず競争の核心を破壊する「ネイキッドな」制限に対する厳格な当然違法の原則(Per Se Rule)を解説し、次に、競争促進効果と反競争的リスクが混在する共同事業を評価するための、より精緻な合理の原則(Rule of Reason)の分析手法を探求します。
§4.1 ネイキッドな制限:ハードコア・カルテル
4.1a 当然違法の原則
長い間、裁判所は、「その性質上、競争促進的な正当化事由が殆ど考えられず、多くの場合に競争を害すると経験的に判断される特定の行為類型を特定してきました。これらの行為は、市場支配力の有無や実際の競争への影響を詳細に分析するまでもなく、その存在自体が違法とされます。これが当然違法の原則(Per Se Rule)です。
水平的制限の中で、この原則が適用される典型例が「ハードコア・カルテル」と呼ばれるもので、主に以下の3つが含まれます。
- 価格カルテル(Price Fixing): 競争者間で価格を固定・維持・安定させるあらゆる合意。最低価格の設定だけでなく、最高価格の設定や価格算定式の統一、リベートの廃止等も含まれます。
- 市場分割(Market Division): 競争者間で、販売する地域・顧客・製品分野を割り振り、互いの領域に侵入しないことを合意します。
- 入札談合(Bid Rigging): 公共事業や民間契約の入札において、競争者間で事前に落札者や落札価格を決定する行為です。
これらの行為は、単一の独占企業と同様の反競争的効果を人為的に作り出すものであり、反トラスト法上の重罪として刑事罰の対象ともなります。
4.1b カルテルの経済学と不安定性
カルテルは、参加企業全体の利益を最大化するために、共同で生産量を独占的水準まで引き下げ、価格を吊り上げることを目指します。しかし、その内部には常に崩壊の危険性をはらんでいます。各参加企業にとっては、協定を破って密かに、カルテルが設定した高い価格より少し下げ、販売量を増やすことで短期的に大きな利益を得るという強力な「協定違反」の誘惑があるためです。
このため、カルテルが成功するためには、参加企業が互いを監視し、違反者を罰するメカニズムが必要となりますが、その維持は困難です。
4.1c 寡占市場と暗黙の共謀
市場が少数の企業によって支配されている寡占市場では、明示的な合意がなくとも、各社が互いの行動を読み合い価格競争を避けることで、カルテルに近い結果が生じることがあります。一社が値上げをすると他社が追随するプライス・リーダーシップなどがその例です。このような意識的並行行為(Conscious Parallelism)は、それ自体が直ちに違法な「合意」とはなりません。各社が独立した経営判断として、市場環境に合理的に反応した結果である可能性もあるからです。
裁判所が、状況証拠から違法な合意の存在を推認するためには、単なる並行行為に加えて、それが「Plus Factors」(例えば、個々の企業にとっては不合理な行動、過去の共謀の歴史、価格情報の交換等)を伴っていることを要求します。
§4.2 共同事業と合理の原則
競争者間の協力が、何らかの効率化を伴う事業統合(生産、研究開発、販売など)を伴う場合、それは共同事業(ジョイント・ベンチャー)として、より柔軟な合理の原則の下で評価されます。
4.2a あからさまな制限と付随的な制限
分析の鍵は、共同事業に伴う競争上の制限が、事業の効率化という主たる目的を達成するために合理的に必要な「付随的な制限(Ancillary Restraint)」なのか、それとも事業とは無関係に競争を制限すること自体を目的とした「あからさまな制限(Naked Restraint)」なのかを見極めることにあります。
例えば、共同研究開発(R&D)を行う2社が、開発した技術のライセンス価格を共同で設定することは、研究開発投資を回収するために必要な付随的制限と見なされる可能性があります。しかし、その2社が、共同開発とは全く関係のない既存製品の価格まで協定すれば、それはあからさまなカルテルと判断されるでしょう。
4.2b 合理の原則による分析枠組み
合理の原則による分析は、一般的に以下の3段階の立証責任の分配を通じて行われます。
- 原告の立証(反競争的効果): まず、原告が、問題となっている行為が関連市場において価格上昇や生産量減少といった反競争的効果を現に生じさせている、又は、生じさせる可能性が高いことを証明します。
- 被告の立証(競争促進効果): 次に、被告が、その行為には競争促進的な正当化事由があることを主張・立証します。例えば、新製品の開発、品質の向上、生産コスト・取引コストの削減といった効率性の向上などがこれにあたります。
- 原告の再反論(より制限的でない代替手段): 最後に、被告が有効な正当化事由を示した場合でも、原告は、その競争促進効果を達成するためには、「より制限的でない代替手段(Less Restrictive Alternatives)」が存在することを証明することで、なお違法性を主張することができます。
4.2c 具体的な共同行為の分析
- 情報交換: 競争者間の価格や生産量に関する情報交換は、市場の透明性を高め、競争を促進する側面もありますが、カルテルを容易にするリスクもあります。交換される情報の種類(価格かコストか、過去か将来か)・公開性・市場の集中度などを考慮して、その競争効果が判断されます。
- 共同研究開発(R&D)・生産: 個々の企業ではリスクやコストが高すぎる研究開発や生産を共同で行うことは、イノベーションを促進し効率性を高めるものとして、一般に好意的に評価されます。国家協力研究開発法(NCRA)は、このような共同事業に対して、反トラスト法上のリスクを低減させるための手続きを定めています。
- 標準設定(Standard Setting): 製品の互換性や品質に関する業界標準を策定する共同事業は、消費者利益に大きく貢献します。しかし、そのプロセスが特定の企業を不当に排除したり、標準必須特許(SEP)を巡って反競争的なライセンス慣行を生んだりする場合には、反トラスト法上の問題となる可能性があります。
- 共同の取引拒絶(ボイコット):競争者を市場から排除することのみを目的としたあからさまなボイコットは当然違法ですが、業界団体が品質基準や倫理規定を維持するために会員を除名するなど、正当な共同事業に付随する取引拒絶は、合理の原則で評価されます。
- 知的財産権のライセンス: 特許権者らが共同でライセンスを行うパテント・プールや、医薬品業界で見られるペイ・フォー・ディレイ(逆支払合意)なども、競争者間の合意として競争効果が厳しく問われます。
結論として、水平的制限の分析は、その行為が競争の本質を否定する「カルテル」なのか、それとも競争を新たな次元で促進する「効率的な統合」なのかという、二項対立を常に意識する必要があります。その境界線は必ずしも明確ではなく、個々の事案における経済的な現実を深く洞察すること不可欠です。