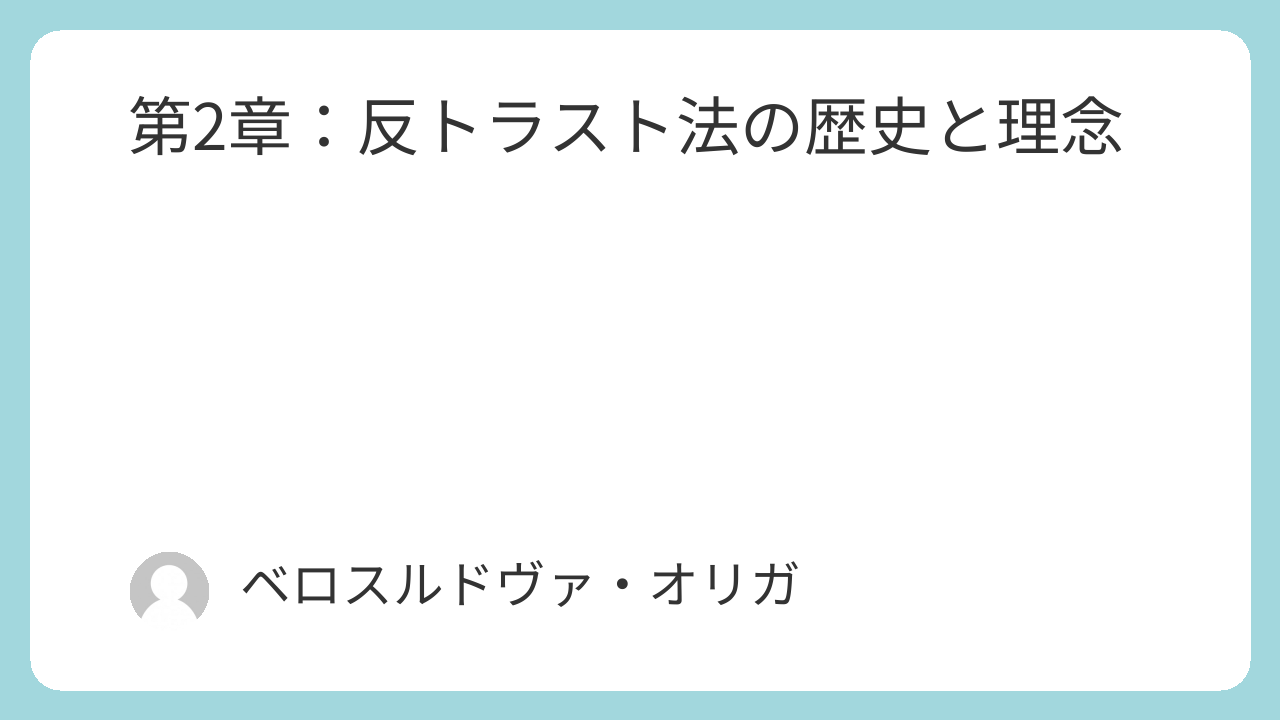§2.1 アメリカ反トラスト法の発展
2.1a シャーマン法の制定背景
19世紀後半、アメリカでは、南北戦争後に急速な工業化が進みました。鉄道網が全土に広がり、全国規模の市場が形成される中で、石油・鉄鋼・砂糖・鉄道といった基幹産業において「トラスト」と呼ばれる巨大な企業連合が次々と誕生しました。ジョン・D・ロックフェラー率いるスタンダード・オイル・トラストに代表されるこれらの企業体は、多数の競争者を吸収・支配し市場を席巻しました。
トラストの形成は、規模の経済による生産性の向上という側面もありましたが、同時に多くの弊害をもたらしました。略奪的な価格設定によって中小の競争者を市場から駆逐し、一旦独占を確立すると価格を吊り上げるという行為が横行しました。また、その強大な経済力を背景に政治的な影響力を行使し、農民や中小事業者、一般消費者の間に深刻な不満・危機感が広がりました。こうした社会的・政治的圧力の高まりが、連邦レベルでの包括的な独占規制の必要性を訴える声となり、1890年のシャーマン法制定へと結実したのです。
2.1b コモンローとの関係
シャーマン法が制定される以前から、アメリカの各州ではイギリスのコモンロー(判例法)に由来する「取引制限(restraint of trade)」を規制する法理が存在しました。しかし、コモンロー上の規制には限界がありました。第一に、その効力は州内に限定され、複数の州にまたがって活動する全国的なトラストには無力でした。第二に、コモンロー上の取引制限契約は、当事者間で「法的強制力がない(unenforceable)」とされるだけで、契約自体を違法として積極的に禁止したり、第三者が損害賠償を請求したりすることは一般に認められていませんでした。
シャーマン法は、この状況を根本的に変えました。取引制限や独占化行為を連邦法上の「違法行為」とし、司法省による刑事訴追や民事差止請求を可能にしました。さらに画期的だったのは、被害を受けた私人が損害額の3倍の賠償を請求できるという強力な私的執行の制度を導入した点です。これにより、反トラスト法は単なる契約法の原則から、市場の競争構造そのものを守るための公法へと性格を転換させました。
2.1c 政策の変遷
シャーマン法の制定後も、反トラスト政策は一様な道を歩んだわけではありません。
- 初期(1890〜1910年代): 当初、裁判所は法の解釈に慎重で、執行は必ずしも活発ではありませんでした。しかし、スタンダード・オイル事件(1911年)やアメリカン・タバコ事件(1911年)で巨大トラストの分割を命じる画期的な判決が下され、反トラスト法の存在意義が確立されました。
- 進歩主義の時代と補完法の制定(1914年): シャーマン法の文言が抽象的すぎるとの批判から、より具体的な行為を規制するクレイトン法と、専門的な執行機関である連邦取引委員会(FTC)を設立するFTC法が制定されました。
- ニューディール期と構造主義(1930〜1960年代): 大恐慌を経て、市場の不完全性に対する認識が深まり、市場構造そのものに問題があるとする構造主義的アプローチ(ハーバード学派)が影響力を増しました。この考え方は、特に第二次大戦後の企業結合(M&A)規制において、市場集中度の上昇に厳しい姿勢で臨む政策へと繋がりました。
- ロビンソン=パットマン法(1936年): 大規模なチェーンストアから中小の小売店を保護することを目的として、価格差別を厳しく規制するロビンソン=パットマン法が制定されました。これは、競争促進という反トラスト法の基本理念とは異質な、特定の競争者を保護する性格を持つ法律として知られています。
§2.2 経済学が果たした役割
2.2a シカゴ学派の台頭と「効率性」基準
1970年代以降、反トラスト法の解釈に革命的な変化をもたらしたのが、シカゴ学派と呼ばれる経済学者・法学者たちです。彼らは、伝統的な構造主義的アプローチを厳しく批判し、新古典派ミクロ経済学の理論を全面的に導入しました。
シカゴ学派の主張の核心は、「反トラスト法の唯一の目的は経済的効率性の最大化、すなわち消費者利益(消費者余剰)の保護であるべきだ」という点にあります。彼らは、市場は一般に効率的であり、独占は長続きしないと考えました。多くの企業行動(特に垂直的制限や価格差別など)は、従来考えられていたように反競争的であることは稀で、むしろ効率性を高めるための合理的な戦略であると論じました。この考え方は、連邦裁判所の判例に大きな影響を与え、多くの行為に対する当然違法の原則が覆され、より柔軟な合理の原則による分析が主流となっていきました。
2.2b ポスト・シカゴ学派と近年の動向
シカゴ学派の分析は反トラスト法に経済学的な観点をもたらしましたが、その単純なモデルでは現実の複雑な市場を説明しきれないとの批判も生まれました。1980年代以降、ゲーム理論や取引費用経済学などの新しい経済学の知見を取り入れた「ポスト・シカゴ学派」が登場しました。
彼らは、シカゴ学派が軽視した市場の不完全性(情報の非対称性、取引費用など)を重視し、企業の戦略的行動が、シカゴ学派が考えるよりも容易に競争を阻害しうることを明らかにしました。これにより、シカゴ学派によってほぼ無害とされた行為でも、特定の条件下では反競争的となりうることが再認識されるようになりました。現代の反トラスト分析は、ポスト・シカゴ学派のアプローチに大きく依拠しています。
§2.3 反トラスト法の目的を巡る議論
反トラスト法の目的は、時代と共に大きく揺れ動いてきました。
- 経済的効率性: シカゴ学派が確立した現代の主流的な考え方です。反トラスト法は、市場における資源配分の効率性を最大化すること、具体的には価格の低下、生産量の増大、品質の向上、イノベーションの促進を通じて消費者利益を高めることを目的とすべきだとしています。
- 社会的・政治的価値: 一方で、反トラスト法には経済的効率性だけでは測れない価値を守る目的があるという主張も根強く存在します。これには、中小企業の保護、経済力の過度な集中がもたらす政治的影響力の排除、個人の経済的自由の確保といったより広範な社会的・民主主義的価値が含まれます。この考え方は、特に巨大デジタル・プラットフォームへの規制が議論される現代において、「ニュー・ブランダイス派」と呼ばれる論者たちによって再び注目を集めています。
今日の裁判所や執行機関は、主として経済的効率性、特に消費者利益を判断の基準としていますが、時代と社会環境の変化に伴い未だに議論は続いています。