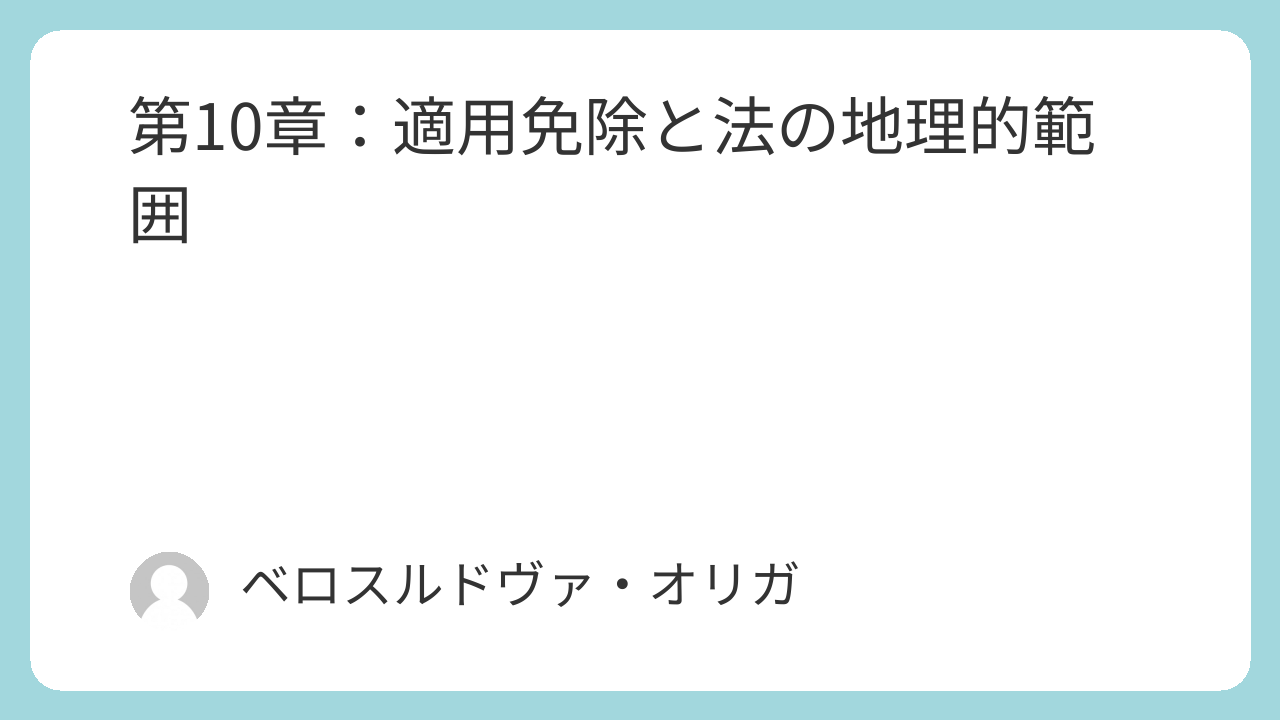アメリカ反トラスト法の適用範囲は極めて広範です。しかし、その力は絶対的なものではありません。民主主義社会における政府の役割、連邦国家としての州の主権、国際社会における他国との関係性といった、より大きな法秩序との調和を図るため、反トラスト法の適用が制限される特定の領域が存在します。
本章では、反トラスト法の適用が及ばない、あるいは制限されるこれらの重要な境界領域について解説します。具体的には、①企業が政府に働きかける行為を保護するノア=ペニントン法理、②他の連邦法による規制産業との関係、③州や地方自治体の規制を尊重する州行為の法理、④法の効力が国境を越えてどこまで及ぶかという地理的適用範囲(域外適用)の問題を取り上げます。
§10.1 政府への請願行為(ノア=ペニントン法理)
企業は、自らに有利な事業環境を創出するため、立法・行政・司法といった政府のプロセスに積極的に働きかけます。たとえその要求の内容が、競争相手を市場から締め出す法律の制定など、極めて反競争的なものであったとしてもです。
ここで、自由競争を保護するという反トラスト法の目的と、アメリカ合衆国憲法修正1条によって保障される「請願権(Right to Petition)」が衝突します。この緊張関係を調整するために、裁判所が確立したのが「ノア=ペニントン法理(Noerr-Pennington Doctrine)」と呼ばれる、反トラスト法の適用免除原則です。
この法理によれば、企業が単独又は共同で政府に対して反競争的な結果を求めて働きかける行為は、その動機を問わず、原則として反トラスト法の適用を受けません。その根底には、取引の制限がもし生じるとすれば、それは私的な共謀の結果ではなく、政府が主権者として下した判断の結果であるという考え方があります。
10.1a 「見せかけ(Sham)」の例外
ただし、この免除は絶対ではありません。裁判所は、請願権の保護が競争を阻害するための単なる「見せかけ(Sham)」に過ぎない行為を隠れ蓑として利用されるべきではないとの重要な例外を設けています。
「見せかけ」の例外が適用されるのは、請願行為が政府による有利な決定を得ることを真の目的としておらず、むしろ請願プロセス自体を利用して競争相手に直接的な損害を与えることを目的としている場合です。プロフェッショナル・リアルエステート・インベスターズ社事件(PRE事件)(1993年)判決で確立された二段階テストによれば、まず、問題となっている訴訟や請願が、①客観的に見て全く無価値で、かつ、②その無価値な請願が競争相手を妨害するという主観的意図を隠すものであったかどうかが判断されます。この要件は極めて厳格であり、実際に「見せかけ」の例外が適用されるケースは稀です。
§10.2 規制産業と黙示的適用除外
通信・エネルギー・運輸・金融といった規制産業では、競争を促進する反トラスト法の論理と価格や参入を制限する規制法の論理が衝突することがあります。
議会が、特定の産業や行為を反トラスト法の適用対象から明確に除外する法律を制定した場合、それは「明示的な適用除外」となります。しかし、多くの規制法は反トラスト法との関係について沈黙しています。このような場合に、規制法の存在によって黙示的に反トラスト法の適用が排除されるかどうかが「黙示的な適用除外(Implied Immunity)」の問題です。
最高裁判所は、黙示的な適用除外は極めて例外的な場合にしか認められないという厳格な立場を一貫してとってきました。適用除外が認められるのは、反トラスト法を適用することが、規制法の枠組みと「明白に矛盾(plain repugnancy)」し、規制制度を機能不全に陥らせてしまうような場合に限られます。単に規制当局による広範な監督が存在するだけでは不十分であり、問題となっている特定の反競争的行為が、規制当局によって積極的に承認・監督されているかどうかが問われます。
§10.3 州行為の法理(State Action Doctrine)
連邦主義の原則に基づき、連邦反トラスト法は、州や地方自治体による正当な規制権限を尊重します。この原則を具体化したものが「州行為の法理」です。これは、反競争的な行為が、私人の自由な選択の結果ではなく州という公権力の命令または承認によるものである場合、反トラスト法の適用を免除するという判例上の法理です(パーカー対ブラウン事件、1943年)。
ただし、州の規制の枠組みの中で活動する私人(企業や業界団体など)の行為が免除されるためには、ミッドカル・テストと呼ばれる以下の厳格な2要件を満たす必要があります。
- 明確な授権(Clear Articulation): 問題となっている反競争的な行為が、州によって「明確に表明され、かつ積極的に表現された州の政策」に基づいていなければなりません。
- 積極的な監督(Active Supervision): その州の政策に基づいて行われる私人の行為が、州によって「積極的に監督」されていなければなりません。
この2つの要件は、州行為の法理が、私的な利益追求のための反競争的行為に悪用されることを防ぐための重要な防波堤となっています。特に第2の「積極的な監督」要件は、州が単に反競争的行為を許可するだけでなく、その内容(価格の合理性など)を実質的に審査しコントロールしていることを要求します。
§10.4 法の地理的適用範囲
10.4a 国内における適用範囲
連邦反トラスト法は、合衆国憲法の通商条項に基づき、州際通商に影響を及ぼす行為に適用されます。現代的な「影響理論」の下では、たとえ州内で完結するローカルな活動であっても、それが州際通商に実質的な影響を及ぼす場合には、原則として法の管轄権が及ぶと広く解釈されています。
10.4b 域外適用とFTAIA
アメリカ国外で行われた行為に対してアメリカの反トラスト法を適用する域外適用は、外国貿易反トラスト改善法(FTAIA)によって規律されています。
FTAIAは、原則としてシャーマン法は外国との取引には適用されないとしつつ、その例外として、外国での行為がアメリカ国内の通商・輸入通商、又は、アメリカの輸出者の輸出通商に対して「直接的、実質的かつ合理的に予見可能な効果(direct, substantial, and reasonably foreseeable effect)」を及ぼす場合には、シャーマン法が適用されると定めています。
つまり、国際的な価格カルテルであっても、それがアメリカ市場の価格に直接的・実質的な影響を与えない限り、アメリカの反トラスト法違反とはなりません。しかし、そのカルテルがアメリカへの輸入品の価格を吊り上げたり、アメリカ企業の輸出を妨害したりした場合には、FTAIAの例外規定に該当し法の適用対象となります。
さらに、エンパグラン社事件(2004年)判決により、FTAIAに基づく請求権は、アメリカへの効果によって生じた損害に限定されることが明確にされました。外国の購入者が外国で受けた損害は、たとえ同じカルテルが原因であっても、アメリカの反トラスト法の保護対象外であるとされました。
10.4c 域外適用を制約するその他の原則
FTAIAの要件を満たす場合でも、裁判所は他国の主権を尊重するため、管轄権の行使を控えることがあります。その根拠となるのが、国際礼譲(International Comity)、外国政府の公的行為の有効性を審査しない国家行為の法理(Act of State Doctrine)、外国政府によって行為を強制された場合の抗弁である外国政府強制の抗弁(Foreign Sovereign Compulsion)といった、国際法上の諸原則です。これらの原則は、反トラスト法のグローバルな執行と、国際社会における法の支配との間のデリケートなバランスを調整しています。