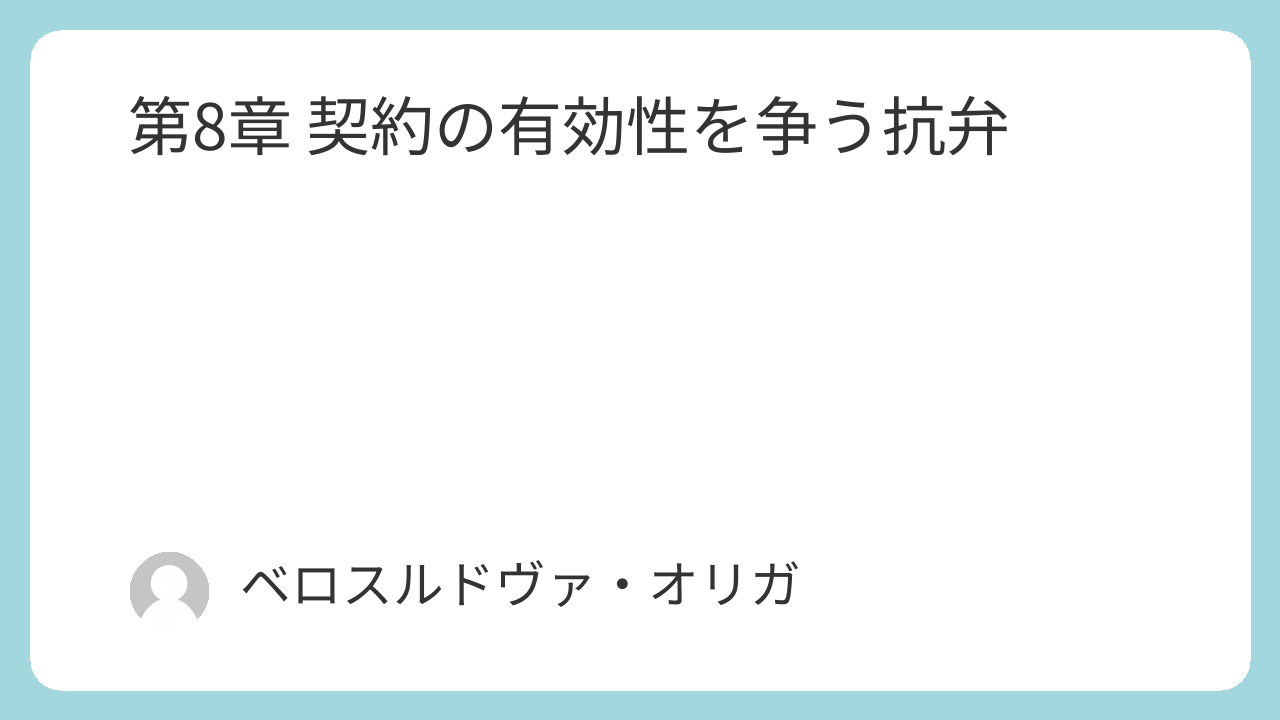契約は、申込・承諾・約因という要素が揃うことで成立します。しかし、これらの形式的な要件を満たしていても、その契約が法的に有効であるとは限りません。契約の効力は、当事者の能力、合意形成の過程、契約内容そのものに潜む問題によって、後から覆されることがあります。
当事者の一方が契約の履行を求めて訴訟を起こしたとき、もう一方の当事者は、単に「契約違反はない」と主張するだけでなく、「そもそもこの契約は法的に強制されるべきではない」という積極的な主張、すなわち「抗弁(Defense)」を提出することができます。この抗弁が認められれば、契約は無効となったり、取り消されたりして、履行義務を免れることができます。
8.1 契約締結能力の欠如(Incapacity)
契約は、自らの意思で法的な義務を負うという、成熟した判断能力を前提としています。そのため、法は、自らの利益を十分に保護できない可能性のある特定の個人を保護するため、彼らが結んだ契約の効力を制限しています。
A. 未成年者(Minors)
アメリカのほとんどの州では、18歳未満の者は未成年者とされ、契約締結能力が制限されています。未成年者が結んだ契約は「無効(void)」ではなく、「取消可能(voidable)」であるというのが原則です。
これは、契約の効力の選択権が未成年者側にのみ与えられることを意味します。未成年者は、自らが結んだ契約を履行することも、あるいは一方的に取り消して無かったことにすることもできます。しかし、相手方である成人は、未成年者であることを理由に契約を取り消すことはできません。
- 取消しと原状回復:未成年者が契約を取り消した場合、受け取った物品を返還する義務があります。しかし、もしその物品が破損したり価値を失ったりしていても、多くの州では、未成年者は現存する限度で返還すればよいとされています。これは、未熟な未成年者を保護するという政策を重視するためです 。
- 追認(Ratification):未成年者が成年に達した後、合理的な期間内に契約を取り消さず、契約の利益を享受し続けるなど、契約を認める言動をとった場合、その契約は追認されたとみなされ、もはや取り消すことはできなくなります。
- 生活必需品(Necessaries):未成年者であっても、食料・住居・医療といった生活必需品に関する契約については、契約そのものではなく、提供された利益の公正な価値について支払う義務を負います。これは、未成年者が生活に必要なものを得られなくなる事態を防ぐためのルールです。
B. 精神上の障害(Mental Incapacity)
精神的な疾患や障害により、契約の性質やその結果を合理的に理解できない者が結んだ契約も、同様に取消可能です。裁判所は、契約締結能力の有無を判断するにあたり、主に2つの基準を用います。
- 認識テスト(Cognitive Test):その者が、取引の性質と結果を理解する十分な精神的能力を欠いていたかどうか。
- 意思テスト(Volitional Test):その者が、取引内容を理解はできていたものの、精神疾患によって自己の行動を合理的に制御することができず、相手方がその状況を知っていたか、または知るべき理由があったかどうか。
また、日本とは異なり、裁判所によって正式に後見(guardianship)の開始が宣言された者が結んだ契約は、「取消可能」ですらなく、当初から「無効(void)」となります。
8.2 合意の瑕疵
たとえ当事者に契約締結能力があったとしても、合意に至るプロセスに重大な欠陥があれば、その合意は真意に基づかないものとして、契約の効力が否定されることがあります。
A. 詐欺・不実表示(Fraud/Misrepresentation)
一方の当事者が、虚偽の事実を告げることによって相手方を騙して契約を結ばせた場合、その契約は取消可能です。
- 詐欺的(Fraudulent)な不実表示:虚偽であることを知りながら、又は、真実かどうかを顧みずに、相手を騙す意図をもって重要な事実を告げること
- 重大的(Material)な不実表示:たとえ騙す意図がなくても、その虚偽表示が、合理的な人であれば契約を結ぶかどうかの判断に影響を与えるような重要な事柄に関するものであった場合
単なる意見やセールストーク(Puffing)は、事実の表示ではないため、原則として不実表示にはあたりません。また、原則として、当事者は自ら積極的に情報を開示する義務はありませんが、相手が重大な誤解をしていることを知りながら沈黙している場合など、特定の状況下では不開示(nondisclosure)が不実表示と同視されることもあります。
B. 強迫(Duress)
一方の当事者が、相手方に対して不当な脅迫(improper threat)を用い、その結果、相手方が合理的な選択肢を他に持たない状況で契約に同意させられた場合、その契約は強迫を理由に取消可能となります。
- 物理的な強迫(銃を突きつけられて署名させられるなど)によって結ばれた契約は、そもそも真の合意が存在しないとして無効です。
- より一般的には、経済的な圧力を利用する経済的強迫(economic duress)が問題となります。例えば、契約の一方当事者が、相手方が窮地に陥っている状況を利用して、「この不利益な修正に応じなければ、契約を履行しない」と脅迫するようなケースです。
C. 不当威圧(Undue Influence)
強迫のようなあからさまな脅しではないものの、一方の当事者が、相手方との信頼関係や相手方の精神的な弱さを利用して不当な説得を行い、契約を結ばせた場合、その契約は取消可能です。これは、弁護士と依頼人、医者と患者、あるいは高齢の親と子といった、一方が他方に強く依存する関係で問題となることが多くあります。
8.3 不当性(Unconscionability)
契約の条項が、社会の良識に照らして著しく不公正であり、一方当事者にとって過酷である場合、裁判所はその条項または契約全体の効力を否定することができます。これをUnconscionabilityの法理と呼びます。これは、契約自由の原則の濫用を抑制するための、裁判所の衡平法上の権限です。
非良心性の判断は、通常、2つの側面から行われます 。
- 手続的な不当性(Procedural Unconscionability):契約締結のプロセスにおける不公正さ。例えば、極端に不平等な交渉力、理解困難な細かい字で書かれた条項(fine print)、内容を交渉する機会が全くない附合契約(contract of adhesion)などがこれにあたります。
- 実体的な不当性(Substantive Unconscionability):契約条項の内容そのものの不公正さ。例えば、法外な価格、一方当事者の権利を過度に制限する条項などがこれにあたります。
多くの裁判所はこれら2つの要素が両方存在することを要求しますが、一方の不公正さが極めて著しい場合には、もう一方の要素がそれほど強くなくても不当性が認められることがあります。
8.4 公序良俗違反(Illegality and Public Policy)
契約の目的や内容が、法律(制定法)や判例法によって確立された公の秩序や善良な風俗(public policy)に反する場合、その契約は無効となります。
- 違法な契約:殺人や賭博等、犯罪行為や法律で禁止されている行為を目的とする契約は、当然に無効です。
- 公序に反する契約:直接的に違法ではなくても、社会の根本的な価値観に反する契約も無効とされることがあります。例えば、司法の公正を害するような証言取引契約や、競争を不当に制限するカルテル協定 、公共の安全を守るための許認可(licensing)を持たない専門家(医師や弁護士など)とのサービス契約などがこれにあたります。
契約の一部のみが公序良俗に反する場合、裁判所はその部分だけを無効とし(分離)、契約の残りの部分の効力を維持することがあります。