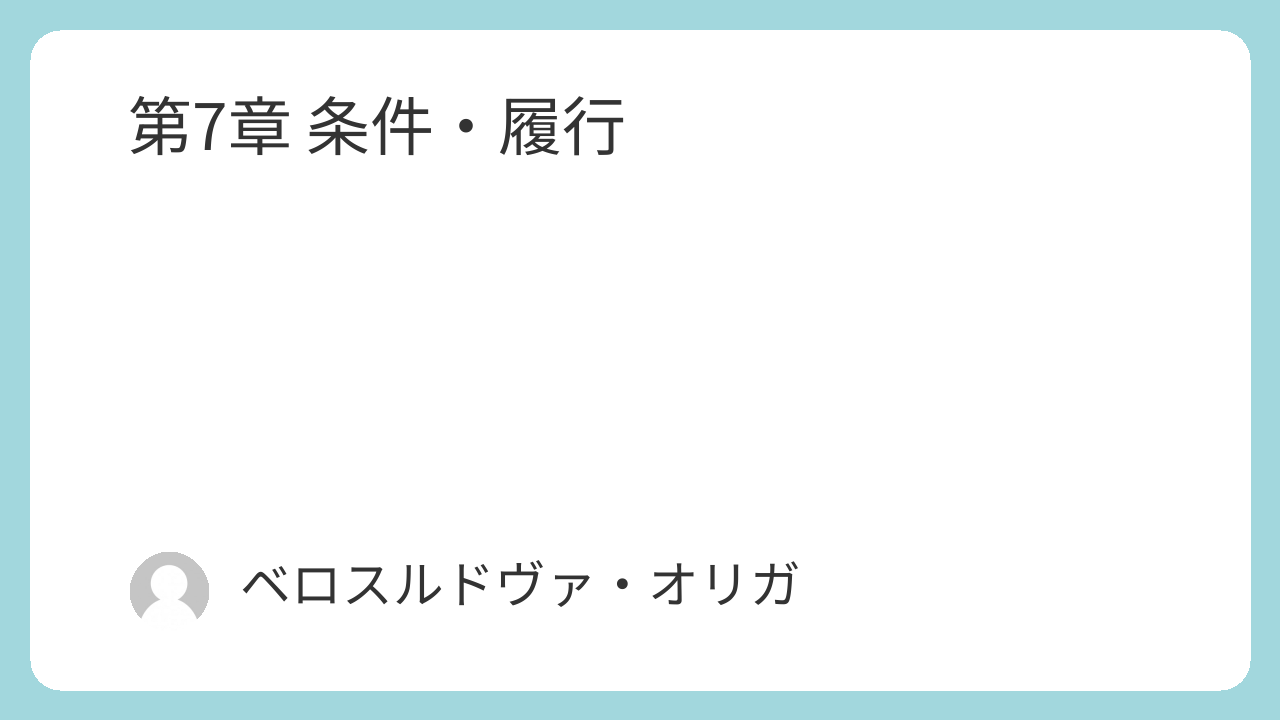契約が成立すると、当事者は約束した内容を履行(performance)する義務を負います。しかし、多くの場合その義務は無条件に発生するわけではありません。特定の出来事が起こることを前提として、義務の発生が左右されることがあります。
7.1 条件(Conditions)とは何か
条件とは、「その発生が不確実な未来の出来事であり、その出来事の発生・不発生によって、契約上の義務が発生したり消滅したりする」ものを指します。
A. 約束と条件の区別
ある契約条項が「約束」なのか「条件」なのかを区別することは極めて重要です。なぜなら、その効果が全く異なるからです。
- 約束(Promise)が破られた場合:それは契約違反(breach)となり、相手方は損害賠償などの救済を求めることができます。
- 条件(Condition)が成就しない(満たされない)場合:それは契約違反ではありません。単に、その条件に紐づけられた一方当事者の履行義務が発生しないという効果が生じるだけです。
例えば、住宅火災保険契約において、「保険料を支払う」というのは被保険者の約束です。これを怠れば契約違反となります。一方、「火災が発生した場合に保険金を支払う」という保険会社の義務にとって、「火災の発生」は条件です。火災が発生しなくても、保険会社が契約に違反したことにはなりません。
契約書の文言が曖昧な場合、裁判所は、当事者に不利益(特に権利の没収)が生じるのを避けるため、その条項を「条件」ではなく「約束」と解釈する傾向があります。
B. 条件の種類
日本法と同様、条件は、その機能と発生源によって分類されます。
- 機能による分類
- 停止条件(Condition Precedent):条件が成就して初めて、履行義務が発生します。例えば、「住宅ローンの審査に通ったら、家を購入する」という契約の「ローンの審査通過」がこれにあたります。
- 解除条件(Condition Subsequent):契約締結時に義務は既に発生するものの、条件が成就すると義務が消滅します。
- 同時履行の条件(Concurrent Conditions):当事者双方の履行が同時に行われるべき場合に、一方の履行の提供が、他方の履行義務の発生条件となります。物品の売買で、代金の支払いと商品の引き渡しが同時に行われるのが典型例です。
- 発生源による分類
- 明示の条件(Express Conditions):「if」「provided that」「subject to」といった言葉で、当事者が契約書の中で明確に定めた条件。明示の条件は厳格に満たされる必要があります。「実質的に」満たされただけでは不十分です。
- 黙示の条件(Implied Conditions):契約の文言には現れていなくても、当事者の意図や取引の性質から当然に存在すると推測される条件
- 擬制条件(Constructive Conditions):当事者の意思とは直接関係なく、裁判所が公平の見地から、当事者間の履行の順序を定めるために法的に「擬制」する条件。例えば、一方が労務を提供し、他方が報酬を支払う契約では、特段の定めがなければ「労務の提供」が「報酬支払」の擬制的な停止条件となります。
7.2 履行と契約違反
当事者が契約上の義務を正当な理由なく果たさない場合、それは債務不履行・契約違反(Breach of Contract)となります。契約違反は、その深刻度に応じて、「実質的な違反(Material Breach)」と「軽微な違反(Minor Breach)」に分けられます。この区別は、違反されなかった側の当事者(非違反当事者)がどのような対抗措置を取れるかを決定する上で、決定的に重要です。
A. 実質的履行と実質的な違反(コモンロー)
建設契約やサービス契約など、UCCの適用がないコモンローの世界では、「実質的履行の原則(Doctrine of Substantial Performance)」が適用されます。これは、契約の主要な目的が達成される程度に義務が履行されていれば、たとえ細部において完全でなくても、契約違反は「軽微」なものにとどまるという考え方です。
- 実質的履行がなされた場合(軽微な違反):
- 非違反当事者は、自らの履行義務(例:代金の支払い)を拒むことはできません。
- ただし、違反によって生じた損害(例:欠陥の修補費用)を、支払うべき代金から差し引く(相殺する)ことができます。
- 実質的履行がなされなかった場合(実質的な違反):
- 非違反当事者は、自らの履行を一時停止し、相手方に是正(cure)の機会を与えることができます。
- 違反が是正されない場合、非違反当事者は契約を解除(cancel)し、自らの履行義務を完全に免れるとともに、全体的な契約違反に対する損害賠償を請求できます。
何が「実質的な違反」にあたるかは、①非違反当事者が期待した利益がどの程度奪われたか、②金銭賠償でどの程度補償可能か、③違反当事者がどの程度履行を終えているか、④違反が悪意によるものかといった要素を総合的に考慮して判断されます。
B. 完全履行の原則(UCCにおける物品売買)
UCCが適用される物品売買契約では、コモンローよりもはるかに厳格な「完全履行の原則(Perfect Tender Rule)」(UCC §2-601)が適用されます。これは、引き渡された物品が契約内容と「いかなる点においてでも(in any respect)」異なっている場合、買主は原則として、その物品の全部の受領を拒絶できる、というルールです。
この原則は非常に厳格ですが、その硬直性を緩和するための例外も設けられています。
- 是正(Cure)の権利:履行期前であれば、売主は不適合な物品を引き取り、履行期までに適合品を再度提供することで、契約違反を「是正」する権利があります。
- 分割払い契約(Installment Contracts):複数回に分けて納品される契約の場合、ある回の納品に不適合があっても、それが契約全体の価値を「実質的に害する(substantially impair)」ものでなければ、買主は契約全体を解除することはできません。
7.3 履行拒絶(Anticipatory Repudiation)
契約違反は通常、履行期が到来しても履行がなされない場合に発生します。しかし、履行期が到来する前に、一方当事者が「私はこの契約を履行するつもりはない」と明確かつ無条件に表明することがあります。これを「予期的契約違反」または「履行拒絶」と呼びます。
この場合、非違反当事者は、履行期まで待つ必要はありません。予期的契約違反があった時点で、直ちに以下のいずれかの行動をとることができます。
- 履行拒絶を最終的なものとみなし、契約を解除して直ちに損害賠償を請求する。
- 自らの履行を停止し、相手方が考え直して履行するのを「商業的に合理的な期間」待つ。
履行の不安と保証の要求
相手方の言動が、明確な履行拒絶とまでは言えないものの、「本当に履行してくれるだろうか」という合理的な不安(reasonable grounds for insecurity)を抱かせる場合があります。例えば、相手方の財政状態が悪化したという噂を聞いたようなケースです。
このような場合、UCC §2-609は、不安を抱いた当事者が、相手方に対して「適切な履行の保証(adequate assurance of performance)」を書面で要求する権利を認めています。保証を要求した側は、回答があるまで自らの履行を停止することができます。相手方が合理的な期間内(最長30日)に適切な保証を提供しない場合、それは法的に「予期的契約違反」とみなされ、契約を解除し損害賠償を請求することができます。