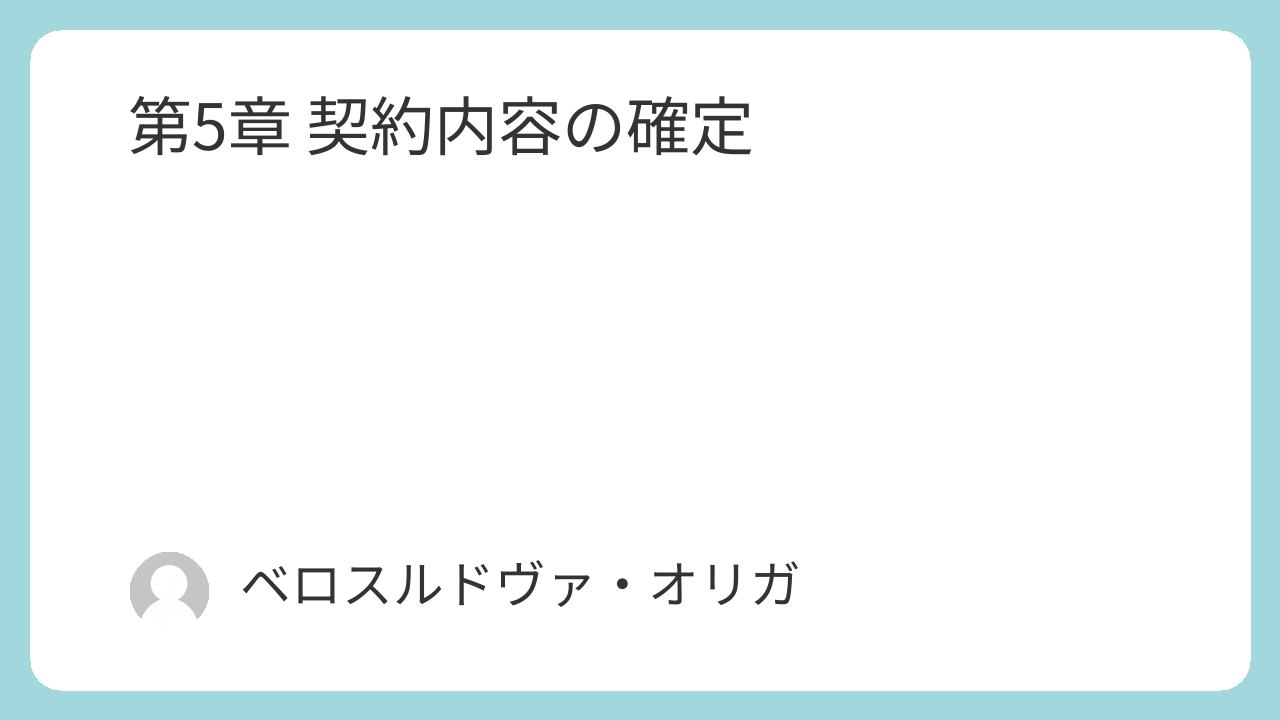契約が有効に成立すると、次に「契約が具体的に何を義務付けているのか」ということが問題になります。当事者が口にした言葉や書面に記した文言は、必ずしも一義的に明らかとは限りません。ある言葉が複数の意味に取れたり、当事者間の特別な文脈で使われていたり、又は、重要な事柄について契約書が沈黙していることもあります。
この時に重要なのが、「契約解釈(Interpretation)」のルールと「口頭証拠排除法則(Parol Evidence Rule)」です。契約解釈は、契約の文言や状況から当事者の真の意図を探る作業です。一方、口頭証拠排除法則は、当事者が最終的な合意として契約書を作成した場合に、その契約書に書かれていない事前の合意(口約束など)を証拠として裁判所が考慮することを制限します。
5.1 契約の解釈
契約解釈の究極的な目的は、契約締結時における当事者の共通の意思(common intention of the parties)を明らかにすることです。しかし、紛争が生じたとき、当事者それぞれの「意図していた」という主観的な主張は食い違うのが常です。そのため、裁判所は客観的な手がかりを用いて、その意思を再構築しようと試みます 。
A. 文理解釈(Plain Meaning) vs. 文脈解釈(Contextual Interpretation)
契約解釈には、大きく分けて2つのアプローチが存在します。
- 文理解釈(Plain Meaning Rule)
これは、契約書で使われている言葉は、辞書に載っているような一般的で明白な意味に従って解釈すべきであり、文言自体が明確である限り、外部の証拠(当事者の交渉過程など)を考慮すべきではない、という伝統的な考え方です。契約書の文言の安定性を重視するアプローチと言えます。 - 文脈解釈(Contextual Interpretation)
これに対し、現代の多くの裁判所が採用するのは、より柔軟な文脈解釈です。言葉というものは、それが使われた文脈によって意味が変わるという考えに基づき、契約の真の意味を理解するためには、契約書の外にある証拠(extrinsic evidence)も積極的に考慮すべきだとします。これには、以下のようなものが含まれます。- 契約交渉の経緯
- 当事者が契約を通じて達成しようとした目的
- 当事者間の過去の取引のあり方
- その業界における慣習
B. 解釈の補助原則(Maxims of Construction)
裁判所は、解釈の指針として、経験則から導かれたいくつかの補助原則を用います。これらは絶対的なルールではありませんが、有力な判断材料となります。
- Contra Proferentem(起草者不利益の原則):契約条項の文言が曖昧な場合、その条項を作成した側に不利に解釈される。特に、保険約款のような附合契約で多用されます。
- 交渉された条項の優先:定型的な印刷条項(ボイラープレート)と、当事者が個別に手書きやタイプで追記・修正した条項が矛盾する場合、後者が優先されます。当事者の個別具体的な意思が、一般的な定型文言に勝ると考えるからです。
- 全体解釈の原則:契約は部分ではなく、全体としてひとつのまとまりを持つものとして解釈されます。ある条項の意味は、他の条項との関連性の中で理解されなければなりません。
C. 慣習による補充:取引慣習・継続的取引経過・履行の過程
契約書に明記されていなくても、当事者間の合意内容の一部をなすとされるものがあります。これらは、契約の「黙示の条項」として機能します。
- 取引慣習(Usage of Trade):特定の業界や地域で、当然の前提として広く受け入れられている慣行。当事者がその慣習を知っているかどうかにかかわらず、その業界に属する者として知っているべきであったとみなされ、契約内容を補充します。
- 継続的取引経過(Course of Dealing):当事者間で、過去の同種の取引において繰り返されてきた行動のパターン。これは、両者の間に形成された「私的な慣習」として、現在の契約の解釈基準となります。
- 履行の過程(Course of Performance):今回の契約において、既に履行が開始された後、相手方が異議を唱えることなく受け入れてきた履行の方法。これは、当事者自身がその契約をどのように理解していたかを示す最も強力な証拠とみなされます。
UCCは、これらの慣習について、①履行の過程、②継続的取引経過、③取引慣習の順で、より個別具体的なものを優先して適用するという優先順位を定めています。
5.2 口頭証拠排除法則(Parol Evidence Rule)
契約交渉の過程では、様々な口約束や仮の合意がなされます。しかし、最終的に当事者が「これが我々の最終的かつ完全な合意である」として1つの契約書に署名した場合、その書面化のプロセスで、それ以前の合意はすべてその最終文書に「統合(integrated)」されたとみなされます 。
口頭証拠排除法則とは、このように当事者が最終的な合意として作成した書面(統合された契約書)が存在する場合、その契約書が作成される以前になされた、又は、契約書作成と同時になされた、契約書の内容と矛盾する口頭または書面による合意の証拠を裁判所が考慮することを禁じるルールです。
この法則の目的は、書面化された最終契約の安定性と信頼性を保護することにあります。もしこのルールがなければ、誰もが契約締結後に「実は署名前にはこんな口約束があった」と主張し始め、契約書を作成した意味が失われてしまうでしょう。
A. 「統合」のレベル:完全統合と部分統合
この法則が適用されるかどうかの鍵は、その契約書がどの程度「統合」されているかによります。
- 完全統合(Complete Integration):当事者が、その契約書を自分たちの合意の「最終的」かつ「完全な」表明であると意図した場合。この場合、契約書の内容と矛盾する証拠はもちろんのこと、契約書に書かれていない内容を補充する証拠さえも排除されます。契約書に「本契約は、当事者間の完全かつ唯一の合意を構成する(This Agreement constitutes the entire agreement between the parties.)」といった完全合意条項(merger clause or integration clause)が含まれている場合、完全統合であることの強力な証拠となります。
- 部分統合(Partial Integration):当事者が、契約書を合意の「最終的」な表明とは意図したものの、「完全な」表明とは意図しなかった場合。つまり、契約書に書かれている条項については最終的な合意だが、書かれていない他の合意事項が存在する可能性がある状態です。この場合、契約書の内容と矛盾する証拠は排除されますが、矛盾しない範囲で内容を補充する証拠は許容されます。
B. 口頭証拠排除法則の「例外」
口頭証拠排除法則が適用されない例外が存在します。これらは、そもそも契約の有効性自体を争う場合など、法則の目的が及ばない場面です。
- 契約の有効性に関する争い:口頭証拠が、契約書の内容を「変更」するためではなく、契約自体が詐欺・強迫・錯誤・約因の不存在などによって当初から無効または取消可能であることを証明するために用いられる場合
- 解釈のための証拠:文言の意味が曖昧(ambiguous)である場合に、その意味を明らかにするための証拠
- 契約成立の前提条件:契約書全体が、ある口頭で合意された条件(condition precedent)が成就するまで有効にならないという合意があったことを証明するための証拠
- 契約後の修正:口頭証拠排除法則が排除するのは、あくまで契約書作成以前または同時の合意です。契約書が作成された後になされた口頭での修正合意(subsequent modification)には、この法則は適用されません。
口頭証拠排除法則は、アメリカ契約法の中でも特に難解で、多くの裁判所を悩ませてきました。しかし、その根底にあるのは、「当事者が最終的な書面合意に込めた意思を尊重する」という、契約法の基本原則です。契約書を作成する際には、この法則の存在を常に意識し、重要な合意事項はすべて最終的な書面に盛り込むことが、後の紛争を避けるための最善策となります。