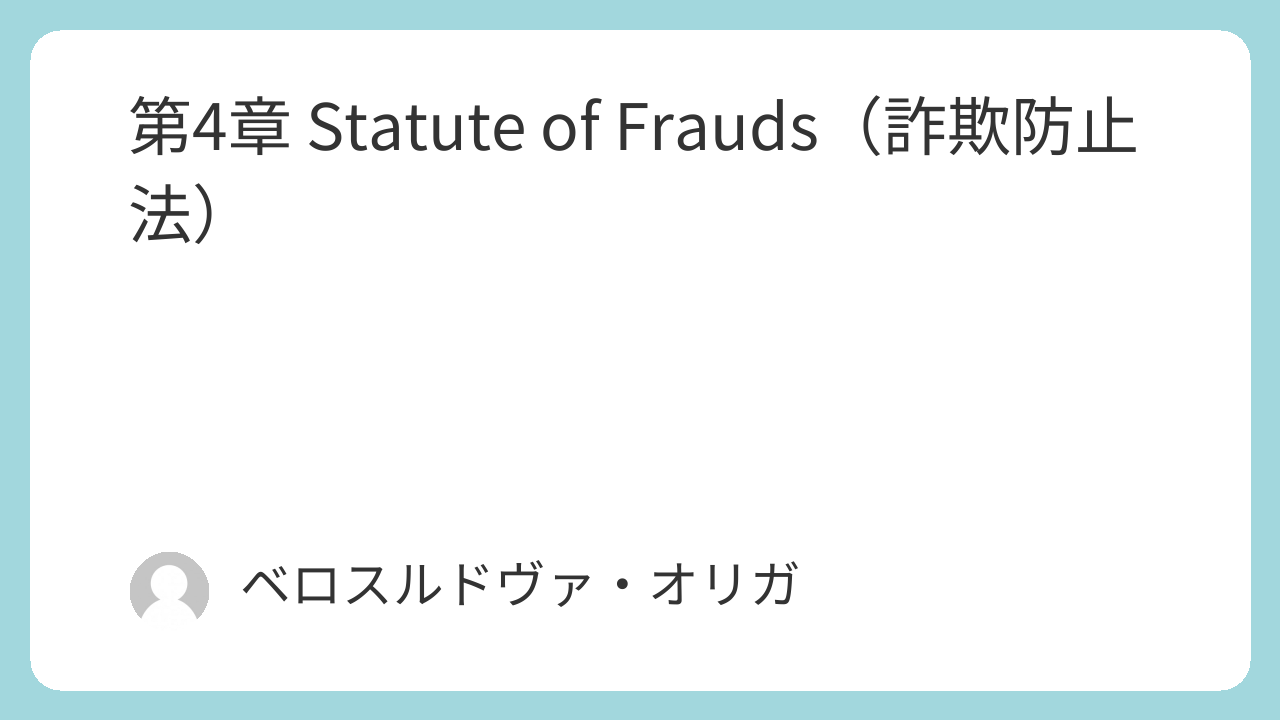アメリカ契約法の基本原則は、口頭での合意であっても法的に有効な契約が成立するというものです。しかし、この大原則には重要な例外が存在します。特定の種類の契約については、その存在と内容を証明するために「書面(a writing)」がなければ、法的に強制することができないのです。このルールを定めた法律を「Statute of Frauds(詐欺防止法)」と呼びます。
4.1 Statute of Fraudsの歴史と目的
詐欺防止法の起源は、17世紀のイギリスに遡ります。1677年に制定されたイギリスの法律がその原型であり、アメリカの各州もこれを継承しました。その名の通り、この法律の主たる目的は「詐欺(fraud)」と「偽証(perjury)」を防ぐことにあります。
口頭契約のみに頼ると、一方の当事者が存在しない契約をでっち上げたり、契約内容について偽りの証言をしたりするリスクが高まります。特に、土地の売買や長期にわたる契約等、利害関係が大きく、当事者の記憶が曖昧になりがちな重要な取引において、そのリスクは高まります。そこで、詐欺防止法は、そのような重要な契約については、信頼性の高い証拠である「署名された書面」の存在を要求することで、当事者を偽りの主張から守ろうとしたのです。
現代において、詐欺防止法は以下の3つの重要な機能を果たしていると考えられています。
- 証拠機能(Evidentiary Function):契約の存在とその内容について、信頼できる証拠を提供する
- 警告機能(Cautionary Function):当事者に署名を求めることで、法的な義務を負うことの重要性を認識させ、軽率な契約締結を防ぐ
- 誘導機能(Channeling Function):当事者が契約内容を明確に書面に残すことを促し、後の紛争を予防する
4.2 書面が必要となる契約類型
詐欺防止法が適用される契約の範囲は、州法によって若干の違いがありますが、コモンローで伝統的に認められてきた主要な類型は以下の通りです。
A. 土地に関する契約(Contracts for an Interest in Land)
土地の売買・借地権の設定・地役権等、土地に関する権利(an interest in land)の移転を目的とする契約は、原則として書面が必要です。土地は価値が高く社会経済の基盤となる重要な資産であるため、その取引の明確性を確保する必要があるからです。
B. 1年以内に履行が完了しない契約(Contracts That Cannot Be Performed Within a Year)
契約締結時から数えて、履行が完了するまでに1年以上を要することが物理的に不可能な契約は、書面がなければ強制できません 。これは、長期にわたる契約は当事者の記憶が不確かになり紛争が生じやすいためです。
ここで重要なのは、「1年以内に履行される可能性が少しでもあれば、この規定は適用されない」という厳格な解釈がなされる点です。
- 例1:生涯雇用契約
「Aさんを生涯雇用する」という口頭契約は、詐欺防止法の対象外です。なぜなら、Aさんが契約後1年以内に死亡する可能性があるからです。その場合、契約は1年以内に「完全に履行された」ことになります。 - 例2:2年間の雇用契約
「Bさんを2年間雇用する」という口頭契約は、詐欺防止法の対象となります。この契約が1年以内に完全に履行されることは物理的に不可能だからです。
C. 他人の債務を保証する契約(Suretyship Agreements)
日本の新民法と同様に、保証人が主債務者の債務を債権者に対して保証する保証契約は書面が必要です。これは、保証人が直接的な利益を得ることなく重い責任を負うため、軽率な保証を防ぐ目的があります。
- 例外:主たる目的ルール(Main Purpose Rule)
ただし、保証人が主債務者のためではなく、自分自身の経済的利益を主たる目的として保証を行った場合には、口頭の保証であっても有効とされます。例えば、自社が主要な仕入先である下請け企業の銀行融資を、自社の安定的な部品供給を確保するために保証するようなケースがこれにあたります。
D. 500ドル以上の物品売買契約(UCC §2-201)
統一商事法典(UCC)は、500ドル以上の価値がある「物品(goods)」の売買契約について、書面を要求しています。これは、商取引における重要な契約の証拠を確保するための規定です。
E. 婚姻を約因とする契約(Contracts in Consideration of Marriage)
結婚そのものの約束ではなく、結婚を「対価(約因)」として財産を譲渡するなどの約束をする契約は、書面が必要です。例えば、「もしBさんと結婚してくれるなら、Aさんの借金を肩代わりする」といった婚前契約(prenuptial agreement)がこれにあたります。
4.3 書面要件を満たすための条件
詐欺防止法を満たすための「書面」は、必ずしも正式な契約書である必要はありません。メモ・手紙・電子メール等、複数の文書を組み合わせることも可能です。ただし、その書面は以下の要件を満たさなければなりません。
- 契約の必須要素が記載されていること:当事者を特定でき、契約の主題が示され、契約が成立したことを示す内容が含まれている必要があります。UCCの物品売買契約では、数量の記載が不可欠です 。
- 強制執行を受ける側の当事者によって署名されていること:契約の履行を強制したい相手方(被告となる側)の署名(signature)が必要です。署名は、手書きのサインに限らず、イニシャル・記号・電子署名等、本人が認証の意思をもって付したものであれば有効です。
4.4 書面がない場合の例外
詐欺防止法の対象となる契約で、かつ、書面が存在しない場合であっても、公平の見地から例外的に口頭契約の履行が認められることがあります。
A. 一部履行(Part Performance)
- 土地に関する契約:買主が代金の一部を支払い土地の占有を開始しかつ恒久的な改良を加えた場合等、口頭契約の存在を強く推認させる行動があった場合には、例外的に契約の履行が認められることがあります。
- 物品売買契約(UCC):代金が支払われ受領された物品又は買主が受領し検収した物品の範囲内では、口頭契約が有効となります 。
B. 約束的禁反言(Promissory Estoppel)
一方の当事者が、相手方の口頭の約束を信頼して、重大かつ予見可能な不利益を被るような行動をとった場合、不正義を避けるために、約束的禁反言の法理によって口頭契約が強制されることがあります。ただし、この例外の適用に慎重な裁判所も多くあります。
C. UCCにおける特別な例外
UCCの物品売買契約には、商人間の取引を円滑にするための独自の例外規定が存在します。
- 商人間の確認書面(Merchant’s Confirmatory Memo):商人同士の取引において、一方が口頭合意の後にその内容を確認する書面を送り、受け取った側が10日以内に書面で異議を述べなければ、受け取った側も署名していなくても詐欺防止法の要件が満たされたとみなされます。
- 特別注文品(Specially Manufactured Goods):買主のために特別に製造され、他には容易に転売できない物品については、製造業者が製造を実質的に開始していれば、口頭契約でも有効です。
- 法廷での自白(Admission in Court):被告となる当事者が、裁判手続の過程(証言や書面など)で契約の存在を認めた場合、その認めた数量の範囲で契約は有効となります。
詐欺防止法は、契約法の世界における重要な「形式」のルールです。しかし、見てきたように、その適用は非常に技術的であり多くの例外が存在します。この法律は、詐欺を防ぐという重要な目的を持つ一方で、当事者が真摯に合意した口頭契約の履行を妨げるという硬直的な側面も持っています。そのため、裁判所は、形式的な要件と実質的な公平のバランスを取りながら、個々の事案に応じてその適用を判断しているのです。