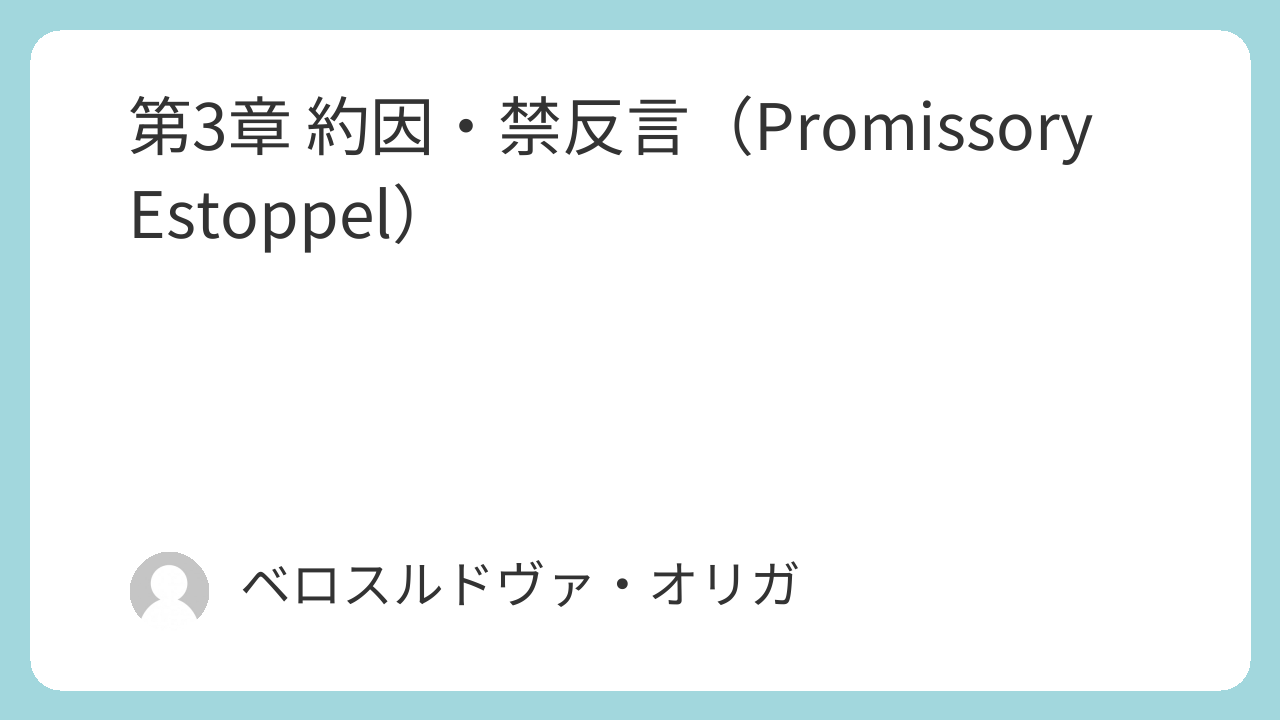前章のとおり、契約は「相互の合意」によって成立します。しかし、アメリカのコモンローの世界では、当事者が合意したというだけでは、その約束が法的に強制可能になるわけではありません。合意に加えて、「約因(Consideration)」が存在しなければならないのです。
この「約因」という概念は、日本の民法には存在しない、コモンローに特有の考え方です。それは、契約を単なる約束事から、法がその実現を後押しする重みのあるコミットメントへと引き上げるための「法的な重り」の役割を果たします。
3.1 約因(Consideration)
約因とは、一言で言えば「対価(a bargained-for exchange)」です。約束が法的に強制されるためには、その約束が一方的なものではなく、何かとの「交換」としてなされたものでなければならないという考え方です。当事者の一方が何かを約束するのは、その見返りとして相手方から何かが提供されることを求めているからであるという「ギブ・アンド・テイク」の関係性こそが、約因の本質なのです。
この考え方は、法がどのような約束を保護すべきかという問いに対する、コモンローの歴史的な答えでもあります。法が保護するのは、社会経済の基盤となる「取引」における約束であり、個人的な好意や愛情から生まれる「贈与の約束(a promise to make a gift)」ではないという、区別を明確にするための道具が「約因」なのです。
A. 約因の要件:法的な利益と不利益
伝統的に、約因は「約束者(promisor)にとっての法的な利益(legal benefit)」または「被約束者(promisee)にとっての法的な不利益(legal detriment)」として説明されてきました。
- 法的な不利益(Legal Detriment):被約束者が、法的にそうする義務がないにもかかわらず何かを行ったり、あるいは法的にそうする権利があるにもかかわらず何かを差し控えたり(不作為)すること
- 法的な利益(Legal Benefit):約束者が、法的に受け取る権利がなかったものを受け取ること
ここで重要なのは、利益や不利益が事実上のものである必要はないという点です。Hamer v. Sidway 事件では、叔父が甥に対し、21歳になるまで飲酒・喫煙・ギャンブルを慎むならば5,000ドルを支払うと約束しました。甥がこの約束を守ったにもかかわらず、叔父の遺産管理人は支払いを拒否しました。裁判所は、飲酒や喫煙を慎むことは甥自身の健康にとって「利益」であったかもしれないが、彼にはそれらを行う「法的な権利」があったと指摘。その権利を行使しなかったこと自体が、法的な不利益にあたり、叔父の約束に対する十分な約因となると判断しました。
B. 約因の核心は「取引」
現代の契約法では、単に利益や不利益が存在するだけでは不十分で、それが約束との間で「取引」されていることが決定的に重要だと考えられています。つまり、約束者は相手方の行為(作為又は不作為)を求めて約束をし、被約束者はその約束を得るために行為をするという相互の誘引関係がなければなりません。
したがって、父親が息子のこれまでの善行に感心し、「褒美として1,000ドルあげよう」と約束しても、そこには約因がありません。息子の善行は、父親の約束と「取引」されたものではないからです。これは「過去の約因(past consideration)」と呼ばれ、有効な約因とはみなされません。
3.2 約因をめぐる諸問題
約因の概念はシンプルに見えますが、実際の取引では様々な問題が生じます。
A. 対価の相当性(Adequacy of Consideration)
裁判所は、原則として、交換された対価が客観的に見て釣り合っているかどうか(相当性)を問いません。たとえ、1粒の胡椒(ペッパーコーン)と高価な馬が交換されたとしても、当事者が真剣にそれを「取引」として合意していたのであれば、約因は存在するとされます。これは「ペッパーコーン理論(peppercorn theory)」とも呼ばれ、契約自由の原則の現れです。当事者が合意した価値の判断に、裁判所は介入しないのです。
ただし、対価の不均衡が著しい場合、詐欺や強迫、不当性といった他の抗弁の評価根拠となることがあります。また、1セントと100ドルの交換のように、交換されるものが同種の通貨で価値が固定されている場合、それは真の取引ではなく、贈与の約束を偽装した「名目的な対価(nominal consideration)」とみなされ、約因として認められないことがあります。
B. 既存の法的義務のルール(Pre-Existing Legal Duty Rule)
既に法的に負っている義務を履行することを約束しても、それは新たな約因にはなりません 。例えば、建設業者が当初の契約金額で工事を完成させる義務を負っているにもかかわらず、途中で「追加で1万ドル支払ってくれなければ工事を中断する」と要求し、施主がやむなく同意したとします。この追加支払いの約束には、業者側に新たな約因がありません。業者は、元々やるべきことをやると約束したに過ぎないからです。
このルールは、一方当事者が相手方の弱みに付け込んで不当な契約変更を強要すること(経済的強迫)を防ぐ役割を果たします。しかし、予期せぬ困難な事態が発生し、当事者双方が誠実に合意の上で契約内容を変更した場合にまで、このルールを厳格に適用するのは不合理です。
そのため、いくつかの例外が認められています。
- 予期せぬ事情の発生:当事者が予測できなかった事情により履行が困難になった場合の公正な修正は、新たな約因がなくとも有効とされることがあります。
- UCCの適用:物品売買契約(UCC)では、この既存の法的義務のルールは完全に撤廃されています。当事者が誠実に合意すれば、新たな約因がなくとも契約の変更は有効です(UCC §2-209)。
C. Illusory Promise
一見すると約束のように見えても、その内容が、約束者に履行するか否かの完全な裁量を与えている場合、それは法的な拘束力を持たない「Illusory Promise(疑似約束)」とされ、約因にはなりません。「気が向いたら、あなたの車を買うことを約束する」というのが典型例です。これでは何も約束したことになりません。
しかし、裁量が無制限でない場合は、有効な約因となり得ます。例えば、requirements contract(買主が必要とする全量を購入する契約)やoutput contract(売主が生産する全量を売却する契約)では、当事者は「誠実に(in good faith)」行動する義務を負うため、その約束は幻想とはみなされません。
3.3 禁反言(Promissory Estoppel)
では、約因がない約束でも、法的に保護される場合があります。公平の観点から、約因がないにもかかわらず、例外的に約束を強制可能とするための重要な法理が「Promissory Estoppel」です。
これは、「ある約束がなされ、約束者がその約束によって相手方が行動を起こすことを合理的に予期すべきであり、そして相手方が実際にその約束を信頼して行動し、その結果、約束が強制されなければ不正義が生じるような状況」において、その約束に拘束力を持たせるという考え方です。約因が「取引」という形式を重視するのに対し、約束的禁反言は約束に対する「信頼(Reliance)」を保護するものです。日本法では約因の代替という必要性はないものの、日本で「契約締結前の過失」を債務不履行構成で考える場合と類似の状況でも用いられます。
A. 約束的禁反言の要件
この法理が適用されるためには、一般的に以下の要素が必要です 。
- 明確な約束の存在
- 約束者が、被約束者の信頼を合理的に予見可能であったこと
- 被約束者が、実際に約束を信頼して行動したこと
- 約束を強制しなければ、不正義を避けることができないこと
B. 約束的禁反言の適用場面
約束的禁反言は、様々な状況で約因の欠如を補います。
- 家族間の贈与の約束:祖父が孫娘に「仕事をやめたら2,000ドルあげよう」と約束し、孫娘がそれを信じて退職した場合、たとえ贈与の約束であっても、孫娘の信頼を保護するために約束が強制されることがあります (Ricketts v. Scothorn 事件)。
- 慈善団体への寄付の約束:多くの裁判所は、慈善団体が寄付の約束を信頼して事業計画を進めることを理由に、約束的禁反言を適用して寄付の約束を強制可能としています。
- 契約交渉段階での約束:正式な契約締結には至らなかったものの、交渉段階でなされた約束を相手方が信頼して多額の投資を行ったような場合に、その信頼を保護するために適用されることがあります (Hoffman v. Red Owl Stores, Inc.事件)。
C. 救済の範囲
約束的禁反言に基づく救済は、必ずしも約束された内容の完全な履行(期待利益)を意味するとは限りません。裁判所は「正義が必要とする限りにおいて(as justice requires)」救済を限定することができます。多くの場合、約束を信頼したことで被った損害(信頼利益)、例えば支出した費用などの賠償に限定されます。
このように、アメリカ契約法は、「約因」という厳格な形式的要件を契約成立の原則としつつも、「約束的禁反言」という柔軟な法理を用意することで、形式的な正義と実質的な公平のバランスを取っているのです。