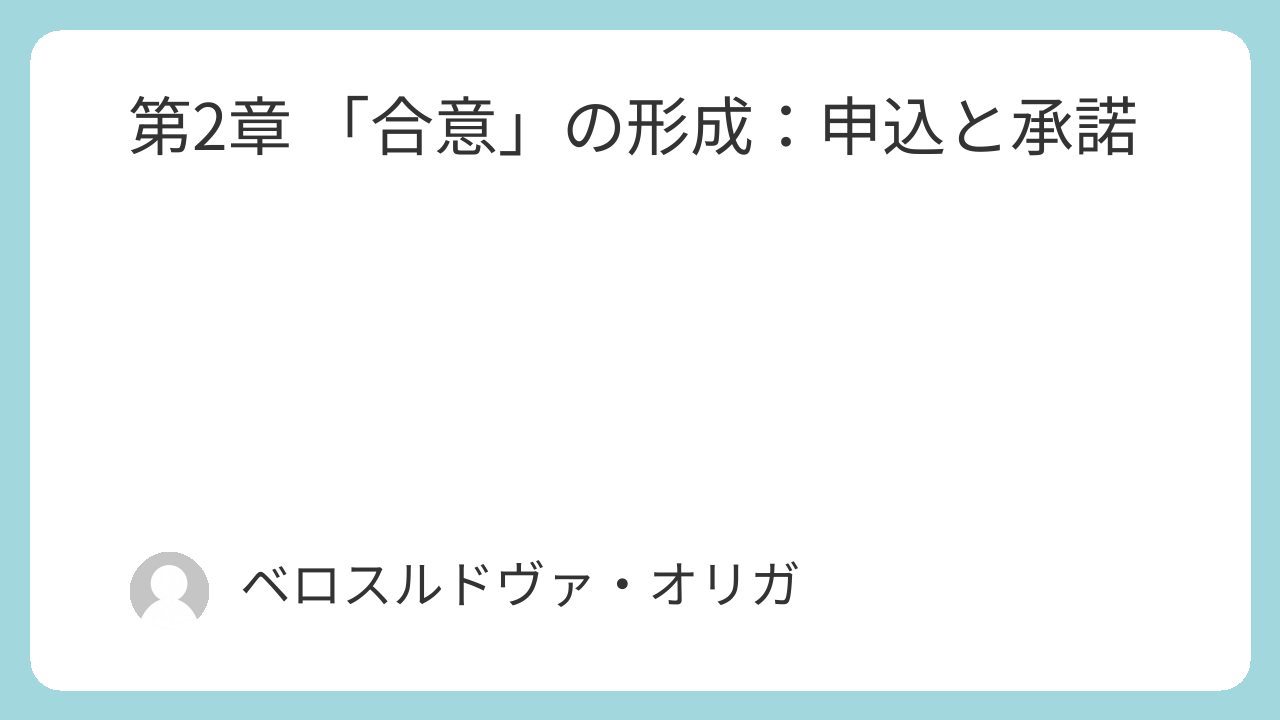契約が成立するための第1の要件は、当事者間に「相互の合意(Mutual Assent)」が存在することです。これは、当事者双方が同じ内容の取引に拘束される意思を持っている状態を指します。この合意は、通常、「申込(Offer)」と「承諾(Acceptance)」という2つのステップを通じて形成されます。
2.1 契約成立の客観的基準
アメリカ契約法は「客観理論(Objective Theory)」を採用しています。これは、契約が成立したかどうかを判断する際に、当事者が内心で何を考えていたか(主観的な意思)ではなく、その言動が合理的な第三者(a reasonable person)の目から見てどのように映るか(客観的な表示)を基準にするという考え方です。
かつては「内心の合致(meeting of the minds)」という言葉が使われましたが、これは誤解を招きやすい表現です。裁判所は当事者の心の中を覗くことはできません。したがって、ある人が「冗談のつもりだった」と内心で思っていても、その言動が客観的に見て真剣な契約の申込みだと合理的に解釈されるならば、法的には有効な申込として扱われます。有名な Lucy v. Zehmer 事件では、酒席で農場の売却契約書に署名した売主が「冗談だった」と主張しましたが、契約書作成の経緯や内容から、買主が真剣な取引だと信じたことは合理的であるとして、契約の成立が認められました。
この客観理論から導かれる重要な帰結として、「契約書を読む義務(duty to read)」があります。原則として、内容を読んでいなかったり理解していなかったりしても、署名した者はその契約内容に拘束されます。詐欺や強迫といった特殊な事情がない限り、「知らなかった」という言い訳は通用しません。
2.2 申込(Offer)
申込とは、「相手方がそれに同意すれば(承諾すれば)直ちに契約が成立する」という最終的な意思を相手方に示す、明確で具体的な提案のことです。申込がなされると、相手方(被申込者)は契約を成立させる力、すなわち「承諾する権能(power of acceptance)」を持つことになります。
A. 申込の要件
申込とみなされるためには、以下の要素が必要です。
- 拘束される意思の表示:単なる希望や意向ではなく、「この条件で契約を結びたい」という明確な拘束意思が示されている必要があります。文言が明確でない場合、それは申込とは見なされません。例えば、「私の車を2万ドルで売りたいと考えている」というのは単なる意向表明ですが、「私の車をあなたに2万ドルで売ります」というのは拘束意思の表示、すなわち申込です。
- 具体的で確定的な内容:誰が・誰に対して・何を・いくらで、といった契約の主要な条件が十分に具体的でなければなりません。条件が曖昧すぎると、裁判所は何についての合意がなされたのかを判断できず、救済を与えることができません。
- 相手方に承諾を求める:その提案が、相手方の同意によって最終的な合意が成立することを意図していることが必要です。
B. 申込ではないもの:予備的交渉
契約交渉の過程で行われるコミュニケーションの多くは、法的な申込にはあたりません。これらは契約前の交渉(preliminary negotiations)や申込の誘引(invitation to make an offer)と呼ばれます。
- 広告・カタログ・価格表:これらは一般に、不特定多数に向けられた情報提供であり、申込とはみなされません。もし広告が申込だとすると、在庫以上の注文が殺到した場合、企業は全ての注文に応じる義務を負うことになり不合理だからです。
- 例外:しかし、広告の内容が「先着1名様、この毛皮のコートを1ドルで!」(Lefkowitz v. Great Minneapolis Surplus Store 事件)のように、非常に明確かつ具体的で、相手方を限定している場合は、例外的に申込とみなされることがあります。
- 価格の見積り(Price Quotations):単に価格を提示するだけでは、通常は申込になりません 。しかし、「即時のお返事をいただければ、この価格で提供します」といった文言が付されている場合など、文脈によっては申込と解釈されることもあります。
C. 申込の効力の消滅
一度なされた申込も、永遠に有効なわけではありません。以下のいずれかの事由によって、承諾の権能は消滅します。
- 時の経過(Lapse of Time):申込に有効期間が定められている場合はその期間の満了、定めがない場合は「合理的な期間(a reasonable time)」の経過によって、申込は効力を失います。対面や電話での会話における申込は、その会話が終了すれば効力を失うのが通常です。
- 申込者による撤回(Revocation):申込者は、相手方が承諾する前であれば原則としていつでも自由に申込を撤回できます。撤回は、相手方に到達した時点で有効となります。
- 被申込者による拒絶(Rejection):被申込者が申込を拒絶する意思表示をすれば、その時点で申込は効力を失います。一度拒絶した後に考え直して承諾しようとしても、それによって契約が有効にはなりません。
- 反対申込(Counteroffer):被申込者が、元の申込の条件を変更するような応答をした場合、それは元の申込に対する拒絶であると同時に、新たな申込すなわち反対申込となります。例えば、「あなたの車を2万ドルで買う」という申込に対し、「1万8000ドルなら買う」と応答するのがこれにあたります。これにより、元の申込は効力を失い今度は元の申込者が反対申込を承諾するかどうかの立場になります。
- 当事者の死亡・無能力:承諾前に申込者又は被申込者が死亡するか、法的な能力を失った場合、申込は自動的に効力を失います。
2.3 承諾(Acceptance)
承諾とは、被申込者が申込の内容に同意し、契約を成立させる意思を表示することです。承諾によって、当事者間の相互の合意が完成します。
A. 承諾の要件
- 無条件かつ明確であること:承諾は、申込の内容を完全に受け入れるものでなければなりません。条件を付け加えたり変更を加えたりする応答は、前述の通り反対申込となり、承諾にはなりません。
- 申込によって指定された方法で行うこと:申込者が「書面でのみ承諾を受け付ける」など、承諾の方法を指定した場合、原則としてその方法に従わなければなりません。
- 申込が有効な期間内に行うこと:申込の効力が消滅した後の承諾は無効です。
B. 承諾の時期:メールボックス・ルール
承諾の意思表示がいつ有効になるかについては、「発信主義」が採用され、「メールボックス・ルール(mailbox rule)」とも呼ばれます。これは、郵便のような時間差のある通信手段を用いる場合、承諾の意思表示は、相手方に到達した時ではなく、被申込者がそれを発送した時点(ポストに投函した時点)で有効になるというルールです。
例えば、申込者が手紙で申込を撤回し、被申込者が手紙で承諾した場合、被申込者が承諾の手紙をポストに投函したのが、撤回の手紙が被申込者に届くよりも早ければ、契約は有効に成立します。このルールは、被申込者が承諾を発信した時点で契約が成立するという確実性を与え、取引の安定を図ることを目的としています。ただし、このルールはあくまで原則であり、申込者が「承諾は到達をもって有効とする」と指定した場合は適用されません。
C. 鏡像の原則とUCC §2-207「Battle of the Forms」
コモンローでは、承諾は申込と寸分違わぬ内容でなければならないという「Mirror Image Rule」が厳格に適用されてきました。少しでも内容が異なれば、それは反対申込とみなされました。
しかし、企業間の物品売買取引では、買主が自社の注文書(Purchase Order)を送り、売主が自社の請書(Acknowledgment Form)を返すという形で契約が交わされるのが通常です。これらの定型書式には、裏面にそれぞれ自社に有利な細かい条件(保証の否認、紛争解決方法など)が印刷されていることが多く、両者の内容が完全に一致することは稀です。
もし鏡像の原則を厳格に適用すると、ほとんどの取引で契約が成立しないか、又は、最後に書類を送った側の条件が一方的に通る(ラストショット・ルール)という不都合が生じます。
そこで、統一商事法典(UCC)§2-207は、この問題を解決するために、この原則を大幅に修正しました。これは「Battle of the Forms」と呼ばれる非常に重要な規定です。その骨子は以下の通りです。
- 契約の成立:たとえ請書に追加・異なる条項が含まれていても、それが明確な承諾の意思表示である限り、契約は成立する。
- 追加条項の扱い:
- 当事者の一方が商人でない場合、追加条項は単なる「修正の提案」にとどまる。
- 当事者双方が商人である場合、追加条項は原則として契約内容の一部となる。ただし、以下の場合は除く。
- 元の申込が、承諾をその条項に限定している場合
- 追加条項が契約内容を「実質的に変更(materially alter)」する場合(保証の否認など)
- 申込者が追加条項に対して既に異議を唱えているか、合理的な期間内に異議を唱えた場合
- 異なる(矛盾する)条項の扱い:多くの裁判所は、両者の書式で矛盾する条項は互いに打ち消し合い(ノックアウト・ルール)、その部分はUCCの補充規定(ギャップフィラー)によって埋められる、という立場をとっています。
UCC §2-207は、当事者が主要な取引条件(品物、数量、価格など)について合意している以上、契約の成立そのものを認めつつ、定型書式の裏面に潜む不意打ち的な条項からは当事者を保護しようとするルールなのです。
次の章では、「合意」と並ぶもうひとつの契約成立要件である「約因」について解説します。