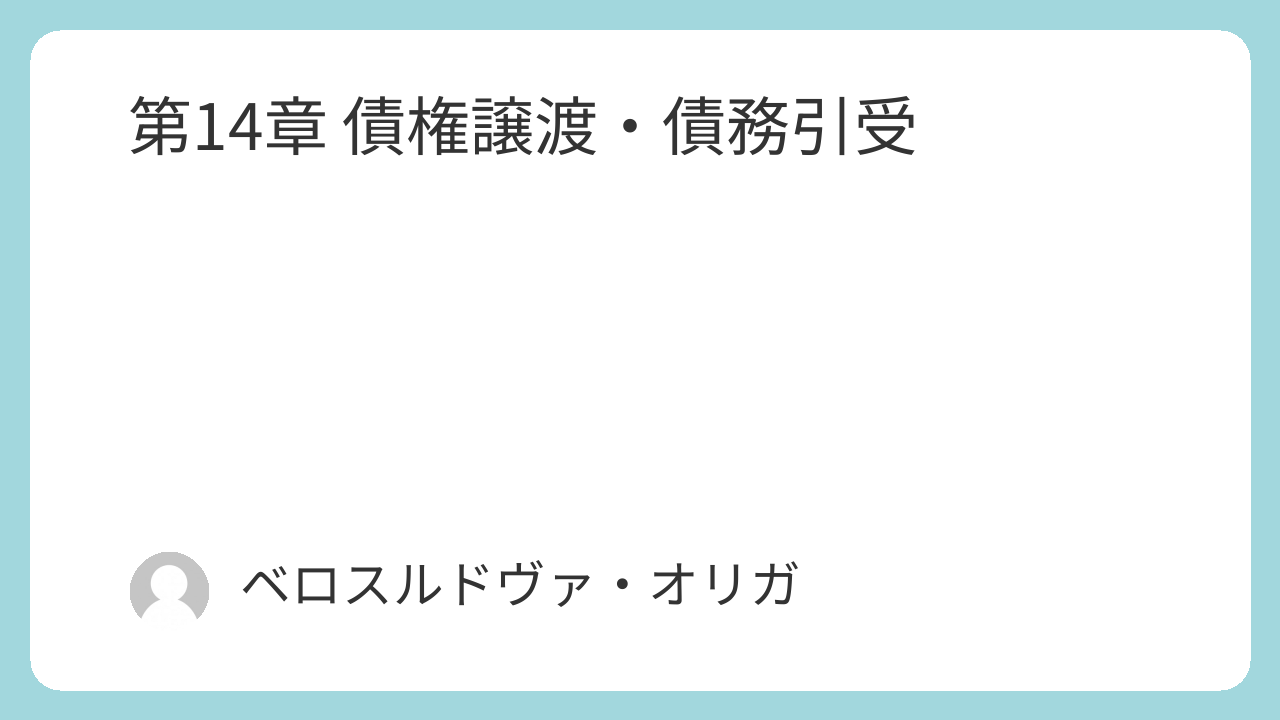前章までは、契約を締結した当初の当事者間の権利と義務を中心に見てきました。しかし、契約から生じる権利や義務は、常に当事者だけのものとは限りません。ビジネスの世界では、契約上の権利を資金調達のために金融機関に売却したり、業務の一部を専門の業者に委託したりと、権利や義務が第三者に移転する場面が頻繁に発生します。
このように、契約成立後に、当事者の一方がその契約上の地位を第三者に移転させる法技術が、「譲渡(Assignment)」と「委任(Delegation)」です。これらは、第三者のためにする契約が契約成立時に第三者の権利を創設するのとは異なり、契約成立後に第三者を契約関係に引き入れる点で区別されます。
14.1 「権利の譲渡」と「義務の委任」の区別
まず、この2つの概念を正確に理解することが不可欠です。これらは契約書で単に “assignment” という言葉で一括りにされたりしますが、法的な性質と効果は全く異なります。
A. 権利の譲渡(Assignment of Rights / 債権譲渡)
権利の譲渡とは、契約当事者の一方(譲渡人 / assignor)が、契約に基づいて相手方(債務者 / obligor)に対して有している権利(典型的には金銭の支払請求権)を、第三者(譲受人 / assignee)に完全に移転させることです。
- 例:建設業者のA社が、施主Bとの間で請負代金1,000万円の建設契約を結んだとします。A社がこの1,000万円を受け取る権利を、資金繰りのためにC銀行に売却した場合、これが権利の譲渡です。
- 効果:有効な譲渡がなされると、元の権利者(A社)の権利は消滅し、譲受人(C銀行)が新たな権利者となります。したがって、施主Bは、譲渡の通知を受けた後は、A社ではなくC銀行に対して代金を支払う義務を負います。
B. 義務の委任(Delegation of Duties / 債務引受)
義務の委任とは、契約当事者の一方(委任者 / delegator)が、契約に基づいて相手方(債権者 / obligee)に対して負っている義務の履行を第三者(受任者 / delegate)に引き受けさせることです。
- 例:先の建設契約で、A社が、契約上の義務である「家の建設」という作業の一部(例えば、電気工事)を、専門業者であるD社に行わせる場合、これが義務の委任です。
- 効果:義務の委任が行われても、極めて重要な点として、元の義務者(A社)は契約責任から免れるわけではありません。もし受任者(D社)が工事を怠ったり、欠陥のある工事をしたりした場合、施主Bは依然としてA社に対して契約違反の責任を追及することができます。
C. 譲渡と委任の組み合わせ
実際の取引では、権利の譲渡と義務の委任が一体となって行われることがよくあります。契約書で単に「本契約を譲渡する」と記載されている場合、それは通常、その契約から生じる権利と義務の双方を移転させることを意味すると解釈されます。企業の合併や事業譲渡の際には、このような包括的な地位の移転がなされます。
14.2 債権譲渡
契約上の権利は財産の一種とみなされ、原則として自由に譲渡可能です。この譲渡自由の原則は、債権の流動性を高め、経済活動を促進する上で重要な役割を果たしています。しかし、この原則にはいくつかの重要な例外があります。
A. 譲渡が禁止・制限される場合
- 譲渡によって債務者(obligor)の義務が実質的に変更される場合
権利者が誰であるかによって、債務者が負う義務の内容やリスクが大きく変わってしまうような権利は、譲渡できません。- 例:A社の「要求(requirements)」に応じて製品を供給する契約における、A社の製品購入権。もしA社がこの権利を、はるかに大規模な需要を持つ大企業Z社に譲渡した場合、売主の供給義務は予期せず増大してしまいます。このような場合、譲渡は無効とされます。
- これに対し、単純な金銭支払請求権の譲渡は、通常、債務者の義務を実質的に変更しないため、自由に譲渡できます。
- 公序良俗(Public Policy)による制限
不法行為(交通事故など)に基づく損害賠償請求権や、将来の賃金債権の譲渡は、訴訟の濫発や労働者の生活保護といった公序上の理由から、多くの州で法律により禁止または厳しく制限されています。 - 契約による譲渡禁止特約
契約当事者は、契約書の中に「本契約に基づく権利は譲渡できない」という譲渡禁止特約を設けることができます。- コモンロー:伝統的に、このような特約は有効とされてきました。
- UCCによる変革:しかし、UCCは債権の流動化を促進するため、このルールを大きく変更しました。金銭支払請求権(an account)の譲渡を禁じる特約は、原則として無効であると定めています(UCC §9-406(d))。これにより、売掛債権などを担保とした資金調達(ファクタリングなど)が容易になっています。
14.3 債務引受
権利の譲渡に比べて、義務の委任が認められる範囲は限定的です。なぜなら、債権者(obligee)は、契約相手の特定の技能・評判・信頼性などを当てにして契約を結んでいることが多いからです。
A. 委任が禁止・制限される場合
原則として、義務の履行者が誰であるかが債権者にとって重要でない非個人的な義務は、自由に委任できます。単純な金銭の支払いや、規格化された物品の納入などがこれにあたります。
これに対し、以下の義務は、相手方の同意がない限り委任できません。
- 義務が個人的な性質を持つ場合
その義務の履行が、委任者の個人的な技能・判断・信頼関係に大きく依存している場合、その義務は委任できません。- 例:有名な建築家との設計契約、特定の弁護士との委任契約、人気歌手との出演契約等。債権者は、その「特定の人」による履行を期待しているのであり、他の誰かによる履行を受け入れる義務はありません。
- 契約による委任禁止特約
権利の譲渡禁止特約とは異なり、義務の委任を禁じる特約は、一般的に有効と解釈されます。
B. 委任の効果:元の債務者は免責されない
前述の通り、義務を有効に委任したとしても、委任者(delegator)は契約上の責任から免れません。受任者(delegate)が履行を怠れば、委任者が最終的な責任を負います(日本法における併存的債務引受)。
委任者が完全に免責されるためには、債権者(obligee)を含めた三者間で、元の債務者を免責し、受任者が新たな債務者となることに合意する「更改(Novation)」という、全く新しい契約を締結する必要があります(日本法における免責的債務引受)。
14.4 譲渡・委任後の当事者関係
権利譲渡や義務委任が行われると、三者間の法律関係は複雑になります。
A. 抗弁の承継(譲受人 vs. 債務者)
権利の譲受人(assignee)が債務者(obligor)に履行を求めたとき、債務者はどのような反論ができるのでしょうか。大原則は、「譲受人は譲渡人の地位に立つ(The assignee stands in the shoes of the assignor.)」というものです。
これは、債務者が、元の権利者である譲渡人に対して主張できたであろう抗弁(例えば、製品の欠陥、詐欺、履行不能など)のほとんどを、譲受人に対しても主張できることを意味します。譲受人は、元の契約に内在するリスクごと権利を譲り受けるのです。
- 例外:抗弁権放棄条項と善意の証券所持人
この原則には、商業取引を円滑にするための重要な例外があります。契約書に、買主が「譲受人に対しては、売主に対する抗弁を主張しない」という抗弁権放棄条項(waiver-of-defense clause)が含まれている場合や支払いが約束手形(promissory note)のような流通証券(negotiable instrument)でなされ、それを譲り受けた者が善意の証券所持人(holder in due course)の要件を満たす場合、譲受人は元の契約から生じる抗弁(製品の欠陥など)に拘束されずに支払いを請求することができます。 - 消費者保護:ただし、このような例外は消費者取引において濫用される危険があるため、連邦取引委員会(FTC)の規則(FTCホルダー・ルール)により、消費者信用契約においてはいかなる譲受人も消費者が売主に対して主張できる抗弁に従わなければならないと定められています。
B. 第三受益者としての権利(債権者 vs. 受任者)
義務の委任において、受任者(delegate)が委任者(delegator)に対して義務を履行することを約束した場合、その約束は元の債権者(obligee)の利益のために意図されたものとみなされます。その結果、債権者は、委任者と受任者の間の契約の第三受益者として、受任者に対して直接履行を請求する権利を得ます。
これにより、債権者は、元の契約相手である委任者と、新たに義務を引き受けた受任者の双方に対して、履行を求めることができるようになります。