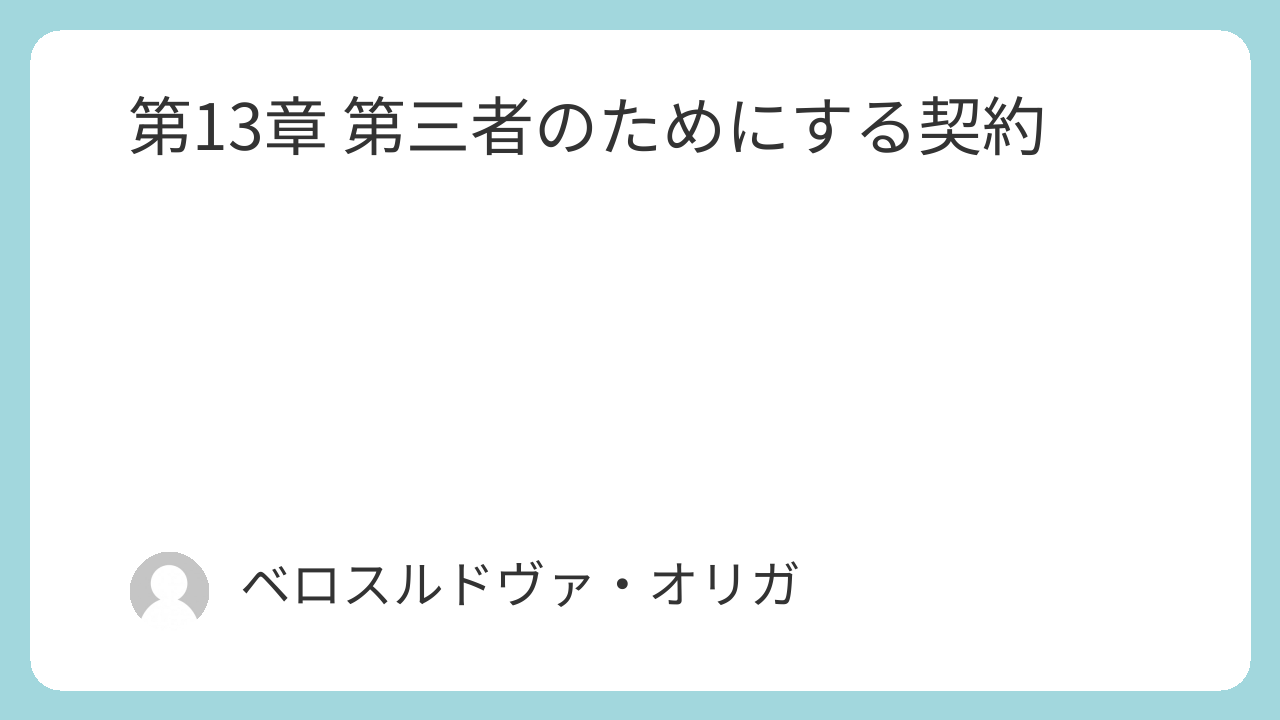契約は、原則として、それを締結した当事者間でのみ権利と義務を生じさせるものです。契約の当事者ではない第三者が、その契約に基づいて法的な権利を主張することは、伝統的に「契約関係の原則(Privity of Contract)」によって固く禁じられてきました。この原則によれば、「契約の当事者のみが、その契約に基づいて訴えることができる」のです。
しかし、現代の複雑な取引社会では、当事者双方が、契約によって意図的に第三者に利益(権利)を与えることを目的とするケースが数多く存在します。最も分かりやすい例が生命保険です。夫が保険会社と契約を結び、保険料を支払うのは、自らの死後、妻という第三者に保険金が支払われるようにするためです。もし、この妻が「契約の当事者ではない」という理由で保険金を請求できないとすれば、生命保険制度そのものが成り立ちません。
そこでアメリカ契約法は、このような現実に即応するため、「契約関係の原則」の重要な例外として、「第三受益者契約(Third-Party Beneficiary Contracts)」の法理を発展させてきました。これは、特定の条件下で、契約の当事者ではない第三者が契約上の権利を直接行使(強制執行)することを認めるものです。
13.1 第三受益者の類型:誰が権利を持つのか
すべての第三者が、契約から利益を受けるからといって、その契約を強制する権利を持つわけではありません。法が保護するのは、契約当事者がその利益を与えることを「意図した」第三者のみです。この「意図」の有無を基準に、第三受益者は大きく2つのカテゴリーに分類されます。
A. 意図された受益者(Intended Beneficiary)
契約当事者(特に、履行を受ける側である被約束者(promisee))が、契約の相手方(約束者(promisor))による履行を、第三者に直接与えることを意図している場合、その第三者は意図された受益者として契約を強制執行する権利を持ちます。
伝統的に、意図された受益者はさらに2つのタイプに分類されてきました。この分類は、現代の契約法リステイトメントでは「意図」という統一的な基準にまとめられましたが、概念を理解する上で今なお非常に有用です。
- 贈与受益者(Donee Beneficiary)
被約束者の意図が、第三者に対して贈与を行うことにある場合です。前述の生命保険契約がその典型です。被保険者(被約束者)は、保険会社(約束者)に保険料を支払う見返りに、保険金を家族(贈与受益者)に支払うことを求めます。被約束者の意図は明らかに家族への贈与です。古典的な Seaver v. Ransom 事件では、死の床にあった妻が、夫(約束者)に「私の姪に一定額の財産を渡す」と約束させ、その見返りに自らの遺言書に署名しました。この約束は、姪(贈与受益者)への贈与を目的としており、姪は夫に対して約束の履行を求める権利が認められました。 - 債権者受益者(Creditor Beneficiary)
被約束者の意図が約束者の履行によって、被約束者自身が第三者に対して負っている債務を返済することにある場合です。この法理を確立した画期的な判例が Lawrence v. Fox 事件です。ホリーはローレンスに300ドルの借金がありました。一方で、ホリーはフォックスに300ドルを貸し付け、その際、フォックス(約束者)に対して、返済は自分(ホリー)ではなく、直接ローレンス(債権者受益者)に行うよう約束させました。フォックスが支払いを怠ったため、ローレンスは契約の当事者ではないにもかかわらず、フォックスを訴えました。裁判所は、この約束がローレンスの利益のために意図されたものであるとして、ローレンスの請求権を認めました。
B. 付随的受益者(Incidental Beneficiary)
契約が履行された結果、事実として利益を受けるものの、契約当事者がその第三者に利益を与えることを主たる目的としていなかった場合、その第三者は付随的受益者と呼ばれます。付随的受益者は、契約上の権利を持たず契約の履行を強制することはできません 。
例えば、ある土地所有者が、隣接する荒廃した土地の所有者と、その土地を美しい公園として整備する契約を結んだとします。この契約が履行されれば、近隣住民の不動産価値は上昇し、大きな利益を得るでしょう。しかし、契約の主たる目的は当事者間の合意であり、近隣住民に利益を与えることは意図されていません。したがって、近隣住民は付随的受益者にすぎず、もし土地所有者が契約を履行しなくても、それを強制する権利はありません。
13.2 第三者の権利はいつ確定するのか(Vesting of Rights)
第三受益者の権利は、契約が成立した瞬間に自動的に確定し変更不能になるわけではありません。元の契約当事者(約束者と被約束者)は、第三者の権利が「確定(vest)」するまでは両者の合意によって自由に契約内容を変更したり、契約自体を解消したりすることができます。
では、権利はいつ「確定」するのでしょうか。現代の契約法リステイトメント(第2次)によれば、以下のいずれかの事象が発生した時点で第三受益者の権利は確定し、もはや当事者は一方的にその権利を奪うことはできなくなります。
- 第三者が、約束を信頼して、自らの立場を実質的に変更したとき(Material Reliance)
- 第三者が、契約上の権利を主張して訴訟を提起したとき
- 第三者が、契約当事者からの求めに応じて、その契約から利益を受けることに同意の意思表示をしたとき
生命保険契約などでは、契約書自体に「被保険者はいつでも受取人を変更できる」という条項が含まれていることが多く、その場合は権利確定のルールが契約条項によって修正されます。
13.3 第三受益者に対する抗弁
第三受益者が約束者に対して契約の履行を求めてきた場合、約束者はどのような反論(抗弁)ができるのでしょうか。
A. 約束者が被約束者に対して主張できる抗弁
原則として、約束者は、元の契約の相手方である被約束者に対して主張できたであろう抗弁のほとんどを第三受益者に対しても主張することができます。第三受益者の権利は、あくまで元の契約から派生するものだからです。
- 例1:被約束者の契約違反
生命保険契約で、被保険者(被約束者)が保険料の支払いを怠っていた場合、保険会社(約束者)は、受取人(受益者)からの保険金請求を拒否できます。 - 例2:契約の不成立・無効
元の契約自体が、約因の欠如・詐欺・強迫等を理由に無効または取消可能である場合、約束者はそのことを第三受益者に対しても主張できます。
B. 被約束者が第三受益者に対して持つ抗弁
日本法における議論と同様、少し複雑なのが、約束者が「被約束者が受益者に対して持っている抗弁」を援用できるかという問題です。これは主に債権者受益者のケースで問題となります。
例えば、AがBに1,000ドルの商品を売り、Bはその代金をAの債権者であるCに支払うことを約束したとします(Cが債権者受益者)。しかし、実はAがCに対して負っていた元の債務は、詐欺によるもので無効だったとします。この場合、BはCからの支払請求に対し、「あなたのAに対する債権は無効なのだから、私は払いません」と主張できるでしょうか。
これに対する答えは、Bが何を約束したかによります。
- もしBが「AがCに対して負っている債務を支払う」と約束したのであれば、その債務の有効性を争うことができ、Cの請求を拒否できます。
- しかし、もしBが「Cという個人に対して、Aの債務とは無関係に、1,000ドルという特定の金額を支払う」と約束したと解釈されるのであれば、BはAとCとの間の事情を抗弁として主張することはできず、Cに支払わなければなりません。