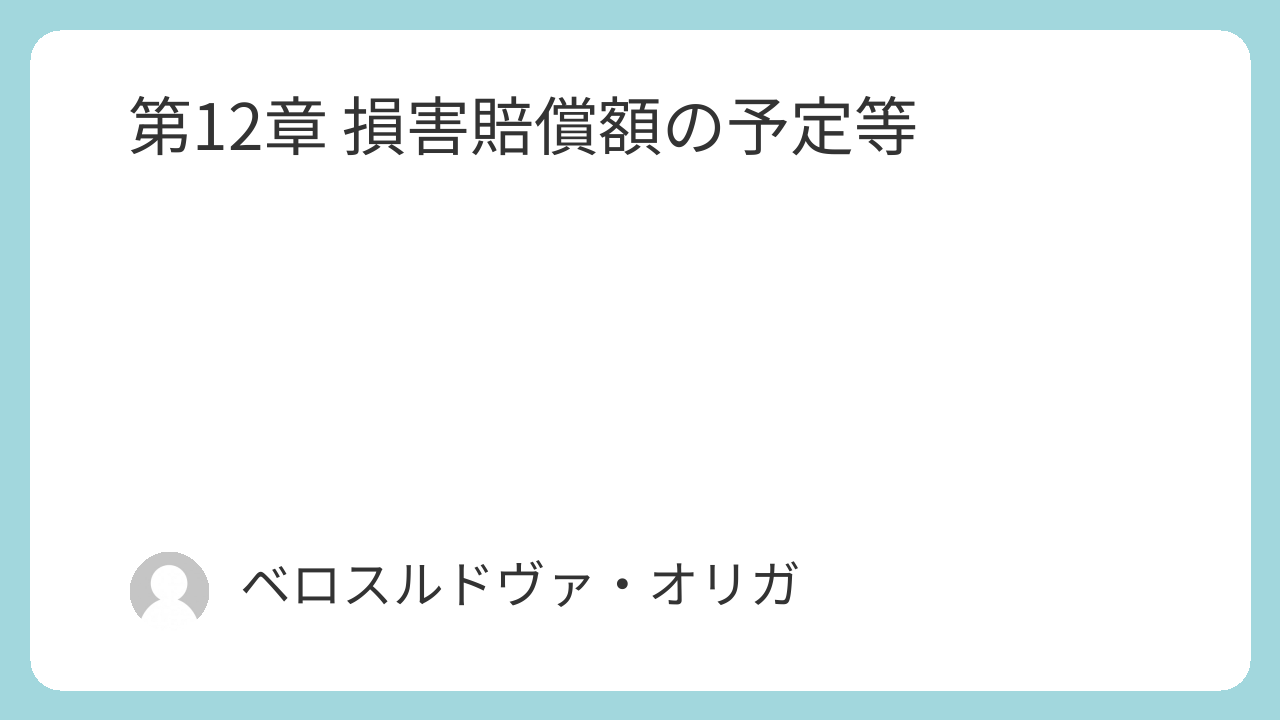将来起こりうる紛争の不確実性を減らし、ビジネス上のリスクをコントロールするために、契約書の中にあらかじめ救済方法に関する条項を盛り込むことがあります。これを「合意による救済(Agreed Remedies)」と呼びます。
当事者が自らの手で救済のルールを定めることは、契約自由の原則から、原則として有効です。しかし、その自由は無制限ではありません。特に、合意された救済が一方当事者にとって過度に過酷であったり、懲罰的な性質を帯びていたりする場合、裁判所はその効力を認めません。
この章では、合意による救済の代表的な2つの形態、①違反があった場合に支払われる金銭の額をあらかじめ定めておく「損害賠償額の予定(Liquidated Damages)」と、②利用可能な救済の種類そのものを制限する「限定的救済(Limited Remedies)」について解説します。
12.1 損害賠償額の予定(Liquidated Damages)
損害賠償額の予定とは、契約違反が生じた場合に、違反当事者が支払うべき損害賠償の金額を、契約締結時にあらかじめ定めておく条項のことです。例えば、建設契約で「工期が1日遅れるごとに1,000ドルを支払う」と定めるのが典型例です。
この条項の最大のメリットは、損害額の立証の困難さを回避し紛争の予測可能性を高めることにあります。実際の損害額を事後的に証明するのは、特に逸失利益などが絡む場合、非常に困難でコストもかかります。損害賠償額を予定しておくことで、当事者は違反時のリスクを明確に把握でき、紛争を迅速に解決することが可能になります。
A. 「有効な予定」と「無効なペナルティ」の境界線
しかし、アメリカの裁判所は、損害賠償額の予定条項を無条件に認めるわけではありません。契約法の損害賠償はあくまで補償(compensation)を目的とするものであり、懲罰(punishment)を目的としてはならないという大原則があるからです。
したがって、予定された賠償額が実際の損害を補償するための合理的な予測ではなく、単に相手方に契約遵守を強要するための見せしめ的な罰金(ペナルティ)としての性質を持つと判断された場合、その条項は公序良俗に反するものとして無効になります。
では、裁判所は「有効な損害賠償額の予定」と「無効なペナルティ」をどのように区別するのでしょうか。多くの裁判所は、以下の3つの要素を総合的に考慮して判断します。
- 契約締結時における損害予測の困難性
契約違反によって生じる実際の損害額が、契約を結んだ時点で予測することが困難であればあるほど、その条項は有効と認められやすくなります。建設プロジェクトの遅延が地域社会に与える無形の損害や新規事業の逸失利益等、金額への換算が難しい損害が典型です。逆に、損害額の計算が容易な場合には、賠償額を予定しておく必要性が低いとみなされます。 - 予定された賠償額の合理性
予定された賠償額が、契約締結時に予測された損害額又は実際に発生した損害額と比較して、合理的な金額でなければなりません。この「合理性」の判断基準時については、裁判所の立場が分かれます。- 伝統的な立場:あくまで契約締結時の予測として合理的であったか
- 現代的な立場(UCCやリステイトメントが採用):契約締結時の予測として合理的であったか、又は、実際に発生した損害額と比較して不合理な金額ではないか、という2つの時点で判断(セカンドルック・アプローチ)
- 当事者の意図
条項の文言(「liquidated damages」と書かれているか「penalty」と書かれているか)は参考にされますが、決定的ではありません。裁判所は、上記2つの客観的な要素から、当事者の真の意図が補償にあったのか、懲罰にあったのかを判断します。
12.2 限定的救済(Limited Remedies)
限定的救済とは、損害賠償の「額」ではなく、利用可能な救済の「種類」を制限する条項です。UCC §2-719がこのルールを定めており、特に製造物責任の世界で広く利用されています。
最も一般的な例は、製品保証書によく見られる「修理または交換(repair or replacement)」に救済を限定する条項です。これは、製品に欠陥があった場合、売主の責任は製品の修理または交換に限られ、買主は代金の返還や、製品が使えなかったことによる逸失利益などの結果的損害を請求することはできないとするものです。
当事者は、このような条項を通じて、製品の欠陥に関するリスクを自由に分配することができます。しかし、この自由にも限界があります。
A. 限定的救済が無効となる場合
- 救済が「排他的」である旨の明確な合意の欠如
UCC §2-719(1)(b)は、契約で定められた救済が「排他的(exclusive)」であると明確に合意されていない限りそれはあくまで任意選択的(optional)なものに過ぎない旨を定めています。つまり、「修理または交換」と書かれているだけでは、買主は依然としてUCCが定める他の救済(損害賠償など)を求めることができ、売主が救済をこれだけに限定したいのであれば、その旨を契約書に明確に記載しなければなりません。 - 救済が「その本質的目的を達しない」場合
たとえ救済が排他的であると合意されていても、その限定された救済が「その本質的目的を達しない(fail of its essential purpose)」場合には、その条項は効力を失い、買主はUCCの一般原則に基づく救済を求めることができます(UCC §2-719(2))。
典型的なのは、「レモンカー」の事案です。売主が「修理に限定する」と保証しておきながら、何度修理に出しても欠陥が治らず、買主が実質的に車を使えないような状況がこれにあたります。「修理」という救済が、買主に欠陥のない製品を提供するという本来の目的を果たしていないため、この限定は無効となります。 - 非良心性(Unconscionability)
限定的救済条項も、不当性の法理による審査を受けます。特に、UCC §2-719(3)は、消費者向け製品の欠陥によって生じた人身傷害に対する結果的損害の賠償責任を免除する条項は、不当であると推定される(prima facie unconscionable)と定めています。これは、消費者の生命・身体の安全を保護するための強力な規定です。
合意による救済は、当事者が自らの取引関係を規律するための重要なツールです。しかし、それは常に「合理性」と「公正さ」という法のフィルターを通して見られます。これらの原則を理解することは、一方的なリスクを回避し、実効性のある契約を設計する上で不可欠です。