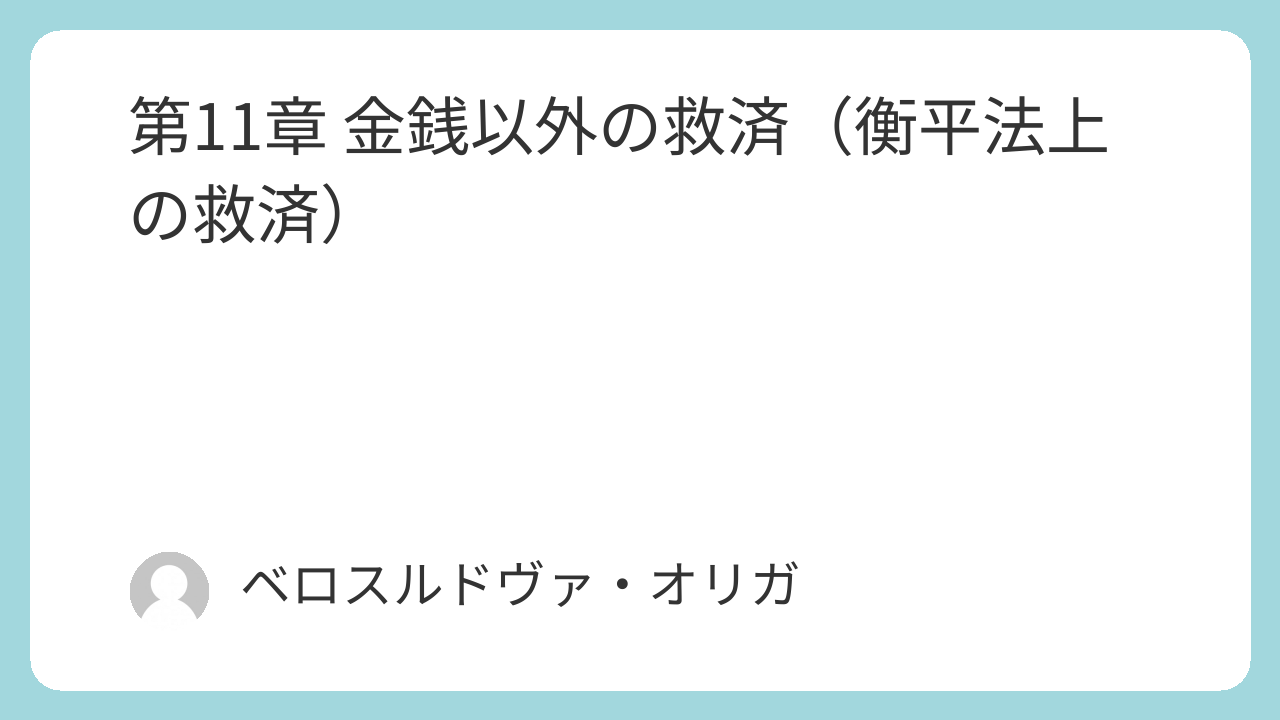世の中には、唯一無二の土地、代替の効かない特別な物品、競合他社への転職を防ぎたい場合等、金銭では埋め合わせることのできない損害が存在します。
このような状況に対応するため、アメリカ契約法は、金銭賠償とは全く異なるアプローチをとる救済手段を用意しています。それが「衡平法(Equity)」に基づく救済です。これは、歴史的にコモンロー(判例法)の裁判所とは別に存在した衡平法裁判所(Court of Chancery)が、厳格な法のルールでは実現できない「公平」や「正義」を達成するために発展させてきた、柔軟かつ裁量的な救済方法です。
この章では、衡平法上の救済の代表格である特定履行(Specific Performance)と差止命令(Injunction)を中心に、どのような場合にこれらの強力な救済が認められるのか、その根底にある思想と具体的な要件について解説します。
11.1 歴史と特徴
中世イングランドのコモンロー裁判所が提供する救済は、原則として金銭賠償のみでした。しかし、これでは正義が実現されないケースが多々ありました。そこで、国王の「良心の番人」とされた大法官(Chancellor)が、コモンローの硬直性を補う形で、個別の事案に応じて公平な裁定を下すようになったのが衡平法の始まりです。
この歴史的背景から、衡平法上の救済には以下の重要な特徴があります。
- 補充性:衡平法上の救済は、あくまで金銭賠償というコモンロー上の救済(legal remedy)が不十分(inadequate)である場合にのみ、それを補充するものとして認められます。
- 裁量性:衡平法上の救済は、当事者が権利として当然に請求できるものではなく、裁判所が諸般の事情を考慮して与えるかどうかを決定する裁量的な救済です。
- 対人的効力:衡平法上の救済は、被告個人の良心に働きかけ、特定の行為を命じたり禁じたりする対人的(in personam)な命令です。この命令に従わない場合、被告は「法廷侮辱罪(contempt of court)」として罰金や収監の対象となり得ます。
11.2 特定履行(Specific Performance)
特定履行とは、契約違反者に対し、契約で約束した通りの履行そのものを行うよう裁判所が命じる救済方法です。「金銭ではなく、約束したその物を引き渡せ」と命じる、非常に強力な救済と言えます。
A. 金銭賠償が不十分であること
特定履行が認められるための大前提は、金銭賠償では被害当事者の損害を十分に回復できない、すなわち「コモンロー上の救済が不十分」であることです。この要件が満たされるかどうかが、特定履行の可否を判断する上での最大のポイントとなります。
B. 特定履行が認められやすい契約類型
- 土地に関する契約
コモンローの世界では、土地は常に唯一無二(unique)であると考えられています。全く同じ土地は地球上に2つと存在しないため、たとえ金銭賠償を得たとしても、被害当事者は契約の目的であったその土地を手に入れることはできません。したがって、土地の売買契約において売主が履行を拒んだ場合、買主は原則として特定履行を請求することができます。 - ユニークな物品の売買契約
土地と同様に、代替品を見つけることが困難なユニークな物品の売買契約についても、特定履行が認められやすい傾向にあります。例えば、特定の芸術作品・アンティーク・家宝等がこれにあたります。
UCC(§2-716)は、この考え方をさらに推し進め、物品が厳密な意味でユニークでなくとも、市場での品不足など「その他の適切な状況(other proper circumstances)」により、買主が代替品を合理的に調達(カバー)できない場合には、特定履行を認めるとしています。
C. 特定履行が原則として認められない契約類型
- 人的役務契約(Personal Service Contracts) 裁判所は、個人に対して特定の労務やサービスの提供を強制すること(例えば、歌手に歌うことを強制したり、画家に絵を描くことを強制したりすること)を原則として行いません。その理由は主に2つあります。
- 監督の困難性:質の高いパフォーマンスが要求されるような役務について、裁判所がその履行の質を適切に監督・評価することは困難です。
- 非自発的労働の禁止:個人の意思に反して労働を強制することは、アメリカ合衆国憲法修正第13条が禁じる「非自発的苦役(involuntary servitude)」につながるという重大な懸念があります。
11.3 差止命令(Injunction)
特定履行が認められない人的役務契約であっても、衡平法は別の形で救済を提供することがあります。それが差止命令です。差止命令は、ある行為を「行うこと」を強制するのではなく、ある行為を「行わないこと」を命じるものです。
有名な Lumley v. Wagner 事件がその典型例です。オペラ歌手であるワーグナーは、ラムリーの劇場で一定期間専属で歌うことを約束すると同時に、その期間中は他のいかなる劇場でも歌わないことを約束しましたが、その後、彼女はより良い条件を提示した別の劇場で歌おうとしました。
裁判所は、ワーグナーにラムリーの劇場で歌うことを強制する「特定履行」は認めませんでした。しかし、彼女が契約期間中に「他の劇場で歌わない」という約束(消極的約束)に違反することを禁じる「差止命令」は認めました。これにより、裁判所は直接的な労働強制を避けつつも、契約の価値を実質的に保護したのです。
このように、差止命令は、特にエンターテイメントやプロスポーツの世界で、ユニークな技能を持つ個人の競合他社への移籍を防ぐために利用されることがあります。
11.4 衡平法上の救済を制限する諸原則
特定履行や差止命令は、たとえ金銭賠償が不十分であっても、常に認められるわけではありません。裁判所は、その裁量を行使するにあたり、以下のような衡平法特有の様々な要素を考慮します。
- 履行の実現可能性と監督の負担:裁判所の命令を実際に執行することが可能か、また、その履行を監督するための裁判所の負担が過大ではないか
- 契約条項の明確性:裁判所が何を命じればよいのかが分かる程度に、契約の条項が十分に明確か
- 当事者間の衡平(Hardship):救済を認めることで違反当事者が被る不利益が、認めなかった場合に被害当事者が被る不利益と比較して、著しく過酷ではないか
- クリーンハンズの原則(Unclean Hands):救済を求める当事者自身が、その取引に関して不正な行為や不誠実な行為をしていないか
- 懈怠(Laches):被害当事者が、権利を主張するのが不合理に遅れたために、違反当事者側が不利益を被るような状況になっていないか
すなわち、衡平法上の救済は、単なる機械的なルールの適用ではなく、個別の事案における具体的な妥当性や公平性を追求する、柔軟な判断となっています