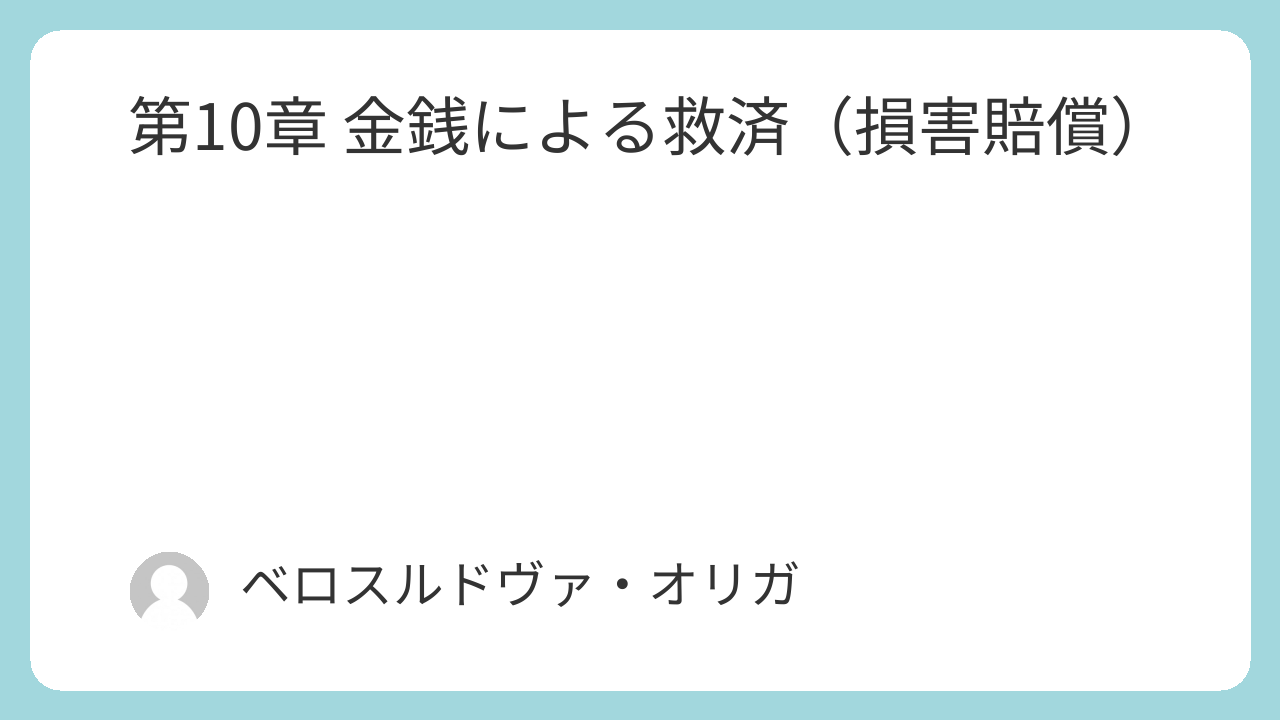アメリカ契約法における救済の基本は、金銭による損害賠償(Damages)です 。
契約違反によって生じた損害を金銭に換算し、被害当事者に支払うことで、契約が履行された場合と同等の経済的状態を実現しようとします。これは、「契約を守る義務とは、それを破った場合に損害賠償を支払う義務である」という、オリバー・ウェンデル・ホームズ判事の言葉にも表れています。
10.1 損害賠償の3つの利益
日本法と同様、損害賠償を計算するにあたり、保護されるべき当事者の利益を3つのカテゴリーに分類します。どの利益を基準にするかによって、賠償額の計算方法が大きく異なります。
A. 履行利益(Expectation Interest)
これが、契約上の損害賠償における最も重要かつ基本的な原則です。履行利益の目的は、被害当事者を「もし契約が完全に履行されていたならば、得ていたであろう経済的状態」に置くことです。言い換えれば、被害当事者に「取引から得られるはずだった利益(the benefit of its bargain)」を金銭で与えることを目指します。
例えば、ある請負業者が、10万ドルの費用をかけて家を建て、施主から11万ドルを受け取る契約を結んだとします。この請負業者の期待利益は1万ドルの儲けです。もし施主が契約に違反し、請負業者がこの取引を完了できなかった場合、期待利益に基づく損害賠償は失われた1万ドルの利益を補填するものとなります。
B. 信頼利益(Reliance Interest)
信頼利益の目的は、被害当事者を「もし契約が締結されていなかったならば、存在したであろう経済的状態」に戻すことです。つまり、契約の存在を信頼して支出した費用を賠償することで、契約前の状態に回復させることを目指します。
先の例で、請負業者が施主の契約違反までに、資材の購入や人件費として6万ドルを支出していたとします。もし、このプロジェクトから最終的にいくらの利益が出たかを証明するのが難しい場合、請負業者は少なくとも、契約を信頼して支出したこの6万ドルを信頼利益として請求することができます。
C. 不当利得の返還(Restitution Interest)
不当利得返還の目的は、契約違反当事者が、被害当事者の犠牲によって不当に得た利益を、被害当事者に取り戻させることです 。これは、違反者の利得を剥奪することに焦点を当てています 。
先の例で、施主が契約違反前に、請負業者に対して1万5000ドルの前払金を支払っていたとします。もし請負業者が全く仕事を始めずに契約に違反した場合、施主は支払った1万5000ドルを取り戻すことができます。これは、請負業者が対価を提供せずに金銭を保持し続けるという「不当利得」を防ぐためです。
これら3つの利益のうち、契約法が最も重視するのは履行利益です。なぜなら、それが「契約」という約束の価値そのものを保護するからです。信頼利益と不当利得も履行利益の計算に含まれることがありますが、期待利益の証明が難しい場合の代替的な救済策として重要な役割を果たします。
10.2 期待利益の計算と懲罰的損害賠償
期待利益に基づく損害賠償額は、一般的に以下の計算式で算出されます。
賠償額 = 履行によって得られたはずの価値 + 付随的損害 + 特別損害 – 履行しなかったことで節約できた費用
- 付随的損害(Incidental Damages):契約違反に直接付随して発生した合理的な費用。例えば、不適合品を返送するための運送費や代替品を探すための費用等です。
- 結果的損害(Consequential Damages):契約違反の結果として間接的に生じた損害。特に逸失利益(lost profits)がこれにあたります。この損害は、次に述べる「予見可能性」の原則によって厳しく制限されます。
懲罰的損害賠償の否定
ここで重要なのは、契約違反に対する損害賠償は、あくまで補償(compensation)を目的としており、懲罰(punishment)を目的としていないという点です。したがって、たとえ契約違反が悪意によるものであったとしても、原則として懲罰的損害賠償(punitive damages)は認められません。
例外的に懲罰的損害賠償が認められるのは、その契約違反行為が、詐欺や不法行為といった独立した不法行為(tort)にも該当する場合に限られます。
10.3 損害賠償額の制限
被害当事者は、契約違反によって生じたすべての損害を無制限に請求できるわけではありません。公平の観点から当事者が負うべきリスクの範囲を限定するため、日本法同様、コモンローでも損害賠償額に3つの大きな制限を課しています。
A. 予見可能性の原則(Foreseeability)
損害賠償の範囲を画定する最も重要な原則が、予見可能性です。これは、19世紀のイギリスの画期的な判例であり、日本法にも継受されているHadley v. Baxendale事件によって確立されました。
この事件は、製粉所のクランクシャフトが破損し、その修理のために運送業者に配送を依頼したところ、運送業者の遅延により製粉所の再開が遅れ多額の逸失利益が生じたという事案です。裁判所は、運送業者は単に部品を運ぶことを依頼されただけで、その遅れが製粉所全体の操業停止につながるという「特別な事情」を知らされていなかったため、逸失利益についての賠償責任はないと判断しました 。
この判例から、以下の二段階のルールが生まれました 。
- 通常損害:契約違反から「通常生ずべき(in the ordinary course of things)」損害は、当然に賠償の対象となる。これは、誰の目から見ても当然発生すると考えられる損害であり、予見可能とみなされます。
- 特別損害(結果的損害):契約違反時に存在した「特別な事情」から生じる損害は、その特別な事情を契約締結時に違反当事者が知っていたか、又は、知るべき理由があった(had reason to know)場合にのみ賠償の対象となります。
つまり、契約当事者は、契約締結時に合理的に予見できた範囲のリスクについてのみ責任を負います。もし、相手方に特別な事情があり、違反した場合に莫大な損害が発生する可能性があるならば、そのことを契約締結時に相手方に伝えておかなければ、その損害を請求することはできません。
B. 損害の確実性の原則(Certainty)
被害当事者は、賠償を求める損害の額を、合理的な確実性(reasonable certainty)をもって証明しなければなりません。損害額が完全に憶測に基づくものであってはなりません。
この原則が特に問題となるのが、逸失利益の請求です。特に、事業を開始したばかりの「新規事業(new business)」の場合、過去の実績がないため、将来得られたであろう利益を確実に証明することは非常に困難です。かつては、新規事業の逸失利益の請求はほぼ認められませんでしたが、現代の裁判所は、市場調査や専門家の分析など、合理的な根拠に基づく計算であれば、より柔軟に認める傾向にあります。
C. 損害軽減義務の原則(Mitigation of Damages)
契約に違反された当事者は、ただ手をこまねいて損害が拡大するのを見ていることは許されません。被害当事者は、損害の拡大を防ぐために、合理的な努力をする義務を負います。これを損害軽減義務と呼びます。
被害当事者は、この義務を怠った結果拡大した損害については、賠償を請求することができません。
- 例:不当解雇
不当に解雇された従業員は、次の仕事を探す合理的な努力をしなければなりません。もし、同等の条件の仕事が見つかったにもかかわらずそれを拒否した場合、得られたはずの賃金分は、元の雇用主に対する損害賠償額から差し引かれます。Parker v. Twentieth Century-Fox Film Corp. 事件では、女優シャーリー・マクレーンが、当初予定されていたミュージカル映画とは全く異なる西部劇への出演を拒否したことは、損害軽減義務違反にはあたらないと判断されました。なぜなら、その仕事は「同等(comparable)」のものではなかったからです。 - 例外:Lost Volume Seller
UCCには重要な例外があります。自動車ディーラーのように、もし契約違反がなくても別の顧客に同じ商品を販売できたであろう売主(Lost Volume Seller)の場合、たとえ違反品を別の顧客に転売できたとしても、損害軽減は認められません。なぜなら、違反がなければ「2台」売れていたはずが「1台」しか売れなかったことになり、1台分の利益をまるまる失っているからです。