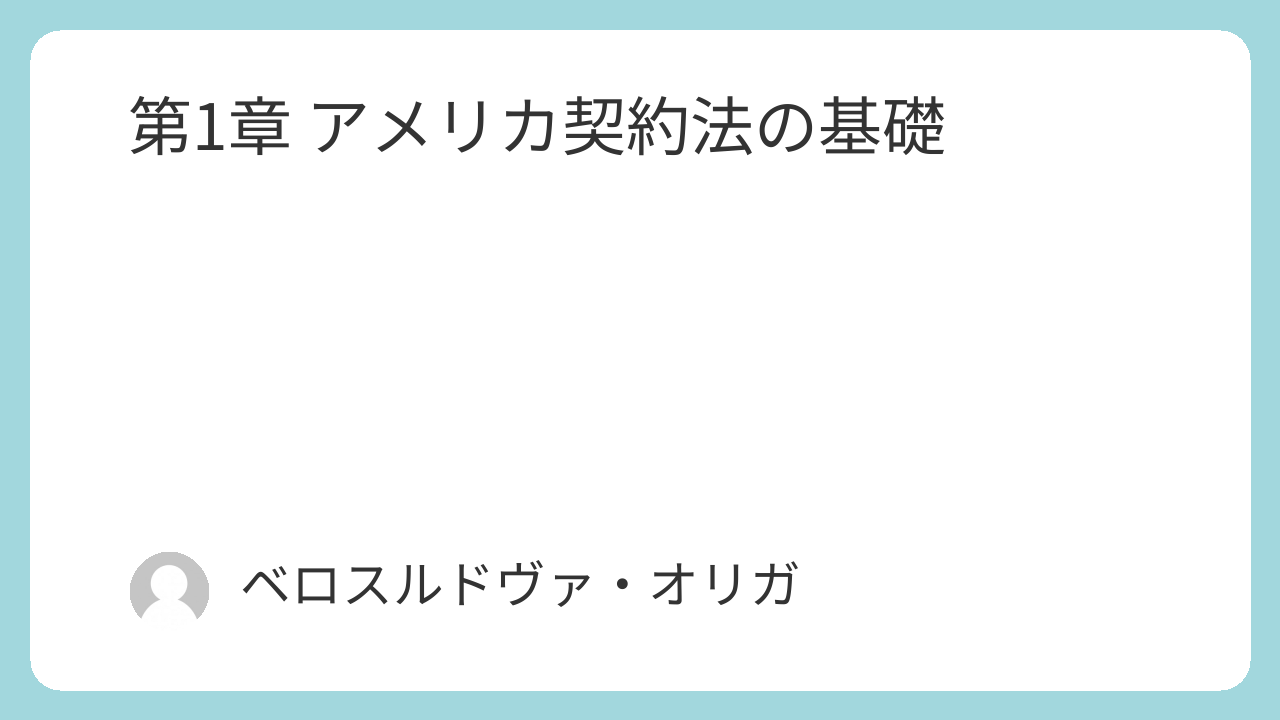1.1 契約とは何か
アメリカ契約法の核心は「法的に強制可能な約束(a legally enforceable promise)」という概念にあります。この言葉の背後には重要な意味が込められています。
第1に、契約の出発点はあくまで当事者間の「約束」であるということです。誰かに強制されたものではなく、自らの意思で特定の行為をなすこと又はなさないことを約束するところから全てが始まります。これは、個人の意思を尊重し、人々が自らの意思に基づいて法的な義務を創り出すことを可能にする「契約自由の原則(freedom of contract)」という、アメリカ契約法の基本思想を反映しています。この「自発的に義務を負う」という点は、社会によって一方的に義務が課される不法行為法(Tort Law)の世界とは対照的です。
第2に、すべての約束が法的に保護されるわけではないという点です 。友人とのランチの約束のように、日常的な約束には通常法的な強制力はありません。法が介入し救済(remedy)を与えるのは、その約束が特定の要件を満たし、「契約」の地位にまで高められた場合に限られます。約束が破られた(契約に違反した)場合に、裁判所が損害賠償を命じたり、特定の行為を強制したりといった救済策を用意しているからこそ、その約束は単なる口約束ではなく、法的な意味での「契約」となるのです。
1.2 契約の種類
アメリカ契約法では、契約を様々な角度から分類します。これらの分類は、単なる学問的な整理にとどまらず、どのルールが適用されるか、どのような救済が認められるかを判断する上で重要な意味を持ちます。
A. 明示契約と黙示契約(Express and Implied Contracts)
当事者の合意が言葉(口頭又は書面)によって明確に示されている場合、それを明示の契約(express contract)と呼びます。一方で、言葉ではなく、当事者の行動や状況から契約の成立が推測される場合、それを黙示の契約(implied contract)と呼びます。例えば、レストランでメニューを指さして注文する行為は、その料理の代金を支払うという契約が「黙示的に」成立したと解釈されます。
ここで注意すべきは、「法定契約(contract implied in law)」または準契約(quasi-contract)との違いです。これは真の契約ではなく、一方の当事者が不当に利益を得る(不当利得)のを防ぐために法が公平の見地から金銭の支払いを命じる法的な擬制です。
B. 双務契約と片務契約(Bilateral and Unilateral Contracts)
契約の成立が「約束の交換」によってなされる場合、それを双務契約(bilateral contract)と呼びます。例えば、「私があなたに100ドルで自転車を売ることを約束するので、あなたは私に100ドル支払うことを約束してください」という合意がこれにあたります。当事者双方が互いに約束を交わした時点で契約が成立し、双方が義務を負います。
これに対し、一方が約束をする見返りに、相手方に対して約束ではなく「行為の完了」を求める場合、それを片務契約(unilateral contract)と呼びます。典型的な例は、「私のなくした猫を見つけてくれたら100ドル支払うことを約束します」という懸賞広告です。この場合、相手方が「猫を探します」と約束しただけでは契約は成立せず、実際に猫を見つけて連れて帰るという行為を完了した時点で初めて契約が成立し約束をした側の支払義務が発生します。
C. 要式契約と不要式契約(Formal and Informal Contracts)
歴史的には、捺印(seal)のような厳格な「方式」に従うことでのみ契約が有効とされる要式契約(formal contract)が存在しました。しかし現代では、捺印の法的効力はほとんどの州で廃止されており、契約は原則として特定の方式を必要としない不要式契約(informal contract)です。口頭であれ簡単なメモであれ正式な契約書であれ、契約の本質は当事者の合意にありその形式にはこだわりません。
D. 無効、取消可能、強制不能な契約(Void, Voidable, and Unenforceable Contracts)
- 無効な契約(void contract):そもそも法的な契約として成立していないものを指します。例えば、犯罪行為を目的とする契約は当初から無効です。
- 取消可能な契約(voidable contract):当事者に契約を取り消す権利が与えられている契約です。例えば、未成年者や詐欺の被害者が結んだ契約は、本人が望めば取り消すことができます。取り消されるまでは有効な契約として扱われます。
- 強制不能な契約(unenforceable contract):契約自体は有効に成立しているものの、詐欺防止法(後述)のような法律上の要件を満たしていないために、裁判所を通じて法的に履行を強制することができない契約を指します 。
E. 附合契約(Adhesion Contracts)
一方の当事者(通常は企業)が事前に作成した定型的な契約条項(約款)を提示し、相手方(通常は消費者)がその内容に同意するか否かの選択肢しか与えられていない契約を附合契約(adhesion contract)と呼びます。保険契約やソフトウェアの利用規約などが典型です。交渉の余地がないため、内容が著しく不公正である場合には、unconscionability(不当性)の法理によって無効とされることがあります。
F. 物品売買契約(Contracts for the Sale of Goods)
アメリカ契約法の中でも、「物品(goods)」の売買には、コモンローとは異なる特別なルールが適用されます。このルールを定めているのが統一商事法典(Uniform Commercial Code, UCC)の第2編です。「物品」とは、土地やサービスとは区別される、契約時に動かすことができる有体物全般を指します。
建設契約のように、物品の供給とサービスの提供が混在する混合契約(hybrid transaction)の場合、その契約の「主たる目的(predominant factor)」が物品の売買にあるのかサービスの提供にあるのかによって、UCCが適用されるかどうかが決まります。
1.3 アメリカ契約法の法源
アメリカ契約法のルールは、単一の法典から導き出されるわけではありません。主に以下の4つの源泉から成り立っています。
A. コモンロー(Common Law)
アメリカ契約法の最も重要な基礎は、裁判官が個々の事件の判決を通じて形成してきた判例法すなわちコモンローです。過去の判例が将来の同様の事件を拘束するという先例拘束の原則(stare decisis)に基づき、法は安定性を保ちつつ社会の変化に対応して少しずつ進化してきました。契約法の主要な原則の多くは、この判例の積み重ねから生まれています。
B. 統一商事法典(Uniform Commercial Code, UCC)
州ごとに法律が異なるアメリカにおいて、商取引の円滑化を図るために制定されたモデル法典がUCCです。特に第2編は、物品売買契約に関する包括的なルールを定めており、ほぼ全米の州で採択されています。UCCは、商人間の取引を想定した現実的なルールを多く含んでおり、コモンローの原則を修正・補完しています。
C. 契約法リステイトメント(Restatement of Contracts)
アメリカ法律協会(ALI)という権威ある法律家団体が、全米の判例法(コモンロー)を体系的に整理し、条文のような形でまとめたものがリステイトメントです。これは法律そのものではなく、裁判所を直接拘束する力はありません。しかし、その内容には権威があり、多くの裁判所が判決を下す際に参照するため、事実上法源に近い影響力を持っています。
D. 国際条約
国際的な物品売買契約については、「国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)」が重要な法源となります。アメリカも加盟しており、加盟国間の企業による物品売買には、原則としてUCCではなくCISGが適用されます 。