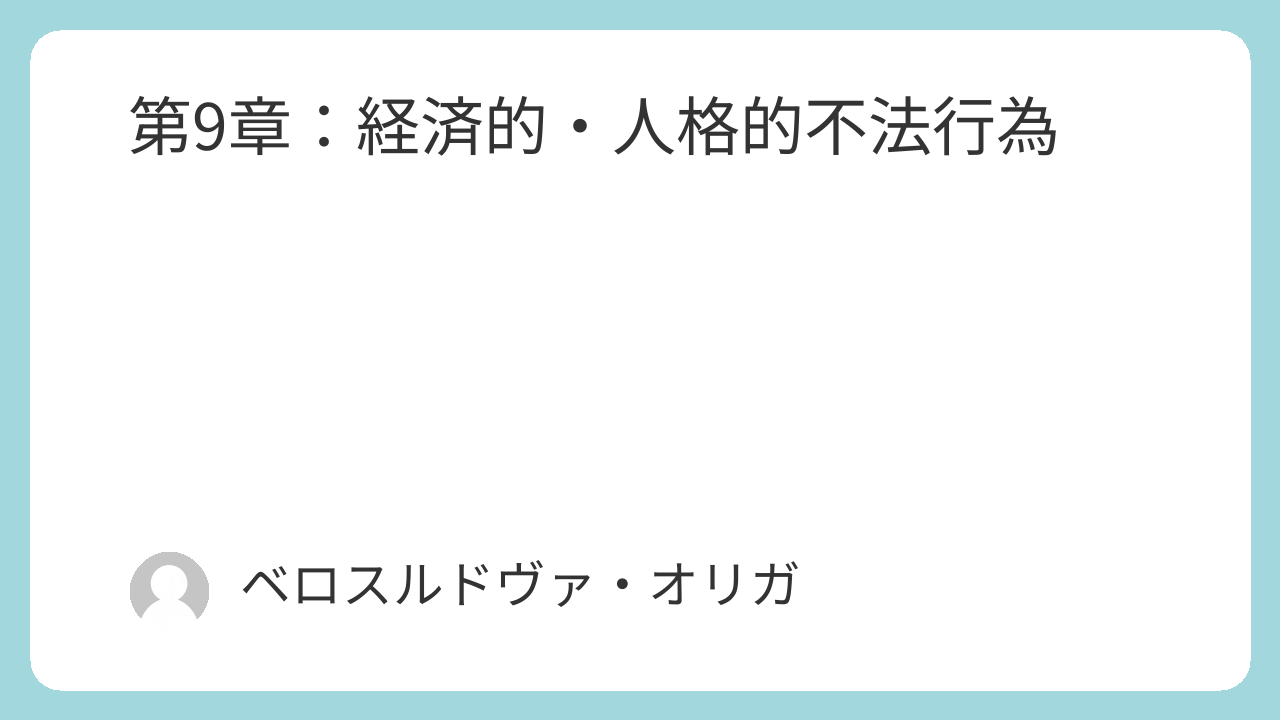不法行為法が保護する利益の範囲は、物理的な安全や財産の保全にとどまりません。人の評判、プライバシーの平穏、そして公正な経済的機会といった、社会生活を営む上で不可欠な無形の利益もまた、不当な侵害から保護されることがあります。
第1部 人格的利益の保護
第1節 名誉毀損 (Defamation)
名誉毀損とは、第三者に対して虚偽の事実を伝達(publication)し、それによって他人の評判(Reputation)を傷つける行為です。人の評判は、信用の源泉であり、社会的・経済的活動の基盤となる重要な無形資産です。名誉毀損法は、この評判という利益を保護することを目的としています。
アメリカの名誉毀損法は、1964年を境に大きくその姿を変えました。それ以前のコモンローは、長らく表現の自由よりも個人の評判を保護することに重きを置いていました。しかし、1964年の画期的な連邦最高裁判決 New York Times v. Sullivan 以降、合衆国憲法修正第1条が保障する表現の自由の観点から、特に公的な事柄に関する言論については、名誉毀損の成立が厳しく制限されるようになりました。
1. コモンローにおける名誉毀損の基本原則
憲法上の制約が加わる以前の伝統的なコモンローでは、原告は比較的容易に名誉毀損の訴えを提起できました。
- 表明の形式: 名誉毀損の表明は、口頭で行われる「口頭名誉毀損(Slander)」と、文書や出版物など、より恒久的な形で行われる「文書名誉毀損(Libel)」に区別されました。一般に、Libel の方がより深刻な損害を与えると考えられ、Slander よりも損害の証明なしに訴訟が認められやすい傾向がありました。
- 厳格責任に近い考え方: 被告が、自らの発言が虚偽であることや、他人の評判を傷つけることを認識していなくても(つまり、故意や過失がなくても)、結果として評判を傷つける虚偽の事実を公表すれば、責任を問われる可能性がありました。
- 虚偽性の証明責任: 発言が真実であること(Truth)は、被告側が証明すべき抗弁事由でした。つまり、原告は、発言が「虚偽であること」を積極的に証明する必要はありませんでした。
- 損害: Libelの場合、しばしば損害(評判低下や精神的苦痛)は「推定」され、原告は具体的な金銭的損害を証明せずとも賠償を得ることができました。
これらの原則の下では、メディアや個人は、他者について批判的な発言をする際に、常に訴訟のリスクを意識する必要がありました。
2. 名誉毀損法の憲法化:New York Times v. Sullivan
1960年代、公民権運動が激化する中で、アラバマ州モンゴメリー市の警察本部長であったサリバン氏は、ニューヨーク・タイムズ紙に掲載された意見広告が自らの名誉を毀損したとして提訴しました。アラバマ州の裁判所はコモンローに基づき、サリバン氏に巨額の賠償を命じました。
しかし、連邦最高裁判所はこの判決を覆しました。最高裁は、公務員に対する批判は、たとえその内容に一部誤りがあったとしても、健全な民主主義に不可欠な表現の自由として、憲法上、手厚く保護されなければならないと判示しました。公務員(Public Official)が、その公的活動に関する言論について名誉毀損の賠償を得るためには、単にその発言が虚偽であったことを証明するだけでは不十分であり、その発言が「現実の悪意(Actual Malice)」をもって行われたことを証明しなければならない、という新たなルールを確立しました。
「現実の悪意」とは、憎悪や敵意といった感情的な意味での「悪意」ではありません。これは法的な専門用語であり、以下のいずれかを意味します。
- 被告が、その発言が虚偽であることを知っていた(Knowledge of Falsity)
- 被告が、その発言が真実か虚偽かを無謀にも無視した(Reckless Disregard for the Truth)
この「現実の悪意」の基準は、後に公人(Public Figure)にまで拡張されました。このルールは、公的な事柄に関する自由闊達な議論を確保するため、メディアや市民が萎縮することなく発言できる場を保障することを目的としています。
3. 現代の名誉毀損法
New York Times 判決以降、名誉毀損法は、原告の地位(公人か私人か)や、発言内容の公共性によって、適用されるルールが異なる複雑な体系となりました。
- 原告が公務員・公人の場合: 上述のとおり、原告は被告の「現実の悪意」を証明しなければなりません。
- 原告が私人の場合:
- 発言内容が公的な関心事(Matter of Public Concern)の場合: 最高裁は、州が厳格責任を課すことを禁じ、少なくとも被告に過失(Negligence)があったことを原告が証明するよう要求することを最低基準としました (Gertz v. Robert Welch, Inc.)。損害の推定も認められず、実際の損害(Actual Damages)の証明が必要です。
- 発言内容が純粋に私的な事柄の場合: 憲法上の制約は緩やかになり、州はより原告に有利なコモンローのルール(損害の推定など)を適用することが許されます (Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc.)。
第2節 プライバシーの侵害 (Invasion of Privacy)
プライバシーの権利は、しばしば「一人にしておいてもらう権利(the right to be let alone)」と表現されます。名誉毀損が他者からの評価という対外的な利益を保護するのに対し、プライバシーの侵害は、個人の私的な領域や感情の平穏といった、より内面的な利益を保護します。
この不法行為は、単一の行為ではなく、性質の異なる以下の4つの類型に分類されるのが一般的です。これらの類型は、しばしば重なり合うこともありますが、それぞれ保護しようとする利益の側面が異なります。
1. 氏名・肖像の盗用 (Appropriation of Name or Likeness)
これは、他人の氏名や肖像(写真、似顔絵など)を、本人の許可なく、自己の商業的な利益のために利用する行為です。例えば、有名人の写真を無断で商品の広告に使用するケースが典型です。この不法行為が主に保護するのは、個人の氏名や肖像が持つ商業的価値(パブリシティ権と呼ばれることもあります)であり、財産権侵害に近い性質を持っています。ただし、非商業的な目的であっても、例えば慈善団体の募金活動に無断で名前を使われた場合なども、この類型に該当する可能性があります。表現の自由との関係で、芸術的表現などの場合には適用が制限されることがあります。
2. 私生活上の事実の公表 (Public Disclosure of Private Facts)
これは、他人の私生活に関する事柄で、一般の人々にとって非常識(highly offensive)と感ぜられるような内容を、正当な公共の関心事(legitimate public concern / newsworthy)でもないのに、広く公衆に暴露する行為です。
例えば、個人の医療情報、過去の犯罪歴(更生している場合)、特異な性的関係などを本人の意に反して公表するケースがこれにあたります。重要なのは、公表された事実が真実であっても責任を問われる可能性がある点です。ただし、公表された事柄が「報道の価値がある」、すなわち公共の正当な関心事であると判断される場合には、表現の自由(報道の自由)が優先され、責任は問われません。この「報道価値」の範囲をどこまで認めるかが、しばしば裁判で争点となります。公的記録に含まれる情報や、公の場で起きた出来事の報道などは、通常、保護されます。
3. 私生活への不法侵入 (Intrusion upon Seclusion)
これは、他人の私的な領域(物理的な場所や私的な事柄)に対して、一般の人々にとって非常識な方法で、意図的に侵入する行為です。盗聴器の設置、隠しカメラによる私室の撮影、郵便物や電子メールの盗み見、しつこいストーカー行為などが典型例です。
この不法行為の核心は、侵入行為そのものにあります。そのため、侵入によって得られた情報が公表されたかどうかは、責任の成立とは無関係です。個人の物理的または電子的な「一人にしておいてもらえる」空間や事柄への侵害行為自体が、不法行為となるのです。ただし、公共の場所での監視など、プライバシーの合理的な期待がない状況での行為は、通常、この類型には該当しません。
4. 誤った印象を与える描写 (False Light)
これは、他人について、公衆に著しく誤った印象(false impression)を与える情報を広く伝え、その描写が一般の人々にとって非常識(highly offensive)なものである場合に成立します。
名誉毀損と似ていますが、必ずしも評判を低下させる情報である必要はありません。例えば、ある人物の写真を、本人の思想とは全く異なる政治的・宗教的グループの記事に添えて掲載し、あたかもそのグループの信奉者であるかのような誤解を生じさせるケースがこれにあたります。情報の一部は真実かもしれませんが、文脈や省略によって全体として誤った光(false light)を当て、個人の感情や尊厳を傷つける点が問題とされます。この類型は名誉毀損と重なる部分が多く、また表現の自由との抵触も懸念されるため、州によっては認めていない場合もあります。公人・公務員が原告となる場合は、名誉毀損と同様に「現実の悪意」の証明が必要とされることがあります。
第2部 経済的利益の保護
第1節 不実表示 (Misrepresentation)
不実表示とは、虚偽の事実を表明することであり、主にビジネス上の取引関係において、相手方に経済的損失を与える典型的な不法行為です。信頼が取引の基盤である社会において、意図的な嘘や不注意な誤情報は、深刻な経済的混乱を引き起こす可能性があります。
不実表示は、表明者の精神状態(意図の有無や注意の程度)に応じて、主に3つの類型に分類されます。
1. 詐欺 (Fraud / Intentional Misrepresentation)
これは、最も悪質で非難されるべき不実表示です。詐欺が成立するためには、一般的に以下の5つの要件が必要とされます。
- 重要な事実に関する虚偽の表明 (False Statement of Fact): 単なる意見(Opinion)や誇張されたセールストーク(Puffing)ではなく、客観的に検証可能な事実に関する虚偽の表明でなければなりません。ただし、専門家による意見表明は事実表明と見なされることがあります。また、特定の状況下では、開示すべき重要な事実を意図的に隠すこと(Nondisclosure / Concealment)も、虚偽の表明と同等に扱われます。
- Scienter: 被告が、その表明が虚偽であることを知っていたか(Knowledge of Falsity)、あるいは真実か虚偽かをことさらに無視して(Reckless Disregard for the Truth)表明したことです。これは、詐欺を単なる過失と区別する、主観的な要件です。
- 原告に信頼させる意図 (Intent That the Plaintiff Rely / Intent to Induce Reliance): 被告が、原告がその虚偽の表明を信頼し、それに基づいて取引などの特定の行動をとることを意図していたことです。
- 正当な信頼(Justifiable Reliance): 原告が、実際にその虚偽の表明を信頼し、かつ、その信頼が状況に照らして正当なものであったことです。明らかに疑わしい情報や、容易に真偽を確認できたはずの情報を鵜呑みにした場合は、信頼の正当性が否定されることがあります。
- 損害の発生 (Damages): その信頼の結果として、原告が実際に経済的損害を被ったことです。損害額の算定方法には、実際に支払った額と受け取ったものの真の価値との差額(Out-of-Pocket Loss)と、もし表明が真実であったならば得られたであろう利益との差額(Benefit-of-the-Bargain Loss)があり、どちらを採用するかは州によって異なります。
2. 過失による不実表示 (Negligent Misrepresentation)
これは、詐欺のような意図はないものの、被告が合理的な注意を払うべき義務があったにもかかわらず、それを怠って不正確な情報を与え、その情報を信頼した者が経済的損失を被った場合に成立します。
この責任が認められるのは、一般的に、被告が情報を提供することを業務としている専門家(会計士、測量士、弁護士、不動産鑑定士など)や、取引の過程で相手方に対して正確な情報を提供するべき「特別な関係(Special Relationship)」にある場合に限定されます。なぜなら、不特定多数に対する無限定な責任を認めると、情報提供者の活動を過度に萎縮させてしまうからです。そのため、責任が及ぶ範囲は、被告がその情報を提供することを意図し、かつその情報が利用されることを知っていた、あるいは知るべきであった特定の相手方や、限定された範囲の第三者(例えば、会計監査報告書を信頼して融資を決定する銀行など)に限定されることが多いです(Ultramares Corp. v. Touche 事件)。
3. 善意の不実表示 (Innocent Misrepresentation)
これは、被告に詐欺の意図も過失もなく、自らも真実であると信じて虚偽の表明を行った場合です。原則として、不法行為上の損害賠償責任は生じません。しかし、契約法の領域では、このような善意の不実表示が契約の重要な要素に関わる場合、相手方は契約を取り消す(Rescission)権利を持つことがあります。損害賠償ではなく、契約をなかったことにする救済が中心となります。
第2節 契約関係への意図的干渉
この不法行為は、経済社会の基盤である契約関係の安定性を保護することを目的としています。確立された契約関係や、成立が期待されるビジネス上の関係を、第三者が不当に妨害することを禁じるものです。
1. 債権侵害 (Intentional Interference with Contract)
これは、被告が、(1)原告と第三者との間に有効な契約が存在することを知りながら、(2)意図的に、(3)不適切な手段(improper means)を用いてその第三者に契約不履行を唆すなどして、(4)契約の履行を妨害し、(5)それによって原告に損害を与える行為です。
例えば、A社が歌手Bと専属契約を結んでいることを知りながら、ライバルであるC社がBにより有利な条件を提示して引き抜き、A社との契約を破棄させたような場合が典型です(Lumley v. Gye 事件が起源)。この不法行為が成立するためには、被告の干渉行為が、単なるビジネス上の正当な競争(例えば、より良い条件を提示すること自体)の範囲を超えた、「不適切」な動機や手段(詐欺、脅迫、契約違反の教唆など)によるものである必要があります。
2. 将来的な経済関係への干渉 (Intentional Interference with Prospective Advantage / Prospective Economic Relations)
これは、まだ正式な契約には至っていないものの、原告が合理的に期待できる将来のビジネスチャンスや経済的関係(例えば、特定の顧客との継続的な取引関係や、有望な契約締結交渉など)を、被告が不適切な手段を用いて意図的に妨害する行為です。
契約への干渉よりも保護される利益(期待)が確定的でないため、責任が認められる範囲はより限定されます。被告の行為は、詐欺、脅迫、名誉毀損、営業秘密の不正利用といった、それ自体が独立して不法となりうるような、より悪質な手段を用いた場合に限定されることが多いです。単に価格競争で顧客を奪うといった、公正な競争の範囲内での行為は、たとえ原告の期待を妨げたとしても、この不法行為にはあたりません。自由競争の利益と、安定したビジネス関係への期待権とのバランスを図ることが、この法理の課題となります。