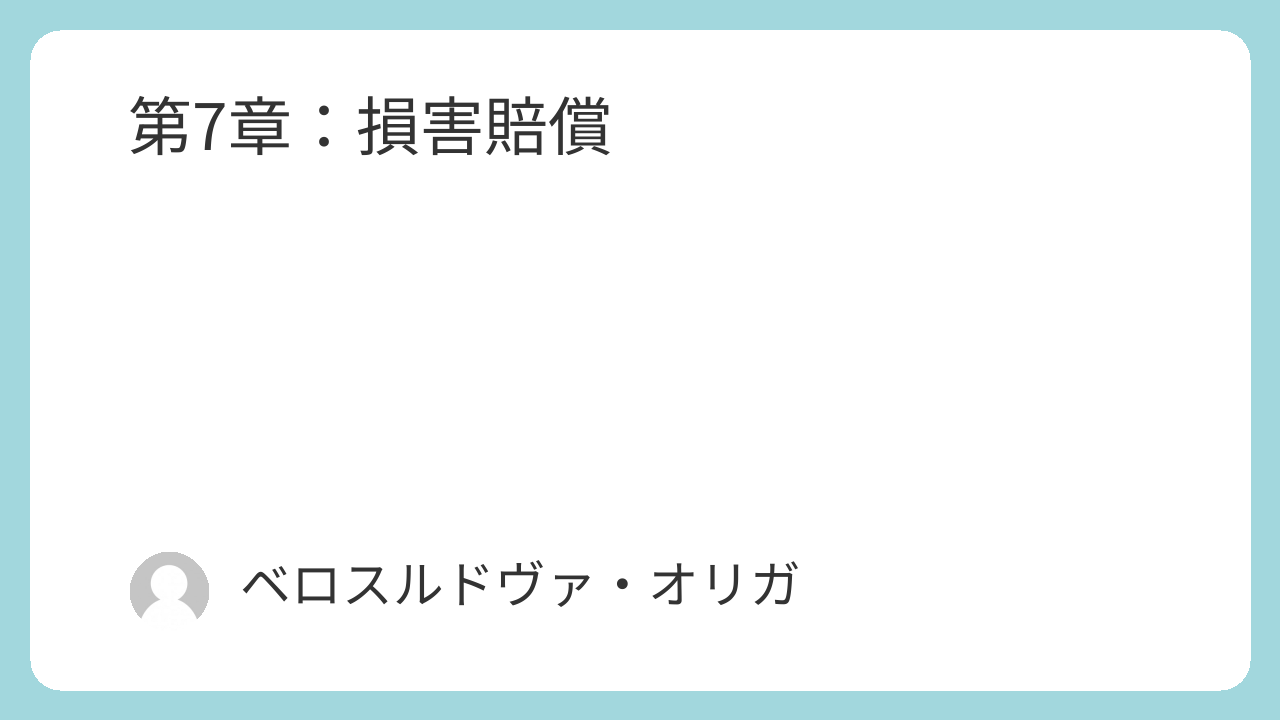アメリカの不法行為法における損害賠償制度は、主に3つの機能を果たしています。第一に、民事上の救済(Civil Recourse)の実現です。これは、被告の不法な行為によって破壊された原告との間の道徳的均衡を回復するため、原告が受けた損失を金銭的に補償することを目的とします。第二に、抑止(Deterrence)の機能です。将来の潜在的な加害者に対し、不法行為を行えばその結果生じる全てのコストを負担しなければならないと警告することで、社会全体として望ましくない危険な行為を抑制する効果を狙います。第三に、原告が受けた損失の個人的・社会的な重大さを認識し、被告の責任の重さを確認する表明的機能です。
第1節 填補賠償 (Compensatory Damages) の基本原則
填補賠償の基本原則は、不法行為訴訟で勝訴した原告を、可能な限り不法行為がなかった元の状態に回復させることにあります。これは、原告が受けた損失を金銭的に評価し、それと同等の額を被告に支払わせることで実現されます。
1. 賠償の対象となる損害の種類
身体傷害(Bodily Injury)を伴う事件における填補賠償は、大きく2つのカテゴリーに分類されます。
- Special Damages:客観的に金銭換算が可能な、具体的な経済的損失を指します。主に以下のものが含まれます。
- 治療費: 事故によって必要となった過去および将来の医療費、リハビリ費用、介護費用など。
- 逸失利益 (Lost Earnings / Lost Earning Capacity): 事故による傷害が原因で得られなくなった過去および将来の収入や、稼得能力そのものの喪失。
- General Damages:客観的な金銭換算が難しい、非経済的な無形の損害を指します。最も代表的なのが、後述する「痛みと苦しみ(Pain and Suffering)」であり、身体的・精神的苦痛、醜状(Disfigurement)、人生の楽しみの喪失(Loss of Enjoyment of Life)などがこれに含まれます。
2. 一括賠償の原則 (The Principle of a Single Recovery)
アメリカの損害賠償法における極めて重要な特徴が、「一括賠償の原則」です。これは、一度の裁判で、原告が過去に受けた損害だけでなく、将来にわたって発生すると予測される全ての損害を含めて、賠償額を一度にまとめて算定・確定するという原則です。判決が確定すれば、たとえ将来、原告の症状が予測より悪化したとしても、再び同じ不法行為を理由に訴訟を起こすことはできません。
3. 現在価値への割引 (Discounting to Present Value)
一括賠償の原則の欠点を補うための重要な仕組みが、「現在価値への割引」です。これは、将来発生する経済的損失(逸失利益や将来の治療費など)に対する賠償額を、現在の時点で一括して支払う場合、その金額を割り引いて算定するというルールです。一般的に、「痛みと苦しみ」のような非経済的損害は割引の対象とならないことが多いです。
この割引の根拠は、金銭の「時間的価値」にあります。今日受け取ったお金は、投資することで将来価値が増えるためです。したがって、将来の損失額をそのまま現在支払うと過剰補償になる可能性があります。
そこで、将来の損失額を、適切な「割引率(Discount Rate)」を用いて現在の価値に換算します。割引率とは、賠償金が将来にわたって安全に運用された場合に得られるであろう期待収益率(利子率)を逆算したものです。この割引率をどう設定するか(インフレを考慮するか否かなど)は、専門家の証言が求められる複雑な問題であり、裁判における争点のひとつとなることがあります。
第2節 痛みと苦しみ (Pain and Suffering)
「痛みと苦しみ」に対する賠償は、一般損害の中核をなし、しばしば損害賠償額の大部分を占めます。
1. 「痛みと苦しみ」賠償の機能
- 損失の承認と慰謝: 重大な傷害を負った被害者にとって、経済的損失の補填だけでは到底「原状回復」とは言えません。痛み、苦しみ、恐怖、人生の楽しみの喪失といった無形の損害に対して賠償を命じることは、法がその損失の重大さを公的に承認し、被害者に慰謝と精神的な満足(Solace)を与える機能を持っています。
- 代替的満足の提供: 賠償金が苦痛そのものを消し去ることはできませんが、被害者はその金銭を用いて、失われた人生の楽しみの「代替」となるものを手に入れることができます。例えば、事故で活動ができなくなった人が、賠償金で新たな趣味を見つけるといったことです。
- 抑止機能の完全化: 抑止の観点から見れば、加害者は自らの行為が生み出した全ての社会的コストを負担すべきです。被害者の身体的・精神的苦痛は、そのコストの紛れもない一部です。もし経済的損失しか賠償の対象とならなければ、加害者は損失の一部しか負担しないことになり、将来の危険な行為に対する抑止効果が不十分なものとなります。加害者に苦痛のコストを支払わせること自体に、抑止的な意義があります。
2. 賠償額の制限と課題
「痛みと苦しみ」の賠償には正当な機能がある一方で、その算定は本質的に主観的であり、陪審によって金額が大きく変動するという問題を抱えています。特に、高額な評決は予測可能性を損ない、企業活動を萎縮させるなどの批判があります。
この問題に対処するため、いくつかの州では立法措置が講じられています。
- 賠償額上限(キャップ)の設定: 約半数の州で、「痛みと苦しみ」の賠償額に絶対的な上限(例えば、25万ドルや50万ドルなど)を設ける法律が制定されています。これは賠償額の予測可能性を高めますが、最も深刻な傷害を負った被害者ほど、上限によって切り捨てられる割合が大きくなるという公平性の問題をはらんでいます。
- 裁判所による減額(Remittitur): 裁判所が、陪審の評決額が証拠に照らして著しく過大であると判断した場合、原告に対し、賠償額の減額を受け入れるか、さもなくば再審理を行うかを選択させる制度です。これは伝統的な手法ですが、適用されるのは極端なケースに限られます。
- 賠償額表(Schedule)の導入: 傷害の種類や重篤度に応じて賠償額の基準を定める方法も提案されていますが、複雑さから導入は進んでいません。
第3節 コラテラル・ソース・ルール
原告が不法行為によって損害を被った際、被告からの賠償とは別に、自ら加入していた健康保険や障害保険、雇用主からの給付など、第三者(副次的損害源)から給付を受けることがあります。この場合、被告が支払うべき賠償額から、これらの給付額を差し引くべきか、という問題が生じます。
これに対する伝統的なコモンローのルールが「コラテラル・ソース・ルール」です。これは、原告が受け取った第三者からの給付は、被告の賠償責任額の算定において考慮されず、被告は給付の有無にかかわらず損害の全額を支払わなければならないという原則です。その結果、一見すると原告は損害の「二重取り」をしているように見えます。
しかし、実際には、現代の保険実務における「代位(Subrogation)」の仕組みによって二重取りとはなりません。
代位(Subrogation)による解決
実際には、ほとんどの保険契約(生命保険を除く)には「代位条項」が含まれています。これは、保険会社が被保険者(原告)に保険金を支払った場合、その支払額を限度として、被保険者が加害者(被告)に対して持つ損害賠償請求権を保険会社が取得するというものです。
コラテラル・ソース・ルールと代位の仕組みが組み合わさることで、以下のような流れが実現されます。
- 原告は、まず自身の保険会社から治療費などの給付を受けます。
- 原告は、被告に対して訴訟を起こし、コラテラル・ソース・ルールに基づき、保険給付分も含めた損害の全額について勝訴判決を得ます。
- 原告が被告から賠償金を受け取ると、保険会社は代位権に基づき、原告に対して、先に支払った保険金相当額の返還を求めます。
- 結果として、原告は二重取りをせず、保険会社は支払った保険金を回収し、最終的な負担は不法行為者である被告が負うことになります。
このように、理論上は、代位によって、抑止効果を維持しつつ(被告は全額を支払う)、二重取りを防ぐ(原告は最終的に損失分しか保持しない)という、理想的な解決が可能となります。ただし、実際には、多くの事件が訴訟前の示談で解決されるため、示談金の配分をめぐって原告と保険会社の間で交渉が必要になるなど、このプロセスは常に円滑に進むわけではありません。
なお、近年では tort reform の一環として、多くの州でこの伝統的なルールを修正または廃止する法律が制定されています。これらの法律は、二重取りを防ぐことを目的としていますが、将来の保険給付の見積もりなど、適用にあたって新たな課題も生じています。
第4節 死亡事件における損害賠償
コモンローの古い原則では、不法行為の請求権は被害者の死亡と共に消滅しました。しかし、19世紀以降、全ての州でこの原則を覆す法律が制定されました。
1. Wrongful Death Actions
これは、被害者の死亡によって経済的・精神的損害を被った遺族(法定の相続人など)が、固有の権利として起こす訴訟です。これは死亡した被害者自身の請求権ではなく、遺族の新たな請求権となります。
- 賠償の対象: 遺族が受けた損害が対象となります。具体的には、被害者が生きていれば得られたであろう経済的扶養(逸失利益)、葬儀費用、そして、配偶者や子供、親を失ったことによる愛情、慰め、交友、指導の喪失といった無形の損害(Loss of Consortium)が含まれます。
- 受益者: 誰が訴訟を起こし、賠償金を受け取れるか(受益者)は、各州の法律で定められています(通常は配偶者、子、親など)。
2. Survival Actions
これは、死亡した被害者自身が、もし生きていれば主張できたであろう損害賠償請求権を、その相続人が引き継いで行う訴訟です。
- 賠償の対象: 被害者が負傷してから死亡するまでの間に受けた損害が対象となります。具体的には、その間の治療費、逸失利益、そして被害者自身が生前に感じた「痛みと苦しみ」が含まれます。
- 受益者: この訴訟で得られた賠償金は、被害者の遺産の一部となり、遺言または相続法に従って分配されます。
第5節 懲罰的損害賠償 (Punitive Damages)
懲罰的損害賠償は、填補賠償とは全く目的が異なります。その目的は、被害者の損失を補償することではなく、被告の行為が特に悪質であった場合に、被告を懲罰し、かつ将来同様の行為が行われることを抑止することです。そのため、「見せしめ的損害賠償(Exemplary Damages)」とも呼ばれます。
1. 認定の要件
懲罰的損害賠償が認められるのは、被告の行為が単なる過失にとどまらず、重過失よりもさらに悪質な場合、例えば詐欺的、悪意的、抑圧的であったり、他人の権利や安全を意図的かつ無謀に無視したりした場合に限られます。これは非常に高いハードルであり、認められるのは例外的です。
2. 機能と問題点
その機能は、填補賠償だけでは抑止効果が不十分な場合に、それを補完することにあります。例えば、被告の行為による個々の被害者の損害は小さいが、その行為が非常に儲かるため、填補賠償を支払っても事業を継続した方が得だと被告が考えるような場合です。懲罰的損害賠償は、そのような計算を成り立たなくさせる「罰金」として機能します。
一方で、懲罰的損害賠償もまた、その予測不能性と時に天文学的な金額になることから、激しい批判の対象となってきました。企業活動を不当に萎縮させ、陪審に過大な裁量権を与えている、との指摘です。
3. 懲罰的損害賠償制度の合憲性
このような批判を受け、連邦最高裁判所は1990年代以降、過大な懲罰的損害賠償は、デュー・プロセス(適正手続)を保障した合衆国憲法修正第14条に違反するとの判断を繰り返し示してきました。
最高裁は、懲罰的損害賠償額が合憲的な範囲内にあるかを判断するための3つの指標(Guideposts)を提示しています。
- 被告の行為の非難可能性の程度: 身体的危害か経済的危害か、無謀か悪意か、一回限りの行為か反復的か、などを考慮します。
- 填補賠償額と懲罰的損害賠償額の比率: 最高裁は、「1桁台の比率(single-digit ratio)」を超えることは滅多に正当化されないとの見解を示しており、事実上、懲罰的損害賠償額が填補賠償額の9倍を超えるようなケースは、違憲と判断される可能性が極めて高くなりました。
- 同種の行為に対する民事・刑事罰との比較: 法律が同種の行為に科している他の罰則の重さを考慮します。