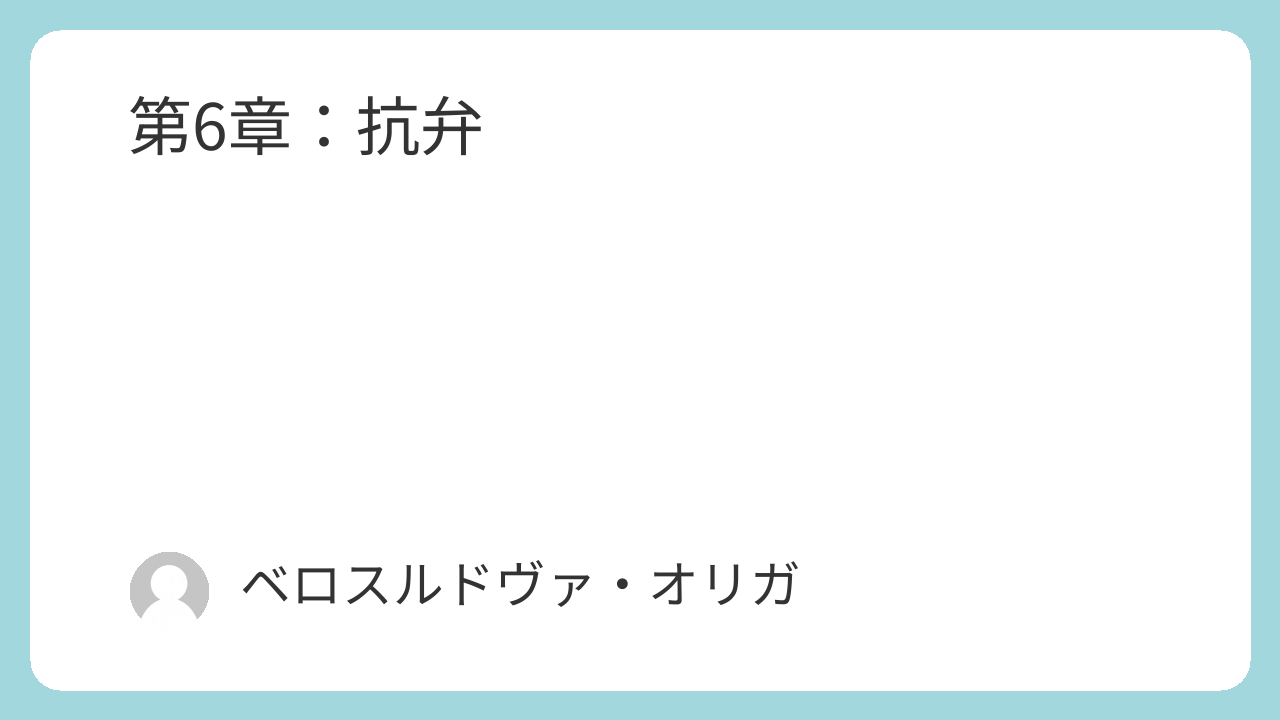本章では、原告の行動に基づく主要な抗弁について、以下の3つの法理を中心に解説します。
- Contributory Negligence:原告の過失が少しでもあれば賠償請求が完全に棄却されるというかつての原則
- Comparative Negligence:現代の主流であり、原告の過失の割合に応じて賠償額を減額する原則
- 危険の引受 (Assumption of Risk):原告が自発的にリスクを引き受けたと見なされる場合の抗弁
第1節 寄与過失 (Contributory Negligence)
1. 寄与過失の原則
19世紀初頭に過失が独立した不法行為類型として確立された後、被告のための強力な抗弁として「寄与過失」のドクトリンが発展しました。これは、原告が自身の安全に対して払うべき合理的な注意を怠り、その不注意が損害発生の一因となった場合、被告の過失の有無や程度にかかわらず、原告は一切の賠償を受けることができないという、オール・オア・ナッシングの厳格な原則でした。
例えば、被告が制限速度を20マイル超過して運転していたという場合であったとしても、原告が脇見運転をしていて衝突を避けられなかった場合、原告のそのわずかな過失が寄与過失と認定されると、原告の請求は完全に棄却されました。
この法理の根拠のひとつは、法廷における「清廉な手(clean hands)」の原則、つまり、自らにも落ち度のある者が他人を非難することは許されないという考え方にあります。
しかし、寄与過失の原則は多くの事案で著しく不公平な結果をもたらしました 。被告に明らかな過失があるにもかかわらず、原告の軽微な不注意によって全責任を免れるという結論は、多くの人々の感覚に反するものでした。そこで、裁判所は長年にわたり、この原則の過酷さを和らげるための様々な例外的な法理を編み出してきました。
2. 寄与過失の過酷さを緩和するための法理
(1) 安全法規違反の例外 (The Safety Statute Exception)
被告の過失が、自らを保護する能力のない特定の集団を保護するために制定された安全法規への違反である場合、その保護対象である原告の寄与過失は抗弁として認められないという例外です 。
例えば、スクールバスの運転手が、生徒が降車する際の安全確認を義務付けた法規に違反し、その結果、不注意に道路に飛び出した生徒が怪我をしたとします。この場合、その法規自体が生徒が常に合理的な注意を払うとは限らないことを前提に制定されているため、生徒の寄与過失を理由にバス会社の責任を免除することは、法規の目的を没却することになります。したがって、このような状況では寄与過失の抗弁は適用されません。
(2) 重過失・故意 (The Greater-Degree-of-Blame Exception)
寄与過失は、あくまで過失(Negligence)に対する抗弁です 。したがって、被告の行為が単なる過失のレベルを超え、重過失 (Gross Negligence) や 無謀な行為 (Reckless Conduct)、悪意のある故意の違法行為 (Wanton and Willful Misconduct) と評価される場合、もはや原告の単なる過失(寄与過失)は抗弁として機能しません。
被告の行為の非難の程度が、原告の不注意の程度をはるかに上回るため、両者を同列に論じることは不公平であるという考えが根底にあります。これは、ある意味で、後の比較過失の考え方の萌芽ともいえる、当事者双方の非難の程度を比較する発想でした。
(3) ラスト・クリア・チャンスの法理 (Last Clear Chance)
寄与過失の例外の中で最も有名かつ複雑なのが、「ラスト・クリア・チャンス」の法理です 。これは、原告が寄与過失によって危険な状況に陥った後でも、被告にその損害を回避するための最後の明確な機会(Last Clear Chance)があったにもかかわらず、それを怠った場合には、原告の寄与過失は免責の効果を失うというものです。
この法理の古典的な例として、Davies v. Mann という19世紀のイギリスの事件があります 。原告は、ロバの前足を縛って道路脇に放置するという過失を犯しました。その後、被告が猛スピードで馬車を走らせ、動けないロバを轢いてしまいました。裁判所は、原告に過失があったとしても、被告にはロバを避けるための最後の明確な機会があったと判断し、被告の責任を認めました。
この法理は、危険を回避する最後の機会を持っていた被告の方が、先に過失を犯した原告よりも非難の程度が高いという考えに基づいていると説明されることがあります 。しかし、この法理の適用は次第に拡大・複雑化し、「最後の機会」ではなかったり、「明確な機会」とは言えなかったりするケースにも適用されるようになりました。
第2節 比較過失 (Comparative Negligence)
1970年代以降、ほとんどの州が「比較過失」の制度を導入しました。
1. 比較過失の基本原則
日本法における過失相殺と同様、比較過失の核心は、原告に過失があったとしても、それが直ちに賠償請求の全面的棄却にはつながらず、裁判所が認定した原告の過失の割合に応じて、賠償額を減額するという点にあります 。
例えば、原告の損害額が10万ドルで、陪審が原告の過失割合を40%、被告の過失割合を60%と認定したとします。この場合、原告の損害額10万ドルから、自身の過失分である40%(4万ドル)が差し引かれ、原告は6万ドルの賠償を受けることができます 。これにより、事案の実態に即した柔軟な解決が可能となりました。
2. 比較過失の2つの主要な形態
比較過失には、主に2つの形態が存在し、どちらを採用するかは州によって異なります 。
(1) 純粋比較過失 (Pure Comparative Negligence)
純粋比較過失を採用する州では、原告の過失割合が被告の過失割合を上回っていても、賠償請求権を失いません。賠償額は、単純に自身の過失割合に応じて減額されるだけです 。
例えば、原告の過失が70%、被告の過失が30%で、損害が10万ドルだった場合、原告は3万ドル(10万ドル × 30%)を受け取ることができます。この方式は、論理的に最も一貫しており、損害の公平な分担という理念に忠実です。
(2) 修正比較過失 (Modified Comparative Negligence)
一方、多くの州で採用されているのが修正比較過失です 。この方式では、原告の過失割合が一定の閾値を超えると、寄与過失の原則が復活し、賠償請求が完全に棄却されます。この閾値には、さらに2つのバリエーションがあります。
- 50%ルール (50% Rule / “Not Greater Than” Rule):原告の過失割合が50%以下であれば、その割合に応じて賠償額が減額されますが、51%以上になると一切の賠償が受けられません 。原告と被告の過失が50%ずつと認定された場合、原告は賠償額の50%を受け取ることができます 。
- 49%ルール (49% Rule / “Not As Great As” Rule):原告の過失割合が49%以下(被告の過失割合よりも小さい)場合にのみ賠償が認められます 。もし過失割合が50%以上(被告と同等かそれ以上)になると、請求は棄却されます 。
修正比較過失は、自らの過失が損害の主要な原因である原告まで保護する必要はないという考え方に基づいています。
3. 比較過失制度が他の法理に与えた影響
比較過失の導入は、関連する他の抗弁法理にも大きな影響を与えました 。
- ラスト・クリア・チャンスの法理:この法理は、寄与過失の過酷さを緩和するためのものであったため、比較過失制度の下ではその存在意義を失いました。現在、ほとんどの州でラスト・クリア・チャンスは独立した法理としては廃止されています。ただし、被告が損害を回避する最後の機会を持っていたという事実は、陪審が過失割合を判断する上での一要素として考慮されることはあります。
- 危険の引受 (Assumption of Risk):後述するように、原告が不合理にリスクを引き受けた場合(Secondary Assumption of Risk)は、比較過失制度の下では、原告の一つの「過失」として扱われ、過失割合の算定に含められるのが一般的となっています 。
第3節 危険の引受 (Assumption of Risk)
「危険の引受」は、原告が自らの自由意思で、損害につながる可能性のある特定の危険を認識し、それを受け入れた場合に適用される抗弁です 。この法理は、しばしば寄与過失と混同されますが、概念的には異なる側面を持ちます。寄与過失が客観的な「不注意」を問題にするのに対し、リスクの引受は原告の主観的な「認識」と「自発的な選択」を中核とします。
1. 明示的なリスクの引受 (Express Assumption of Risk)
これは、原告が契約などによって、将来発生しうる特定の損害について、被告の責任を免除することを事前に明示的に合意した場合です。例えば、スポーツジムの会員契約書や、スカイダイビング参加前の免責同意書に含まれる条項がこれにあたります。
このような免責合意は、それが任意になされ、免除されるリスクの範囲が明確である限り、原則として有効です。ただし、当事者間の交渉力に著しい格差がある場合や、免責の対象となる行為が公序良俗に反する場合(例えば、医療過誤に対する事前の包括的な免責など)には、無効とされることがあります。
2. 黙示的なリスクの引受 (Implied Assumption of Risk)
原告の言動から、リスクを認識し、かつ自発的にそれを受け入れたことが黙示的に推認される場合です。これはさらに2つに区別されます。
(1) 第一次的リスクの引受 (Primary Assumption of Risk)
これは、厳密には被告の抗弁ではなく、そもそも被告が原告に対して注意義務を負っていなかった、又は、義務違反がなかったという、原告の訴訟要件の不充足を指す概念です 。
最も典型的な例が、野球観戦中にファウルボールが当たって観客が怪我をした場合です。野球というスポーツには、打球が観客席に飛び込むという内在的なリスクが伴います。今はMLBの球場でもネットを張る範囲が広くなりましたが、かつて、球場所有者には、バックネット裏など一定の危険なエリアに防護ネットを設置する義務はある一方で、球場全体の全ての座席をネットで覆うまでの義務はないと一般的に考えられていました。今でも、外野席にはネットが張られていません。観客は、その内在的リスクを承知の上で観戦に来ていると見なされています。したがって、球場所有者は観客に対する注意義務に違反しておらず、責任を負いません 。原告がリスクを引き受けたから免責されるのではなく、被告にそもそも法的義務違反がないという構成です。
(2) 第二次的リスクの引受 (Secondary Assumption of Risk)
こちらは、被告が注意義務に違反して危険な状況を作り出しており、その危険を原告が実際に認識しながらも、自発的かつ不合理にその危険な状況に身を投じた場合を指します。
例えば、被告が床に水をこぼしたまま放置した(過失)とします。原告は床が濡れていて滑りやすいことを認識していましたが、急いでいたため、あえてその上を走って渡ろうとして転倒しました。この場合、原告は被告が作り出したリスクを認識し、不合理にそれを受け入れたと評価される可能性があります。
寄与過失の時代には、第二次的リスクの引受もまた、原告の請求を完全に棄却する効果を持っていました。しかし、比較過失が主流となった現代では、この第二次的リスクの引受は、もはや独立した完全な抗弁とは見なされないのが一般的です。代わりに、それは原告の一つの「過失」の形態として扱われ、被告の過失との比較衡量の中で、過失割合を算定する一要素として考慮されます。
ただし、例外的に、原告が危険を認識しつつも、その危険に立ち向かうことが合理的であった場合(例えば、燃え盛る家の中にいる子供を救助するため、危険を承知で飛び込む救助者のようなケース)は、リスクの引受とは評価されず、抗弁は成立しません。