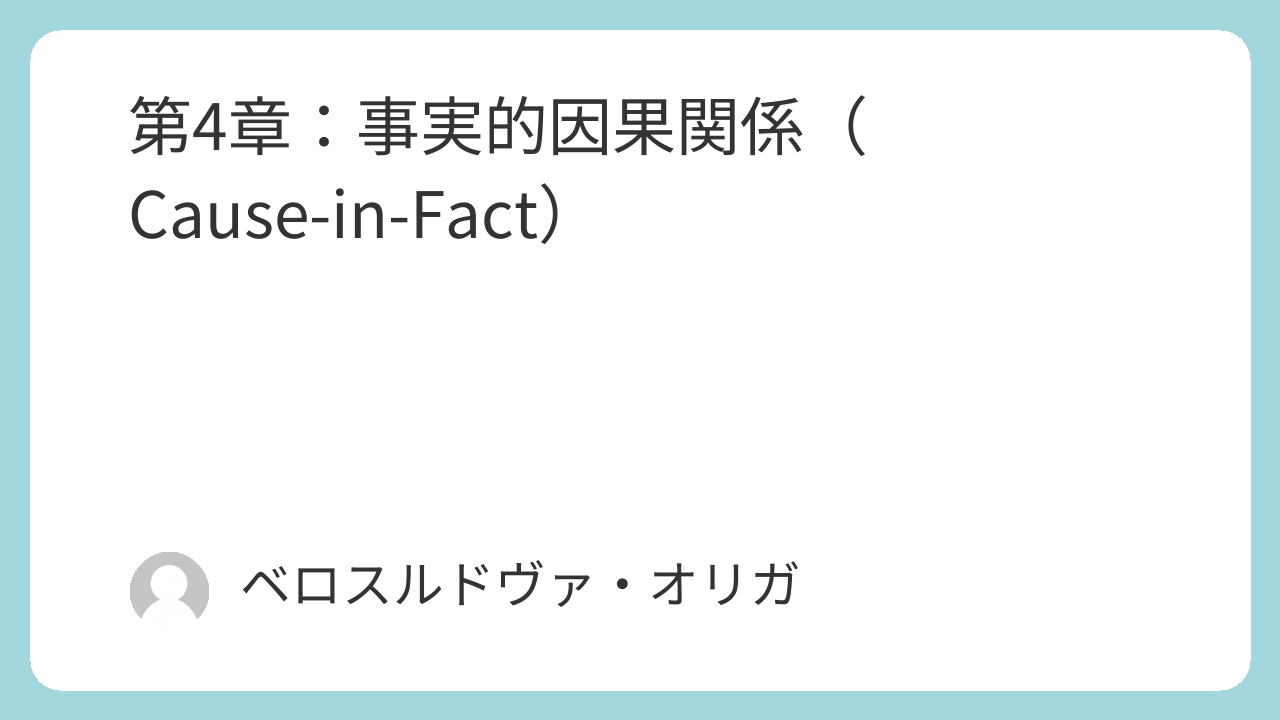不法行為訴訟において、原告は、被告が適用されるべき注意基準に違反したこと(義務違反)を証明するだけでは不十分です。それに加えて、その義務違反が、原告が賠償を求める損害を引き起こしたということを証明しなければなりません。これが「因果関係(Causation)」の要件です。被告の不法行為がなければ、原告の損害は発生しなかったであろう、という繋がりを示す必要があります。
日本法における議論と同様、因果関係の要件は、2つの異なる概念を含んでいます。ひとつは、本章で扱う「事実的因果関係(Cause-in-Fact)」であり、もうひとつは次章で詳述する「法的因果関係(Proximate Cause)」です。事実的因果関係は、被告の行為と原告の損害との間の、純粋に物理的・経験的な繋がりを問題にします。いわば、科学的な因果律の世界です。この繋がりがなければ、そもそも被告の行為を損害の原因として議論することができません。
1. 「But-For」テストとその限界
事実的因果関係を判断するための、最もシンプルで広く受け入れられている基準が「But-Forテスト」です。これは、ラテン語の sine qua non(あれなければこれなし)という言葉に集約される考え方であり、「被告の過失行為がなければ、原告の損害は発生しなかった」と言えるかどうかを問うものです。
あれなければこれなしの関係にあれば、事実上の因果関係は肯定されます。例えば、被告が赤信号を無視して交差点に進入し、青信号で進行してきた原告の車と衝突したとします。被告の信号無視という過失がなければ、衝突という損害は発生しなかったでしょうから、因果関係は明白です。
逆に、あれなければこれなしの関係になければ、因果関係は否定されます。例えば、被告が船から落ちた原告を救助するために浮き輪を投げる義務を怠ったとしても、仮に浮き輪を投げていたとしても原告がそれに到達する前に溺死していたであろう状況では、被告の不作為と原告の死亡との間にBut-Forの因果関係は認められません。
このテストは、現実には起こらなかった「反事実的(counterfactual)」な世界を想定する思考実験です。つまり、「もし被告が過失行為をしていなかったとしたら、何が起こっていたであろうか」という問いを立てるものです。陪審員は、自らの経験則や専門家の証言に基づいて、この問いに答えを出します。
しかし、このBut-Forテストは万能ではありません。特に、複数の原因が損害の発生に寄与している場合、その適用は困難を極めます。
2. 複数の原因が存在する場合の諸問題
現実の事故は、単一の原因によって引き起こされるとは限りません。複数の行為が絡み合い、ひとつの損害を生じさせることがあります。このような状況に対応するため、裁判所はBut-Forテストを修正・補完するいくつかの例外的な法理を発展させてきました。
A. Multiple Sufficient Causes
二人の被告が、それぞれ独立に、しかし同時に過失行為を行い、そのいずれの行為も単独で原告の損害を引き起こすのに十分であった場合を考えます。例えば、2つの異なる場所から発生した火災(いずれも被告の過失による)が、同時に原告の家に到達し、家を全焼させたとします。
この場合、厳格なBut-Forテストを適用すると、奇妙な結論が導かれます。被告Aの火災がなくても、被告Bの火災によって家は全焼していたであろうし、逆に被告Bの火災がなくても、被告Aの火災によって家は全焼していたであろうためです。これでは、どちらの被告の行為も、損害のBut-Forの原因とは言えなくなってしまいます。
このような事態を避けるため、裁判所は、複数の行為がそれぞれ損害を引き起こすのに十分であった場合、そのすべての行為者を事実上の原因とみなします。これは、But-Forテストの論理的な例外であり、加害者の過失行為が損害発生の「実質的な要因(substantial factor)」であったか否かを問うことで、因果関係を肯定するものです。
B. Alternative Liability
複数の被告が過失行為を行ったことは明らかですが、そのうちの誰の行為が実際に原告の損害を引き起こしたのかを特定できないという状況があります。この問題に対する画期的な解決策を示したのが、カリフォルニア州最高裁判所のSummers v. Tice 事件です。
この事件では、二人のハンター(被告)が同時に同じ方向へ向かって散弾銃を発砲し、そのうちの一発が原告の目に当たりました 。二人の被告が共に過失行為を犯したことは明らかでしたが、どちらの銃弾が命中したのかを証明することは不可能でした。
ここでも、But-Forテストを原告に厳格に適用すれば、訴えは棄却されてしまいます。しかし裁判所は、2人の過失行為者のうちのどちらかが原因であることは確実であることから、因果関係の立証責任を被告側に転換するという大胆な手法をとりました。すなわち、各被告は、自らの行為が損害の原因ではなかったことを証明しない限り、連帯して責任を負うと判示したのです。
この代替的責任の法理は、罪なき被害者を原因の特定不能というリスクから救済し、そのリスクを状況を作り出した過失ある加害者側に負担させるものです。
C. 生存の機会の喪失(Loss of a Chance to Survive)
医療過誤の分野で特に問題となるのが、この法理です。医師の過失(例えば、がんの診断の遅れ)が、患者の生存確率を低下させたものの、たとえ適切な診断がなされていたとしてもその患者の生存確率が50%未満であった場合に、因果関係をどう考えるかという問題です。
伝統的なBut-Forテストの下では、原告(患者側)は、医師の過失がなければ患者が「蓋然性をもって(more probably than not)」生存していただろうこと、すなわち生存確率が50%を超えていただろうことを証明しなければなりません。したがって、もともとの生存確率が50%未満であった場合、因果関係は否定され、患者側は一切の賠償を得られないことになっていました。
しかし、多くの裁判所は、このような結果は不公平であると考えるようになりました。患者は、たとえ50%未満であっても、生存の「機会」という重要な利益を医師の過失によって奪われているからです。そこで、多くの州で採用されるようになったのが、「生存の機会の喪失」という考え方です。これは、患者が失った生存確率そのものを一個の損害として捉え、それに対する賠償を認めるものです。
例えば、医師の過失によって生存確率が40%から25%に低下した場合、患者は15%の生存の機会を失ったことになります。この場合、患者がもし生存していた場合に得られたであろう損害賠償額の全額ではなく、その15%に相当する額の賠償が認められます。この法理は、因果関係の証明における「オール・オア・ナッシング」のアプローチを緩和し、より柔軟な救済を可能にするものです。
D. マーケット・シェア責任(Market-Share Liability)
Alternative Liabilityの法理をさらに発展させ、多数の企業が関与する大規模な薬害事件などに対応するために生み出されたのが、マーケット・シェア責任です。これは、Sindell v. Abbott Laboratories 事件で初めて認められました。
この事件は、流産防止薬として投与されたDES(ジエチルスチルベストロール)を母親が妊娠中に服用したことによって、その娘たちが後年になって癌などを発症したというものでした。DESは多数の製薬会社によって製造・販売されており、しかもすべての製品が化学的に同一であったため、被害者が、自らの母親が服用したDESをどの会社が製造したのかを特定することは事実上不可能でした。
カリフォルニア州最高裁判所は、ここでも被害者救済の道を選びました。裁判所は、原告が、問題となったDES市場の実質的なシェアを占める被告らを訴えている場合、各被告企業は、自社の市場占有率(マーケット・シェア)に応じて損害賠償責任を負うという新たなルールを創設しました。因果関係の立証責任はここでも転換され、各被告は、自社製品が原告の母親に投与されなかったことを証明しない限り責任を免れないとされました。
もっとも、この法理は個別の因果関係の証明という伝統的な原則からの大きな逸れるもので、その適用はDESのような特殊な状況に限定される傾向にあります。