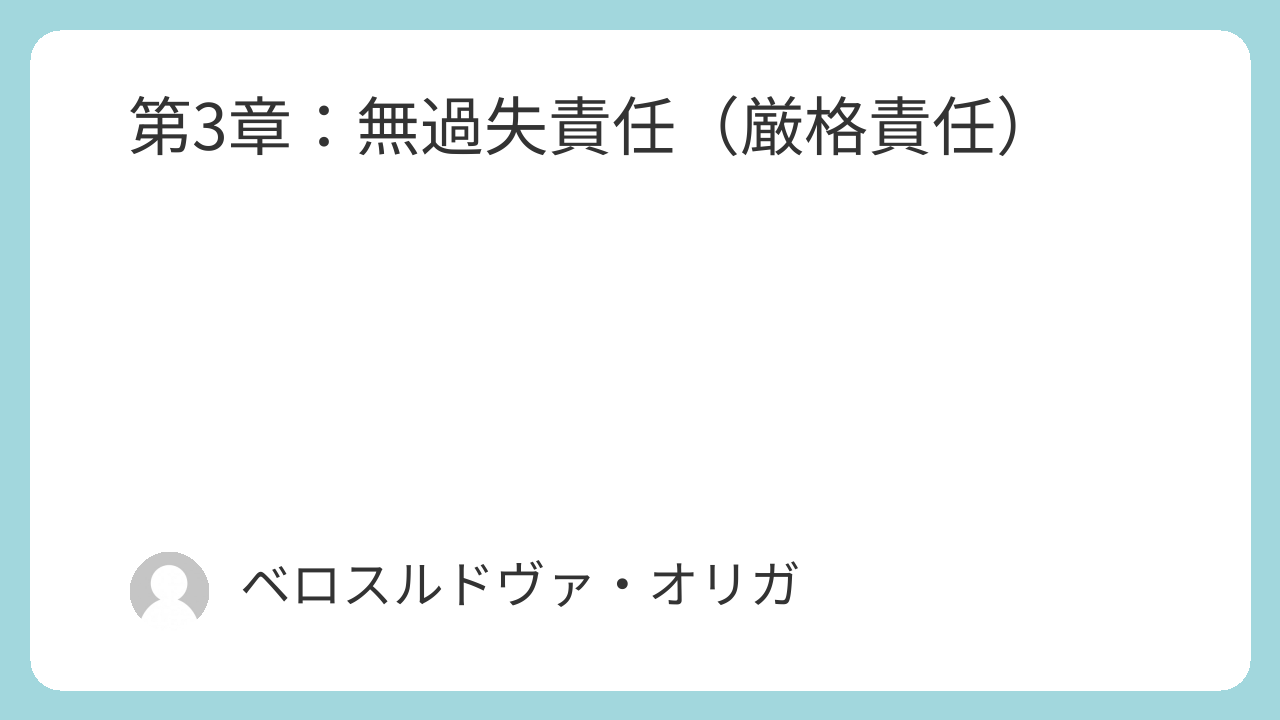特定の状況下において、加害者に故意も過失もなかったとしても、損害の発生そのものから責任を認める場合があります。これが「無過失責任(Strict Liability)」又は「厳格責任」と呼ばれる第三の類型です。
この責任は「絶対責任(absolute liability)」とは異なります。被告がある活動に従事したというだけで、そこから生じるあらゆる損害に責任を負うわけではありません。責任が課されるのは、法が定める特定のカテゴリーに該当する活動に限られます。
1. 厳格責任の理論的根拠
A. 情報コストと誤審リスクの削減
過失の有無を判断する審理は、しばしば事実関係の集中的な調査を伴います。原告は、被告の行為が合理的な注意を欠いていたことを証明するために、専門家の証言を求めたり詳細な証拠を収集したりする必要があります。厳格責任は、この「過失」の立証を不要とすることで、訴訟のプロセスを簡素化し、訴訟コスト(litigation costs)を削減する可能性があります。また、特に事故によって証拠が失われやすい活動(例:爆発物の使用)においては、過失の有無を正確に判断することが困難な場合があります。このような状況で過失責任のみを認めると、本来責任を負うべき加害者が免責されてしまう誤審リスクが高まります。厳格責任は、こうしたケースでより公正な結果をもたらす可能性があります。日本においては立証責任の転換という形で解決しようとしている課題を、アメリカの不法行為法においては無過失責任という形で解決しようとしているのです。
B. 活動レベルへの影響と研究開発のインセンティブ
過失責任は、人々が特定の活動を「より安全に」行うことを促しますが、その活動を「どれくらいの頻度で行うか」(活動レベル)についてはあまり影響を与えません。例えば、安全運転を心がけている限り、どれだけ多くの距離を運転しても通常は過失を問われません。
これに対し厳格責任は、活動主体に、過失の有無にかかわらずその活動から生じる事故コストを内部化させます。これにより、企業等は、単に安全対策を講じるだけでなくより安全な代替活動を選択したり、活動の規模自体を縮小したりするインセンティブを持つことになります。さらに、事故コストを削減するための新たな技術や方法論を開発する研究開発への動機づけも、過失責任の場合より強く働く可能性があります。
C. 保険機能と損失の広範な分配
事故による損失は、1人の被害者に集中すると壊滅的な打撃となりえます。不法行為法の機能のひとつは、損失をより広い範囲に分配(loss distribution)することです 。例えば、ある事業活動から損害が生じた場合、事業者はその賠償コストを価格に転嫁したり、賠償責任保険に加入したりすることで、最終的にはその事業者から便益を得ている消費者や社会全体でコストを分担することができます。多くの場合、事業者(潜在的加害者)は、個々の被害者よりも、保険に加入したりリスクを価格に織り込んだりする能力に長けています。この観点から、厳格責任は、損失をより効率的かつ公平に負担できる側にそれを配分するためのメカニズムと見なすことができます。
D. 権利に基づく責任規範の充足
以上のような功利主義的な理由だけでなく、権利・公平といった規範的な価値観からも厳格責任は説明されます。例えば、ある活動から便益(benefit)を得ている者は、その活動に伴って発生するコストも負担すべきであるという考え方(報償責任)です。また、一方の当事者が他方に対して、社会で許容されるレベルを超えた非相互的なリスク(non-reciprocal risk)を課している場合、そのリスクを創出した側が厳格責任を負うべきだとする「相互性」理論もあります。飛行機が地上に墜落した場合、地上の人々は飛行機に対して同等のリスクを課していないため、航空会社は厳格責任を負うべきだとされるのがその一例です。
2. 伝統的な厳格責任:異常に危険な活動
厳格責任の現代的な発展は、19世紀のイギリスのRylands v. Fletcher 事件から始まりました。この事件で被告は、自らの土地に貯水池を建設しましたが、その地下に古い炭鉱の坑道があることを知らず、水が漏れ出して隣接する原告の炭鉱に損害を与えました。被告に過失は認められませんでしたが 、貴族院は、「土地の非自然的利用(non-natural use)のために持ち込まれたものが外部に漏れ出して損害を与えた場合、その者は厳格責任を負う」という原則を確立しました。
この「非自然的利用」という概念は、当初アメリカの一部の裁判所において、産業の発展を妨げるものとして強い抵抗がありました。しかし、爆薬の使用。石油の掘削。大量の貯水といった、明らかに周囲に大きな危険を及ぼす活動については、徐々に厳格責任を認める判例が積み重ねられていきました。
やがて、これらの判例を体系化し、アメリカ法における厳格責任の基準を明確にしたのが、リステイトメント(Restatement of Torts)です。当初は「超危険活動(ultrahazardous activity)」という概念が用いられ、当該活動がもたらす危険の程度と当該地域における活動の一般性が判断基準とされました。
その後、第二次リステイトメントでは、より洗練された「異常に危険な活動(abnormally dangerous activity)」という概念が採用されました。ある活動がこのカテゴリーに該当するか否かは、以下の6つの要素を総合的に考慮して、陪審員ではなく裁判官が法的問題として判断します。
- 高度な危害のリスクが存在するか
- その危害が重大なものとなる蓋然性
- 合理的な注意を払ってもリスクを排除できないこと
- その活動が一般的な慣行でないこと
- その活動が行われる場所にとって不適切であること
- 活動の地域社会への価値と、その危険性との比較衡量
これらの要素は、厳格責任の理論的根拠と密接に関連しています。例えば、③の要素は、過失責任の法理では適切に抑止できないリスクであることを示唆し、④と⑤の要素は、被害者がそのリスクを予期し自衛することが困難であることを示しています。
3. 使用者責任(Vicarious Liability)
現代社会で最も頻繁に適用される厳格責任が使用者責任です。これは、respondeat superior(「主人をして答えしめよ」) の法理に基づき、従業員がその「職務の範囲内(within the scope of employment)」で犯した不法行為について、使用者(雇用主)が責任を負うというものです。
これは、使用者が従業員の選任・監督において過失を犯した場合に問われる直接の責任とは異なります。使用者責任は、使用者自身に何らの過失がなくても、従業員の不法行為から生じた損害について責任を負わせる真性厳格責任です。
この責任の根拠は、前述の厳格責任の理論の多くによって説明できます。使用者は従業員の活動から利益を得ており(便益理論)、従業員の行為を管理・監督する立場にあり(抑止)、被害者に比べて資力や保険加入能力が高く、損失を分配するのに適した立場にいるからです。
使用者責任が成立するためには、2つの重要な要件が満たされなければなりません。
1. 誰が「従業員」か
使用者責任は、従業員(employee)に適用され、独立した請負人(independent contractor)には原則として適用されません。両者の区別は、使用者がその者の仕事の遂行方法について、具体的な指揮監督権(control)を有しているか否かが最も重要な基準となります。
2. 何が「職務の範囲内」か
従業員の行為がすべて使用者責任の対象となるわけではありません。その行為は「職務の範囲内」で行われたものでなければなりません。この判断基準として、伝統的に「detour」と「frolic」の区別が用いられてきました。
- Detour:職務遂行の過程で、わずかに本来のルートや目的から逸脱する行為です。この間の不法行為は、職務の範囲内とされる可能性があります。
- Frolic:職務とは全く無関係な、純粋に個人的な目的のために行われる、時間的・空間的に大きな逸脱です。この間の不法行為は、職務の範囲外とされます。
近年では、この伝統的な区別に加え、その従業員の行為が使用者の事業活動に内在する予測可能なリスクの一環であったかというより広い視点から判断する傾向も見られます。Ira S. Bushey & Sons, Inc. v. United States 事件では、泥酔した船員が乾ドックのバルブを開けて船とドックに損害を与えた行為について、裁判所は、使用者の責任を認めました。