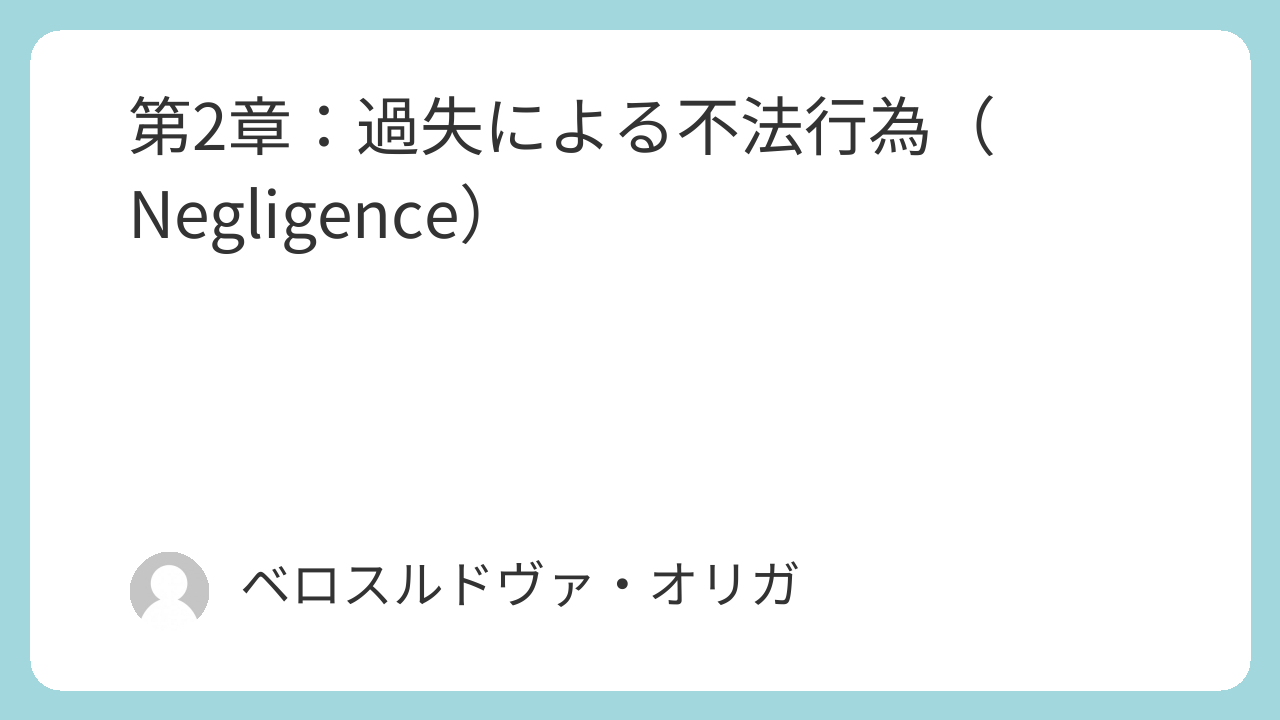過失とは、他者に危害を加える意図はなかったものの、社会の一員として払うべきであった「合理的な注意(reasonable care)」を怠った結果、損害を生じさせた場合に問われる責任です。
過失責任が認められるためには、①義務・②義務違反・③因果関係・④損害がすべて立証されなければなりません。他者に予見可能な物理的損害を及ぼすリスクがある場合、人は通常、それを回避するための合理的な注意を払う義務を負います。したがって、多くの過失事件では、「義務」の存在自体は自明であり、争点はむしろ、被告がその義務に「違反」したか、すなわち「過失があったか」という点に集約されます。
1. 過失責任の歴史的背景
過失責任の法理は、中世イングランドの厳格な法形式主義から離脱する中で形成されてきました。
かつて、他者に直接的かつ物理的な損害を与えた場合の訴訟は、「Trespass(不法妨害)」という訴訟形式によって行われていました。Trespassでは、被告の行為が直接損害を引き起こしたことさえ証明されれば、被告に「全く過失がなかった(utterly without fault)」ことを自ら証明しない限り責任を負わされました。これは、現代における厳格責任に近いものでした 。
これに対し、損害が間接的に生じた場合には、「Case(状況に応じた訴訟)」という別の訴訟形式が用いられました。Caseでは、原告が被告の「過失」を証明しなければなりませんでした。この二元的な構造は、損害が直接的か間接的かという「恣意的」な区別によって、当事者の立証責任や責任の有無が大きく左右されるという不合理を生んでいました。
この状況に終止符を打ち、現代の過失責任原則を確立したのが、19世紀半ばのマサチューセッツ州最高裁判所による Brown v. Kendall 事件です。この事件で、被告は喧嘩している犬を止めようとして持っていた棒で、誤って背後にいた原告の目を突いてしまいました。ショー裁判長は、損害が直接的か間接的かにかかわらず、被告に責任を負わせるためには、原告が「被告に過失があったこと」を証明しなければならないと判示しました。その上で、被告が払うべき注意義務の基準は、「状況下で合理的な人が払うであろう通常の注意(ordinary care)」であると述べました。
この判決は、アメリカ不法行為法の転換点となりました。責任の根拠は、被告の行為の「過失」へと移行し、過失の立証責任は原告が負うことになりました。これにより、産業革命の進展とともに増加する様々な事故に対して、統一的で柔軟な判断基準が提供されることになり、過失は不法行為法の中心的支柱としての地位を確立しました。
2. 「一般通常人」の基準(The Reasonable Person Standard)
過失とは、「状況下において合理的な注意を怠ること」と定義されます。この判断基準となるのが、一般通常人すなわち「合理的に慎重な人(the reasonably prudent person)」です。陪審員は、特定の状況に置かれた被告の行為を、この「合理的な人」であればどう行動したであろうか、という視点から評価します。
A. 客観的基準(The Objective Standard)
「合理的な人」の基準の特徴は、それが客観的な基準であるという点です。つまり、問題となるのは、被告個人が誠実に最善を尽くしたかどうか(主観的基準)ではなく、平均的で通常の知性と判断力を持つ人間が同じ状況下でどのように行動したかです。
例えば、Vaughan v. Menlove 事件では、被告は自身の干し草の山が自然発火する危険性を警告されたにもかかわらず放置した結果、火災が発生して隣家の原告のコテージを焼損させました。被告は、自らの判断力が他人より劣っていると主張しましたが、裁判所はこれを退け、「他人の財産の安全を考慮する上で、一般的な慎重さの基準に従う義務がある」として、客観的基準を適用しました。
この客観的基準にはいくつかの利点があります。第一に、審理の容易性です。被告個人の知性や判断力をその都度評価するのは煩雑であり、また、被告による偽りや誇張の温床となりかねません。客観的基準は、陪審員が自らの常識と経験に基づいて判断することを可能にします。第二に、抑止効果です。人々は、自らの能力不足を言い訳にできず、社会が要求する一定水準の注意を払うよう動機づけられます。自らがその基準を満たせないと自覚する者は、危険な活動への参加を控えるようになることが期待されます。第三に、公平性です。社会で活動するすべての者に等しく同じ基準を適用することは、被害者から見れば、誰から危害を加えられるかによって保護のレベルが変わることのない、予測可能で公平な社会を保障することにつながります。
B. 子どもと心身障害者(Children and the Infirm)
この厳格な客観的基準には、いくつかの重要な例外が存在します 。
- 子ども:幼い子ども(例えば5歳未満)は、過失責任を負う能力がないとされます。それ以上の年齢の子どもについては、多くの州で「同等の年齢・知性・経験に基づいた合理的な慎重さを有する子ども」という、半客観的・半主観的な基準が適用されます。ただし、子どもが自動車の運転やモーターボートの操縦といった、本来大人が行う危険な活動に従事していた場合には、例外的に成人と同一の客観的基準が課されます。これは、周囲の者が相手を子どもだと予期できず、特別な注意を払うことができないためです。
- 障害者:身体的な障害については、通常、それが考慮されます。例えば、盲目の人が払うべき合理的な注意は、視力のある人のそれとは異なります。しかし、その障害ゆえに、健常者以上に他の予防措置(白杖の使用など)を講じることが期待される場合もあります。一方、精神的な障害については、伝統的に客観的基準が維持されてきました。これは、精神障害の程度を客観的に測定・証明することが困難であることや、責任を免除すると監督者の注意を喚起するインセンティブが失われるといった政策的配慮が背景にあります。
C. 予見可能性の要件(The Foreseeability Requirement)
合理的な注意義務の前提として、その危害が予見可能(foreseeable)であったことが必要です。合理的な人は予見不可能なリスクに対してまで予防措置を講じることは期待されません。Blyth v. Birmingham Waterworks 事件では、記録的な厳寒によって地中の水道管が破損し、原告の家が浸水しました。裁判所は、このような異常な寒波は「極地以外では通常起こり得ない」ものであり予見不可能であったとして、水道会社の責任を否定しました。
ただし、何が予見可能で何が不可能かの線引きは、常に明確なわけではありません。あるリスクの発生確率が極めて低いとしても、それだけで直ちに予見不可能とされるわけではありません。リスクの発生確率の低さは、むしろ次に述べる「calculus of negligence」において、予防措置の負担と比較衡量されるべき要素となります。
3. 過失のカルキュラス:ラーニッド・ハンドの公式
「合理的な注意」という基準は、依然として抽象的です。この基準をより分析的に、そしてある意味で数量的に捉えようとする試みが、ラーニッド・ハンド裁判官が United States v. Carroll Towing Co. 事件で提示した「calculus of negligence」です。
ハンド判事は、ある予防措置を講じる義務の有無を判断するための3つの変数を提示しました。
- P(Probability):その事故が発生する確率
- L(Injury):事故が発生した場合に生じる損害の大きさ
- B(Burden):その事故を防止するための予防措置にかかる負担(コスト)
彼はこの関係を次のような代数式で表現しました。
B < P × L
この式が意味するのは、予防措置の負担(B)が損害の期待値(事故の発生確率Pと損害の大きさLの積)よりも小さい場合には、その予防措置を講じなかった行為は過失と評価されるということです。逆に、予防措置の負担が損害の期待値より大きい場合であれば、その予防措置を講じなかったとしても過失とはなりません。
例えば、Eckert v. Long Island R.R. 事件では、過失をもって運行されていた列車の前にいた幼児を救うために線路に飛び込み、命を落とした男性の行為が問題となりました。鉄道会社は、男性の行為は無謀であり過失にあたると主張しました。しかし裁判所は、「人の命を救うための努力」は、よほど無謀でない限り過失とは見なされないと判断しました 。これをハンドの公式に当てはめれば、B(救助者の生命のリスク)は極めて大きいですが、PL(幼児がほぼ確実に死亡するという損害の期待値)もまた極めて大きいと言えます。両者を比較衡量した結果、救助行為は「合理的」と評価されたのです。
この計算式は、道徳的には、他者に与える可能性のある損害(PL)を自己の負担(B)と同等に考慮することを求める、公平性の原則の現れと見ることができます。経済学的には、社会全体の資源を最も効率的に配分するためのツールと見なされます。すなわち、予防コストが損害の期待値を下回る場合にのみ予防を義務付けることで、社会的な浪費を防ぎ、富を最大化するという考え方です。
多くの場合、これらの変数を正確に数量化することは不可能です。しかし、この計算式は、当事者が「講じられなかった予防措置(untaken precaution)」を巡って議論する際の、思考の枠組みとなります。原告は、被告がより安価で効果的な予防措置を講じられたはずだと主張し、被告は、その措置が実際には高価であったり非現実的であったと反論します。これらの議論を通じて、陪審員は、被告の行為が合理的であったか否かをより具体的に判断することができると考えられています。
4. 慣習(Custom)の役割
ある業界や地域社会で広く行われている「慣習」は、過失判断においてどのような役割を果たすのでしょうか。この点に関するルールは明確です。慣習の遵守・不遵守の証拠は、過失の有無を判断する上で許容され関連性有するものの、それ自体が決定的となるわけではないというものです。
被告が業界の慣習に従っていたという証拠は、自らの行為が合理的であったことを示す防御方法として用いることができます 。逆に、原告は、被告が慣習に従っていなかったという証拠を被告の過失を示す攻撃方法として用いることができます。しかし、最終的にその慣習自体が合理的であったか否かを判断するのは陪審員です。
このルールを確立したのが、ハンド裁判官によるThe T.J. Hooper 事件の判決です。この事件では、曳航船が、当時まだ慣習となっていなかった無線機を搭載していなかったために、嵐の接近を知ることができず積荷を失いました。船主は、無線機の搭載は業界の慣習ではなかったと主張しました。しかし裁判所は、「業界全体が、新たな利用可能な装置の採用において不当に遅れている可能性がある」と述べ、たとえ慣習に従っていたとしても、その慣習自体が不合理であれば、過失責任を免れないと判示しました。
慣習の証拠は、陪審員が特定の活動におけるリスクや予防措置の実現可能性を理解し、より情報に基づいた判断を下すのを助けるための重要な情報源となります。しかし、最終的な合理性の基準は、慣習ではなく、常に「合理的な人」の基準なのです。
5. 専門家の責任(Professional Liability)
医師・弁護士・会計士といった専門家の行為については、通常の過失とは異なる特殊なルールが適用されます。これを専門家責任、特に医療分野では医療過誤(medical malpractice)と呼びます。
通常の過失事件において慣習は決定的な意味を持ちませんが、専門家責任の分野では、その専門職における「慣習」、すなわち専門的注意基準(professional standard of care)が、事実上、過失の有無を決定します。医師は、その専門分野において一般的に認められている知識と技能を行使する義務を負います。したがって、原告は、被告医師の治療が、確立された医療基準から逸脱していたことを証明しなければなりません。逆に、被告医師は、自らの治療が一般的に認められた基準に準拠していたこと、少なくとも「尊敬されるべき少数派(respectable minority)」によって支持される学説に基づいていたことを証明できれば責任を免れます。
この特殊なルールの根拠は、医療のような高度に専門的な分野において、一般市民である陪審員が専門家の行為の是非を独自に判断することは不可能に近いという点にあります。そのため、法は、その判断基準を専門家集団自身の基準に委ねることを選択したのです。
また、医療過誤の分野では、インフォームド・コンセント(Informed Consent)の法理も重要です。これは、医師が、治療に伴う重大なリスク・利益・代替治療の選択肢について患者に十分な情報を提供し、患者が自己決定権に基づいて治療に同意できるようにする義務です。この情報提供義務の基準についても、州によって「合理的な医師であれば何を説明するか(専門家基準)」と「合理的な患者であれば何を知りたいか(患者基準)」という2つの異なるアプローチが存在します。
6. 法令違反(Violation of Statutes)
ある行為が、交通法規や建築基準といった安全に関する法令に違反している場合、それは過失判断にどのような影響を与えるのでしょうか。多くの州が採用するルールは「正当な理由なく(unexcused)安全法令に違反する行為は、それ自体が過失である(Negligence Per Se)」というものです。
このルールを明確に示したのが、カルドーゾ裁判官によるMartin v. Herzog 事件です。この事件では、夜間に無灯火で馬車を走行させていた原告が対向車と衝突しました。無灯火走行は州法に違反していました。カルドーゾ裁判官は、立法府が定めた安全基準を無視すること自体が、合理的な注意の欠如の証拠であると述べ、法令違反が過失を構成すると判断しました。
この「当然の過失」のルールが適用されると、陪審員は、被告の行為が合理的であったか否かを判断する裁量を失います。法令違反の事実が認定されれば、原則として義務違反(過失)があったと結論づけられます。
ただし、このルールには2つの制限があります。第1に、違反に正当な理由があれば過失とはなりません。例えば、Tedla v. Ellman 事件では、原告らは、法令の規定とは逆の車線を歩いていた方が交通量が少なく安全であったため、そちらを歩いていました。裁判所は、法令遵守がかえって危険を増大させるような緊急時においては、違反は正当化されるとしました。第2に、その法令が保護しようとしていたのが、原告が属する階級の人々であり、かつ、原告が被った損害が当該法令が防止しようとしていた種類の危害であった場合にのみ、このルールは適用されます(限定された法令目的の抗弁)。
7. 裁判官と陪審員の役割
原則として、被告が合理的であったか否かは、コミュニティの常識を代表する陪審員が判断すべき事実問題です。
しかし、合理的な人々が意見を異にし得ない(reasonable people could not disagree)ほど、一方の当事者の行為が明白に合理的・非合理的である場合があります。そのような場合、裁判官は、その問題を陪審員に付すことなく、「法律問題として(as a matter of law)」過失の有無を自ら決定することができます。例えば、目隠しをして幹線道路を運転する行為は、法律問題として過失であると判断されるでしょう。
かつて、オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア裁判官は、裁判官がより積極的に「法律問題として」の判断を下し、具体的な状況に対する明確な行動ルールを判例によって確立していくべきだと主張しました。彼はそのような考えから、Baltimore & Ohio R.R. v. Goodman 事件において、踏切を渡る運転手は「停止し、降りて、見る」義務があるという厳格なルールを打ち立てました。しかし、そのわずか数年後、カルドーゾ裁判官は Pokora v. Wabash Railway Co. 事件でこのGoodmanルールを事実上覆し、踏切での注意義務のあり方は個々の状況に応じて陪審員が判断すべき柔軟な問題であるとしました。
過失による不法行為に関しては、これら2つの裁判例のように、明確で予測可能な「ルール」を求める要請と、個々の事件の特殊な事情に応じた公平な判断を可能にする「スタンダード(基準)」を求める要請との間で揺れ動いてきました。現代においては、おおむね、過失の最終的な判断を陪審員の常識的な評価に委ねるという後者のアプローチに傾いています。