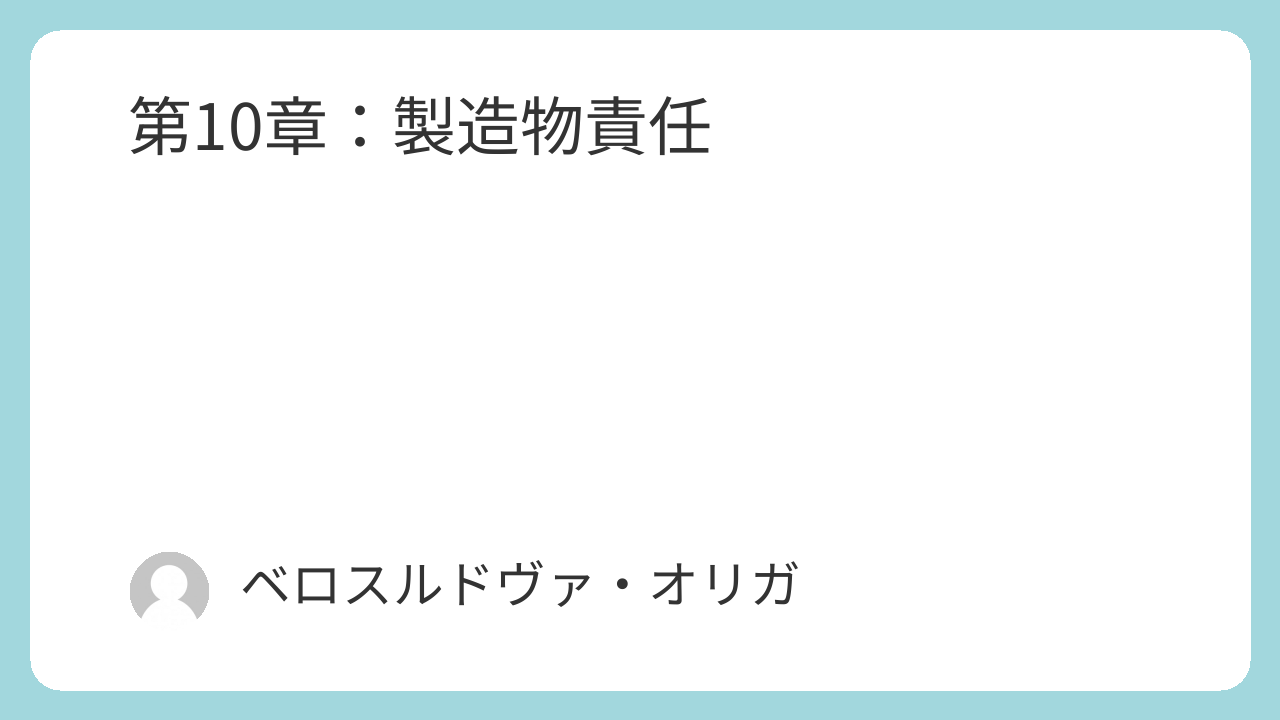第1節 製造物責任法の発展:厳格責任へ
かつて、消費者が欠陥製品の製造業者に責任を問うことは、「契約関係の要件(Privity of Contract)」によって極めて困難でした。消費者は通常、小売業者から製品を購入するため、製造業者との間に直接の契約関係がなく、訴訟を起こす資格がないとされたのです。
この壁を打ち破ったのが、1916年の画期的な判決 MacPherson v. Buick Motor Co. でした。この判決により、製品が過失をもって製造されれば危険を生じさせることが予見できる場合、製造業者は最終消費者に対しても過失責任(Negligence Liability)を負うことが確立されました。しかし、巨大企業の製造工程における過失を消費者が証明することは依然として困難でした。
この「過失証明の壁」を乗り越えるために裁判所が次に用いたのが、契約法上の「保証(Warranty)」、特に「商品適格性の黙示の保証(Implied Warranty of Merchantability)」という概念でした。これは、製品が通常期待される品質を備えていることを売主が黙示的に保証するという考え方で、過失の有無に関わらず責任を問える点で厳格責任に近いものでした。まず食品分野で製造業者への直接適用が認められ、1960年の Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc. 判決によって自動車などの一般製品にも拡大され、さらに免責条項も無効とされました。
この Henningsen 判決は、事実上、不法行為法における厳格責任への道を開きました。そして1963年の Greenman v. Yuba Power Products, Inc. 判決において、カリフォルニア州最高裁判所は、もはや「保証」という契約法的な擬制は不要であるとし、製品に欠陥があり、それが原因で損害が生じた場合には、製造業者は不法行為法上の厳格責任を負うと明確に判示したのです。この考え方は、「不法行為法リステイトメント第2次」第402A条 に結実し、全米に広まりました。
第2節 現代の製造物責任:3つの欠陥類型
現代の製造物責任法の中核は、「欠陥」がある製品に起因する損害に対する厳格責任です。ただし、これは無過失責任とは異なります。責任が認められるのは、あくまで製品に欠陥(Defect)があった場合に限られます。そして、その欠陥は主に以下の3つの類型に分類されます。
1. 製造上の欠陥 (Manufacturing Defects)
これは、個々の製品が、製造業者の意図した設計仕様や品質基準から逸脱してしまった状態を指します。つまり、製品ライン全体の問題ではなく、特定の製品が組立ミスや材料不良などによって「ハズレ」として出来上がってしまった場合です。
- 責任基準: この欠陥に対しては、文字通りの厳格責任が適用されます。原告は、製品が出荷時に設計から逸脱していたこと及びその逸脱が損害を引き起こしたことを証明すれば足ります。製造業者がいかに高度な品質管理体制を敷いていたとしても、それは原則として免責理由になりません。
- 証明: 製造時の欠陥の存在を直接証明することが難しい場合でも、事故の状況(例:新品の製品が通常の使用で破損した)から欠陥の存在を推認することが認められる場合があります。
- 理論的根拠: 消費者は製品が設計通りに作られていると期待する権利があり、製造業者はその期待を裏切った責任を負うべきです。また、製造業者はリスクを管理・分散する上で最も有利な立場にいます。
2. 設計上の欠陥 (Design Defects)
これは、製品ライン全体に共通する設計そのものに、不合理な危険性が内在している状態を指します。製品は設計通りに製造されているものの、その設計自体が安全配慮に欠けていると評価される場合です。
- 基準: 製造上の欠陥とは異なり、設計上の欠陥に対する責任は純粋な厳格責任とは言えません。なぜなら、全ての製品設計は安全性、コスト、機能性の間のトレードオフを含むからです。裁判所は主に2つの基準を用いて設計の欠陥性を判断します。
- リスク・効用基準 (Risk-Utility Test): これが多くの州で採用されている支配的な基準です。設計がもたらす予見可能なリスクが、その設計の持つ効用(便益、コスト、美的魅力など)を上回る場合に欠陥と判断します。この比較衡量においては、実行可能な代替設計案(Reasonable Alternative Design – RAD)の存在とその実現可能性が極めて重要な要素となります。RADとは、問題となっているリスクを低減または回避でき、経済的・技術的に実行可能であり、かつ製品全体の効用を大きく損なわないような代替設計案のことです。多くの裁判所は、原告がこのRADの存在と優位性を具体的に証明することを、設計上の欠陥を立証するための要件としています。この基準は、実質的には過失の判断に非常に近いものと言えます。
- 消費者期待基準 (Consumer Expectations Test): 一部の州で用いられる基準で、製品が、通常の消費者が合理的に期待する安全性を欠いていた場合に欠陥と判断します。製品が通常の使用において予期せず危険な挙動を示した場合(例:通常走行中のタイヤの突然の破裂)など、欠陥が比較的明白なケースには適用しやすいですが、複雑な設計(例:自動車の衝突安全性)に関する消費者の具体的な期待を定義することが困難なため、適用範囲は限定的です。
- 証明の課題: 設計上の欠陥の証明は、しばしば高度な専門知識を要します。原告は、工学的な専門家証言を用いて、リスク・効用分析を行ったり、RADの存在と実現可能性を立証したりする必要があります。陪審員が複雑な設計の是非を判断することの難しさも指摘されています。
3. 警告上の欠陥 (Warning Defects / Failure to Warn)
これは、製品の使用に伴う予見可能なリスクについて、製造業者などが適切な指示や警告を提供しなかったために、製品が不合理に危険なものとなった状態を指します。たとえ設計上・製造上の欠陥がなくても、適切な情報提供がなければ製品は「欠陥品」と見なされ得ます。
- 基準: 製造業者は、製品に関して知っていた、または合理的に知るべきであった(Knew or Should Have Known)リスクについて、予見可能な使用者に対し、適切な警告を与える義務があります。
- 警告の適切性 (Adequacy): 警告は、単に存在すれば良いわけではなく、内容(リスクの性質、重大性、回避方法など)、表現(明確さ、理解しやすさ)、形式(目立ちやすさ、場所)において適切でなければなりません。あまりに多くの些末な警告は、かえって重要な警告の効果を薄める「ラベル・クラッター」の問題も考慮される必要があります。
- 警告すべき対象: 警告は、通常の使用者はもちろん、合理的に予見可能な誤使用をする可能性のある者に対しても必要な場合があります。ただし、「自明の危険(Open and Obvious Danger)」(例:ナイフは切れる)については、通常、警告義務はないとされます。
- 因果関係: 原告は、適切な警告があれば損害を回避できたことを証明する必要があります。多くの裁判所は、特に医薬品の副作用などについて、「警告があればそれに従ったであろう(Heeding Presumption)」という推定を原告に有利に働かせることがあります。
- 設計との関係: 重要なのは、警告は安全な設計の代替物ではないということです。もし合理的な代替設計(RAD)によってリスク自体を除去または低減できるのであれば、単に警告するだけでは不十分であり、設計上の欠陥が問われる可能性があります。警告は、設計上除去することが不合理な残存リスクについて与えられるべきものです。
第3節 製造物責任に対する抗弁 (Defenses)
被告(製造業者や販売業者)は、製造物責任訴訟において、いくつかの抗弁を主張することができます。
- 原告の行動:
- 比較過失 (Comparative Negligence): 厳格責任の訴訟であっても、多くの州では、原告自身の過失(例:不注意な製品の使用)が損害の発生・拡大に寄与した場合、その過失割合に応じて賠償額が減額されます。
- 危険の引受 (Assumption of Risk): 原告が製品の欠陥とそれがもたらす具体的なリスクを主観的に認識し、自発的かつ不合理にそのリスクを受け入れた(例:欠陥を知りながら危険な使い方を続けた)場合、賠償額が減額されたり、請求が棄却されたりすることがあります。比較過失の枠組みに吸収されることが多いです。
- 製品の誤使用 (Product Misuse): 原告が製品を予見不可能な方法で使用したことが損害の唯一の原因である場合、被告は責任を免れます。ただし、予見可能な誤使用については、設計や警告で配慮すべき義務が生じることがあります。
第4節 連邦法による専占 (Federal Preemption)
現代の製造物責任訴訟における重要な論点として、「連邦法による専占(Federal Preemption)」があります。これは、特定の製品カテゴリー(例:医薬品、医療機器、自動車、農薬など)について、連邦法や連邦機関(FDA、NHTSAなど)が詳細な安全基準や表示基準を定めている場合に、それらの連邦規制が州の製造物責任法(コモンロー)に優先し、州法に基づく訴訟を排除するかどうか、という問題です。
- 根拠: 合衆国憲法の優越条項(Supremacy Clause)に基づきます。
- 種類:
- 明示的な専占 (Express Preemption): 連邦法自体に、州法の適用を排除する明確な規定がある場合。
- 黙示的な専占 (Implied Preemption): 連邦法の規定がなくても、(a) 連邦規制が非常に包括的で、連邦がその分野を完全に占有する意図が推認される場合(Field Preemption)、または (b) 州法を適用することが連邦法の目的達成を著しく妨げる場合(Conflict Preemption)。
- 影響: 専占が認められると、たとえ州法の下では製造物責任が認められるようなケースであっても、原告は連邦法が定める基準を満たしていることを理由に訴えを退けられることになります。これは、特に医薬品や医療機器の警告に関する訴訟で頻繁に争われます。連邦最高裁は、個別の法律や規制の解釈に基づき、専占を認める場合と認めない場合があり、ケースバイケースの判断が必要です。