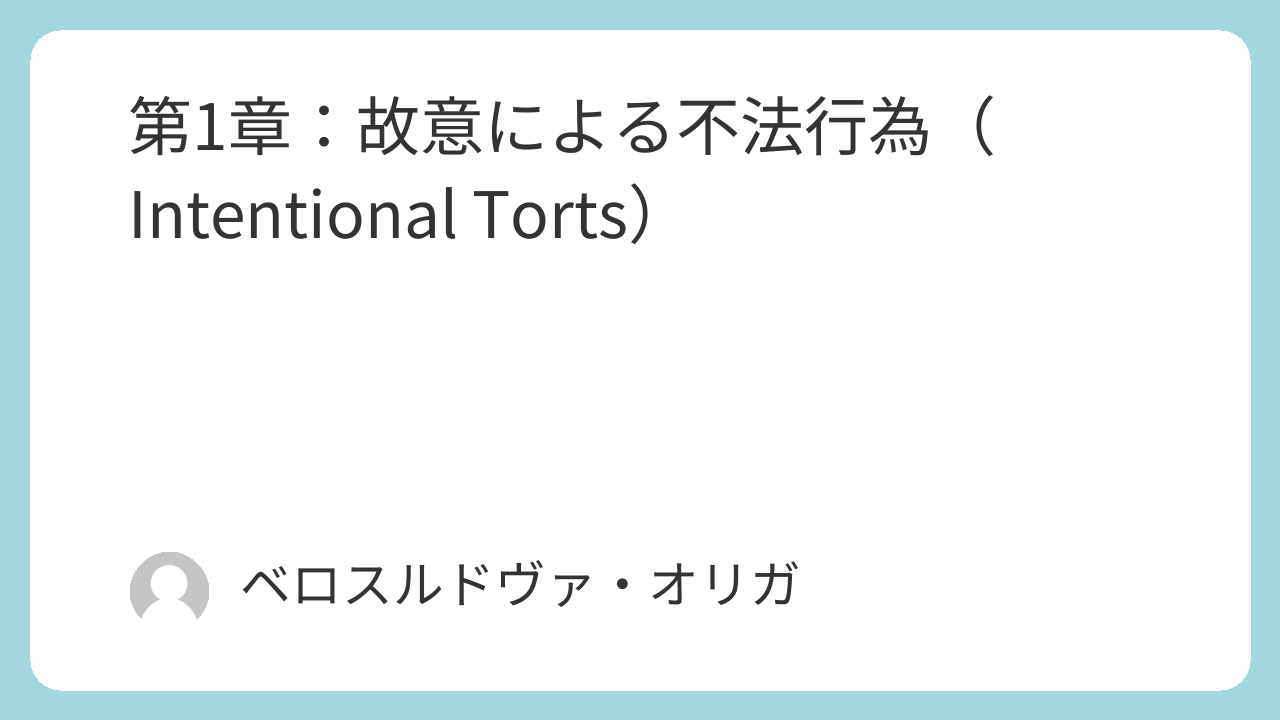不法行為法は、加害者の行為態様によって大きく3つに分類されますが、その出発点となるのが「故意による不法行為」です。これは、不注意(過失)や、行為の危険性そのもの(厳格責任)から責任が問われるのとは異なり、加害者の「故意(Intent)」が責任の中核をなす分野です。ここでいう故意とは、必ずしも相手に危害を加えようとする悪意や敵意を意味するわけではありません。法的に保護された他者の利益(身体の安全・精神の平穏・財産の占有等)を侵害する結果を、自らの行為によって引き起こそうと意図すること、又は、その結果が生じることが確実(substantially certain)であると認識しながら行動することが「故意」の本質です。
1. 人に対する故意の不法行為
A. Battery(有害又は不快な身体的接触)
Batteryは、他者の身体に対する意図的かつ同意のない「有害(harmful)」・「不快(offensive)」な接触によって成立します。ここで保護しようとしているのは、単に物理的な危害から身体を守る権利だけでなく、個人の尊厳と身体的自己決定権、即ち「望まない接触から自由である権利」です。
接触(Contact)の要件
接触は、加害者の身体が直接被害者に触れる場合に限りません。加害者が投げた石が当たることや、Garratt v. Dailey事件のように被害者が座ろうとしていた椅子を引いた結果被害者が地面に接触した場合も含まれます。被害者の身体に密接に関連している物(手に持っている皿など)への接触も、Batteryを構成します。
「有害・不快」な接触
接触が「有害」であることの判断は比較的容易ですが、「不快」であるか否かは文脈に依存します。「合理的な個人の尊厳の感覚を害する(offends a reasonable sense of personal dignity)」接触が、その基準となります。満員電車でのやむを得ない接触は通常、不快とは見なされませんが、同意のないキスや不適切な状況で肩をなでる行為等は、たとえ身体的な危害がなくとも個人の尊厳を侵害する「不快」な接触としてバッテリーに該当することがあります。
Vosburg v. Putney事件では、教室で生徒が向かいの席の生徒の足を軽く蹴った行為がバッテリーとされました。裁判所は、その行為が教室の秩序と礼儀に反する「不法な」ものであったことを重視しました。これがもし校庭での出来事であれば、ある程度の身体的接触は黙示的に同意されていると見なされたかもしれません。このように、接触が許容されるか否かは、その場の状況や社会的規範に大きく左右されます。
故意(Intent)の要件
Batteryにおける「故意」の解釈には、2つの考え方が存在します。
- Single-Intent:被告が「接触」そのものを意図していれば足り、その接触が有害又は不快であることを意図・認識している必要はないとする考え方です。
- Dual-Intent:被告が「接触」を意図していることに加え、その接触が「有害または不快であること」をも認識している必要があるとする考え方です。
多くの州ではSingle-Intentルールが採用されています。このルールによれば、被告が良かれと思って行った接触であっても、客観的に見てそれが不快なものであればBatteryが成立します。一方、Dual-Intentルールでは、被告がその接触の不快性を認識していなければ責任を問われません。
また、意図は「結果の発生を欲すること」だけでなく、「結果の発生が実質的に確実であると認識していること」でも足ります。さらに、Transferred Intentの法理により、Aを殴ろうとして誤って隣にいたBを殴ってしまった場合でも、Bに対するBatteryが成立します。加害者の非難可能性は、対象を誤ったからといって消滅するわけではないからです。
B. Assault:差し迫った危惧
Assaultは、バッテリーが成立するような有害・不快な接触が「今にも起ころうとしている(imminent)」という危惧(apprehension)を、相手に意図的に抱かせる行為です。Batteryが身体的自己決定権の保護を目的とするのに対し、Assaultは「差し迫った身体的侵害の恐怖からの自由」すなわち精神の平穏(mental peace)を保護します。
Assaultが成立するためには、被害者が現実に「恐怖」を感じる必要はありません。屈強な格闘家が非力な相手から殴りかかられ、恐怖は感じなくとも接触が差し迫っていると「認識」すれば、Assaultは成立します。
重要なのは「差し迫った(imminent)」という要件です。「明日、お前を殴りに行く」といった将来の危害の告知や電話口での脅迫は、脅威が時間的・空間的に切迫していないため、通常Assaultにはあたりません。また、「もし俺が暴力的な男だったら、お前を殴っていたところだ」といった条件付きの脅迫も、現実の脅威ではないためアサルトを構成しません。言葉だけでなく、拳を振り上げるなどの行為が伴うことで、脅威はより切迫したものとなります。
C. 監禁(False Imprisonment)
BatteryとAssaultが身体への接触とその危惧を問題にするのに対し、監禁は移動の自由(freedom of movement)を保護する不法行為です。これは、被告が原告を、その意に反して、一定の限定された領域内に意図的に閉じ込める行為を指します。
監禁は「完全(total)」でなければなりません。部屋に閉じ込める、物理的に出口を塞ぐ又は暴力の脅威によってその場を動けなくさせるといった行為は監禁にあたります。しかし、単に進路を妨害され迂回を余儀なくされたにすぎない場合は、完全な監禁とはいえません。監禁されているという事実を被害者が認識しているか、認識していなくても監禁によって何らかの身体的危害を被ったことが、多くの州で要件とされています。
D. 精神的苦痛(Intentional Infliction of Emotional Distress, IIED)
社会が複雑化するにつれ、Battery・Assault・監禁という伝統的な枠組みでは捉えきれない、悪質な精神的攻撃から被害者を保護する必要性が認識されるようになりました。そこで20世紀に確立されたのが精神的苦痛(IIED)です。
IIEDが成立するためには、単に相手を怒らせたり、侮辱したりするだけでは不十分です。裁判所は、訴訟の門戸が無制限に開かれることを警戒し高いハードルを設けています。その要件は、以下の通りです。
- 被告の行為が「常軌を逸した(extreme and outrageous)」ものであること。これは、「文明社会において到底許容されない」レベルの行為を意味します。
- 被告が原告に深刻な精神的苦痛を与えることを意図したこと
- 被告の行為と原告の精神的苦痛との間に因果関係があること
- 原告が被った精神的苦痛が「深刻(severe)」なものであること。一時的な不快感や悲しみでは足りず、合理的な人間が耐えがたいほどの苦痛である必要があります。
悪質な冗談で近親者の死亡を偽って伝えたり、執拗かつ脅迫的な借金の取り立てを行ったりする行為が、典型的なIIEDの例です。この不法行為は、具体的な行為類型を限定せず柔軟な基準を用いることで、社会通念の変化に対応しうる枠組みとなっています。しかしその反面、何が「常軌を逸した」行為にあたるかの予測が難しく、裁判官や陪審員の価値判断に委ねられる部分が大きいという特徴も持ちます。
2. 財産に対する故意の不法行為
故意の不法行為は、個人の身体だけでなく、財産権も保護の対象とします。
- 土地への不法侵入(Trespass to Land):他人の土地に意図的に立ち入ったり物を置くなどして、土地の排他的な占有権を侵害する行為です。損害の発生は要件ではありません。
- 動産への不法侵入(Trespass to Chattels):他人の動産(自動車、PCなど)を意図的に損傷させたり、一時的にその使用を妨げたりする行為です。
- 横領(Conversion):他人の動産に対して、所有権を侵害するような重大な支配を意図的に行う行為です。例えば、他人の車を盗んで売り払う行為がこれにあたります。救済としては、通常、その動産の完全な市場価値の賠償が命じられます。
- Nuisance:土地の占有そのものではなく、土地の「利用と享受(use and enjoyment)」を実質的かつ不合理に妨害する行為です。騒音や悪臭、煤煙などが典型例です。
3. 故意の不法行為に対する抗弁(Defense)
原告が故意の不法行為の成立要件を立証したとしても、被告は特定の状況下で自らの行為が正当化される、あるいは免責されると主張することができます。
A. 同意(Consent)
最も基本的な抗弁は、被害者が加害者の行為に同意していたという主張です。同意は、明示的な言葉によるものだけでなく、行為や状況から黙示的に推断される場合もあります。例えば、ボクシングの試合に参加する選手は、ルール内の打撃を受けることに黙示的に同意していると見なされます。
しかし、同意には限界があります。Mohr v. Williams事件では、患者が右耳の手術に同意していたにもかかわらず、麻酔中に医師が左耳の方がより深刻だと判断し、左耳の手術を行いました。裁判所は、左耳への手術は同意の範囲を超えているとして、Batteryの成立を認めました。また、詐欺や強迫によって得られた同意や、未成年者など法的に有効な同意を与える能力がない者からの同意は無効となります。
B. 正当防衛・第三者防衛(Self-Defense and Defense of Others)
差し迫った危害から自己または他者を守るために合理的な範囲の実力(reasonable force)を行使することは、法的に許容されます。成立のためには、攻撃が差し迫っていると合理的に信じることが必要であり、その防御行為は脅威の程度に相応したものでなければなりません。例えば、素手で殴りかかってきた相手に対し、銃器で反撃することは、通常、過剰防衛と見なされます。
C. 緊急避難(Necessity)
自己または他者の生命や財産を、より大きな危害から守るために、やむを得ず他人の財産を侵害する行為は、緊急避難として正当化される場合があります。緊急避難には2つの類型があります。
- 公的緊急避難(Public Necessity)
火事の延焼を防ぐために家屋を破壊する破壊消防等、公共の利益を守るために個人の財産を侵害する場合です。この場合、緊急避難は「絶対的(absolute)」であり、行為者は財産の所有者に対して賠償責任を負いません。 - 私的緊急避難(Private Necessity)
個人の生命や財産を守るために他人の財産を侵害する場合です。Ploof v. Putnam事件では、嵐を避けるために原告が被告の所有する桟橋にボートを係留しました。被告の使用人がこれをほどいたため、ボートが破壊され原告らが負傷しました。そもそも自らに所有権のない桟橋に原告がボートを係留した行為について、裁判所は原告に緊急避難が成立し桟橋に留まる権利があったとした上で、被告(桟橋の所有者)の不法行為責任を認めました。 一方で、Vincent v. Lake Erie Transportation Co.事件では、嵐の間、被告が自らの船を守るために原告の桟橋に係留し続けた結果、船が桟橋に衝突し、桟橋が損傷しました。裁判所は、被告が桟橋に留まることは緊急避難として許されるとしつつも、その特権は「条件的(qualified)」あるいは「不完全(incomplete)」なものであるとしました。すなわち、自らの財産を守るために他者の財産を利用することは許されるが、それによって生じた損害については賠償する義務を負うと判断しました。法は、危険を回避するために積極的に他者の財産を利用することを選択した者が、その選択に伴うコストも負担すべきである、という判断を下したのです。