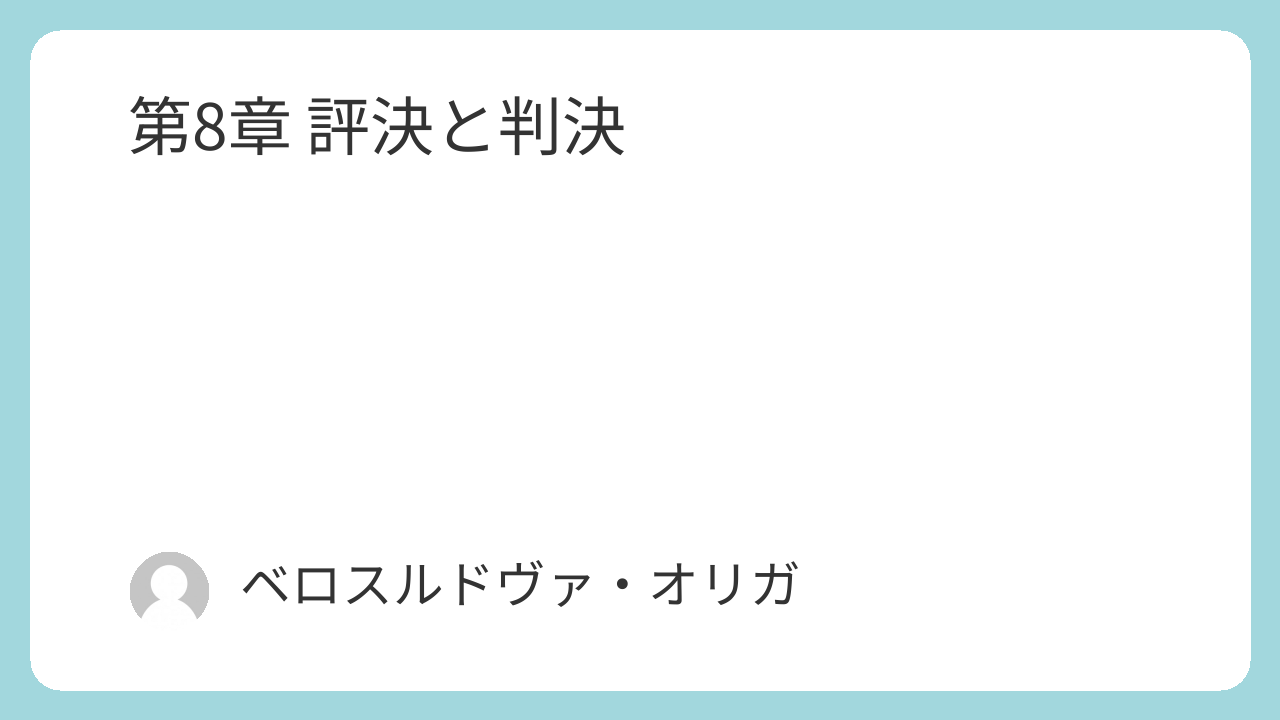8.1 評決(Verdict)
トライアル(事実審理)におけるすべての証拠調べと弁論が終結すると、事実認定者(陪審審理では陪審、裁判官審理では裁判官)は、提示された証拠と法廷での議論を基に、事件の事実関係についての結論を導き出します。陪審が下すこの結論を「評決(Verdict)」と呼びます。これに基づいて裁判官が最終的な法的判断である「判決(Judgment)」を言い渡すことになります。
陪審がその結論を示す評決の形式には、主に3つの種類があります。どの形式を用いるかは、事件の複雑さや、裁判官が陪審の判断プロセスをどの程度コントロールすべきかといった考慮に基づき、裁判官の裁量に委ねられます(連邦民事訴訟規則49条)。
(1)一般評決(General Verdict)
最も伝統的で、今なお最も一般的に用いられているのが「一般評決」です。これは、陪審が、単に「我々は原告(または被告)を支持することを認める(We find for the plaintiff/defendant)」と結論を示し、原告勝訴の場合は損害賠償額を具体的に記入するという、極めてシンプルな形式です。
一般評決の最大の利点は、その簡潔さにあります。そして、それは陪審が持つ歴史的な役割、すなわち、厳格な法のルールにコミュニティの常識や衡平の感覚を注入するという役割を最大限に尊重する形式でもあります。陪審は、裁判官から与えられた法の指示を、自らが認定した事実に適用する過程で、複雑な事実関係や法解釈を総合的に判断し、1つの包括的な結論を導き出します。このプロセスは、外部からは見えない「ブラックボックス」の中で行われ、評決はその最終的なアウトプットのみを示します。
しかし、この「ブラックボックス」性こそが、一般評決の最大の弱点であるとも指摘されています。陪審がどのような事実認定に基づき、どのように法を適用してその結論に至ったのか、その論理的な過程が全く明らかにされないためです。もし、原告が複数の請求原因を主張しており、そのうちの1つに法的な誤りがあった場合、陪審がどの請求原因に基づいて原告勝訴の評決を下したのかが不明確であれば、上訴審は評決全体を取り消し、再審理(new trial)を命じざるを得なくなる可能性があります。また、陪審が裁判官の説示を誤解したり、感情に流されたり、あるいは法を無視して自らの正義感に基づいて判断を下したりしたとしても、それを外部から検証することは極めて困難です。
(2)特別評決(Special Verdict)
このような一般評決の曖昧さを克服するために考案されたのが「特別評決」です。この形式では、裁判官は陪審に対して、最終的な勝敗の判断を求めるのではなく、事件の核心となる具体的な事実問題に関する一連の質問(written questions)を提示します。陪審の役割は、これらの質問に対して事実認定の結果を回答することに限定されます。そして、裁判官が、陪審から返された事実認定の回答に、自ら法を適用して、最終的な判決を下すのです。
特別評決の利点は、陪審の判断プロセスを透明化し、その結論がどのような事実認定に基づいているかを明確にできる点にあります。これにより、上訴審は、法的な誤りの影響が評決のどの部分に及んだかを正確に判断でき、不必要な再審理を避けることができます。また、陪審を、その本来の役割である事実認定に集中させ、複雑な法律論の適用という作業から解放する機能も持ちます。
一方で、特別評決には、質問の作成が極めて難しいという大きな課題があります。訴訟のすべての争点を網羅し、かつ、陪審が混乱しないよう簡潔で中立的な言葉で質問を作成することは、大きな負担となります。不適切な質問は、かえって陪審を誤導し、評決の矛盾を招く危険性さえはらんでいます。
(3)質問付き一般評決(General Verdict with Written Questions)
「質問付き一般評決」は、一般評決と特別評決の利点を組み合わせたハイブリッド型の評決形式です。この形式では、陪審は、まず原告と被告のどちらが勝訴かという最終結論(一般評決)を下します。それに加えて、裁判官が提示する一つまたは複数の重要な事実問題についても、書面で回答することが求められます。
この手続の目的は、一般評決という陪審の伝統的な役割を尊重しつつ、その結論が重要な事実認定と論理的に矛盾していないかを確認することにあります。もし、質問への回答と一般評決の内容が整合的であれば、判決はそのまま成立します。しかし、両者が矛盾している場合、裁判官は、①陪審に再度の評議を命じる、②質問への回答に合わせて判決を下す(一般評決を無視する)、③再審理を命じる、といった選択肢の中から、適切な措置をとることができます。これにより、一般評決の「ブラックボックス」性をある程度緩和し、評決の論理的な一貫性を担保することが可能となります。
8.2 裁判官審理における事実認定と法律上の結論
裁判官審理(Bench Trial)においては、裁判官自身が事実認定者となります。この場合、裁判官は、評決に代わるものとして、自らの判断の根拠を明確に示さなければなりません。連邦民事訴訟規則52条(a)項は、裁判官に対し、「事実認定(findings of fact)」と「法律上の結論(conclusions of law)」を、それぞれ別個に陳述することを義務付けています。
この要請には、3つの重要な目的があります。
第一に、上訴における審査を容易にすることです。上訴審は、第一審裁判官の事実認定については「明白な誤り(clearly erroneous)」がない限りこれを尊重しなければならないという、厳格な審査基準に服します。一方で、法律上の結論については、何らの拘束も受けずに、自ら改めて判断(de novo review)することができます。事実認定と法律上の結論が明確に分離されていることで、上訴審は、どの部分にどの審査基準を適用すべきかを正確に判断できるのです。
第二に、既判力(res judicata / collateral estoppel)の適用範囲を明確にすることです。後の訴訟で、前の判決のどの部分が既判力を持つかを判断する際、判決の基礎となった事実認定と法律上の結論が明確に示されていれば、争点効(collateral estoppel)が及ぶ範囲を特定することが容易になります。
第三に、第一審裁判官による慎重な判断を促すことです。自らの判断の論理的な根拠を、事実と法律に分けて明示することを要求されることで、裁判官は、証拠をより注意深く吟味し、より説得力のある結論を導き出すことが期待されます。
8.3 評決と判決に対する異議申し立て
トライアルが終結し、評決または判決が下されたとしても、訴訟が完全に終わったわけではありません。敗訴した当事者には、その結果を覆すためのいくつかの重要な手続(post-trial motions)が残されています。これらの申立ては、上訴という時間と費用のかかるプロセスに訴える前に、第一審のレベルで誤りを是正する最後の機会を提供するものです。
(1)法律問題としての判決申立て(Judgment as a Matter of Law)
これは、陪審の評決が出た後で、敗訴した当事者が、「陪審が下した評決は、法廷に提出された証拠に照らして、合理的な人間であれば到底下し得ないものである」と主張し、裁判官に対して、陪審評決を覆して自らに有利な判決を下すよう求める手続です(連邦民事訴訟規則50条(b)項)。すなわち、「Judgment Notwithstanding the Verdict(JNOV)」を求めるものです。
この申立てが認められるための基準は、トライアルの最中に行われる「法律問題としての判決申立て(いわゆる指示評決、Directed Verdict)」の基準と同一であり、極めて厳格です。裁判官は、証拠の信用性を自ら評価したり、証拠の重みを比較衡量したりすることは許されません。全ての証拠を、評決で勝訴した側(被申立人)にとって最も有利に解釈した上で、それでもなお、被申立人を支持する評決を裏付ける法的に十分な証拠が全く存在しないと結論できる場合にのみ、この申立ては認められます。
この手続は、陪審の事実認定権という憲法修正第7条で保障された権利と緊張関係にあります。しかし、最高裁は、証拠が一方の結論しか許さない場合にまで陪審に判断を委ねることは憲法が要求するところではないとし、その合憲性を認めています。連邦裁判所では、トライアル終了後にこの申立てを行うためには、評決が下される前に、同じ理由で一度、「法律問題としての判決申立て」を行っておくことが、手続上の前提条件とされています。
(2)新規審理の申立て(Motion for a New Trial)
新規審理の申立ては、評決を覆して自らの勝訴判決を求めるJNOVとは異なり、トライアルで生じた何らかの重大な誤りを理由に、評決を破棄して、もう一度新しいトライアルを開くことを求める手続です(連邦民事訴訟規則59条)。
申立てが認められる理由は多岐にわたりますが、主なものとしては、以下が挙げられます。
- トライアルにおける手続上の重大な誤り: 裁判官による不適切な陪審への説示、証拠の不当な採用・排除、又は、弁護士・陪審員の不正行為など。
- 評決が証拠の圧倒的多数に反する(Verdict is against the great weight of the evidence): これはJNOVの基準よりも緩やかです。JNOVが「合理的な陪審なら…あり得ない」というレベルを要求するのに対し、新規審理の申立てでは、裁判官は自ら証拠の重みをある程度衡量し、評決が明らかに「証拠の圧倒的多数」に反すると判断した場合には、たとえJNOVを認めるほどの証拠の欠如はなくとも、新規審理を命じることができます。このことから、裁判官が「13番目の陪審員」として機能する、と表現されることもあります。
- 損害賠償額の過大または過小: 陪審が認定した損害賠償額が、証拠に照らして、著しく過大または過小である場合。この場合、裁判所は、remittitur(賠償額が過大な場合に、原告が減額に同意しなければ新規審理を命じる)や、additur(賠償額が過小な場合に、被告が増額に同意しなければ新規審理を命じる)といった条件付きで新規審理を命じることがあります。ただし、連邦裁判所では、additurは憲法修正第7条に違反するとして認められていません。
- 新証拠の発見: トライアルの時点で存在していたにもかかわらず、当事者が相当な注意を払ってもトライアルが終結するまでに発見することができなかった、結果を覆すに足る重要な証拠が、トライアル終結後に発見された場合に認められます。
8.4 陪審員の不正行為と評決の弾劾
陪審員は、外部からの影響を絶たれた空間で、自由闊達な議論を通じて結論に至ることが期待されます。このため、一度下された評決の有効性を、後から陪審員自身の証言によって覆すことには、歴史的に極めて厳しい制限が課せられてきました。
この原則は「マンスフィールド・ルール」として知られ、いかなる理由があっても、陪審員は自らの評決を無効にするための証言をすることはできない、とされてきました。その根拠は、もし評決後に陪審員が外部からの圧力で証言を翻すことが容易になれば、評決の安定性が損なわれ、陪審員が自由な評議を行えなくなる、という点にありました。
しかし、この厳格なルールは、陪審員による明白な不正行為があった場合にまで正義の実現を妨げるという批判を浴びました。これを受け、現代の証拠法、特に連邦証拠規則606条(b)項は、この原則を維持しつつも、重要な例外を設けています。
現在のルールによれば、陪審員は、自らの評議の内容、評議中の発言、思考過程、あるいは評決に至った際の感情といった、評議の内部的なプロセスについて証言することは、依然として固く禁じられています。例えば、「あの陪審員は証拠を誤解していた」「コイン投げで決めた」「賠償額を12で割るという妥協の産物だった」といった証言は、評決を弾劾するためには使えません。
しかし、以下の3つの外部からの影響については、陪審員の証言が例外的に許されます。
- 評議の場に、無関係な先入観を与えうる情報が持ち込まれた場合(extraneous prejudicial information): 例えば、陪審員の一人が、事件について報じた新聞記事を評議室に持ち込んで読んだり、インターネットで独自に調査した情報を他の陪審員に話したりした場合。
- 外部からの不当な影響があった場合(outside influence): 例えば、第三者が陪審員を買収しようとしたり、脅迫したりした場合。
- 評決書への記載に誤りがあった場合(mistake in entering the verdict on the verdict form): 例えば、全員が被告勝訴で合意したのに、誤って原告勝訴の用紙に署名してしまった場合。
このルールは、評議の自由という価値と、不正行為から当事者を保護するという価値との間の、デリケートなバランスを保とうとするものです。
8.5 判決内容の変更または判決からの救済を求める申立て
トライアル後の申立てには、上記のJNOVや新規審理の申立ての他に、判決そのものの内容の変更や、確定した判決からの救済を求める手続があります。
判決内容の変更または修正を求める申立て(Motion to Alter or Amend a Judgment)(連邦民事訴訟規則59条(e)項)は、判決言渡し後、比較的短い期間内(連邦では28日以内)に、明らかな法律上の誤りを是正したり、トライアルでは入手できなかった新証拠を考慮させたりするために行われます。
判決からの救済を求める申立て(Motion for Relief from a Judgment or Order)(連邦民事訴訟規則60条(b)項)は、より例外的で強力な救済手続です。これは、既に確定した(final)判決について、(1)錯誤・不注意・過失、(2)新証拠の発見、(3)相手方当事者による詐欺・不正行為、(4)判決が無効であること、(5)先行する判決が破棄・変更されたこと、(6)その他、救済を正当化するあらゆる理由、といった特別な事情が存在する場合に、その判決の効力を取り消すか、あるいは変更することを求めるものです。この申立ては、判決の安定性(finality)という極めて重要な価値との衡量において判断されるため、認められるためのハードルは非常に高いです。